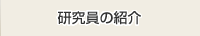- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 研究員の紹介 >
- 塩澤 誠一郎
塩澤 誠一郎のレポート
-

2025年07月08日
住宅を社会的資産に-ストック型社会における住宅のあり方
ストック型社会とは、蓄積された社会資本を長く有効に活用する社会をいう。そこでは自然資源を用いた新たな物質の投入や廃棄が抑制され、代わり...
-

2025年06月25日
住宅を社会的資産に~ストック型社会における住宅のあり方~
ストック型社会とは、蓄積された社会資本を長く有効に活用する社会をいう。そこでは自然資源を用いた新たな物質の投入や廃棄が抑制され、代わり...
-

2025年04月09日
「計画修繕」は、安定的な入居確保に必須の経営手法~民間賃貸住宅における計画修繕の普及に向けて~
国土交通省住宅局の補助事業でニッセイ基礎研究所が制作した、「民間賃貸住宅管理業者向け計画修繕ガイドブック」は、民間賃貸住宅管理業者が利...
-

2024年08月13日
空き家の管理、どうする?~空き家の管理を委託する際、意識すべき3つのこと~
2023年12月の空き家法改正により、管理不全空き家を自治体が指定し、行政指導を行っても改善されない場合、固定資産税の減額措置が解除さ...
-

2024年08月07日
空き家の管理から活用へ~「不動産業者による空き家管理受託のガイドライン」の策定を機に、空き家を管理から活用へと導く不動産業者の増加に期待~
先頃、国土交通省が、「不動産業者による空き家管理受託のガイドライン」(以下、ガイドライン)を公表した。不動産業者が所有者から空き家の管...
-

2024年06月24日
賃貸住宅の断熱・遮音改修のススメ~家主にとっても入居者にとっても、地球温暖化対策にとっても意義のある賃貸住宅経営を目指して~
2025年4月1日から、原則全ての建築物について、省エネ基準適合が義務づけられる。適合義務の対象は、新築の場合建物の全て、増改築の場合...
-

2024年02月08日
聖地巡礼から気付くこと~地元民のための地元の聖地化に必要な創作の力~
郷里の山梨県に、巡礼スポットがあることを知ったのはごく最近のことだ。「スーパーカブ」、「ゆるキャン△」といった作品に接してである。アニ...
-

2023年12月07日
空き家対策のその先-住み継ぐことを前提にした社会の構築に向けて
空家等対策の推進に関する特別措置法が改正され、新たに定義された、管理不全空き家を自治体が指定し、行政指導を行っても改善されない場合、固...
-

2023年11月22日
空き家対策のその先-住み継ぐことを前提にした社会の構築に向けて
空家等対策の推進に関する特別措置法が改正され、新たに定義された、管理不全空き家を自治体が指定し、行政指導を行っても改善されない場合、固...
-

2023年10月20日
賃貸住宅修繕共済の登場で期待される計画修繕の普及~賃貸住宅オーナーに修繕・点検時期セルフチェックのすすめ~
賃貸住宅における計画修繕の普及が課題になっている。計画修繕とは、修繕の実施時期を予定して計画的に資金を準備し、予防的に修繕を実施するこ...
-

2022年12月20日
東京ドーム198コ分の農地が、数年のうちに宅地に変わる~2022年問題以降の都市農地のゆくえ 4~
前回見たように、国土交通省の調査結果では、現状で特定生産緑地に指定する生産緑地は、全体の89%で、面積は9,382㏊である。これは東京...
-

2022年12月09日
残る農地、残らない農地~2022年問題以降の都市農地のゆくえ 3~
特定生産緑地指定制度は、2017年の生産緑地法の改正により設けられた。生産緑地の指定公告から30年経過すると、生産緑地を所有する農家は...
-

2022年12月02日
2022年を迎えた生産緑地の2022年問題~2022年問題以降の都市農地のゆくえ 2~
2015年6月に「『2022年問題』に警鐘を鳴らす ~ 都市農地のゆくえ ~」というコラムを公表してから、世間の関心を集めてきた生産緑地の...
-

2022年11月25日
都市農業を支持するファン層は、今やマジョリティ~2022年問題以降の都市農地のゆくえ 1~
11月、都内では農業関連のイベントが所々で開催この日は、そこを運営する、「NPO法人武蔵野農業ふれあい村」主催で、市民向けの収穫祭を開...
-

2021年01月29日
人生100年時代を支える新たな住宅金融~老後のライフスタイルに応じた選択肢
高齢期になって、住み替えたり、自宅を改装したりする人が増えています。2018年の住生活総合調査で見ると、最近5年以内に住み替えた高齢世帯...
-

2021年01月22日
住宅団地の多世代居住に向けた取り組み~持続可能な地域社会を築くために
平均寿命だけでなく、健康寿命を延ばすことが、個人の人生をより豊かにすると考えられています。健康寿命の延伸は、社会活動寿命と密接に関係し...
-

2020年05月26日
コロナ禍で農産物直売利用者が増加~生産の場が日常生活圏にあることのありがたさ
コロナ禍で筆者も在宅勤務を続けている。平日はほとんど外出せず、土日は運動不足解消のためのウォーキングとスーパーへの買い出し程度となった...
-

2020年03月12日
生産緑地への農業法人参入の可能性
都市農地貸借法の施行により、多様な主体が生産緑地を貸借して営農することが可能となった。当然ながら、多様な主体の中には農業法人も含まれる...
-

2020年01月22日
自動運転は年間約10兆円の経済損失をプラスの経済効果に変えることができるか?
先日出張帰りに羽田空港からバスで帰ってきたときのことだ。終点の自宅最寄駅に近づいたことを告げるアナウンスで、ふと時計に目をやると20時...
-

2019年07月18日
まちづくりレポート|大阪の農空間づくり-大阪府農空間保全地域制度による、協働型コモンズの形成
2015年に成立した都市農業振興基本法(以下、基本法)では、第3条基本理念で、「都市農業が、農産物の供給の機能以外の多様な機能を果たし...
-

2019年06月07日
駐車場とまちの未来-自動運転の時代に駐車場は社会に必要なインフラとなり得るか?
自動運転の時代が足音を立てて近づいてきている一方で、その時代には必要なくなるとされている駐車場は、いまだ増え続けている。このような中、...
-

2019年03月28日
3方よしの観点で公共空間を見直すと
前回、好きなことをする人よし、それを見る人よし、その光景を眺める人よしの、3方よしを成立させる空間的条件を述べた好きなことをする人の活...
-

2019年03月27日
3方よしの関係が地域の価値を高める?
3方よしの関係は、公共施設に限ったことではない。例えば、筆者がよく通りかかる一角に、住まいのエントランス周りに花を飾り、よく手入れして...
-

2019年03月26日
公共空間の3方よし
通勤途中に横切る公園内にある野球場は、休日になると少年野球などの試合が行われることが多く、選手たちはもちろん、チーム関係者や保護者など...
-

2019年03月13日
公共施設のシェア利用
いつも通勤途中に横切る公園で、キャッチボールをする親子が目に入った。冬休みに入り、お父さんも休みが取れたのだろう。親子で楽しそうにボー...
-

2019年03月07日
農と食と健康
今、都市農業をめぐる状況は大きく変化しようとしていて、関係するイベント告知を頻繁に目にするようになった。そうした場に参加して感じるのは...
-

2019年02月27日
生産緑地を借りるのは誰?-都市農地の貸借円滑化法施行の効果と課題(その2)
前回のレポート、その1では、生産緑地法の主たる従事者要件と都市農地貸借法の認定要件を解説した。その2では、都市農地貸借法に基づき生産緑...
-

2019年02月20日
都市農地貸借の要件-都市農地の貸借円滑化法施行の効果と課題(その1)
昨年9月に、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(以下、都市農地貸借法)が施行された。法の詳細は2018年2月のレポートで解説したところ...
-

2018年10月18日
まちづくりレポート|大阪の農空間づくり-大阪府農空間保全地域制度による、協働型コモンズの形成
2015年に成立した都市農業振興基本法(以下、基本法)では、第3条基本理念で、「都市農業が、農産物の供給の機能以外の多様な機能を果たし...
-

2018年07月05日
2022年問題の不動産市場への影響-生産緑地の宅地化で、地価は暴落しない
生産緑地の30年買取り申出 によって多くの生産緑地が一斉に宅地として放出され、不動産市場に大きな影響を与えるのではないかとの懸念が生産緑...
-
2018年03月30日
自動運転が普及したときのまちづくり-完全自動運転が普及した社会とまちづくり。その9
筆者が完全自動運転の移動サービスに最も期待することは、すべての人をあらゆる移動制約から解放することだ。クルマがなくても自由に移動できる...
-

2018年03月30日
自動運転の普及のために大切なこと-完全自動運転が普及した社会とまちづくり。その8
そもそも完全自動運転の普及になにが重要になるのだろうか?そのためには、まず完全自動運転の前に、望ましい移動手段とは何かを考える必要があ...
-

2018年03月30日
自動運転の普及を見越したまちづくり-完全自動運転が普及した社会とまちづくり。その7
現在多くの自治体が、市街地のコンパクト化に取り組んでいる。もう少し正確に言うと、現在のまちづくりの方向性は、「コンパクトシティ・プラス...
-

2018年03月29日
自動運転の普及とその道のり-完全自動運転が普及した社会とまちづくり。その5
前回、2030年頃には完全自動運転の移動サービスが社会に広く普及するだろうと予測したのであるが、それまでしばらくは、所有型とサービス型...
-

2018年03月29日
自動運転の普及と駐車場の集約化-完全自動運転が普及した社会とまちづくり。その6
完全自動運転の普及によって、都市空間から必要なくなるものの代表選手が駐車場である。少し踏み込んでまちづくりの観点から完全自動運転の普及...
-

2018年03月28日
自動運転の普及とMaaS-完全自動運転が普及した社会とまちづくり。その3
自動運転を強力にサポートするのは、土木構造物としてのインフラではなく、MaaS(マース)というシステムである。これは、新たな交通インフ...
-

2018年03月28日
自動運転の普及とその時期-完全自動運転が普及した社会とまちづくり。その4
2013年8月のニュースに当時筆者は非常に驚いた。日産自動車が2020年までに複数車種において自動運転を実用化すると発表したからだ。当...
-

2018年03月27日
自動運転の普及と都市の形-完全自動運転が普及した社会とまちづくり。その2
自動車が誕生した当時は、インフラも一緒に造る必要があった。T型フォードが生産され、自家用車の普及にあわせて、全米にハイウェイが張り巡ら...
-

2018年03月27日
自動運転の普及とインフラ-完全自動運転が普及した社会とまちづくり
新幹線が登場した当時のことを筆者はよく知らない。しかし、「夢の超特急」と呼ばれていたと聞くと、当時の国民にはそれが実現することへのワク...
-

2018年03月20日
2022年問題の不動産市場への影響~生産緑地の宅地化で、地価は暴落しない~
生産緑地の2022年問題をはじめに指摘したコラムを執筆したのは筆者である。しかしその後の意向調査結果、市街化区域内農地の状況、一連の法...
-

2018年02月14日
生産緑地の貸借によって変わる都市農業と都市生活―都市農地の貸借円滑化法案の内容と効果
「都市農地の貸借の円滑化に関する法律案(以下、法案)」が、1月22日を召集日とする今通常国会に提出される予定である。この法案は昨年9月...
-

2018年01月17日
生産緑地に関する税制改正とその影響-平成30年度税制改正による都市農地の見通しと課題
生産緑地法の一部改正を受けて、平成30年度税制改正大綱(以下大綱)において関連税制が決定した。これにより、地区指定から30年経過を迎え...
-
2017年07月07日
生産緑地法改正と2022年問題ー2022年問題から始まる都市農業振興とまちづくり
2022年は、1992年に生産緑地地区が最初に指定されてから30年となり、生産緑地の買い取り申出が可能になる年である。対象となる土地所...
-
2017年06月15日
まちづくりレポート|古材と一緒に家主のこころをレスキュー~リビルディングセンター・ジャパンが信州諏訪にもたらした幸福な状況
リビルディングセンター・ジャパンは古材をレスキューし、古材の魅力を人々に伝え、再利用を促す。その過程でレスキューを依頼した人の気持ちも...
-

2017年06月07日
まちづくりレポート みんなで創るマチ 問屋町ー若い店主とオーナーの連携によりさらなるブランド価値向上に挑む岡山市北区問屋町
問屋町は、今では中国・四国地方を代表するオシャレなまちとして知られている。しかし、もともとは卸売団地として形成された。岡山駅から南西約...
-
2017年05月31日
生産緑地法改正と2022年問題―2022年問題から始まる都市農業振興とまちづくり
生産緑地法の改正によって、生産緑地の2022年問題として懸念された土地・住宅市場への影響は一定程度抑えられ、生産緑地を保全、活用するこ...
-

2017年04月07日
シェアリングエコノミーの原点は公園にあった!? -空間と時間を分かち合う文化に見る幸せの法則
先日、石神井池のほとりを通りかかったときのことだ、前方に人だかりが見えた。近づいてみると、池でラジコンボートを航行させている人たちと、...
-

2017年03月29日
まちづくりレポート|みんなで創るマチ 問屋町(といやちょう)-若い店主とオーナーの連携によりさらなるブランド価値向上に挑む岡山市北区問屋町
かつて計画的に造ったまちの特徴を生かして、倉庫だった建物を活用し、魅力的な店舗にリノベーションして、人を呼び込みそれをエリア全体に波及...
-

2017年03月08日
日本初の「クリエイティブリユース」の拠点とは?-倉敷玉島のまちに息づく“創造の源”を訪ねて
とあるプロジェクトに関わるようになってから、「廃材」が気になるようになった。廃材は「ごみ」として廃棄されたものであるが、「ごみ」にしな...
-

2017年03月08日
自動運転の普及と住宅-完全自動運転が普及した社会を想像する
現在、既に一部の操作を自動化した乗用車が市販されており、自動運転技術に関する話題を目にする機会が増えている。自動運転車の普及に対する消...
-

2017年02月28日
シェアハウスのチャノマが商店街の空気を動かした!?-縁をつなぎ、縁を広げる空間「コトナハウス」とは?
「コミュニティ型賃貸住宅」は、入居者同士や入居者と地域住民とのコミュニティを育む賃貸住宅のこと、「共感コミュニティ」は、人々の共感に基...
-

2017年02月01日
シェアリングエコノミーの原点は公園にあった!?-空間と時間を分かち合う文化に見る幸せの法則
先日、石神井池のほとりを通りかかったときのことだ、前方に人だかりが見えた。近づいてみると、池でラジコンボートを航行させている人たちと、...
-

2017年01月26日
1日300人が訪れる「五月が丘まるごと展示会」-40軒の家庭が紡ぐ“物語”に触れて想うこと
先日執筆した、「まちづくりレポート|住宅団地活性化なるか!」でも触れたのだが、広島市内の戸建住宅団地を見学する機会を得て、住宅団地に対...
-

2017年01月16日
自動運転の普及とコスト-完全自動運転が普及した社会を想像する。その5
これまで、完全自動運転が普及した社会をまちづくりの視点から想像し描いてきた。現在と決定的に異なるのは、クルマを自己所有しなくても、自宅...
-

2017年01月10日
自動運転の普及と観光-完全自動運転が普及した社会を想像する。その4
完全自動運転が普及した社会の観光を想像してみたい。観光の場合も、たまたま時間が空いたので、日帰りでどこかに行きたいと希望を伝えれば、ク...
-

2017年01月04日
自動運転の普及と住宅-完全自動運転が普及した社会を想像する。その3
前回は、完全自動運転が普及すると、集客施設の駐車場が必要なくなることを論じたが、同じ理屈で個人住宅の駐車スペースも必要なくなる。現在、...
-

2016年12月26日
自動運転の普及と駐車場-完全自動運転が普及した社会を想像する。その2
今回も想像力を膨らませて、完全自動運転が普及した社会のまちづくりについて考えたい。完全自動運転が普及した社会では、需要に応じて最適な台...
-

2016年12月16日
自動運転の普及と津波避難対策-完全自動運転が普及した社会を想像する。その1
以前、自動運転に触れたコラムを執筆したが、それからたった3年ほどしか経っていないのに、ずいぶん現実味を増してきた。既に一部の操作を自動...
-
2016年11月29日
まちづくりレポート|住宅団地活性化なるか!-広島市戸建住宅団地活性化の取り組み
2015年3月、広島市は「住宅団地の活性化に向けて」と題する冊子を発行した。冊子には、高齢化する住宅団地の活性化に向けた市の方針、施策...
-
2016年06月07日
心地よい地域社会は、“共感”から生まれる-まちづくりをもっと楽しくする新案「共感コミュニティ」とは
東京の多摩地域では、人々の共感に基づくゆるやかなつながりを活動のベースにした「共感コミュニティ」が、ここ数年目立って増加している。共感...
-

2016年05月26日
子育て世帯の住宅取得事情‐昨今の住宅取得事情(その8)
「昨今の住宅取得事情」の第8回は、平成25年住生活総合調査から、子育て世帯の傾向を見る。子育て世帯は、「家族の集いや交流を促す間取り」...
-

2016年05月23日
今後の住み替え希望‐昨今の住宅取得事情(その7)
「昨今の住宅取得事情」の第7回は、平成25年住生活総合調査から、今後の住み替え意向について傾向を見る今後住み替えを希望している世帯は全...
-

2016年04月19日
借り上げ仮設住宅に求められるコミュニティの視点-熊本地震を機にコミュニティを育む賃貸住宅の普及を
熊本県熊本地方を震源にした熊本地震は、発生以降震度5弱を超える地震が頻発し、震源域も阿蘇地方や大分県中部地方へと拡大したことから、被害...
-

2016年03月31日
まちづくりレポート|多摩に広がる共感コミュニティ
東京の多摩地域に、人々の共感によるゆるやかなつながりを活動のベースにした「共感コミュニティ」が、ここ数年連鎖的に増加している。共感コミ...
-

2016年03月28日
持ち家に住み替えて、良くなったこと、わるくなったこと‐昨今の住宅取得事情(その6)
「昨今の住宅取得事情」の第6回は、平成25年住生活総合調査から、持ち家への住み替え前後における、住宅や周辺環境の変化を見る。持ち家を取...
-

2016年03月24日
中古住宅を取得した理由‐昨今の住宅取得事情(その5)
「昨今の住宅取得事情」の第5回は、近年取得者が増えている中古住宅に着目する。中古住宅を取得する人は年々増えており、その背景には持ち家取...
-

2016年03月22日
地域により異なる住宅取得事情‐昨今の住宅取得事情(その4)
住宅取得の状況も、地域別に見るとやや異なってくる。「昨今の住宅取得事情」の第4回は、「戸建注文住宅の顧客実態調査」から地域別の傾向を読...
-
2016年03月17日
住宅取得資金の状況‐昨今の住宅取得事情(その3)
「昨今の住宅取得事情」の第3回は、国土交通省が毎年実施している「住宅市場動向調査」から、平成26年度中に住宅を取得した世帯が、取得資金...
-
2016年03月14日
初めて持ち家を取得した層と2回目以上の違い‐昨今の住宅取得事情(その2)
「昨今の住宅取得事情」の第2回は、平成25年住生活総合調査を用いて、初めて持ち家を取得した層と2回目以上の層とを比較する。持ち家取得2...
-
2016年03月10日
昨今の住宅取得事情(その1)‐最近住まいを取得した人の傾向
今号から6回にわたり、昨今の住宅取得事情について、一般的な統計を用いて様々な角度から分析した結果を紹介する。初回は最近持ち家を取得した...
-
2016年03月08日
「作っては壊す」から「長く大切に使う」へ‐中古住宅の新たな評価方法
これまで中古戸建住宅は、築20年程度で価値が一律ゼロになるという市場慣行を前提とした評価を行っていた。これを、建物本来の機能に着目した...
-
2016年02月08日
住宅取得に対する消費税率引き上げの影響-2013、2014年における戸建注文住宅の動向
2017年4月より、消費税率を10%に引き上げることが予定されている。それが国民の住宅取得にどのような影響を及ぼすのか、8%に引き上げ...
-
2015年12月04日
住宅取得に対する消費税率引き上げの影響-2013、2014年における戸建注文住宅の動向
「戸建注文住宅の顧客実態調査」は2000年から毎年、主として一般社団法人住宅生産団体連合会法人会員企業や関連団体を対象に、各企業におい...
-
2015年08月07日
「2022年問題」に警鐘を鳴らす-都市農地のゆくえ
「2022年問題」と聞いてピンとくる読者はどのくらいいるだろうか。副題を「都市農地のゆくえ」としているので、関係者にとってはそれが「生...
-
2015年06月15日
ガチャガチャ式古書店から考える-今、地域に求められる、人と人をつなげる仕組み
筆者の自宅付近に、無人の古書店がある。無人と聞いて「?」となる読者がほとんどだと思うが、仕組みはこうだ。一坪ほどのスペースの壁一面に本...
-
2015年06月01日
「2022年問題」に警鐘を鳴らす ~ 都市農地のゆくえ ~
「2022年問題」と聞いてピンとくる読者はどのくらいいるだろうか。副題を「都市農地のゆくえ」としているので、関係者にとってはそれが「生...
-
2015年03月16日
まちづくりレポート|「地方創生」にも示唆を与える四日市方式-四日市市都市計画マスタープランの策定プロセス
■要旨都市計画マスタープラン(市町村の都市計画に関する基本的な方針)は、制度創設時から、策定に住民参加が義務付けられていたことから、各...
-
2015年02月06日
高齢期の社会的孤立の予防策-ニッセイ基礎研究所「長寿時代の孤立予防に関する総合研究」より
誰にも看取られることなく最期を迎える「孤立死」。その数は年間約3万人と推計される。日本は世界が羨む長寿大国になった一方で、孤立死を含め...
-
2014年05月30日
戦略的賃貸住宅誘導論-賃貸住宅が地域を変える
■要旨民間賃貸住宅を戦略的に誘導することで、地域の担い手を確保する方法論の提案を試みたのが本稿である。将来にわたり地域を持続させていく...
-
2014年04月22日
地域の課題に応える賃貸住宅-地域経営的観点からのコミュニティ型賃貸住宅の可能性
最近、賃貸住宅の災害対策について、特に共助の関係構築に注目して、調査研究を行ってきた中で、入居者同士あるいは入居者と地域住民との交流の...
-
2014年03月27日
まちづくりレポート|モノづくりのまちのまちづくり-東大阪市住工共生のまちづくり条例
■要旨モノづくりのまちとして有名な東大阪市は、2013年4月に、モノづくり企業の集積を維持しながら、良好な住環境の創出をめざして、「住...
-
2014年03月26日
シニア層の建て替え増加が意味すること-2012年における戸建注文住宅の動向
■はじめに2011年のレポートで予測したとおり2012年も「建て替え」が増加した。加えて、世帯主の平均年齢が高くなった。それには60歳...
-
2014年03月25日
アクティニアが住まいに求めるもの~首都圏112万のアクティニアに今後住み替えの可能性が~
■はじめに拙著「持ち家から賃貸に住み替えたアクティニア、その実態」では、持ち家や他のUR賃貸住宅からUR賃貸住宅に住み替えたアクティニ...
-
2014年02月28日
年代に応じて異なる住み替え派アクティニアの住まいへの要求~アクティニアもリノベーションに着目か~
■要旨拙著「アクティニアが住まいに求めるもの」では、今後、アクティニアのライフスタイルにフィットしない戸建持ち家から、賃貸住宅に住みか...
-
2013年11月28日
コミュニティ形成に期待される学生の力-地域の課題に向き合う再開発
先日、御茶ノ水駅のほど近くにある再開発施設「ワテラス」1で、4月にオープンして初めての避難訓練が行われた。この日は、土曜日ということも...
-
2013年11月08日
東京オリンピックと自動運転車と、都市の未来
筆者が小学校低学年くらいに手に取った子ども向けの乗り物図鑑に、未来の乗り物が未来都市のイメージと共に描かれていた。超高層ビルの間を縫う...
-
2013年10月16日
シニア層の建て替え増加が意味すること - 2012年における戸建注文住宅の動向
■要旨昨年のレポートで予測したとおり2012年も「建て替え」が増加した。加えて、世帯主の平均年齢が高くなった。それには60歳以上の増加...
-
2013年09月25日
素材の魅力を捉えて自由に発想する力 - 第3回産廃サミットから見えてきたこと
子どもがモノを使って遊ぶことの本質を理解した気がした。株式会社ナカダイ1主催の第3回産廃サミット2で開催された、「まちの保育園」3によ...
-
2013年09月12日
東京オリンピックと自動運転車と、都市の未来
筆者が小学校低学年くらいに手に取った子ども向けの乗り物図鑑に、未来の乗り物が未来都市のイメージと共に描かれていた。超高層ビルの間を縫う...
-
2013年07月05日
賃貸住宅の防災力を高めるために必要なこと
■要旨災害に対する備えに持ち家も賃貸も違いはない。建物そのものの安全性を高めること、被災後インフラ復旧まで生活できる最低限の物資を備え...
-
2013年04月23日
アクティニアが住まいに求めるもの ~首都圏112万のアクティニアに今後住み替えの可能性が~
■見出し1――はじめに2――アクティニアのボリューム3――アクティニアが求める住まい4――アクティニアが住まいに求めるもの5――おわり...
-
2013年04月17日
マンションの防災力を強化する本当のメリット-自治体によるマンション認定制度に期待
防災力を強化したマンションを認定する制度を導入する自治体が増え始めている。2009年度に大阪市が創設した「防災力強化マンション認定制度...
-
2013年03月28日
持ち家から賃貸に住み替えたアクティニア、その実態 ―アクティニアの住み替え誘導が、地域再生の担い手へと導く―
■見出し1――はじめに2――アクティニアの住み替え実態3――アクティニアが関心を寄せる仕事以外の活動4――アクティニアのニーズに応じた...
-
2013年03月15日
まちづくりレポート|都心と郊外、ふたつの再生戦略 -福岡市の都市再生と低層住宅地の容積率緩和
■見出し1――はじめに2――福岡市の概要3――都心部のまちづくり4――郊外住宅地の容積率緩和5――都心と郊外ふたつの再生戦略■はじめに...
-
2013年03月11日
まちづくり条例の魂を受け継ぐ ~復興過程のまちづくりに神戸市まちづくり条例が果たした役割に学ぶ~
神戸市まちづくり条例は、1981年に日本で最初のまちづくり条例として制定された。住民の意向を調整する場としての「協議会方式」とそれを提...
-
2013年03月11日
2011年における戸建注文住宅の動向 -5年ぶりに建て替え世帯が増加、震災を機に老後を意識した住まいに投資を高めるシニア層
■見出し1――戸建注文住宅の顧客実態調査とは2――2011年の戸建注文住宅新築世帯像3――建て替え世帯の特徴4――建て替え増加への期待...
-
2013年03月04日
減災まちづくりを普及させるために~減災の柱の一つ、住民の共助を促す住宅地開発~
今年、東京都立川市に減災の考え方を取り入れた住宅地が誕生する。減災の第一人者である関西大学社会安全学部の河田惠昭教授の監修の下に開発さ...
-
2013年03月01日
「すてる」と「つくる」をつなぐ仕事-アップサイクルによるモノづくりと、まちづくり
■見出し1――アップサイクルによるモノづくり2――「すてる」と「つくる」をつなげる事業者の取り組み3――アップサイクル5つの側面4――...
-
2013年02月28日
まちづくりレポート|都心と郊外、ふたつの再生戦略 - 福岡市の都市再生と低層住宅地の容積率緩和
■見出し1――はじめに2――福岡市の概要3――都心部のまちづくり4――郊外住宅地の容積率緩和5――都心と郊外ふたつの再生戦略■intr...
-
2013年01月29日
「すてる」と「つくる」をつなぐ仕事 - アップサイクルによるモノづくりと、まちづくり
■見出し1――アップサイクルによるモノづくり2――「すてる」と「つくる」をつなげる事業者の取り組み3――アップサイクル5つの側面4――...
-
2013年01月09日
保険と見守りによる高齢者居住支援策の推進~賃貸住宅における高齢者入居のリスクに備えて~
住宅セーフティネット法1や改正高齢者住まい法2の施行以降、高齢者に対する居住支援策が充実してきたが、今後ますます高齢者のみ世帯の増加が...
-
2012年10月31日
一戸建注文住宅取得層の若年化傾向を読み取る-2000年代における一戸建注文住宅の動向
12000年代における一戸建注文住宅の顧客動向をみると、顧客の低年齢化が特徴として挙げられる。その背景には、初めて住宅を取得する層(一...
-
2012年10月24日
減る屋上緑化、増える壁面緑化-都市緑化月間に屋上緑化を考える
10月は都市緑化月間に当たり、全国各地で様々な催しが行われている。そのようななか気になる調査結果を眼にした。都市緑化月間初日にプレスリ...
-
2012年10月09日
公共交通が便利な徒歩圏への、医療・介護施設の誘導
■見出し1――都市空間構造の再編と地域包括ケア推進体制2――医療・介護施設の誘導手法3――誘導手法導入の留意点4――高齢者福祉の推進体...
-
2012年10月01日
2011年における戸建注文住宅の動向~5年ぶりに建て替え世帯が増加、震災を機に老後を意識した住まいに投資を高めるシニア層~
■見出し1――戸建注文住宅の顧客実態調査とは2――2011年の戸建注文住宅新築世帯像3――建て替え世帯の特徴4――建て替え増加への期待...
-
2012年06月26日
公共交通が便利な徒歩圏への、医療・介護施設の誘導
■見出し1――都市空間構造の再編と地域包括ケア推進体制2――医療・介護施設の誘導手法3――誘導手法導入の留意点4――高齢者福祉の推進体...
-
2012年04月27日
一戸建注文住宅取得層の若年化傾向を読み取る ― 2000年代における一戸建注文住宅の動向
12000年代における一戸建注文住宅の顧客動向をみると、顧客の低年齢化が特徴として挙げられる。その背景には、初めて住宅を取得する層(一...
-
2011年12月26日
まちづくりレポート|官民一体でコンパクトなまちづくりへの挑戦を続ける富山市-中心市街地活性化のセカンドステージに向けて
富山市は、2011年度で第1期中心市街地活性化基本計画の計画期間末を迎えることから計画の事後評価を実施した上で第2期の計画づくりを行っ...
-
2011年11月11日
日本の復興をいわきから
9月に策定されたいわき市復興ビジョンの表紙には「日本の復興をいわきから」と力強く示されている。東日本大震災後、福島第一原発を中心に30...
-
2011年09月01日
先手を打つまちづくり―国有地処分における二段階一般競争入札方式に期待
横浜市みなとみらい21地区における未利用国有地の売却において、二段階一般競争入札方式が全国で初めて導入される。この方式は、まちづくりに...
-
2011年06月24日
アクティニアの新たな住宅選好とその影響
アクティニアとは、アクティブなシニアを意味する造語であり、「健康的で生活にある程度ゆとりがあり、知的好奇心を持って自立した生活を送って...
-
2010年09月24日
夢の実現を支える親の贈与
終の棲家に対する日本人の意識に関しては、多様化の兆しがみられるものの、今も一度は持ち家を取得したい、できれば戸建てが望ましいとの考えが...
-
2010年09月17日
都市ビジョンの重要性 ―まちを「こう変えたい」と意思表示する富山のマスタープラン
約6年ぶりに訪れた富山市は、市内中心部をLRT(次世代型路面電車)「セントラム」が環状運行しており、その車窓からの眺めは従来の市電やバ...
-
2010年06月25日
超高齢社会に求められる都市空間構造とは
■目次1--------はじめに2--------高齢者の特徴から求められる都市空間の条件と課題3--------集約型都市空間構造へ...
-
2010年06月10日
超高齢社会に求められる都市空間構造とは
■目次1――はじめに2――高齢者の特徴から求められる都市空間の条件と課題3――集約型都市空間構造への再編の有効性と政策的論点4――高齢...
-
2009年11月25日
都市計画マスタープラン改訂の課題 -ビジョン実現型都市づくりを担う市町村マスタープランの共有化に向けた改訂プロセス-
11992年の都市計画法改正により創設された市町村都市計画マスタープラン(以下、マスタープランと記述)は、法律上、都市計画を定める全て...
-
2009年01月26日
住宅耐震化の促進に向けて
47都道府県が策定した耐震改修促進計画を比較することで、都道府県により想定される地震被害の規模や耐震化の現状に違いがあることが分かる。...
-
2008年09月26日
7年後の耐震化率90%
2006年の改正耐震改修促進法により、都道府県に策定が義務付けられた耐震改修促進計画は、2007年度末までに47都道府県で策定が完了し...
-
2007年12月26日
賃貸版計画修繕積立制度の創設に向けて -賃貸住宅における計画修繕普及のための制度構築に関する研究-
平成18年に制定された住生活基本法において、量から質への住宅政策の転換が明確に打ち出され、それを受けた200年住宅ビジョンに謳われてい...
-
2007年11月26日
賃貸住宅長寿命化への処方箋
住宅を社会的資産と捉え、超長期に循環利用できる質の高い住宅ストックの形成が課題となっている。住宅の資産価値を長期にわたり維持するために...
-
2007年08月13日
耐震改修は地域の課題
耐震改修の促進には、工事に要する費用の一部を助成する補助制度などの経済的支援が効果的であるが、国土交通省の調べによると、今年4月の時点...
-
2007年08月06日
耐震改修の促進は市区町村の取組みから
新潟県中越沖地震では11人の命が奪われた。その内、建物の下敷きになって亡くなった方が9人に及んだ。全壊した住宅は1,069棟、半壊が2...
-
2007年06月29日
200年住宅ビジョン・賃貸住宅の長寿命化は計画修繕積立制度の確立から
昨月末に自民党が「200年住宅ビジョン」をとりまとめ公表した。これは、昨年6月の「住生活基本法」制定により、それまでの量の確保から、質...
-
2006年05月25日
都市計画マスタープランの実効性ある推進に向けて
1992年の都市計画法の改正により、市町村に策定が義務づけられた「市町村の都市計画に関する基本的方針」いわゆる市町村都市計画マスタープ...
-
2005年11月25日
災害時要援護者避難支援体制の確立に向けて
市街地整備などのハード面のまちづくりと、避難支援体制などのソフト面の整備とは、災害対策の両輪である。2004年7月の新潟・福島豪雨など...
コンテンツ紹介
-
レポート
-
受託実績・コンサルティング
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る