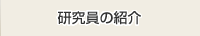- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 研究員の紹介 >
- 福本 勇樹
福本 勇樹のレポート
-

2025年08月15日
生成AIを金融リスク分析の視点から読み解いてみる-なぜ人間によるファクトチェックが必要なのか
近年、調査や研究の現場においても、生成AIの活用が急速に広がっている。壁打ちツールとして自身の思考を深めたり、要点を整理したりするだけ...
-

2025年07月08日
家計はなぜ破綻するのか-金融経済・人間行動・社会構造から読み解くリスクと対策
日本では、家計が深刻な資金難に直面した際の最終的なセーフティネットとして、自己破産と個人再生という二つの法的整理制度が用意されている。...
-

2025年06月24日
日本国債市場における寡占構造と制度的制約-金利上昇局面に見られる構造的脆弱性の考察
本稿は、日本国債市場における市場構造の寡占状況をハーフィンダール・ハーシュマン指数(HHI)を用いて定量的に分析し、金融政策の正常化局...
-

2025年06月12日
金融技術革新の4類型とその波及効果-キャッシュレス化にみる「制度から始まるイノベーション」の形
政府が掲げた「2025年6月までにキャッシュレス決済比率を40%程度に引き上げる」という目標は、2024年に前倒しで達成された。スマホ...
-

2025年06月04日
企業価値向上と家計の資産形成を結ぶ「人的資本」の役割
日本において「人的資本経営」が重要視されるようになり、企業が人的資本を適切に評価し、企業価値へと変換する仕組みを構築する中で、報酬制度...
-

2025年05月13日
家計はなぜ破綻するのか-金融経済・人間行動・社会構造から読み解くリスクと対策
自己破産は近年再び増加に転じており、2023年は前年比10%増であったが、個人再生は横ばいか微減であった。再建よりリセットを選ぶ傾向が...
-

2025年04月21日
日本国債市場は市場機能を回復したか-金融正常化における価格発見機能の構造変化
2024年3月、日本銀行はYCC(長短金利操作付き量的・質的金融緩和)を正式に解除し、金融政策は正常化フェーズへ移行した。本稿では、Y...
-

2025年04月08日
決済デジタル化は経済成長につながったのか-デジタル決済がもたらす新たな競争環境と需要創出への道筋
2019年6月、政府は「2025年6月までにキャッシュレス決済比率(民間最終消費支出に占めるキャッシュレス決済の割合)を40%程度にす...
-

2025年04月03日
家計債務の拡大と老後に向けた資産形成への影響
家計調査によると、49歳以下の世代では住宅ローン債務の拡大に伴い純金融資産のマイナス幅が広がる一方、50歳以上の世代では横ばいまたは増...
-

2025年03月26日
決済デジタル化は経済成長につながったのか-デジタル決済がもたらす新たな競争環境と需要創出への道筋
2019年6月、政府は「2025年6月までにキャッシュレス決済比率(民間最終消費支出に占めるキャッシュレス決済の割合)を40%程度にす...
-

2025年01月08日
勤労者世帯と勤労者以外の世帯の貯蓄構造と自助努力の重要性
家計調査によると、勤労者世帯の平均貯蓄額は1,474万円、勤労者以外の世帯は2,449万円である。この差は、雇用状況、社会保障や税制の...
-

2024年10月03日
市場参加者の国債保有余力に関する論点
2024年7月の金融政策決定会合にて、日本銀行は国債買入れの減額計画を決定した。国債市場では、日本銀行以外の市場参加者に国債保有余力が...
-

2024年09月06日
利上げによる住宅ローンを通じた日本経済への影響
長らく金利低下局面にあったことから、住宅ローン貸出残高の伸びが継続している。また、円安を背景とする建築資材価格の高騰、人件費の高まりな...
-

2024年06月28日
利上げによる住宅ローンを通じた日本経済への影響-住宅ローンの支払額増加に関する影響分析
低金利環境が長期化したことで住宅ローン残高に占める変動金利型の割合が拡大しており、日本銀行が利上げした際の住宅ローンを通じた経済への影...
-

2024年04月03日
GX経済移行債のグリーニアムの発生要因
2024年2月に日本政府によりクライメート・トランジション利付債が初めて発行された。流通市場では10年債では満期日が同じ利付国債との間...
-

2024年02月29日
マイナス金利政策を撤廃した際の長期金利水準を推定する-日銀の金融緩和政策による長期金利の下押し効果の測定
日本銀行が全ての金融政策を解除した場合に想定される長期金利の上昇幅について、統計的なモデルを構築して推定を行った。2024年1月末時点...
-
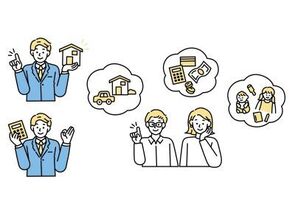
2024年01月09日
金商法等の改正(令和5年)が後押しする金融経済教育の推進
2023年11月に「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が可決、成立した。この法改正では、資産形成の支援に関する施策を総合的に推進す...
-

2023年10月04日
LDIショックにみる金利リスクへの対処の難しさ
2022年10月頃に生じた英国債市場の混乱では、中央銀行の金融引き締め策と政府による減税策が同時期に実施されて国債利回りが急上昇した。...
-

2023年09月07日
金融システムにおけるサイバーカスケード問題-シリコンバレーバンクの破綻事例から預金者行動について考える
2023年3月10日のSVB( シリコンバレーバンク)の破綻は、インターネットと金融システムとの深いつながりについて考えさせられる出来事...
-

2023年08月28日
金融システムにおけるサイバーカスケード問題-シリコンバレーバンクの破綻事例から預金者行動について考える
2023年3月10日のSVB( シリコンバレーバンク)の破綻は、インターネットと金融システムとの深いつながりについて考えさせられる出来事...
-

2023年07月12日
さらなるキャッシュレス化に向けた課題について整理する
政府は2025年の大阪万博までにキャッシュレス決済比率を40%とするKPI(重要業績評価目標)を掲げている。2022年のキャッシュレス...
-

2023年04月05日
金融政策の修正に対してデュレーション・マッチングは機能したか
市場予想に反して、日本銀行は2022年12月にYCC(イールドカーブ・コントール)を修正し、さらに2023年1月には共通担保オペの拡充...
-

2023年03月20日
さらなるキャッシュレス化に向けた課題について整理する(2)-さらなるキャッシュレス化に必要な施策について考える
キャッシュレス決済の利用は日本において日常的なものになってきているが、今後さらなるキャッシュレス化を実現するための課題や施策について整...
-

2023年03月20日
さらなるキャッシュレス化に向けた課題について整理する(1)-2022年の日本のキャッシュレス化の進展状況の振り返り
2022年のキャッシュレス決済比率を推定すると、分子のキャッシュレス決済額が前年比で約18%増加、分母の民間最終消費支出が約5%増加し...
-

2023年03月15日
金利先高観が強まる住宅ローン金利市場
2022年12月と比較して、2023年3月時点の期間選択型(10年)の住宅ローン店頭金利が、大手5行で平均で0.278%上昇するなど、...
-
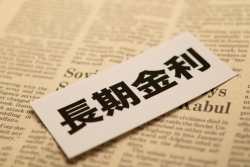
2023年03月13日
YCCを撤廃した際の長期金利水準を推定する-日銀の金融緩和政策による長期金利の下押し効果の測定
日本銀行が全ての金融政策を解除した場合に想定される長期金利の上昇幅について、統計的なモデルを構築して推定を行った。2023年2月末時点...
-

2022年11月08日
住宅ローン利用者は金利上昇に対してどのように備えるべきか
世界的なインフレ率の高まりを受けて、海外の中央銀行の多くが金融引き締めに舵を切っている。日本においてもエネルギーや食料品の価格上昇や円...
-

2022年10月24日
キャッシュレス化は本当に環境にやさしいのか
日本においても着実にキャッシュレス化が進展している中で、SDGsやESGの取組みにおいて、キャッシュレス化がサステナブルな社会の実現に...
-

2022年10月05日
世界経済の減速懸念とヘッジ付き外国債券投資への影響
インフレ率の高まりへの対応策として海外の主要中銀が金融引き締めに舵を切っている。金融引き締めによるインフレ抑制効果にはラグが見込まれる...
-

2022年08月31日
住宅ローン利用者は金利上昇に対してどのように備えるべきか
金利上昇を予測する住宅ローン利用者が増えている。変動金利型の住宅ローン金利は短期金利に連動し、固定金利型の住宅ローンは長期金利に連動し...
-

2022年08月26日
2021年の住宅ローン市場の動向と今後の注目点について-世界的なインフレに伴う金融引き締めと景気減速が懸念材料
個人の住宅ローン残高が増加傾向にある。その理由として、低金利環境の長期化、住宅ローン減税による順ざや、マンション価格の上昇が挙げられる...
-

2022年08月22日
決済手段の選択が「粋(いき)な計らい」になる日-2021年の日本のキャッシュレス化の進展状況の振り返りと今後の注目点について
2021年のキャッシュレス決済比率は、分子のキャッシュレス決済額が前年比で約10.6%増加、分母の民間最終消費支出が1.1%増加して3...
-

2022年08月16日
連続指値オペの導入効果-日銀の金融緩和政策による長期金利の下押し効果の測定
日本銀行が全ての金融政策を解除した場合に想定される長期金利の上昇幅について、統計的なモデルを構築して推定を行った。2022年7月末時点...
-

2022年07月14日
2022年の税制改正による住宅ローン契約者への影響-住宅ローン減税から得られる経済メリットの最大化問題について
2021年12月24日に閣議決定された令和4年度税制改正の大綱において、控除率の1%から0.7%への引き下げ、一般住宅の借入限度額の4...
-

2022年04月07日
日本銀行の金融緩和解除で長期金利はどの程度上昇するか-日銀の金融緩和政策による長期金利の下押し効果の測定
世界的にインフレ抑制のための金融引き締めが議論される中で、日本では1月の金融政策決定会合を前に、日本銀行が物価目標の2%に到達する前に...
-

2022年04月05日
日銀の金融政策正常化時にとるべき国内債券のアクティブ戦略
国内債券投資におけるイールドカーブの変動に着目したアクティブリターンの獲得方法として、デュレーションの調整、年限構成比の調整、債券種別...
-

2022年02月08日
日本銀行の金融緩和解除で長期金利はどの程度上昇するか-日銀の金融緩和政策による長期金利の下押し効果の測定
日本銀行が全ての金融政策を解除した場合に想定される長期金利の上昇幅について、統計的なモデルを構築して推定を行った。2022年1月末時点...
-

2022年01月18日
2022年の税制改正による住宅ローン契約者への影響-住宅ローン減税から得られる経済メリットの最大化問題について
2022年の税制改正において、住宅ローン減税が延長され、カーボンニュートラルに向けた省エネ住宅等に対する優遇が行われる一方で、控除率の...
-

2022年01月11日
変動金利型と固定金利型のどちらの住宅ローンを選択すべきか-市場動向から最適な住宅ローンの借入戦略について考える
住宅金融支援機構の「業態別の住宅ローン新規貸出額及び貸出残高の推移」によると、個人の住宅ローン借入残高は2021年3月末時点で約207...
-

2022年01月11日
コロナ禍で拡大した非金融法人による余資運用-民間非金融法人企業の余資運用に関する分析
コロナ禍において民間非金融法人企業の資金余剰が強まっており、現預金や有価証券投資といった金融資産の増加幅は(株式等を除く)金融負債の増...
-

2021年12月22日
2022年の米ドル円のヘッジコストに関する留意点-米国の金融政策と金融規制の動向に注視すべき
2021年11月末時点で米ドル円のヘッジコストは上昇傾向にあるが、年末特有の資金繰りに伴う一時的なものとみられる。来年以降は、米国の金...
-

2021年11月08日
変動金利型と固定金利型のどちらの住宅ローンを選択すべきか-市場動向から最適な住宅ローンの借入戦略について考える
個人の住宅ローン残高が増加傾向にある。その理由として、低金利環境の長期化、住宅ローン減税の順ざや、マンション価格の上昇が挙げられる。こ...
-

2021年10月05日
日銀の気候変動対応オペで期待されるESG債投資の拡大
日本銀行は2021年7月の金融政策決定会合において、気候変動対応オペの骨子素案を公表した。骨子素案によると、日銀のバックファイナンスの...
-

2021年07月01日
キャッシュレス化による経済成長への波及効果について考える-VARモデルによる日本のキャッシュレス化に関する分析
キャッシュレス化には現金を持ち運ぶ必要がなくなるなど、決済インフラの高度化によって社会全体が効率化するため、経済成長と何かしらの関連性...
-

2021年04月05日
NOMURA-BPI(総合)のリターン悪化の背景
国内債券の主要なインデックスであるNOMURA-BPI(総合)はこの1.5年間ぐらい下降トレンドにある。低金利環境の長期化による構成銘...
-

2021年03月18日
コロナ禍における日本のキャッシュレス化の進展状況
2020年のキャッシュレス決済比率は、キャッシュレス決済の決済額(分子)の増加と民間最終消費支出(分母)の減少によって、29%程度にま...
-

2021年02月16日
ヘッジコストの低下はいつまで継続するか
2021年1月末の米ドル/円のヘッジコスト(資金調達コスト)は2020年1月末と比較して1.6%低下して0.39%であった。ヘッジコス...
-

2021年02月03日
リスク・リターンの推移から日本国債への投資について考える
低金利環境が長らく継続したことで、日本国債の期待収益率は低下した。また、最終利回りの低下に加えて、債券発行時のクーポンの水準低下や償還...
-

2021年02月02日
米ドルLIBORの公表停止をめぐる市場予想の変化
2021年1月25日にISDAのプロトコルが発効された。これ以降、ISDAを参照してデリバティブ取引を行う場合、LIBORにリンクする...
-

2020年12月14日
米ドルLIBOR公表停止の延期案と金利市場への影響
2020年11月30日にICEが主要な米ドルLIBORの公表停止時期を2023年6月末まで延長する案を提示した。米ドルLIBOR公表停...
-

2020年07月16日
日本のキャッシュレス化の現在と未来-政府によるポイント還元策の導入効果に対する考察
日本政府は、クレジットカード、デビットカード、電子マネーによる決済を「キャッシュレス決済」と定義し、民間最終消費支出に対するキャッシュ...
-

2020年07月03日
日本銀行による国債買入れの今後の展望
日本銀行はイールドカーブコントロール導入後より長期国債の買入れペースを減少させてきたが、ネットベースでの買入れ方針について「80兆円め...
-

2020年05月25日
キャッシュレス化による感染症対策について考える-公衆衛生とデータ利活用に関する問題点の整理
「現金決済の公衆衛生上の問題点を解決する目的でキャッシュレス決済を推奨すべきかどうか」「感染症拡大を阻止する目的での購買履歴データの利...
-

2020年04月03日
家計債務からマイナス金利政策について考える
スウェーデン中央銀行は民間債務の膨張による副作用が無視できず、マイナス金利政策の解除に踏み切った。日本においても同様に、マイナス金利政...
-

2020年03月26日
ポイント還元策の導入効果と今後のポイント
2019年10月のポイント還元策の導入により、特にクレジットカードによる決済額が増加したことで、キャッシュレス決済比率は27%程度にま...
-

2020年02月05日
口座維持手数料を導入した場合に予想される投資行動の変化
銀行による口座維持手数料の導入について議論が盛り上がっているが、すべての預金口座に対して口座維持手数料が賦課されるには相当の時間がかか...
-

2020年01月30日
変動金利型住宅ローンの残高増加が家計支出に与える影響
低金利環境が長期化したことで、住宅ローン残高に占める変動金利型の割合が上昇している。変動金利型の選択は、金利上昇による利払い負担増のリ...
-

2019年08月30日
政府のポイント還元策に「割引」還元で対応するメリット-参加者のメリットを大きく左右する「ポイント失効率」の存在
2019年10月の消費増税に伴って、政府より「キャッシュレス・消費者還元事業」(いわゆる「ポイント還元策」)の導入が予定されている。2...
-

2019年08月07日
日本のキャッシュレス化の現在と未来-政府によるポイント還元策の導入効果に対する考察
日本では主に大手企業がキャッシュレス化を進展させているとみられる。日本は少子高齢社会にあり、近い将来訪れる労働人口減少の問題に対処して...
-

2019年07月03日
利回り確保が困難になったヘッジ付き外国債券
為替変動リスクを回避したヘッジ付き米国債利回りはマイナスの状態で推移している。この要因として、ヘッジコストが高止まりしていること、米国...
-

2019年06月11日
日本のキャッシュレス化の現在と未来-政府によるポイント還元策の導入効果に対する考察
2018年時点でキャッシュレス決済比率は24%にまで達しており、クレジットカード決済を中心に伸びている。しかしながら、海外各国のカード...
-

2019年04月03日
個人投資家の長期資産形成における金融リテラシー向上の重要性
海外の調査において、日本の成人で金融リテラシーのある人の割合が43%であったことが報告されており、他の先進国と比較して高いとは言えない...
-

2019年02月05日
銀行預金の東京一極集中に起因した金利低下圧力
個人名義の預金(個人預金)は、東京都に一極集中しつつある。東京都に集中した銀行預金の多くは、法人預金も含めて日銀当座預金に蓄積されてい...
-

2019年02月05日
2018年末に生じた長期金利の低下要因について-フォワードガイダンス導入時の政策変更に関する効果測定
フォワードガイダンス導入時の各種政策変更の影響を加味した重回帰モデルを構築して、長期金利に対するこれまでの日本銀行による金融政策の影響...
-

2018年12月07日
中小の小売店におけるキャッシュレス化のポイント
事業者サイドから見たキャッシュレス化のメリットとして、消費者の購買履歴データを分析することでマーケティングを高度化できること、現金取扱...
-

2018年10月16日
中小の小売店におけるキャッシュレス化のポイント
政府によるキャッシュレス化推進の施策は2014年に閣議決定された「日本再興戦略(改訂)」において、キャッシュレス決済の普及による利便性...
-

2018年10月15日
米ドル/円のヘッジコストが9月に高騰する理由
2018年9月の米ドル/円のヘッジコスト(米ドルの資金調達コスト)は、月末にかけて3.14%にまで急上昇し、ヘッジ付き米国債利回り(1...
-

2018年10月09日
キャッシュレス先進国にみる金融インフラの効率化
2018年4月に公表された「キャッシュレス・ビジョン」(経済産業省)では、キャッシュレス決済比率4割の達成目標を2025年としている。...
-

2018年08月15日
キャッシュレス先進国にみる金融インフラの効率化
2018年4月に経済産業省より公表された「キャッシュレス・ビジョン」では、大阪・関西万博(2025年)に向けて、キャッシュレス決済比率...
-

2018年07月10日
日本のキャッシュレス化について考える
2017年5月に日本政府は「Fintechビジョンについて」の中で、「キャッシュレス決済比率」を民間消費支出に占めるクレジットカード、...
-

2018年07月04日
英国事例に見るLIBOR廃止の年金運用への影響
2017年7月に英国の金融監督当局であるFCA(金融行為規制機構)は、代表的な金利指標であるLIBORを2021年末に廃止すると言及し...
-

2018年04月16日
米国債利回りと連動しなくなった日本国債利回り
日本国債利回りを米国債利回りで回帰すると回帰係数がゼロ近辺にあり、日本国債利回りと米国債利回りが連動しなくなっていると考えられる。主成...
-

2018年04月09日
マイナス金利政策による投資家の運用資産の保有割合の変化
マイナス金利政策導入後、日本の短期金融市場ではマイナス金利が常態化している。家計と確定給付年金は、現預金の保有にコストがかかるため、現...
-

2018年04月04日
マイナス金利が常態化した短期金融市場と現預金への影響
2016 年1 月末のマイナス金利政策の導入後より、日本の短期金融市場ではマイナス金利の状況が常態化しており、その背景として民間金融機関に...
-

2018年03月12日
利回り低下が継続するヘッジ付き米国債
ヘッジ付き米国債の利回りの低下傾向が継続している。ヘッジ付き米国債の利回りが低下している原因は、米国債利回りは上昇しているものの、それ...
-

2018年02月26日
負のタームスプレッドで取引される中期国債
マイナス金利政策導入後より、中期国債の利回りが翌日物金利(無担保コールレートやレポレート)よりも低い状態が継続している。海外投資家は、...
-

2018年02月07日
日本におけるキャッシュレス化の進展状況について-日本のキャッシュレス化について考える
2017年5月に日本政府は「FinTechビジョンについて」の中で、「キャッシュレス決済比率」を民間消費支出に占めるクレジットカード、...
-

2017年12月26日
米国債のフラット化の原因に対する仮説-タームスプレッドとユーロ建て米国債利回りに関する分析
最近、米国債のフラット化について議論されている。過去に米国債のイールドカーブが逆イールドになると景気後退が生じており、今回のFRBの利...
-

2017年12月25日
日本のキャッシュレス化に向けた課題-日本のキャッシュレス化について考える(3)
前々回、前回と、日本におけるキャッシュレス化の進展状況とキャッシュレス化することのメリットについてまとめてきたが、日本においてキャッシ...
-

2017年12月20日
キャッシュレス化のメリット-日本のキャッシュレス化について考える(2)
前回は、日本におけるキャッシュレス化の進展状況と海外との比較を行った。今回は、キャッシュレス化が進展することで、具体的にどのような便益...
-

2017年12月18日
日本におけるキャッシュレス化の進展状況について-日本のキャッシュレス化について考える(1)
2017年5月に日本政府は「Fintechビジョンについて」の中で、「キャッシュレス決済比率」を民間消費支出に占めるクレジットカード、...
-
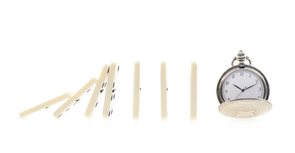
2017年11月27日
リーマンショック前の水準にまで上昇した米ドル円のヘッジコスト
2017年10月末の米ドル円のヘッジコストは1.91%で、リーマンショック前の水準にまで上昇している。2017年のヘッジコストの上昇は...
-
2017年10月19日
YCC導入後の20年国債金利-金融政策の出口に関する情報はどこに織り込まれるか
2016年9月のYCCとオーバーシュート型コミットメント導入後の20年国債金利の動向について考える。YCC導入後は、10年国債金利がゼ...
-
2017年10月16日
金融政策の超長期国債金利への影響について考える-金融政策による超長期国債金利の押し下げ効果の測定
20年国債金利を「10年国債金利」と「20年国債金利と10年国債金利の差分(スプレッド)」に分解して、物価の安定目標の導入による時間軸...
-
2017年10月04日
企業年金における積立比率の上昇要因と今後の留意点
過去5年間を振り返ると、割引率の低下により退職給付債務が拡大してきた一方で、運用環境の改善によってそれ以上に年金資産が拡大したため、積...
-
2017年09月25日
金融政策の10年国債金利への影響を振り返る-金融政策による金利の押し下げ効果の測定
イールドカーブ・コントロール(YCC)の影響を加味した重回帰モデルを構築し、過去1年間の金利推移とこれまでの日本銀行による金融政策の影...
-
2017年08月01日
主成分分析の観点から見た日本国債金利と米国債金利の連動性-アベノミクス下のイールドカーブの変化を振り返る
米国の金融政策では今後も利上げを行う方向性が示されている一方で、日本では異次元金融緩が継続されると見られている。日本国債金利と米国債金...
-
2017年07月21日
通貨スワップ市場の変動要因について考える-通貨スワップの市場環境が与えるヘッジコストへの影響
通貨スワップとは、米ドルや円といった異なる通貨のキャッシュフローを交換する取引のことである。通貨スワップは1年以上の比較的長期で取り組...
-
2017年04月24日
ヘッジ付き米国債の利回りに復活の兆し-日本円と米ドルの短期金融市場が示唆していること
昨年後半から、ヘッジ付き米国債の利回りが上昇している。利回り上昇の要因として、昨年末までは米国債利回りの上昇が寄与しており、今年に入っ...
-
2017年04月05日
予想インフレ率の上昇と運用資産への影響
昨年後半から、トランプ氏の大統領選勝利やFRBによる利上げ等をきっかけに世界的に予想インフレ率が上昇しており、日本にもその影響が及んで...
-
2016年10月25日
ヘッジ付き米国債利回りが一時マイナスに-為替変動リスクのヘッジコスト上昇とその理由
米国10年国債を為替予約(3ヶ月)で為替変動リスクをヘッジしたときの運用利回りが2016年9月末にマイナスになった。利回り低下の主な要...
-
2016年10月19日
通貨スワップ市場の変動要因について考える-通貨スワップの市場環境が与えるヘッジコストへの影響
リーマンショック後より、通貨スワップ市場においてクロスカレンシー・ベーシス・スワップ(スワップ・スプレッド)がマイナス方向に拡大し、現...
-
2016年09月29日
日本企業の信用リスクは磐石か-CDSスプレッドの縮小トレンドに潜む不安材料
新しく「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策が導入されたことにより、社債等の信用リスクを内包する金融商品が注目される可能性がある。...
-
2016年07月15日
利益調整に関する財務指標に着目した信用リスク分析(2)-Accruals Ratioと発行体格付けの関係
Accruals Ratioの発行格付けの関係について分析を行った。Accruals Ratioとは企業の営業活動と投資活動に関する指標で...
-
2016年07月13日
利益調整に関する財務指標に着目した信用リスク分析-「粉飾」に起因した企業倒産の予見は可能か?
帝国データバンクの『2014年度 コンプライアンス違反企業の倒産動向調査』によれば、日本においてコンプライアンス違反 に起因した企業倒産が...
-
2016年05月09日
量的・質的金融緩和政策導入後の年金運用資産の推移
2013年4月の量的・質的緩和政策導入後の企業年金と公的年金の資産推移を振り返る。両者とも年金資産全体(ストック)は増加しており、フロ...
-
2016年04月22日
対外証券投資と為替変動リスクのヘッジ-為替予約を用いたリスクヘッジの注意点
2013年4月の量的・質的金融緩和政策導入後、主要機関投資家が保有する対外証券投資残高は増加しており、円安や世界的な株高・金利低下の効...
-
2016年04月05日
為替スワップ取引を用いた時のヘッジコストの考え方
外貨を持たない国内投資家が外貨投資を行う際、為替リスクのヘッジのために為替スワップ等を用いて外貨調達を行うことがある。為替スワップ市場...
-
2015年10月26日
過度な利益調整は企業倒産の可能性を高めるかもしれない-ここ10年間の倒産企業に起きている変化
■要約昨今、粉飾起因の企業倒産が増加している。そこで、倒産企業の財務指標に変化が生じているか調査を行った。2005年前後を境に、「営業...
-
2015年10月19日
利益調整に関する財務指標に着目した信用リスク分析-「粉飾」に起因した企業倒産の予見は可能か?
■要旨ここ数年「粉飾」に起因した企業倒産が増加傾向にある。「粉飾」等により財務指標が「良く」なるように調整されている場合、通常の財務分...
-
2015年05月25日
資産形成の計画を練ると幸福度が向上するかもしれない?
2014年のPew Research Centerの調査1によると、日本は「先進国(Advanced)」の中で最も幸福度が低い国の一つであ...
-
2015年04月07日
通貨スワップ市場がもたらす外貨投資インセンティブの非対称性-外貨を保有する投資家にとって円建て資産への投資が魅力的な理由
1―はじめに日本の金利市場において金利低下が進んでいることから、「本邦投資家が利回り確保のために外国債券へのアロケーションを増やす」と...
-
2015年04月07日
為替市場の長期トレンドと「時間効果」の関係-長期トレンドはミクロな動的特性から形成される
過去の調査「円安になりやすい時間帯は存在するか?(1)(2)(3)」において、為替市場のもつマーケット・マイクロストラクチャーの特性と...
-
2015年04月03日
通貨スワップの市場環境とヘッジコストに与える影響について
米ドルと円を交換する通貨スワップ市場において、スワップ・スプレッドがマイナスの状況が恒常的に続いている。スワップ・スプレッドがマイナス...
-
2015年02月24日
通貨スワップ市場がもたらす外貨投資インセンティブの非対称性
■要旨日本の金利市場において金利低下が進んでいることから、本邦投資家が利回り確保のために外国債券へのアロケーションを増やすといった外貨...
-
2015年01月13日
円安になりやすい時間帯は存在するか?(3)-円安に対する米ドル高の影響を検証してみる
「円安になりやすい時間帯は存在するか?-米ドル/円の「時間効果」を計測してみる」では、米ドル/円について円安になりやすい時間帯の有無に...
-
2014年11月26日
円安になりやすい時間帯は存在するか?(2)-「時間効果」から得られる為替差益を計測する
前回の「円安になりやすい時間帯が存在するか?-米ドル/円の「時間効果」を計測する」では、少なくとも過去5年間の米ドル/円の動的特性につ...
-
2014年11月19日
円安になりやすい時間帯は存在するか?-米ドル/円の「時間効果」を計測してみる
2014年10月31日に日銀が追加金融緩和を決定した後、1週間で米ドル/円は一時115円まで円安が進んだ。2012年9月時点の米ドル/...
コンテンツ紹介
-
レポート
-
受託実績・コンサルティング
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る