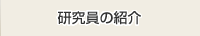- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 研究員の紹介 >
- 梅内 俊樹
梅内 俊樹のレポート
-
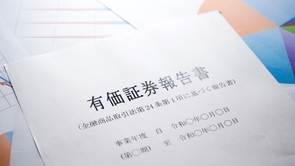
2025年07月16日
サステナビリティ情報開示の法制化の概要
国内で最初のサステナビリティ開示基準として、以下の3つの基準が2024年3月に公表された。今後は当該サステナビリティ開示基準(以下、S...
-

2025年04月03日
資産配分の見直しで検討したいプライベートアセット
米国の年金運用では、プライベートアセットへの投資が拡大している。伝統的資産とはリターン源泉が異なるプライベートアセット投資は、年金運用...
-

2025年02月28日
日本版サステナビリティ開示基準を巡る議論について-開示基準開発の経過と有価証券報告書への適用の方向性
国際サステナビリティ基準審議会(ISSB:International Sustainability Standards Board)が、サス...
-

2024年09月06日
持続的な発展に向けて-SDGsの先を見据えた継続的な取組が必要か?
5つの「P」で、どのようなワードを思い浮かべますか。資産運用にかかわる業務経験をお持ちの方であれば、運用評価において重要な要素となる、...
-

2024年09月05日
持続的な発展に向けて-SDGsの先を見据えた継続的な取組が必要か?
5つの「P」で、どのようなワードを思い浮かべますか。資産運用にかかわる業務経験をお持ちの方であれば、運用評価において重要な要素となる、...
-

2024年04月03日
私的年金の拠出枠組みについての更なる検討が必要
私的年金の2020年の制度改正や2021年の税制改正の最後を締めくくるものとして、今年12月に確定拠出年金の拠出限度額にかかわる新ルー...
-

2023年07月21日
IFRSサステナビリティ開示基準の概要-企業にも認められるグローバルスタンダード確立の意義
国際サステナビリティ基準審議会は6月26日、IFRSサステナビリティ開示基準を公表した。当該基準は、公開草案へのフィードバックを踏まえ...
-

2023年04月05日
「新しい資本主義」によるDC給付の底上げへの期待
新型コロナウイルス感染症の拡大から3年強が経過したが、この間のリスク性資産の騰落率は総じてプラスとなった。しかし、元本確保型商品のみで...
-

2023年02月01日
サステナビリティ開示の動向-国際サステナビリティ審議会の基準案および国内の取り組み
国際会計基準を策定するIFRS財団は、サステナビリティ開示基準の包括的なグローバルベースラインを提供することを目指し、国際サステナビリ...
-

2023年01月11日
バランスと協調-地球温暖化の原因と対応から考える
WMO(世界気象機関)とUNEP(国連環境計画)は、気候変動に関する科学的知見をとりまとめた報告書を作成し、各国政府の気候変動に係る政...
-

2023年01月06日
持続可能な食料システム-SDGs達成のための必要条件
人が生きていく上で必要不可欠な食料は、農業、林業、漁業、及び食品産業による生産・加工、流通、消費、廃棄といった一連の食料システムと呼ば...
-

2022年12月22日
バランスと協調-地球温暖化の原因と対応から考える
WMO(世界気象機関)とUNEP(国連環境計画)は、気候変動に関する科学的知見をとりまとめた報告書を作成し、各国政府の気候変動に係る政...
-

2022年10月31日
水関連のリスクについて
持続可能な世界目標(SDGs)では、6番目の目標として「すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する」が掲げられており...
-

2022年08月31日
ESGと企業価値
ESG投資の戦略ごとの残高推移によると、2012年においてはネガティブ・スクリーニングが7通りの投資戦略の中で最も残高が多くなっている...
-

2022年08月03日
改正が進むDC制度の更なる普及拡大に向けて
2020年以降、長期化する高齢期の所得環境の充実に向けて、確定拠出年金の制度改正が順次、施行されている。2024年までの一連の改正を通...
-
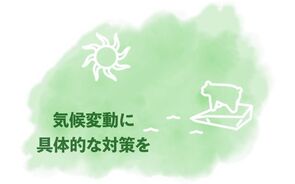
2022年06月30日
生物多様性とは-生物多様性を巡る動向及び持続可能な開発目標(SDGs)との関係
ESGの環境課題は多岐にわたるが、その一つに生物多様性の保全がある。人類は地球上の生物の一員として他の生物と共存しており、生物多様性に...
-

2022年05月31日
家計の現金・預金への偏重は解消されるか?
日銀の「2021年第4四半期の資金循環(速報)」によれば、2021年12月末時点の家計の金融資産残高は2,023兆円となり、史上初めて...
-

2022年04月28日
カーボンプライシングとは-脱炭素に向けた経済的手法の特長と課題および導入状況
気候変動の緩和に向けてCO2などの温室効果ガスの早急かつ大幅な排出削減が求められるなか、その実現に向けて注目される政策の一つにカーボン...
-

2022年02月16日
ESGと情報開示-国際的な開示基準の統一化で高まる気候関連情報開示
ESG投資の拡大に伴って、ESG要素に関する企業の情報開示を求める投資家等の動きが広がっている。こうした中、投資家等の要請に応えるべく...
-

2021年12月16日
ESG投資と超過収益-開示情報の拡充が好影響をもたらす可能性
「投資分析や意思決定プロセスにESG課題を組み込むことは、投資パフォーマンスの向上を図る上で欠かせず、受託者責任の観点からも求められる...
-

2021年10月14日
企業年金とESG投資-ESGを意識した経営の広がりで見直されるESG投資
わが国では、公的年金の運用を担うGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が2015年にPRI(責任投資原則)に署名したことを契機とし...
-

2021年09月29日
私的年金制度の普及に向けて-金融教育の実効性を高めることが重要
昨年、DC制度への加入・拠出に係わる規定の見直しが相次いで決定された。一連の改正を通じて、DC制度への実質的な加入範囲が広がるとともに...
-

2021年09月07日
ESGのGとは-重要視されるコーポレートガバナンス
ESGを構成するの3つの側面のうち、G(ガバナンス)を最も重視する機関投資家が多いことは各種調査で明らかになっているが、同様の傾向は企...
-

2021年08月31日
DB導入企業の積立状況-退職給付信託が積立比率の改善に寄与。しかし課題も。
日銀によって国内金利がゼロ近傍でコントロールされる状況が続き、分析対象企業の割引率の平均が0.6%弱の水準で安定するなか、退職給付債務...
-

2021年08月04日
米国における企業年金の受託者責任とESG投資の動向
米国では公的年金によるESG投資が着実に拡大する一方、企業年金においては目立った増加が見られない。背景には、受託者責任の観点でESG投...
-

2021年07月28日
ESGのGとは-重要視されるコーポレートガバナンス
ESGを構成するE(環境)、S(社会)、G(ガバナンス)の3つの要素のうち、ガバナンスを最も重視する機関投資家は多いが、上場企業の間で...
-

2021年05月25日
ESGのEとは-世界的に危機意識が高まる環境課題
ESGは2006年に国連が発表した責任投資原則(PRI)の中で提唱されたことを切っ掛けに、広く認識されるようになった投資判断の新たな観...
-

2020年12月25日
DC拠出限度額の見直しで重要性が高まる企業の取り組み
確定給付企業年金などの給付建ての年金制度(以下、DB)を実施する場合の企業型DCの拠出限度額は、企業型DCのみを実施する場合の拠出限度...
-

2020年10月27日
投資信託とは?~品揃えが豊富な金融商品
投資信託は、投資家から集めたお金をひとつの大きな資金としてまとめ、資産運用の専門家が株式や債券などに投資する商品で、その運用成果が投資...
-

2020年10月27日
つみたてNISAとiDeCoとは?~長期・積立・分散投資が可能な2つの非課税制度
つみたてNISAは、日本在住の20歳以上の方を対象とする少額から始められる積立投資の非課税制度です。毎年40万円を上限に投資信託を購入...
-

2020年10月27日
長期・積立・分散とは?~資産形成における基本的な投資方法
現在の金利環境では、預貯金だけでお金を増やすことはできません。しかし、投資となると、損が怖くて手を出せないといった方も多いのではないで...
-

2020年10月07日
公的年金の繰下げ受給って何?
わが国の公的年金は、日本国内に住む20歳以上の全ての人が加入する「国民年金(基礎年金)」と会社などに努める人が加入する「厚生年金」の2...
-

2020年10月07日
iDeCoの加入対象はどう変わるの?
iDeCoは個人型確定拠出年金の愛称ですが、確定拠出年金には個人型のほかに企業型があります。iDeCoが任意で個人が加入できる制度であ...
-

2020年09月30日
英国と日本の私的年金制度の加入状況について
英国では2013年以降、職域年金の加入率が飛躍的に上昇している。背景には、自動加入制度の導入がある。NESTの創設、職域DCのデフォル...
-
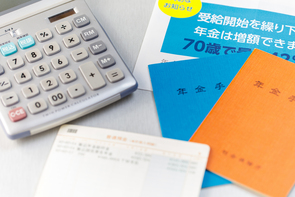
2020年08月31日
長生きリスクに備える繰下げ制度の利用拡大に必要なことは?
平均的な寿命の延びが見込まれるなか、想定を超える長生きに対して如何に生活資金を確保するかは、個人・家計においてはもとより、社会全体の課...
-

2020年08月05日
企業型DCの指定運用方法の選定について
企業型DCで指定運用方法の新たな枠組みが2018年5月から施行されている。これを契機に、投資信託が指定運用方法に選定されるケースが増え...
-

2020年06月01日
確定拠出年金法改正の概要-加入や受給に係る要件の緩和と、今後の課題-
年金制度を見直す年金制度改正法案が5月29日に成立した。高齢者の就労が拡大していることを踏まえるとともに、長期化する高齢期の経済基盤の...
-

2020年04月01日
年金制度改正案の概要
昨年9月以降にスタートした全世代型社会保障検討会議での議論を経て、雇用や年金制度に係わる改正案が国会に提出された。本稿では、近く成立が...
-

2019年11月25日
企業型DCの商品選び-効率的な資産形成に欠かせない投資信託の活用
今年6月、金融庁は「人生100年時代を見据えた資産形成を促す報告書」をまとめ、定年退職後30年生きるには、公的年金とは別に、夫婦で約2...
-

2019年08月30日
退職給付会計における割引率の動向
退職一時金や確定給付企業年金のように、従業員の退職に伴って予め約束された給付金を支払う給付建ての退職給付制度を導入する企業は、退職給付...
-

2019年08月05日
米国におけるESG 投資の動向について
米国最大の公的年金であるカルパース(カルフォルニア州職員退職年金基金)が主導する形で、ESG課題を投資に取り入れる動きが進む米国におい...
-

2019年06月28日
企業年金ガバナンスについて
企業年金におけるガバナンスは、最終受益者である加入者・受給者の利益を最大化する仕組みであり、その確保が企業年金の運営者には求められる。...
-

2019年05月31日
家計の保守的な投資行動の転換には投資教育の拡充が必要
日本の家計の金融行動が主要な先進国に比べ保守的であることは、以前より広く指摘されている。日銀によれば、日本では2018年3月時点で家計...
-

2019年05月10日
公的年金等に係る税制について
国民年金や厚生年金といった公的年金のほか、厚生年金基金や確定給付企業年金、確定拠出年金などから受け取る年金には、所得税が軽減される優遇...
-

2019年03月25日
公的年金等に係る税制について
国民年金や厚生年金といった公的年金のほか、厚生年金基金や確定給付企業年金、確定拠出年金などから受け取る年金には、所得税が軽減される優遇...
-

2019年02月05日
成熟度の高まりを考慮したDB運営
良好な運用環境を背景に、DBの平均的な積立状況は大きく改善している。その一方で、成熟度は高まっており、給付支払額が掛金収入額を上回るD...
-

2018年11月30日
圧縮進む退職給付に係る負債
確定給付型の企業年金や退職一時金制度を導入する企業は、退職給付に関する積立状況を母体企業の財務諸表に反映する必要がある。連結財務諸表に...
-

2018年07月31日
日米で異なる高齢期の収入構成
やや古い情報になるが、米国の従業員福利厚生研究所の2012年時点のデータによれば、65歳以上の平均収入において、公的年金が占める割合は...
-

2018年06月29日
DC制度の普及に向けた課題
DC制度を中心とする一連の普及・拡大策が5月までに施行された。しかしながら、公的年金を補完する制度してDC制度を普及させる上では、様々...
-

2018年06月05日
DC改正法施行後も求められる高齢期の所得確保策の検討
2016年5月に成立したDC制度の普及拡大を促す改正法が、この5月にすべて施行されるに至った。しかし、施行から1年半が経過する個人型D...
-

2018年02月28日
自ら備える長生きリスク
厚生労働省の資料によれば、大正時代(1920年)の夫の現役引退後の生活期間は1年、妻は5年というのが平均的な姿であった。しかし、200...
-

2018年02月05日
財政安定化に向けたリスク対応掛金設定の検討
株価上昇や円安の進展により、確定給付企業年金の平均的な積立状況は数年前に比べ大きく改善している。足もとの積立状況は、20年に一度の頻度...
-

2017年11月30日
DC運用の商品選択の改善に向けて
昨年成立したDC法改正では、個人型DCの加入範囲拡大が注目されることが多いが、それ以外にも多岐にわたる改正が盛り込まれている。DC加入...
-

2017年07月31日
iDeCoで株式投資
個人の資産形成において株式投資が拡大しない背景の一つに、国内株式が長期的な膠着状況から抜け出せないことが挙げられよう。TOPIXは20...
-

2017年06月30日
企業型DC運用改善に向けて
税制適格年金、厚生年金基金、確定給付企業年金(以下、DB)の3つの確定給付型企業年金の加入者数は年々減少する一方で、企業型確定拠出年金...
-
2017年04月28日
損失抑制に向けたDB運用-国内債券の保険的な役割の有効性や必要性を踏まえて
日銀の金融緩和政策がイールドカーブ・コントロールの導入によって大きく転換されるなか、市場金利の動きは、導入前と異なることが想定される。...
-
2017年02月03日
米国401(k) 加入者の2006年改革後の資産構成
米国401(k)では、20代の実質的な株式構成比率が高まっている。背景には、2006年の年金保護法を通じたDC制度の改革がある。日本で...
-

2016年11月30日
DCバランス型商品の選好と投資教育の必要性-DCの発展には投資教育の実施率向上だけでなく、内容面の拡充も欠かせない
DC制度には様々な運用商品がラインナップされているが、DC制度全体で見て、預金や生保商品などの元本確保型商品に次いで資産残高が多い商品...
-
2016年09月30日
導入迫るリスク分担型企業年金-DB制度改正(案)の概要とリスク分担型企業年金への移行時に留意すべきポイント
昨年度来、検討が進められてきた掛金の弾力的な拠出を可能とするリスク対応掛金と、この仕組みを活用した新たな制度としてのリスク分担型企業年...
-

2016年07月07日
個人型DCの加入対象拡大-改正法成立。当面の経済環境がDC 制度の行方を左右?
昨年4月に、確定拠出年金改正法案が国会に提出されてから1年強が経過し、漸く改正法が成立に至った。今回の改正は、DCの利便性向上や普及・...
-

2016年05月25日
個人型DCの加入対象拡大-改正法成立。当面の経済環境がDC制度の行方を左右?
昨年4月に、確定拠出年金改正法案が国会に提出されてから1年強が経過し、漸く改正法が成立に至った。今回の改正は、DCの利便性向上や普及・...
-
2016年01月06日
DB運用のリスク抑制に向けた更なる取り組みが必要
確定給付企業年金では、平均的な運用利回りが3年続けて10%近辺となる実績が続いた。一方で、市場の変動性が高い状況に収束の目処は立ってい...
-

2015年11月30日
長期積立てが重要な老後の備えを考える時機が到来-DC制度改正を控えて、自助努力を考える-
公的年金や企業年金は老後生活を支える貴重な制度です。ただし、公的年金はマクロ経済スライドという仕組みのもとで、向こう数十年かけて実質的...
-
2015年10月27日
受給権保護の実効性を高めるには利害関係者の意識が重要-加入者等への積極的な情報開示が受給権保護には欠かせない
■要旨確定給付企業年金(以下、DB制度)は、積立基準・受託者責任・情報開示など、受給権を保護する基準が明確化された企業年金制度である。...
-
2015年09月17日
リスク分担型DB(仮称)の導入意義とは-公的年金を補完する役割としてのDB・DC制度の違いから考える
■要旨社会保障審議会の下に設置された企業年金部会での議論が9月11日に再開された。今年1月に一旦打ち切られるまでに結論が得られなかった...
-
2015年09月03日
実績連動型CBプランとハイブリッド型の検討ポイント
ハイブリッド型企業年金の導入が検討されている。現行の制度体系で可能なハイブリッド型制度である実績連動型CBプランの特徴や導入状況を確認...
-
2015年05月29日
公的年金は増額傾向? 欠かせないデフレ脱却
昨年に引き続き、今年度も2%台の賃上げが実施される見込みである。ベースアップに踏み切る企業は全体の半数程度に留まりそうであるが、個人の...
-
2015年02月06日
利便性を高める確定拠出年金の見直しについて
1―はじめにこのほど、平成27年度の与党税制改正大綱が示された。この中には、昨年5月以降、社会保障審議会企業年金部会で議論され、一定の...
-
2015年01月07日
ダウンサイドの抑制に向けた動的管理の活用について
ダウンサイドの抑制は、年金運用の目標であり課題である。しかし、静的管理によって特徴付けられる現在の基本ポートフォリオ運営では、ダウンサ...
-
2014年12月16日
確定拠出年金の見直しの方向性について
■要旨現在、社会保障審議会に設置された企業年金部会で、企業年金を中心とする私的年金の今後の在り方等について議論されています。今年5月以...
-
2014年12月02日
資産形成の一手段ドルコスト平均法の注意点-市場への関心を深めることが欠かせない-
安倍政権発足以降の2年間で株価は大きく上昇した。とは言え、日経平均は2000年3月のITバブル時の高値を未だ下回ったままだ。しかし、そ...
-
2014年10月30日
企業年金の財政安定化に資する積立剰余の活用について
■要旨公的年金の減額・縮小が見込まれる中、民間サラリーマンの退職後の所得保障においては、資産残高53兆円と確定拠出年金の7兆円を大きく...
-
2014年06月04日
国際的な会計基準の統一に向けた日本の当面の対応について
退職給付に関する会計基準が2012年5月に改正され、2013年度より適用が開始されたこと等により、日本の基準とIFRSとのコンバージェ...
-
2014年05月30日
投資家別売買金額と株式市場-短期的な市場変動に惑わされない冷静さと慎重さが必要-
近年、国内株式市場では海外投資家の売買動向が注目されている。東証1部の売買代金に占める海外投資家の割合が5~6割にまで達し、その動向が...
-
2014年04月15日
退職給付会計基準改正の概要-2014年3月期以降の主な改正点と今後の方向について-
■要旨給付建て制度の会計処理の詳細を定める退職給付に関する会計基準が2012年5月に基準が改正(企業会計基準第26号「退職給付に関する...
-
2014年02月05日
キャッシュバランスプランの弾力化と運用リスク
キャッシュバランスプランの弾力化により、従前に比べ母体企業にとって運用リスク負担の軽い確定給付企業年金の導入に道が開かれることになる。...
-
2013年12月19日
成熟期の企業年金運用について-資産取崩しの影響を緩和するため求められる対応-
■要旨日本の将来推計人口をもとに、人数ベースの成熟度(加入者に対する受給者の割合)を計算すると、2030年代後半にかけて上昇することが...
-
2013年11月26日
個人の資産形成を見直す契機に
昨年の政権交代からおよそ1年が経過し、日経平均は60%強上昇し、円ドルレートも20%強円安が進みました。こうした市場環境の改善を受け、...
-
2013年10月16日
キャッシュバランスプランの弾力運営により見込まれる企業年金制度の多様化
■要旨わが国には確定給付型と確定拠出型の大きく分けて二つの企業年金制度があります。運用リスクを企業か個人かのいずれかが負担するという意...
-
2013年10月03日
割引率の水準で異なる金利上昇リスクへの対応
超低金利が続くなか、運用利回りの向上を目指す上では将来的な金利上昇に備えた国内債券運用が欠かせない。しかし今期末から始まる会計上の積み...
-
2013年05月30日
5月売り―相場格言からの上放れは可能か?
ウォール街でよく知られた株式市場にまつわる格言に、「Sell in May and go away(5月に株を売れ)」というものがある。イギリス...
-
2013年03月01日
企業価値評価から考える年金運用の在り方 ~あらためて基本に立ち返って考える~
昨今、確定給付型企業年金を維持・運営するための母体企業の負担の増大が懸念されている。こうした中、確定給付型企業年金の本来の導入意義を見...
-
2013年02月18日
債務指向運用への段階的な移行
■見出し1――はじめに2――退職給付会計の時価主義化3――即時認識における貸借対照表への影響4――市場金利に応じた段階的なポートフォリ...
-
2012年10月31日
大統領選挙と株価の動き―対照的な日本の現状-
株価は経済を映す鏡といわれるように、その時々の経済ファンダメンタルズを反映して、株価は形成されると考えられる。経済が好転すれば株価は上...
-
2012年10月01日
超低金利下における“守り”の運用スタンス
個別財務諸表での即時認識は見送られたが、財政上と会計上の2つの負債を意識した運用が引き続き求められよう。しかし現在の超低金利下でサープ...
-
2012年06月04日
悲観克服の経済効果は?
景気が良いとは、経済活動が活況を帯びている状況のことである。その活気は、国民一人一人の活力や気力が結集されて作り出されるものだ。極論す...
-
2012年02月24日
ダイナミック・ヘッジ活用とポートフォリオ管理について
現在のような低成長かつボラタイルな市場環境で中長期的な年金資産の成長を図るには、ポートフォリオのダウンサイド・リスクの抑制が不可欠であ...
-
2011年11月25日
高齢化時代の個人金融資産運用に求められる視点
■見出し1--------はじめに2--------現役世代の資産形成の一般的な考え方3--------現実の金融資産運用の世代別傾向...
-
2011年10月03日
退職給付会計上の積立比率の推移と今後の年金運用について
リーマンショックによって大きく悪化したものの、その後、退職給付会計上の実質的な積立比率は改善した。しかし将来的なポートフォリオ像を描き...
-
2011年08月31日
高齢化時代の個人金融資産運用に求められる視点
■目次1――はじめに2――現役世代の資産形成の一般的な考え方3――現実の金融資産運用の世代別傾向4――退職後世代の金融資産運用で認識す...
-
2011年08月01日
リバランス方法に見直しの余地はあるか?
政策アセットミックスを意識した一般的なリバランス方法は、常に有効に機能するとは限らない。リバランスによる結果とその意味を認識した上で、...
-
2011年01月04日
平常時と危機時を明確に区分したリスク管理
政策アセットミックスの決定に際しては複数のツールが活用される。漫然と複数のツールを利用するのではなく、『平常時』と『異常時』のリスクを...
-
2010年12月01日
グローバル株式指数による運用は効率的か?
年金ポートフォリオの株式の国内比率は低下傾向を辿っている。その1つの背景として、日本を含むグローバル株式指数をベンチマークとする運用の...
-
2010年11月24日
世界株式はアセットクラスとして有効か?
世界の株式の市場ポートフォリオでの運用、すなわち、国内外で区別をせずに株式を世界株式として1つのアセットクラスとする運用は有効だろうか...
-
2009年09月01日
配当の変化と株式リターンの関係について
増配が株式リターンにポジティブな影響を及ぼすことはよく知られているが、08年度については、正反対の傾向が見られた。その原因は急激な経済...
-
2009年08月26日
多角化戦略が企業の価値に及ぼす影響について
1多角化戦略が企業の価値を破壊することについては、過去の研究によって数多く報告されている。その大半は米国企業を対象とするものであるが、...
コンテンツ紹介
-
レポート
-
受託実績・コンサルティング
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る