- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >
- 高齢化問題(全般) >
- AIオンデマンド乗合タクシーの成功の秘訣(中)~全国30地域に展開するアイシン「チョイソコ」の事例から
AIオンデマンド乗合タクシーの成功の秘訣(中)~全国30地域に展開するアイシン「チョイソコ」の事例から

生活研究部 准主任研究員・ジェロントロジー推進室兼任 坊 美生子
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
チョイソコの収益性を上げるためには、全国展開と、サービスの多様化がカギ
加藤氏: 豊明だけだったら大変なことになりますよ(笑)。
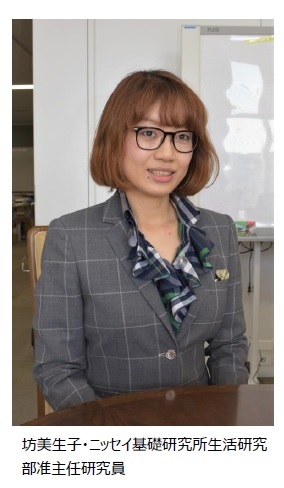 坊: 私は、企業が移動サービスを単体の事業として行うのは、なかなか難しいと思っています。大きな理由として二つのことが考えられます。一つ目は、企業が新規事業として移動サービスを始めようと思っても、既存の公共交通事業の乗客を奪って、地域から公共交通がなくなってはいけないということで、自治体や交通事業者などで構成する地域公共交通会議での協議が必要になり、運行エリアも運行時間も、利用対象者も限られてしまうということです。結果的に、自社の収益性確保のために、必要な運営条件をクリアできなくなる可能性があります。
坊: 私は、企業が移動サービスを単体の事業として行うのは、なかなか難しいと思っています。大きな理由として二つのことが考えられます。一つ目は、企業が新規事業として移動サービスを始めようと思っても、既存の公共交通事業の乗客を奪って、地域から公共交通がなくなってはいけないということで、自治体や交通事業者などで構成する地域公共交通会議での協議が必要になり、運行エリアも運行時間も、利用対象者も限られてしまうということです。結果的に、自社の収益性確保のために、必要な運営条件をクリアできなくなる可能性があります。二つ目は、人々は、移動というサービスに、そんなにお金を払わないということです。例えば、高齢者世帯がスーパーへ3日分の食料を買いに行って、3,000円以内で収めようというときに、タクシー代に1,000円使うかというと、なかなか使わない。移動サービスに支払う一人当たり単価が安いのです。大量輸送じゃないとなかなか成り立たない。
だから、交通事業のビジネスモデルと言えば昔から、私鉄であれば、沿線に住宅地や商業施設を開発して住む人を増やす、巨大なインフラビジネスとするか、バスであれば、収益率の高い高速バスや貸し切りバスで儲けて、採算の悪い路線バスを支え、自治体からも赤字補填してもらうという具合だった。でも今は、人口減少でインフラビジネスも難しい、コロナで高速バスや貸し切りバスも利用が激減しています。自治体の財政も厳しい。いわば、ビジネスモデルを失った状態です。今後、交通事業はどうしたら良いのか、という深刻な問題です。
本対談企画の別の会でも話したことですが、私はメディア出身なのですが、ニュースと移動は似ているところがあると感じています。ニュースも、移動と同じで、人々の生活に必要不可欠なものだと思いますが、安いお金しか払ってもらえない。記事を配信するためには、取材や編集、システムなどに大きな経費がかかるのですが、消費者は、ニュースはテレビやインターネット上で、無料で見る習慣がついてしまった。新聞のように紙で製作、販売して、大量に買ってもらえれば良いけど、ウェブ上の有料記事はなかなか買ってもらえない。だから、多くのネットメディアでは、人々に関心の高いニュースを無料で流して、ユーザーに自社のプラットフォームを訪れてもらい、別のサービスで課金して儲けている。
そのような仕組みを、フィジカル空間で行うのがMaaSかなと思います。移動サービスを軸に、他の物販やサービスを付加して売り上げを出していく仕組みです。アイシンは、既にチョイソコを使った様々なサービスを始められていますが、今後、どのようなビジネスモデルのイメージを描いていらっしゃるのでしょうか。
これまでチョイソコを3、4年走らせてみて分かったことは、いろいろな自治体さんが、いろいろなプライシング設定をするのですが、1回の利用料が500円を超えた瞬間に、利用が大きく落ち込む傾向があるということです。自治体さんは「タクシーより安いでしょ、500円で乗れるからいいじゃないの」と言うのですが、違うんですよ。お金がないじゃない訳じゃないが、往復1,000円払うことに一つの壁、抵抗感があるんだな、と感じています。これが200~300円なら乗るというところもある。
これはもう、文化と言える気がします。日本全国で同じなんですよね。移動に1,000円を出せないわけじゃないが、1,000円出すぐらいなら、もうちょっと行くのを我慢して、まとめて行こうという考え。でも我々としては、回数を多く乗ってもらわないと困ります。だから、シンプルに公共交通だけを運賃収入でやっていくという方法では、絶対に事業として成立しなくなってしまいます。
もちろん、地域ごとにカスタマイズすれば、いろいろなお金はかかりますが、まずは広げるのが大事ということになります。そして、広げれば広げるほどコストが薄まっていくのは事実ではありますから。我々が地域担当を作って、一生懸命全国を営業に回っているという訳は、そこにあります。一つの自治体に、担当の営業スタッフ2人を配置し、それ以外にもイベントの担当者も置いています。これが一つ目のポイントです。
また、乗合サービスだけで事業を成立させるのは無理だということは見えてきているので、いろんなサービスをやっています。「みちログ」と言って、車にカメラやセンサーをつけて、道路の破損のデータを自治体の土木課さんに送ったり、大気汚染センサーを付けたりしています。
それから、今年の下期に全国展開することが決定しましたが、まったく同じチョイソコのシステムで「めしクルー」という弁当宅配サービスをやります。これは初め、刈谷市でやっていたサービスですが、今年度中に全国展開します。これも、「ウーバーイーツ」や「出前館」と仕組みは同じですが、我々は車を使うので、50食でも一度に運べる。そのメリットを生かして、いろんな組み立てをしています。チョイソコシステムをちょっと変えているだけなので、追加費用も安くて済む。一番お金がかかったのはリーフレット代、という具合です。こういうところで収益を上げていく。
車椅子対応車両を2022度の実証実験で導入。一人で乗り降りできない高齢者もパイに取り込んでいく
 加藤氏: あとは、新たな移動需要を掘り起こしていくことです。今は、全国のオンデマンド交通で、車いす対象にしているところは、ほぼありません。なぜなら、車いすだと搭乗に時間がかかって他の人が待たないといけないから。でも、いつまでもそんなことを言ってると、健常者しか乗れない、それだと搭乗数が増えません。会員数が伸びません。会員数を増やすにはどうしたら良いかと言うと、車いす対応は避けられません。
加藤氏: あとは、新たな移動需要を掘り起こしていくことです。今は、全国のオンデマンド交通で、車いす対象にしているところは、ほぼありません。なぜなら、車いすだと搭乗に時間がかかって他の人が待たないといけないから。でも、いつまでもそんなことを言ってると、健常者しか乗れない、それだと搭乗数が増えません。会員数が伸びません。会員数を増やすにはどうしたら良いかと言うと、車いす対応は避けられません。車いすって重くて、1人で移動するのがめちゃくちゃ大変なんですよ。車いすを自分で動かして外出していると、筋肉むきむきになりますよ。100m先のバス停まで行くのもとても無理、という人がいっぱいいるんです。その点、デマンド交通だと、自宅への横着けでも何でもできる。その特長を生かさない手はないな、ということで、車いすの方に対して「停留所まで行かなくても、障がい者手帳を持っている方は、家の横まで行きますよ」とお知らせして、2022年度、埼玉県入間市で実証実験をすることにしました。
車いす対応ができるようになれば、今後高齢者が増えていっても、これまでは高齢者の中でもあくまで自力で歩ける人だけがチョイソコを利用できたところから、今後は一人で歩けない人まで乗れるようになる。そうすれば搭乗数が増えます。より多くの皆様に移動手段を提供していきたいのです。
加藤氏: 法律もだいぶ緩和されてきているので、荷物の発送先の個人情報さえ載っていなければ、乗客とも混載できます。宅急便と違って、弁当には住所も電話番号も書いていないので、パスタ屋さんやお好み焼き屋さんの弁当が一つの袋にどさっと入っていて、それを渡すだけですから、方法はあります。
坊: 全国で、チョイソコに関心を持っている自治体は多いと思いますが、導入に適した人口や面積、事業所の分布などがあれば教えてください。
加藤氏: 人口や面積等についての条件は、あまりありませんが、住民が1,000人を切る、世帯数が500世帯を割るようなところは、チョイソコを1台入れるともったいないので、トヨタさんの「地域の足」というプロジェクトを紹介しています。地域の足は、地域でボランティア運転手を募って、電話予約で受付する乗合タクシーのプロジェクトです。ただボランティア輸送は黒字には絶対にならないですが、住民の移動手段は確保できます。
坊: チョイソコを始めてみて、道路運送法の法規制や、地域公共交通会議の関係などで、驚いたこともあると思いますが、何か規制緩和への希望や、感想はありますか。
加藤氏: 法的なところは、これまでのスキームでクリアしてきたので、特段言うことはありません。いろんな地域から、導入に向けたご相談があった時も、基本は現行の道路運送法の3つの条項、4条(定期運行)か、21条(実証実験)か、78条(自家用有償旅客運送)のうち、自治体さんの状況を見て、適当なフレームを当てはめるようにしています。
ただ、ひとつ言えるなら、先ほどから出ている貨客混載の関係で、チョイソコを使って物販の収益性を上げていけるとかなり採算がよくなるので、その条件が緩和されると良いなと思います。現行法では、貨客混載が認められるのは「過疎地」のみですが、実際には、どんな大きな市でも、例えば岡崎市や豊田市もそうですが、交通不便な山奥がいっぱいあるんです。「過疎地」という規定があいまいなので、可能なら見直して頂ければと思います。
坊: 次に、豊明市の、移動サービスに取り組む交通事業者さんへの対応について整理したいと思います。まず、行政として利用促進に協力するということがあると思いますが、先ほど早川さんから、チョイソコの車両を増やすことは、予算上の問題から当面難しいので、ダイナミックプライシングなどの手法を用いて、乗合率を上げる工夫をしていきたいというお話がありました。
次に、交通事業者に補助金を出すことに対する市としての考えを教えていただきたいと思います。先ほど私は、ニュースと移動が似ているという個人的な意見を申し上げましたが、逆に、最大の相違点は、移動には経済外部性がある点だと思います。移動サービスの場合は、輸送によって、乗客が行った先の店で買い物をすれば、店も潤う。病院へ行けば、病院の報酬が増える。サービスの受益者が、地域に広く分布するという点です。そうであれば、地域全体で、つまり行政が、公的なお金を交通事業に支出する妥当性はあると思います。
川島氏: 住民の移動手段を確保することには、我々行政の責任も必ずあると思います。もし地域から交通手段がなくなると、街がどうなるかと考えると、大変なことです。地域の持続可能性のために、交通事業者が黒字なら補助金を出す必要はありませんが、赤字なら公的負担をすべきだし、実際に、どこの自治体も赤字路線に対しては補填して、何とか移動手段を確保しています。
ただ、重要なのは負担の割合、バランスだと思うんですよね。行政が出しすぎて、運賃をただにすれば良いという訳ではなく、エリアスポンサーからガンガンお金をもらって、行政は1円もお金を出さないというのもおかしい。地域の足を守るために、住民も事業者も行政も、皆である程度負担し合っていこうよと。その結果、交通事業者さんの利益にもつながるし、住民の移動手段も守れるし、持続的な街にもつながる。
多分、その負担割合が重要かなと思うんです。行政が負担すること自体は、住民も「そりゃ妥当だよね」と思っている。ただ、その額がでかすぎると「行政が出しすぎじゃない、もうちょっと利用者からお金もらったらいいんじゃない」という話になる。例えば、コミュニティバスでよくある、運賃100円というのは、個人的には安すぎるかなと思うが、200円だったら、残りは行政が出すか、地域の企業さんからもらってもいいんじゃないか、という考えもあります。
ちょっと話がそれますが、チョイソコは企業さんから協賛金をもらっていますが、スーパーは、加藤さんがおっしゃるようにリターンが無いんじゃないか、というお話がありましたが、豊明市公共交通会議で委員から出ていた意見で、「スーパーは車で大きな駐車場を整備して、多額の固定資産税を払い、車で来る人へのサービスは手厚い。その割に、車で来られない人へのサービスは何らしていない。だから協賛金を出してもらっても、公平性はあるんじゃないか」と言ってて、なるほどと思いました。
高齢者サービスに民間の力を使うことで、介護保険給付や税金の支出を減らせる
これは移動に限ったことではありませんが、今後、自治体にとっても企業との連携がこれまで以上に必要になってくるのではないかと私は思います。人口減少や東京一極集中で、地域から住民が減って、事業所が減って、行政の財政力も縮小していく。何でも地域で支え合わないといけない場面が増えてくるでしょう。そんな中で、行政もこれまで疎遠だった企業や団体とも、お付き合いを広げていかないといけないのではないでしょうか。
豊明市は、先ほど川島さんからご説明があったように、介護保険を使わずに民間の力で高齢者の健康増進を進めるということで、チョイソコに限らず、様々な民間企業と協定を結び、一緒にサービスをしていらっしゃいます。民間企業との良いお付き合いの仕方や、注意すべき点などがあれば、教えてください。
川島氏: 民間企業の力を使うことに関しては、行政は公平性を保たないといけないので、一企業の利益につながるようなことに積極的に手出しするのはどうか、という議論がよくあります。しかし我々にとっては、福祉の向上につながるなら、民間のどんな力を使っても公平性に問題はない。むしろ、民間の力を使わないで全部行政でやろうとすると、無駄な税金を使うことになる。
我々がやりたいのは、地域のために貢献してくれる企業さんをどんどん応援していこうよということです。その分、我々は税金を使わなくて済むので、お互いにとって良いはずです。別に一つの企業にだけどうのこうのではなくて、我々は、協力してくれる企業には全て門戸を開いています。だから、民間の活用は、積極的にやるべきじゃないかなと思います。その結果、域内の活性化につながるし、持続可能な街作りにもつながります。
(2022年02月07日「ジェロントロジーレポート」)
このレポートの関連カテゴリ
関連レポート
- AIオンデマンド乗合タクシーの成功の秘訣(上)~全国30地域に展開するアイシン「チョイソコ」の事例から
- 自動運転は地域課題を解決するか(上)~群馬大学のオープンイノベーションの現場から
- 自動運転は地域課題を解決するか(中)~群馬大学のオープンイノベーションの現場から
- 自動運転は地域課題を解決するか(下)~群馬大学のオープンイノベーションの現場から
- 過疎地において自動運転サービスは持続可能か(上)~レベル3の最前線・福井県永平寺町の取組みから~
- 過疎地において自動運転サービスは持続可能か(下)~レベル3の最前線・福井県永平寺町の取組みから~
- MaaSは超高齢社会の移動問題を解決するか~バス会社「みちのりホールディングス」の取り組みから考える~

03-3512-1821
- 【職歴】
2002年 読売新聞大阪本社入社
2017年 ニッセイ基礎研究所入社
【委員活動】
2023年度 「次世代自動車産業研究会」幹事
2023年度 日本民間放送連盟賞近畿地区審査会審査員
2023年度~ 和歌山市「有吉佐和子文学賞」意見聴取員
坊 美生子のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2025/09/10 | 女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |
| 2025/07/09 | 低所得の妻に「所得補償」を続けるのか、「生活再建」を促すのか~通常国会で法改正された「年収の壁」と「遺族年金」から考える~ | 坊 美生子 | 研究員の眼 |
| 2025/03/31 | 男女別にみたミドル(40代後半~50代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |
| 2025/03/17 | 男女別にみたシニア(50代後半~60代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |
新着記事
-
2025年09月17日
ふるさと納税「お得競争」の終焉-ポイント還元の廃止で問われる「地域貢献」と「持続可能な制度」のこれから -
2025年09月17日
貿易統計25年8月-関税引き上げの影響が顕在化し、米国向け自動車輸出が数量ベースで大きく落ち込む -
2025年09月17日
「最低賃金上昇×中小企業=成長の好循環」となるか?-中小企業に託す賃上げと成長の好循環の行方 -
2025年09月17日
家計消費の動向(二人以上世帯:~2025年7月)-実質賃金改善下でも「メリハリ消費」継続、娯楽支出は堅調を維持 -
2025年09月16日
インド消費者物価(25年9月)~8月のCPI上昇率は+2.1%に上昇、GST合理化でインフレ見通しは緩和
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【AIオンデマンド乗合タクシーの成功の秘訣(中)~全国30地域に展開するアイシン「チョイソコ」の事例から】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
AIオンデマンド乗合タクシーの成功の秘訣(中)~全国30地域に展開するアイシン「チョイソコ」の事例からのレポート Topへ


















 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




