- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 経済 >
- 日本経済 >
- 30歳代と50歳以上の物価上昇率格差は消費増税後に3%まで拡大
2020年01月17日
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
●30歳代と50歳以上の物価上昇率格差は消費増税後に3%まで拡大
(消費税率引き上げ後も低水準で推移する物価上昇率)
消費税率は2019年10月に8%から10%へと引き上げられたが、消費者物価上昇率は依然として低水準で推移している。消費者物価(生鮮食品を除く総合、以下コアCPI)は2019年4月の前年比0.9%をピークに消費税率引き上げ直前の9月には同0.3%まで伸びが鈍化していたが、税率引き上げ後の10月が同0.4%、11月が同0.5%と引き続き低い伸びにとどまっている(図表1)。
前回(2014年4月)の消費税率引き上げ時には、コアCPI上昇率が1%台前半から3%台前半まで跳ね上がった。今回の上昇率が低水準にとどまっている理由としては、(1)税率の引き上げ幅が小さかったこと、(2)食料(酒類と外食を除く)及び新聞に軽減税率が導入されたこと、(3)幼児教育無償化が導入されたことが挙げられる1。
ここで、消費税率引き上げ月のコアCPI上昇率を寄与度分解すると、前回(2014年4月)は消費税率引き上げが1.7%、その他が1.5%となっていた。一方、今回(2019年10月)は消費税率引き上げが1.1%、軽減税率が▲0.3%、幼児教育無償化が▲0.6%、その他が0.2%であった(図表2)。もともとの物価の基調が弱いことに加え、制度要因(消費税率引き上げ、軽減税率導入、幼児教育無償化)による押し上げ幅が小さいことが物価上昇率の低位安定につながっている。
なお、消費税課税品目のうち、電気代、都市ガス代、通信料(固定電話、携帯電話)等は、経過措置で新税率の適用が11月以降となる。課税品目すべてに新税率が適用された場合の消費税率引き上げによるコアCPI上昇率の押し上げ幅は前回が2.0%程度、今回が1.3%程度である。
消費税率は2019年10月に8%から10%へと引き上げられたが、消費者物価上昇率は依然として低水準で推移している。消費者物価(生鮮食品を除く総合、以下コアCPI)は2019年4月の前年比0.9%をピークに消費税率引き上げ直前の9月には同0.3%まで伸びが鈍化していたが、税率引き上げ後の10月が同0.4%、11月が同0.5%と引き続き低い伸びにとどまっている(図表1)。
前回(2014年4月)の消費税率引き上げ時には、コアCPI上昇率が1%台前半から3%台前半まで跳ね上がった。今回の上昇率が低水準にとどまっている理由としては、(1)税率の引き上げ幅が小さかったこと、(2)食料(酒類と外食を除く)及び新聞に軽減税率が導入されたこと、(3)幼児教育無償化が導入されたことが挙げられる1。
ここで、消費税率引き上げ月のコアCPI上昇率を寄与度分解すると、前回(2014年4月)は消費税率引き上げが1.7%、その他が1.5%となっていた。一方、今回(2019年10月)は消費税率引き上げが1.1%、軽減税率が▲0.3%、幼児教育無償化が▲0.6%、その他が0.2%であった(図表2)。もともとの物価の基調が弱いことに加え、制度要因(消費税率引き上げ、軽減税率導入、幼児教育無償化)による押し上げ幅が小さいことが物価上昇率の低位安定につながっている。
なお、消費税課税品目のうち、電気代、都市ガス代、通信料(固定電話、携帯電話)等は、経過措置で新税率の適用が11月以降となる。課税品目すべてに新税率が適用された場合の消費税率引き上げによるコアCPI上昇率の押し上げ幅は前回が2.0%程度、今回が1.3%程度である。
消費税率引き上げ時の価格転嫁率にも違いがある。消費税の課税品目の上昇率を税率引き上げ前後で比較すると、前回は消費税の課税品目(4月から新税率適用)の上昇率が3月の前年比1.0%から4月には同4.1%(+3.1%ポイント)となり、上昇率の拡大幅は消費税率引き上げ分(2.86%(=(1.08-1.05)÷1.05)を若干上回った。これに対し、今回は課税品目の上昇率が9月の前年比0.3%から10月には同1.7%(+1.4%ポイント)となり、上昇率の拡大幅は消費税率引き上げ分(1.85%(=(1.10-1.08)÷1.08))を下回った。
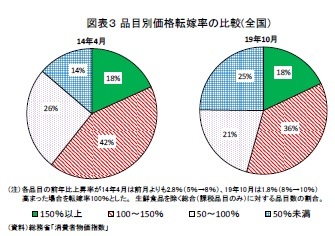 課税品目について、品目別の価格転嫁率を確認すると、転嫁率が150%以上の品目が18%(14年4月は18%)、100~150%の品目が36%(14年4月は42%)、50~100%の品目が21%(14年4月は26%)、50%未満の品目が25%(14年4月は14%)であった。半数以上(54%)の品目で上昇率の変化幅が消費税率引き上げ分と同じかそれ以上となったが、その割合は前回の消費増税時(61%)を下回った(図表3)。
課税品目について、品目別の価格転嫁率を確認すると、転嫁率が150%以上の品目が18%(14年4月は18%)、100~150%の品目が36%(14年4月は42%)、50~100%の品目が21%(14年4月は26%)、50%未満の品目が25%(14年4月は14%)であった。半数以上(54%)の品目で上昇率の変化幅が消費税率引き上げ分と同じかそれ以上となったが、その割合は前回の消費増税時(61%)を下回った(図表3)。前回の消費増税時には、政府は消費税の転嫁拒否や消費税分を値引きする等の宣伝・広告を禁止することによって、円滑な価格転嫁を促進することに軸足を置いていた。今回は税率引き上げの日に一律一斉に税込み価格の引き上げが行われないようにすることで、駆け込み需要と反動減を抑制することに重点を置いた。具体的には、「消費税還元セール」など消費税と直接関連した宣伝・広告は禁止する一方で、事業者の価格設定のタイミングや値引きセールなどの宣伝・広告自体を規制するものではないことを強調するなど、企業に柔軟な価格設定を認めていた。消費税率引き上げ時に税込み価格から税抜き価格に切り替えることなどで実質的に値上げをした品目も一部で見られたが、税込み価格を据え置くことなどで実質的に値下げした品目が前回増税時よりも多かったようだ。
1 キャッシュレス決済に対するポイント還元は実質的な値引きと考えられるが、ポイント還元は消費者物価指数に反映されていないため、ここでは取り扱わない。
(一部の世帯に限られる幼児教育無償化の恩恵)
前回の消費税率引き上げ時には物価上昇率が急速に高まったことにより、実質賃金が大きく目減りし、このことが消費低迷の長期化につながった。今回は名目賃金の伸び悩みは続いているものの、消費税率引き上げ後も物価上昇ペースがほとんど加速していないため、実質賃金の落ち込み幅は限定的にとどまっている(図表4)。
前回の消費税率引き上げ時には物価上昇率が急速に高まったことにより、実質賃金が大きく目減りし、このことが消費低迷の長期化につながった。今回は名目賃金の伸び悩みは続いているものの、消費税率引き上げ後も物価上昇ペースがほとんど加速していないため、実質賃金の落ち込み幅は限定的にとどまっている(図表4)。
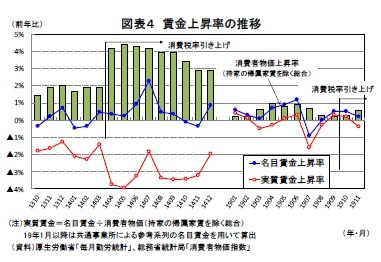 ただし、消費者物価を押し下げている幼児教育無償化の影響は一部の世帯に限られている。
ただし、消費者物価を押し下げている幼児教育無償化の影響は一部の世帯に限られている。消費者物価指数は家計調査(二人以上世帯)における2015年平均1ヵ月間の1世帯当たりの品目別支出金額のウェイトを基に算出されるが、これに加え、世帯属性別指数(ア 総世帯4中分類指数、イ 勤労者世帯年間収入五分位階級別中分類指数、ウ 世帯主60歳以上及び65歳以上の無職世帯中分類指数、エ 世帯主の年齢階級別10大費目指数、オ 住居の所有関係別10大費目指数)が作成、公表されている。このうちア~ウは月別、年平均が公表されているが、エ、オは年平均のみの公表となっている。
幼児教育無償化の対象となる世帯の割合は世帯主の年齢階級によって大きく異なるため、消費税率引き上げ後には物価上昇率の格差が拡大していることが見込まれる。そこで、月次ベースの年齢階級別の物価上昇率を試算した。
消費者物価指数において幼児教育無償化の対象となる品目は、幼稚園保育料(公立)、幼稚園保育料(私立)、保育園保育料の3品目で、それぞれのウェイトは0.03%、0.27%、0.53%だが、世帯主の年齢階級別指数では10大費目のウェイトしか公表されていない。一方、消費者物価指数のウェイトを算出する際の基となっている「家計調査」では年齢階級別の幼児教育費用、保育費用に対する支出ウェイトを求めることができる。消費者物価指数の幼稚園保育料、保育園保育料のウェイトは家計調査の幼児教育費用、保育費用を統合、配分することによって作成されている。
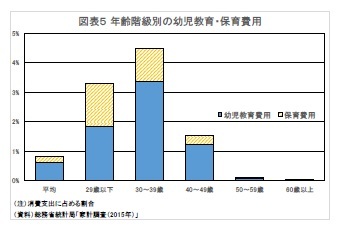 家計調査で年齢階級別の消費支出全体に占める「幼児教育費用+保育費用」の割合を、現行の消費者物価指数と同じ2015年平均でみると、最も高いのが30~39歳の4.5%でそれに続くのが29歳以下の3.3%、40~49歳の1.6%で、50~59歳(0.1%)、60歳以上(0.0%)になると幼児教育費用、保育費用はほぼゼロとなる(図表5)。
家計調査で年齢階級別の消費支出全体に占める「幼児教育費用+保育費用」の割合を、現行の消費者物価指数と同じ2015年平均でみると、最も高いのが30~39歳の4.5%でそれに続くのが29歳以下の3.3%、40~49歳の1.6%で、50~59歳(0.1%)、60歳以上(0.0%)になると幼児教育費用、保育費用はほぼゼロとなる(図表5)。10大費目については、総務省統計局から公表されている年齢階級別のウェイトを用い、幼稚園保育料(公立)、幼稚園保育料(私立)、保育園保育料の3品目については、家計調査における年齢階級別の幼児教育費用、保育費用の割合をもとにウェイトを調整する。その上で消費者物価指数の10大費目別指数、幼稚園保育料、保育園保育料の指数を用いて月次ベースの世帯主の年齢階級別・消費者物価上昇率を試算した2。
なお、消費者物価指数における幼稚園保育料(公立)、幼稚園保育料(私立)、保育園保育料の2019年10月以降の上昇率はそれぞれ前年比▲100%、同▲95.0%、同▲58.1%である。
2 年齢階級によって費目内の品目ウェイトが異なるため、年齢階級別の費目別指数の上昇率は異なるが、品目ウェイト、月次の費目別指数が公表されていないことから、ここでは幼稚園保育料が含まれる教育、保育園保育料が含まれる諸雑費以外は平均の費目別指数を用いた。
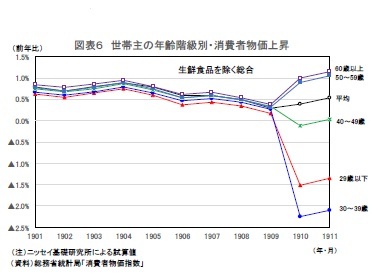 (世帯主30~39歳の物価上昇率は▲2%台のマイナス)
(世帯主30~39歳の物価上昇率は▲2%台のマイナス)このようにして求めた年齢階級別のコアCPI上昇率は図表6のとおりである。2019年9月までは年齢階級によって上昇率に大きな差はないが、消費税率が引き上げられた10月に格差が急拡大していることが分かる。平均よりも上昇率が高いのは50歳以上の世帯で、50~59歳、60歳以上の世帯では2019年11月にそれぞれ1.0%、1.1%となった。
49歳以下の世帯は平均を下回っており、幼児教育無償化の恩恵が最も大きい30~39歳の世帯では前年比▲2%台のマイナス、29歳以下の世代では同▲1%台のマイナスとなっている。50歳以上と30歳代では消費税率引き上げ後の物価上昇率格差が約3%まで拡大した。
消費税率引き上げ後の世帯主の年齢階級別・消費者物価上昇率を寄与度分解すると、それぞれの年齢階級別の支出ウェイトが異なるため、消費税率引き上げ、軽減税率導入の影響が若干異なる3が、その差はそれほど大きなものではない。圧倒的に差が大きいは幼児教育無償化の影響である。
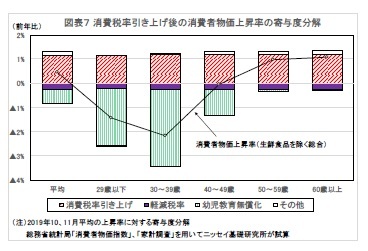 幼児教育無償化によるコアCPI上昇率の押し下げ幅は29歳以下が▲2.3%、30~39歳が▲3.2%、40~49歳が▲1.1%、50~59歳が▲0.1%、60歳以上が▲0.0%(数値は2019年10、11月の平均)である(図表7)。
幼児教育無償化によるコアCPI上昇率の押し下げ幅は29歳以下が▲2.3%、30~39歳が▲3.2%、40~49歳が▲1.1%、50~59歳が▲0.1%、60歳以上が▲0.0%(数値は2019年10、11月の平均)である(図表7)。幼児教育無償化の恩恵を大きく受けている世帯主39歳以下の世帯の割合は11.5%(29歳以下が1.5%、30~39歳が10.0%)にすぎない(2018年の家計調査(二人以上世帯)による)。一方、消費税率引き上げ後の物価上昇率が1%程度となった50歳以上の世帯の割合は70.0%(50~59歳が17.8%、60~69歳が22.8%、70歳以上が29.5%)である。消費税率引き上げ後の物価上昇率が低水準にとどまっているのは、一部の世帯の物価上昇率が大きく下がっているためで、全体の7割を占める50歳以上の世帯は1%程度の物価上昇に直面している。なお、この世帯割合は消費者物価指数に合わせて家計調査の二人以上世帯をもとにしている。幼児教育無償化の恩恵をほとんど受けない単身世帯を含めればその割合はさらに高くなる4。
3 たとえば、60歳以上の世帯は軽減税率の対象となる食料のウェイトが高いため、軽減税率導入による消費者物価の押し下げ幅は大きくなる。
4 「家計調査」によれば、単身世帯の割合は総世帯(二人以上+単身世帯)の3割強である。
(幼児教育無償化による消費押し上げ効果は限定的か)
幼児教育無償化によって消費者物価上昇率の平均値は大きく押し下げられているが、そのことが実質所得の上昇を通じて個人消費を押し上げることは期待できないだろう。幼児教育無償化で支払う必要のなくなった保育料のかなりの部分は貯蓄される公算が大きいためである。
幼児教育無償化によって消費者物価上昇率の平均値は大きく押し下げられているが、そのことが実質所得の上昇を通じて個人消費を押し上げることは期待できないだろう。幼児教育無償化で支払う必要のなくなった保育料のかなりの部分は貯蓄される公算が大きいためである。
(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。
(2020年01月17日「Weekly エコノミスト・レター」)
このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836
経歴
- ・ 1992年:日本生命保険相互会社
・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ
・ 2019年8月より現職
・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)
・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)
・ 2018年~ 統計委員会専門委員
斎藤 太郎のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |
| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |
| 2025/09/19 | 消費者物価(全国25年8月)-コアCPIは9ヵ月ぶりの3%割れ、年末には2%程度まで鈍化する見通し | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |
| 2025/09/17 | 貿易統計25年8月-関税引き上げの影響が顕在化し、米国向け自動車輸出が数量ベースで大きく落ち込む | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |
新着記事
-
2025年10月21日
インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 -
2025年10月21日
中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) -
2025年10月21日
今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】 -
2025年10月20日
中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -
2025年10月20日
ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【30歳代と50歳以上の物価上昇率格差は消費増税後に3%まで拡大】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
30歳代と50歳以上の物価上昇率格差は消費増税後に3%まで拡大のレポート Topへ

















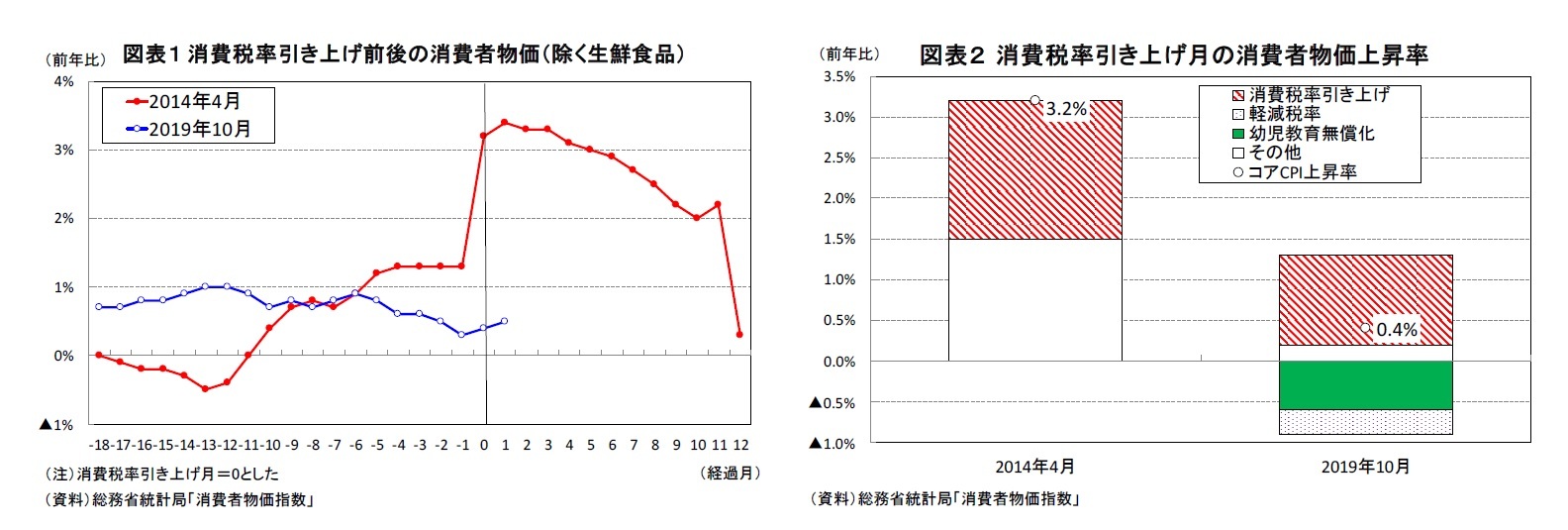
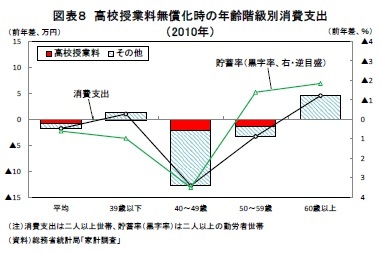
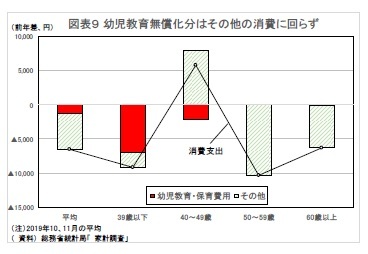

 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




