- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >
- 高齢者のQOL(生活の質) >
- 歩道領域の自動運転システム開発へ-利用者のラストマイルを支援しQOLを向上-
歩道領域の自動運転システム開発へ-利用者のラストマイルを支援しQOLを向上-

青山 正治
このレポートの関連カテゴリ
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
1 自動運転車の英語表記には、オートノマス・カー(autonomous car)やセルフドライビング・カー(self-driving car) など幾つかある。
2 MaaS(マース):Mobility as a Serviceの略。出発地から目的地までの移動ニーズに対して最適な移動手段をシームレスに一つのアプリで提供するなど、移動を単なる手段としてではなく、利用者にとっての一元的なサービスとして捉える概念。(出所:国土交通省「都市と地方の新たなモビリティサービス懇談会」資料より)。なお、直訳すれば「サービスとしての移動」。
1.自動運転のパーソナルモビリティの開発
 また、同社の製品開発のコンセプトは、障がいの有無や年齢に関わらず、だれもが楽しく安全に乗れるパーソナルモビリティの開発、普及を目標としている。勿論、介護保険の福祉用具貸与の対象であり、要介護者は安価なレンタル費で活用することも出来る。
また、同社の製品開発のコンセプトは、障がいの有無や年齢に関わらず、だれもが楽しく安全に乗れるパーソナルモビリティの開発、普及を目標としている。勿論、介護保険の福祉用具貸与の対象であり、要介護者は安価なレンタル費で活用することも出来る。さて、2019年初めに米国で発表した「WHILL 自動運転システム」は、「WHILL 自動運転モデル(プロトタイプ)」(図表1、2)と、複数の機体を管理・運用するシステムの2つから構成されている。
前者は外観の特徴として、自動運転のために左右のアーム(写真:ブルーの部分)の先端部に自動運転時の衝突防止や自動走行のためのステレオカメラが搭載されている。後者の複数機体を管理・運用するシステムは、複数人で移動する際や様々な活用方法が考えられ今後の開発を注目したい。
次に同社が考える「WHILL 自動運転システム」活用のイメージ図を2点見てみよう。
2.WHILLの活躍が期待されるMaaSのラストマイル問題
将来的に「WHILL自動運転モデル」が、様々な場所で活用されるシーンを期待したい。
3 通信事業や物流事業で使われる言葉で、事業者の最終拠点からエンドユーザー宅までの最も負荷のかかるサービス提供の距離を象徴的に「ラストワンマイル」と呼ぶが、実際に1.6キロメートルということではない。MaaSのサービスでは、サービスのシームレス化が重要なポイントであり、各交通サービスの結節点やファースト又はラストワンマイルのサービス提供が重要な解決課題となる。(本稿では「ラストマイル」と表記する。)
3.様々な取組が始まるMaaSについて
MaaSは基本的に、利用者を中心とした移動サービスの概念である。脚注2に定義を記したが、初めにユーザーは出発地から目的地までの最適な移動手段を検索する。そのため、様々な移動サービス事業者のデータの標準化とオープン化が必要であり、それらを一元的に管理し、経路検索・予約・決済を全てスマートフォンなどのアプリで実行可能とする。このためMaaSの実現化には、オープンデータの活用環境の整備や移動サービス事業者の協力体制、さらに対象地域全体への社会実装に向けた普及啓発が必要となる。勿論、地域ユーザー(利用予定のユーザーだけでなく非利用者へも)への普及広報や説明とともにインバウンド(複数の国の訪日外国人)への対応も重要な課題である。
この新しい移動サービスの概念は、数年前よりフィンランドのヘルシンキ市で取組がスタートしたマルチモーダルなサービス4である。その社会実装の進展による効果(マイカーの通勤利用者の減少等)も生じ、欧州の数カ国で取組が開始され、国内でも国の検討が実施されている。また、国内では2018年6月に閣議決定された「未来投資戦略2018」の複数箇所に「次世代モビリティ・システム」や「MaaS」の開発促進が記載され、複数の民間企業による実証試験に向けた動きも始まっている。
既に、従来の鉄道系のサービスでも、ICTの活用で、スマホで新幹線などのチケットが予約・購入でき、MaaS構築に向けての環境は各方面で徐々に整いつつあると思われる。しかし、様々な事業者が連携し、一元的なオープンデータの管理に向けた環境構築の合意形成とその実現には一定の時間を要すると推測され、中長期での取組が重要となろう。
4 複数の交通の連携を通じて、利用者のニーズに対応した効率的で良好な交通環境が提供されるサービス(国土交通白書などより)
今後、各方面でこのMaaSへの取組がさらに活発化すればラストマイルの課題解決が重要となる。
例えば、ユーザーが移動サービスアプリで検索した最終移動サービスの終点とユーザーの最終目的地の間に隙間や切れ目がある場合、そのラストマイルの解消は重要な解決課題である。
近年、このラストマイルの解決を目指し多数の企業が、一人~二人乗りの小型ビークルや6~8人乗りのゴルフカートを大きくしたような自動運転車、遠隔監視型のコミュニティバスを発表している。そして、国内の複数のテストエリアで自動運転等の実証試験が実施されている。
このほか、ホテルなどの宿泊施設内での車いすの利用を考えれば、廊下やドアの幅、さらに段差の課題がある。バリアフリー化され部屋の中で電動車いすの活用が円滑に行えれば、車いすを活用する宿泊客や車いすを活用する高齢の祖父母との家族旅行は一段と楽しくなろう。ラストマイルの課題解決に加え、建物や宿泊設備内のバリアフリー化のさらなる進展にも期待したい。
またMaaSは海外で一部で実現しつつあるものの、国内ではまだ開発段階であったり、実証試験前後の段階にある。当然、対象地域の状況は多様な都市構造や交通事情などが存在するため、理想的な唯一のMaaSの雛形が存在する訳ではない。さらに大都市と地方の中小都市とでは移動サービスの資源やユーザーのニーズも異なる。したがって、地域別モデルの検討や地域モデルの類型化の検討は重要であり、さらに既存の交通機関を中心とした検討に加え、今後の新たな自動運転車等のモビリティサービスを組込んだ検討も重要であると思われる。なぜならば、その様な検討が新たなモビリティサービスを実現する契機となる可能性もあり、今後の国や地方自治体の検討動向にも注目したい。
この地域ごとの検討においては、各サービス事業の関係者を中心とした検討だけではなく、地域の高齢者や障がい者、生活者(小学生くらいから大人まで)といったモビリティサービスのユーザーの意見をも反映してもらいたいと思う。
おわりに
<参照>
・WHILL Model Aについて(下記、P2)
基礎研レポート2016年05月26日
「新たな価値を提供する先進的な福祉用具 -ユーザー目線の開発がもたらす利用者のQOL向上-」
・WHILL Model Cについて(下記、P1)
基礎研レター2017年12月04日
「超高齢社会の人の“移動”を支援する機器開発の動き -モーターショーに見るパーソナルモビリティやコンセプトモデル-」
<参考資料>
1. 政府及び行政などの公表資料
・政府「未来投資戦略2018 -「Society5.0」「データ駆動型社会」への変革-」2018(平成30)年6月15日
・国土交通省「都市と地方の新たなモビリティサービス懇談会」(2018年10月17日~)等の公開資料
・ほか多数
2.ニッセイ基礎研究所「基礎研レポート(Web版)」
・「高齢社会の深化で必要性高まる多彩なハイテク福祉機器 -「H.C.R.2018」の開発最前線に見るアートやICT、IoTの活用-」(2018年12月18日)
・「介護ロボットの『導入・利用で考えられる課題・問題』の一部再考-「平成28年度介護労働実態調査」に見る導入状況と課題-」(2018年3月14日)
・「小型コミュニケーションロボットの活用に向けて-目指す活用シーンはビジネスからパーソナル、ホームと多彩-」(2016年12月27日)
・「ロボット介護機器(介護ロボット)の利用意向 -東京都の調査に見る現役世代の高い利用意向-」(2016年11月22日)
・「新たな価値を提供する先進的な福祉用具-ユーザー目線の開発がもたらす利用者のQOL向上-」(2016年5月26日)
・「福祉用具・介護ロボット実用化支援事業の現状と今後-介護現場との協働と共創が必須の介護ロボット開発-」(2016年2月3日)
3.ニッセイ基礎研究所 「基礎研レター(Web版)」※:紙出力の「ニッセイ基礎研REPORT」へ転載
※「超高齢社会の人の“移動”を支援する機器開発の動き –モーターショーに見るパーソナルモビリティやコンセプトモデル-」(2018年2月)
・「超高齢社会の人の“移動”を支援する機器開発の動き –モーターショーに見るパーソナルモビリティやコンセプトモデル-」(2017年12月4日)
・「ロボット介護機器の『重点分野』が改定され6分野13項目に -コミュニケーションロボットや排泄予測機器など1分野5項目を追加-」(2017年11月1日)
・高まる介護ロボット導入による『効果的な活用』への注目度 –多くの関係者が詰め掛けた『介護ロボットフォーラム2016』 -」(2017年3月30日)
・「技術革新が進む『障害者自立支援機器』の開発 –シーズ・ニーズのマッチングを促進する重要な取組-」(2017年2月13日)
4.ニッセイ基礎研究所 「研究員の眼(Web版)」
・「こどもたちの瞳に映る“介護の未来”シーン -厚生労働省の「こども霞が関見学デー」に見るこどもたち- 」(2018年8月30日)
・「ロボット介護機器の『重点分野』が改定され6分野13項目に -コミュニケーションロボットや排泄予測機器など1分野5項目を追加-」(2017年11月1日)
(※上記、レポート類及び、過去のレポート類は「執筆一覧」よりダウンロード可能)
(2019年03月05日「研究員の眼」)
このレポートの関連カテゴリ
青山 正治
青山 正治のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2020/05/21 | 赤ちゃんの明るい笑い声の力-本物でもヒーリング・ロボでもパワーは同じ- | 青山 正治 | 研究員の眼 |
| 2020/05/18 | サービスロボットやICTの新たな利活用分野-防疫対策でのICTやロボット技術活用の可能性- | 青山 正治 | 研究員の眼 |
| 2019/09/11 | 介護ロボットの導入・活用への着実な取組-東京都の「次世代介護機器の活用支援事業」への取組 | 青山 正治 | 研究員の眼 |
| 2019/07/11 | 新しい放送メディアの開発と超高齢社会での活用-4K・8Kの普及やパブリックビューイングの展開を期待 | 青山 正治 | 研究員の眼 |
新着記事
-
2025年10月14日
今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】 -
2025年10月10日
企業物価指数2025年9月~国内企業物価の上昇率は前年比2.7%、先行きは鈍化予想~ -
2025年10月10日
中期経済見通し(2025~2035年度) -
2025年10月10日
保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など -
2025年10月10日
若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【歩道領域の自動運転システム開発へ-利用者のラストマイルを支援しQOLを向上-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
歩道領域の自動運転システム開発へ-利用者のラストマイルを支援しQOLを向上-のレポート Topへ


















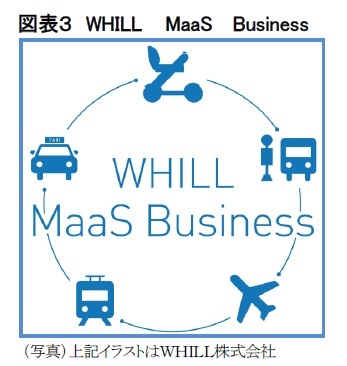


 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




