- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 社会保障制度 >
- 医療保険制度 >
- 地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は?
地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は?

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳
このレポートの関連カテゴリ
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
4――地域医療連携推進法人のメリット
以上のような事例を見ると、それぞれの「地域の実情」に沿って地域医療連携推進法人を活用している様子を読み取れる。これは制度創設時の経緯が影響していると考えられる。
具体的には、創設時の議論で営利性が排除されたものの、事業検討会の報告書で「非営利新型法人全体における研修を含めたキャリアパスの構築、医薬品・医療機器の共同購入、参加法人への資金貸付等を実施できるほか、介護事業その他地域包括ケアの推進に資する事業のうち非営利新型法人が担う本部機能に支障のない範囲内の事業について実施できる」という規定が入ったことで、目的が広範囲に広がり、地域から見ると使い勝手が良い仕組みとなった。
その結果、本来の目的として想定されていた病床融通や資材の共同購入などに限らず、医師不足の解消や病院統合の地ならしなど「地域の実情」に応じて、それぞれの地域で地域医療連携推進法人を活用できる余地が広がった。
しかし、こうした曖昧さは弱みにもなる。つまり、目的が明確になっていないケースでは、有効に使われない危険性がある。実際、2019年1月の連絡会議では「選択肢が広くなった代わりに、趣旨が曖昧になった」「どんな役割を果たすべきなのかを明確にしないと、予算付けなども曖昧になる」との声が出た11。言い換えると、連携の実績が少なかったり、関係者の機運が高まったりしていないような状況で、法人の設立を目的化しても、有効に機能するとは思えない。地域医療の再編や連携強化を図る一つのツールと位置付けつつ、「地域の実情」に沿って、上手く活用することが重要と言える。
11 2019年1月28日『m3.com』配信記事における日本海ヘルスケアネットの栗谷義樹代表理事の発言を引用。
一つの利点として、経営の透明性向上を指摘できる。日本は民間中心の提供体制であり、医師一人でも設立できる「一人医療法人」が多数を占めるなど、ガバナンス(統治)は十分と言えない12。
これに対し、地域医療連携推進法人の認定を受ける上では、業務などを定めた医療連携推進方針を都道府県知事に提出することが義務付けられる上、地域の医療関係者や学識経験者などで構成する評議員会の設置も求められる。さらに認定を受けると、医療連携推進方針や評議員会のメンバーなどが都道府県のウエブサイトに掲載される。この結果、外部の「目」が入りやすくなるため、医療提供体制の公共性を高める一つの方法と理解できる。
12 2023年改正医療法では、医療の本業で稼いだ「医業収益」「医業利益」や材料費、給与費、委託費などの情報提出が必須となり、属性などでグルーピングされた情報が公開される予定。
5――今後の展望
最後に、地域医療連携推進法人の今後を展望する。政府は「2040年」を視野に入れた医療・介護提供体制の見直し論議を本格化させており、今後も地域医療の再編論議が進む可能性が高い。具体的には、これまでは人口的にボリュームが大きい「団塊の世代」が75歳以上になる2025年をターゲットに据え、地域医療構想などの提供体制改革が意識されていたが、その年が到来したため、政府は基本線を維持しつつ、その期限を2040年に伸ばそうとしている。特に、2040年頃には人口的にボリュームが大きい「団塊ジュニア世代」が引退し始めるため、人材不足が深刻化することが予想されているほか、独居の認知症高齢者など複雑・困難な事例が増える可能性が高い。
そこで、社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)医療部会が2024年12月、「2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見」(以下、総合的な改革意見)を公表し、2040年を意識した「新たな地域医療構想」がスタートすることになった13。
つまり、地域医療の再編論議は今後も続く可能性が高く、こうした中で地域医療連携推進法人は重要なツールになる可能性を秘めている。実際、経済財政政策の方向性を示す2025年6月の「経済財政運営と改革の基本方針」(いわゆる骨太方針)では、2040年を想定した提供体制改革の一環として、地域医療連携推進法人の活用が言及された。
しかし、2040年を想定した総合的な改革意見では、なぜか「地域医療連携推進法人」が言及されていない。こうした不整合は分かりにくく、議論の整理が必要であろう。
13 2024年12月の取りまとめを基に、2025年通常国会に医療法改正案が提出されたが、継続審査となった。今後、都道府県は2026年度に新たな地域医療構想を策定し、2027年度から協議を始める予定。さらに、介護・福祉分野でも2025年7月に「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ」が公表され、人口減少地域を対象にした特別な報酬体系の必要性などが示された。
今後、特に重要になるのが人口減少局面における活用と思われる。人口減少地域では、医療機関が患者獲得を巡って争うよりも、関係者が連携しつつ、人材、物、資金を有効に活用する必要がある。さらに、採算が取りにくい地域や診療科については、民間医療法人に担ってもらう局面も予想される。こうした中、関係者が意思疎通を図れるとともに、公共性を担保しやすい地域医療連携推進法人の枠組みが有効になると思われる。
実際、好事例とされる日本海ヘルスケアネットが紹介される雑誌記事などでは、「医療資源の少ない地方では消耗戦の時代はもう終わりです。地域全体の最適化を見据えて、肩を寄せ合って助け合わないともう生き残れません」「(注:人口減少を踏まえて)今後は事業をどう畳んでいくかの”撤退戦”になります。地域にとって最適化された医療・介護資源、仕組みを次の世代に渡すためのツール」といった発言14が繰り返し紹介されている。
14 2023年8月号『日経ヘルスケア』における栗谷氏の発言を引用。
さらに、2040年を意識した一段のテコ入れ策として、インセンティブ設計が考えられる。例えば、現時点では税制上の優遇措置や予算面での支援などが実施されておらず、一つの選択肢として検討できる。診療報酬でも加算(ボーナス)の要件に設定するなどの選択肢も考えられる。
このほか、一定規模の定住が見込まれるのに、医療機関の減少スピードが早い地域を対象にしたテコ入れ策15のツールとして、地域医療連携推進法人を活用できるのではないだろうか。例えば、人口減少地域での地域医療連携推進法人に対する診療報酬に関しては、検査など治療行為ごとに評価する出来高払いではなく、地域の人口などに応じて支払う包括払いに切り替える方法である。
これには少し解説を要する。現在、身近なケガや病気に対応する開業医や中小病院に対する診療報酬は出来高払いが中心となっているが、これでは人口が減少する局面で医療機関が十分な患者と診療報酬を確保できなくなる可能性が高まる。その結果、医療機関の縮小、撤退、廃止といった事態も懸念される。
このため、人口が著しく減っている地域で、かつ周辺地域の提供体制で中心的な病院や診療所については、高齢者の集住や医師偏在対策の強化などの選択肢と絡めつつ、出来高払いではなく、周辺の人口などを考慮した包括払いも検討する必要が出てくると考えている。つまり、地域医療連携推進法人への参画を要件とし、同法人を核にしつつ、地域の医療提供体制を効果的かつ効率的に維持するイメージである。
もちろん、これは全国一律を前提とした現行の診療報酬制度から逸脱しており、日医が反対している地域別診療報酬制度に繋がる考え方である16。さらに包括払いの下では、必要な治療が実施されない「過少診療」が起きるリスクもある。このため、一部で出来高払いを絡めたり、成果(アウトカム)で支払う成績払いを採用したりする必要もある。
このほか、地域での医療行政を司る都道府県や保険者(保険制度の運営者)との関係とか、既存制度との整合性など整理しなければならない問題も多い。
しかし、報酬制度の見直しなども絡める形で、人口減少地域における医療機関の再編や機能維持を図る一つのツールとして、地域医療連携推進法人を一層、活用することは検討に値すると考えられる。
15 2024年12月に示された「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」では、一定規模の定住が見込まれるのに、医療機関の減少スピードが早い地域について、都道府県が「重点医師偏在対策支援区域」として設定し、施策を重点化する方向性が示された。2027年度から具体的な対策が進む見通し。パッケージ策定に至る経緯や論点については、2024年11月11日拙稿「医師の偏在是正はどこまで可能か」を参照。
16 地域別診療報酬制度は2008年度改正から導入され、「1点=10円」と定められている全国一律の診療報酬点数を都道府県の判断で調整できるようになった。さらに、奈良県が都道府県内で負担と給付の関係を完結させる手段として活用する考えを示したが、日医が猛反対した。その後、奈良県知事の交代などで沙汰止みになったが、財務省は2024年5月の財政制度等審議会(財務相の諮問機関)で、医師偏在是正の手段として地域別診療報酬制度を活用することを提案した。筆者自身は様々な論点をクリアする必要があるものの、「地域単位で負担と給付の関係を明確にする究極的な手段」として、検討に値すると考えている。2024年7月17日拙稿「全世代社会保障法の成立で何が変わるのか」を参照。
6――おわりに
さらに、一層のテコ入れ策を意識するのであれば、予算や税制、診療報酬によるインセンティブ設計なども論点になる可能性がある。特に、2040年の提供体制改革では、人口減少を見据えて今まで以上に「撤退戦」が求められるため、地域医療連携推進法人を活用した制度設計も検討する必要がある。
(2025年10月28日「保険・年金フォーカス」)
このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1798
- プロフィール
【職歴】
1995年4月~ 時事通信社
2011年4月~ 東京財団研究員
2017年10月~ ニッセイ基礎研究所
2023年7月から現職
【加入団体等】
・社会政策学会
・日本財政学会
・日本地方財政学会
・自治体学会
・日本ケアマネジメント学会
・関東学院大学法学部非常勤講師
【講演等】
・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数
・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)
【主な著書・寄稿など】
・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)
・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)
・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)
・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)
・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数
三原 岳のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? | 三原 岳 | 保険・年金フォーカス |
| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |
| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |
| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |
新着記事
-
2025年10月28日
試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -
2025年10月28日
地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -
2025年10月28日
東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -
2025年10月28日
今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -
2025年10月27日
大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は?のレポート Topへ

















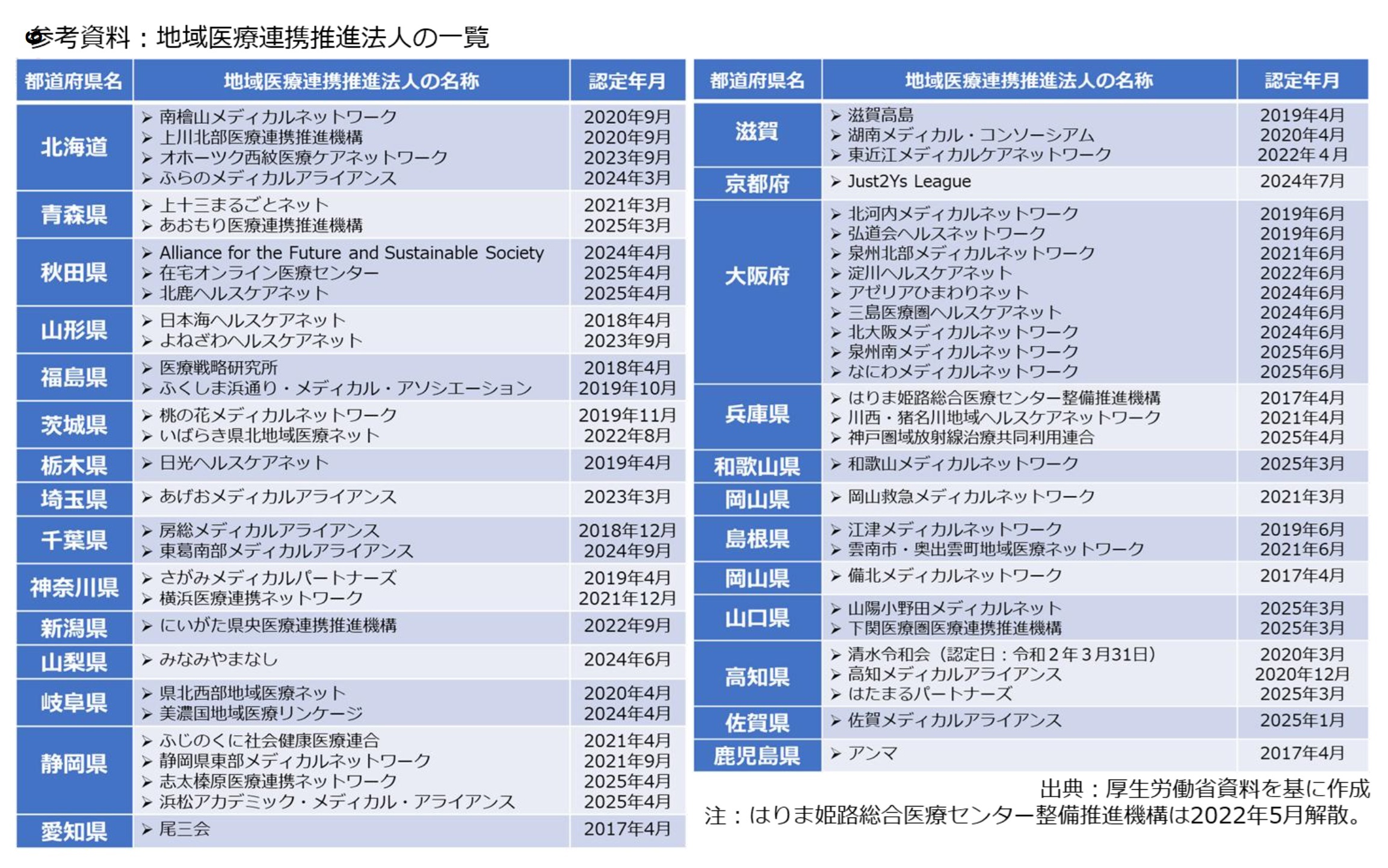

 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




