- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 経営・ビジネス >
- 法務 >
- 米国でのiPhone競争法訴訟-司法省等が違法な独占確保につき訴え
2024年04月24日
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
Appleは独自のデジタルウォレットとして、Apple WalletをiPhoneに搭載しており、支払にはApple Payでデジタル決裁を行う。他方、サードパーティのデジタルウォレットにはiPhoneではタップ・トゥ・ペイが行えないように妨害を行っている。
Apple Wallet を利用するiPhone利用者がAndroid端末に移行する際には特定の認証情報や個人データへのアクセスを失う可能性がある。他方、クロスプラットフォームのデジタルウォレットができれば同じカード、ID、支払履歴、P2P決済の連絡先等の情報が利用できるため、スマートフォン間の乗り換えが容易になる。
しかし、iPhoneはApple WalletのApple Payにしかタップ・トゥ・ペイ機能を有していないため、独占状態であり、他のサービスに乗り換えるのには困難を伴う。AppleはApple Payによる支払いに関して、銀行に0.15%の決済手数料を要求してきた。比較して、サムソンやGoogleの決済アプリは銀行に手数料を課していない。
AppleはそもそもApple Pay以外にタップ・トゥ・ペイを認めてこなかったが、欧州ではApple Pay以外にも認めるとの意向である。
Appleはまた、他のデジタルウォレットがAppleのアプリ内決済(IAP)の代替となることを阻止している。Appleはサードパーティがその運営者のアプリで代替の支払手段でより安い価格で直接支払いを行うことを禁止している21。
20 前掲注1 p43参照
21 前掲注1 p46参照
Apple Wallet を利用するiPhone利用者がAndroid端末に移行する際には特定の認証情報や個人データへのアクセスを失う可能性がある。他方、クロスプラットフォームのデジタルウォレットができれば同じカード、ID、支払履歴、P2P決済の連絡先等の情報が利用できるため、スマートフォン間の乗り換えが容易になる。
しかし、iPhoneはApple WalletのApple Payにしかタップ・トゥ・ペイ機能を有していないため、独占状態であり、他のサービスに乗り換えるのには困難を伴う。AppleはApple Payによる支払いに関して、銀行に0.15%の決済手数料を要求してきた。比較して、サムソンやGoogleの決済アプリは銀行に手数料を課していない。
AppleはそもそもApple Pay以外にタップ・トゥ・ペイを認めてこなかったが、欧州ではApple Pay以外にも認めるとの意向である。
Appleはまた、他のデジタルウォレットがAppleのアプリ内決済(IAP)の代替となることを阻止している。Appleはサードパーティがその運営者のアプリで代替の支払手段でより安い価格で直接支払いを行うことを禁止している21。
20 前掲注1 p43参照
21 前掲注1 p46参照
6――Appleの独占力の不当な維持(まとめ)
以上の通り、AppleはiPhone利用者がiPhone以外への機器への乗換を阻害する行為に出ている。このほかにも、クロスプラットフォームの位置追跡可能な機器を弱体化させた。また、クロスプラットフォームのビデオコミュニケーションアプリを妨害する一方で、利用者を自社のビデオコミュニケーションアプリであるFaceTimeに誘導した。
また、Appleは自社でニュース、ゲーム、ビデオ、音楽、クラウドストレージ、フィットネスなど定額制サービスの利用者を自社につなぎとめるため自社で提供する動きを強めている。このようにiPhoneでしか提供されない定額制サービスを利用する場合、他のスマートフォンに乗り換えるには多大なコスト、時間、コンテンツの消失といった摩擦が生ずることとなる。
近時、Appleはアプリ内決済以外のサードパーティのウェブ上で決済することを阻止することを禁じられた。しかし、報道によると、このようにiPhone以外での決済であるにもかかわらず、Appleはウェブ上での購入に課金するようになったとのことである。
さらにはAppleのスマートフォン支配はAppleのインフォテインメント・システムであるCarPlayにまで及んでいる。これは自動車のセンター・ディスプレイをiPhoneのディスプレイとして使用できるようにするもので、iPhoneを利用して地図を表示すること等ができるものである。
このようにiPhone経済圏が広がっていくとともに利用者をますますiPhoneに閉じ込めることが計画されている。
また、Appleは自社でニュース、ゲーム、ビデオ、音楽、クラウドストレージ、フィットネスなど定額制サービスの利用者を自社につなぎとめるため自社で提供する動きを強めている。このようにiPhoneでしか提供されない定額制サービスを利用する場合、他のスマートフォンに乗り換えるには多大なコスト、時間、コンテンツの消失といった摩擦が生ずることとなる。
近時、Appleはアプリ内決済以外のサードパーティのウェブ上で決済することを阻止することを禁じられた。しかし、報道によると、このようにiPhone以外での決済であるにもかかわらず、Appleはウェブ上での購入に課金するようになったとのことである。
さらにはAppleのスマートフォン支配はAppleのインフォテインメント・システムであるCarPlayにまで及んでいる。これは自動車のセンター・ディスプレイをiPhoneのディスプレイとして使用できるようにするもので、iPhoneを利用して地図を表示すること等ができるものである。
このようにiPhone経済圏が広がっていくとともに利用者をますますiPhoneに閉じ込めることが計画されている。
7――反競争的効果
1|Appleの反競争的行為22
(1) 上述、2~6で述べたようなことを行ったのは、Appleの自社製品の改善のためではなく、他社製品の劣化のための行為である。競争の減少という恩恵を受けて、Appleは莫大な利益を引出し、自社のためにイノベーションを規制する。その結果、すべてのスマートフォン利用者の選択肢が減少し、価格や料金が上昇し、スマートフォンその他の質が劣化し、技術革新が停滞する。Appleの行為が続けばスマートフォンの独占を維持、強化し、他から脅威を与えられなくするだろう。
(2) Appleの行為はスマートフォン利用者の選択肢を減少させ、有意な競争者としてはGoogleとサムソンしか残っていない。
(3) AppleはiPhoneから他のスマートフォンへ機種変更する場合のコストを増大させ、競争を減少させ、Appleの独占力を強化している。これはクロスプラットフォームを可能とするスーパーアプリへの圧迫やクラウドストリーミングアプリなどに対する上記で述べた各種阻害行為に起因して問題を生じさせている。これらAppleの行為がなければ、Appleに競争圧力をかけ、サードパーティおよび利用者の手数料の減少や品質の向上をもたらしたであろう。
(4) Appleの行為は上記以外でも利用者に損害をもたらしている。たとえばデジタルウォレットをApple Pay限定にしたことにより銀行に手数料を発生させ、価格の上昇や品質の低下を招いている。また、代替のデジタルウォレットはよい特典を提供したり、よりプライベートで安心な決済体験を提供したりできる。しかし、現在、代替するタップ・トゥ・ゴーはAppleには存在しない。
(5) Appleの行為はまたApple自身の品質の低下を招いている。サードパーティがスーパーアプリやクラウドベースのゲームアプリを市場投入するため多額の投資を行ったにもかかわらず、開発計画を断念しなければならなかった。そのほか、教育、人工知能など革新的な高付加アプリの開発を遅らせた可能性もある。
(6) Appleの行為は他のスマートフォン利用者にも損害を与えている。たとえば米国企業はデジタルウォレット開発を断念し、また別の企業は革新的な車のデジタルキーについて、そのほかの機能もすべてApple Wallet搭載を求められたためサービス提供を断念した。
(7) Appleの行動は関連市場で独占力を構築・維持するという反競争的目的で動機づけられている。このため、スーパーアプリ、ミニアプリ、クラウドストリーミングアプリその他のアプリから得られたはずの多額の収益を犠牲にした。これらの収益や品質向上よりもスマートフォンの競争が減少することによる長期的な利益を優先した。
(8)Appleによるスマートフォンの競争による損害はAppleがアプリ配布をApp Storeを独占的なチャネルとする決定によって増幅された。もしAppleが他の方法を認めていればサードパーティはiOS専用ではなく、あらゆるスマートフォン向けにプログラムを書くことができ、利用者の乗り換えコストは減少し、サードパーティのAppleの依存度も減少するだろう。
(9)Appleのスマートフォン独占は反競争的行為によって確保されたものである。Appleの定めたルールを変更せざるを得なくなった場合であっても、他の方法で競争阻害するようなルール、制限、機能を採用する能力を有する。たとえばAppleで問題視されたアンチステアリング条項(音楽などの購入をアプリ外での購入に誘導することなどの禁止)についても、Appleは別の手段で厳格な制限を設けている。
22 前掲注1 p49~p54参照
(1) 上述、2~6で述べたようなことを行ったのは、Appleの自社製品の改善のためではなく、他社製品の劣化のための行為である。競争の減少という恩恵を受けて、Appleは莫大な利益を引出し、自社のためにイノベーションを規制する。その結果、すべてのスマートフォン利用者の選択肢が減少し、価格や料金が上昇し、スマートフォンその他の質が劣化し、技術革新が停滞する。Appleの行為が続けばスマートフォンの独占を維持、強化し、他から脅威を与えられなくするだろう。
(2) Appleの行為はスマートフォン利用者の選択肢を減少させ、有意な競争者としてはGoogleとサムソンしか残っていない。
(3) AppleはiPhoneから他のスマートフォンへ機種変更する場合のコストを増大させ、競争を減少させ、Appleの独占力を強化している。これはクロスプラットフォームを可能とするスーパーアプリへの圧迫やクラウドストリーミングアプリなどに対する上記で述べた各種阻害行為に起因して問題を生じさせている。これらAppleの行為がなければ、Appleに競争圧力をかけ、サードパーティおよび利用者の手数料の減少や品質の向上をもたらしたであろう。
(4) Appleの行為は上記以外でも利用者に損害をもたらしている。たとえばデジタルウォレットをApple Pay限定にしたことにより銀行に手数料を発生させ、価格の上昇や品質の低下を招いている。また、代替のデジタルウォレットはよい特典を提供したり、よりプライベートで安心な決済体験を提供したりできる。しかし、現在、代替するタップ・トゥ・ゴーはAppleには存在しない。
(5) Appleの行為はまたApple自身の品質の低下を招いている。サードパーティがスーパーアプリやクラウドベースのゲームアプリを市場投入するため多額の投資を行ったにもかかわらず、開発計画を断念しなければならなかった。そのほか、教育、人工知能など革新的な高付加アプリの開発を遅らせた可能性もある。
(6) Appleの行為は他のスマートフォン利用者にも損害を与えている。たとえば米国企業はデジタルウォレット開発を断念し、また別の企業は革新的な車のデジタルキーについて、そのほかの機能もすべてApple Wallet搭載を求められたためサービス提供を断念した。
(7) Appleの行動は関連市場で独占力を構築・維持するという反競争的目的で動機づけられている。このため、スーパーアプリ、ミニアプリ、クラウドストリーミングアプリその他のアプリから得られたはずの多額の収益を犠牲にした。これらの収益や品質向上よりもスマートフォンの競争が減少することによる長期的な利益を優先した。
(8)Appleによるスマートフォンの競争による損害はAppleがアプリ配布をApp Storeを独占的なチャネルとする決定によって増幅された。もしAppleが他の方法を認めていればサードパーティはiOS専用ではなく、あらゆるスマートフォン向けにプログラムを書くことができ、利用者の乗り換えコストは減少し、サードパーティのAppleの依存度も減少するだろう。
(9)Appleのスマートフォン独占は反競争的行為によって確保されたものである。Appleの定めたルールを変更せざるを得なくなった場合であっても、他の方法で競争阻害するようなルール、制限、機能を採用する能力を有する。たとえばAppleで問題視されたアンチステアリング条項(音楽などの購入をアプリ外での購入に誘導することなどの禁止)についても、Appleは別の手段で厳格な制限を設けている。
22 前掲注1 p49~p54参照
2|Appleの反競争的行為の今後23
(1) Appleの行為は今後の新たなイノベーションの発展にも重大なリスクをもたらす。Appleはその独占的な規則制定能力を利用して、次世代デバイスや技術に関する権力を獲得又は維持する可能性がある。Appleが支配力を強めるにつれ、利用者をAppleのデバイスに囲い込むため、クロスプラットフォーム企業のイノベーションを遅延させたり、抑制し続けたりする可能性がある。
(2) Appleの保有する製品群は、反競争的行為を行うための将来の道筋と救済措置を回避する能力を提供する。このため、将来を見据えた適切な救済措置が必要である。
(3) Appleの行為は経済的な独占利益だけにとどまらず、言論の流れにまで影響を及ぼしている。
(4) Appleはその独占力を利用して収集した利用者データを利用し、自動車業界のイノベーションを阻害してきた。iPhoneを妨害する可能性のある代替技術を排除することでiPhoneにおけるAppleの権力をさらに強化する。
(5) Appleはスマートフォン市場を独占することで何百万人もの米国人の生活を支配する巨大な権力を手にしている。今日、Appleは競合するスマートフォンを弱体化させ、革新的な技術を抑制し、消費者の選択を妨げている。明日、Appleはその力を使って自社の利用者(とそのデータ)を次の収益性の高い製品に強制するかもしれない。
23 前掲注1 p54~p55参照
(1) Appleの行為は今後の新たなイノベーションの発展にも重大なリスクをもたらす。Appleはその独占的な規則制定能力を利用して、次世代デバイスや技術に関する権力を獲得又は維持する可能性がある。Appleが支配力を強めるにつれ、利用者をAppleのデバイスに囲い込むため、クロスプラットフォーム企業のイノベーションを遅延させたり、抑制し続けたりする可能性がある。
(2) Appleの保有する製品群は、反競争的行為を行うための将来の道筋と救済措置を回避する能力を提供する。このため、将来を見据えた適切な救済措置が必要である。
(3) Appleの行為は経済的な独占利益だけにとどまらず、言論の流れにまで影響を及ぼしている。
(4) Appleはその独占力を利用して収集した利用者データを利用し、自動車業界のイノベーションを阻害してきた。iPhoneを妨害する可能性のある代替技術を排除することでiPhoneにおけるAppleの権力をさらに強化する。
(5) Appleはスマートフォン市場を独占することで何百万人もの米国人の生活を支配する巨大な権力を手にしている。今日、Appleは競合するスマートフォンを弱体化させ、革新的な技術を抑制し、消費者の選択を妨げている。明日、Appleはその力を使って自社の利用者(とそのデータ)を次の収益性の高い製品に強制するかもしれない。
23 前掲注1 p54~p55参照
3|セキュリティとプライバシー保護は正当化理由とはならない24
(1) Appleは利用者のセキュリティとプライバシーを主張し、独占的状態を正当化している。しかし、Appleが抑圧する代替技術の多くは利用者のセキュリティとプライバシーを強化するものである。たとえばデジタルウォレットをターゲットとしたAppleの行為は、利用者がその個人情報を銀行や医療機関その他信頼できる第三者とだけ共有することを望んだとしても、Appleと情報を共有することを強制する。同様に、スーパーアプリや代替アプリは利用者とその家族のセキュリティとプライバシーをより保護する。
(2) Appleは独占力を維持するためであれば、iPhoneの安全性やプライバシー保護を低下させることもいとわない。たとえばiPhoneからAndroid端末に送信されるテキストメッセージは暗号化されていない。
(3) Appleはまた、利用者の個人データを収集することに依存する広告から得られる収益を共有する契約を結んでいる。たとえば、より利用者のプライバシーを保護できるとAppleが認識している検索エンジンではなく、Google検索をsafariウェブブラウザのデフォルトに設定するために、Googleより多額の利益を得ている。
(4) 結局のところ、AppleがiPhoneのセキュリティとプライバシー保護をすることはAppleに利益をもたらす場合に限定されている。
24 前掲注1 p55~P57参照
(1) Appleは利用者のセキュリティとプライバシーを主張し、独占的状態を正当化している。しかし、Appleが抑圧する代替技術の多くは利用者のセキュリティとプライバシーを強化するものである。たとえばデジタルウォレットをターゲットとしたAppleの行為は、利用者がその個人情報を銀行や医療機関その他信頼できる第三者とだけ共有することを望んだとしても、Appleと情報を共有することを強制する。同様に、スーパーアプリや代替アプリは利用者とその家族のセキュリティとプライバシーをより保護する。
(2) Appleは独占力を維持するためであれば、iPhoneの安全性やプライバシー保護を低下させることもいとわない。たとえばiPhoneからAndroid端末に送信されるテキストメッセージは暗号化されていない。
(3) Appleはまた、利用者の個人データを収集することに依存する広告から得られる収益を共有する契約を結んでいる。たとえば、より利用者のプライバシーを保護できるとAppleが認識している検索エンジンではなく、Google検索をsafariウェブブラウザのデフォルトに設定するために、Googleより多額の利益を得ている。
(4) 結局のところ、AppleがiPhoneのセキュリティとプライバシー保護をすることはAppleに利益をもたらす場合に限定されている。
24 前掲注1 p55~P57参照
(2024年04月24日「基礎研レポート」)
このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1866
経歴
- 【職歴】
1985年 日本生命保険相互会社入社
2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長
2015年4月 生活研究部部長兼システム部長
2018年4月 取締役保険研究部研究理事
2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事
2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事
2025年4月 取締役保険研究部研究理事
2025年7月より現職
【加入団体等】
東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)
東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)
大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)
金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)
日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等
【著書】
『はじめて学ぶ少額短期保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2024年02月
『Q&Aで読み解く保険業法』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2022年07月
『はじめて学ぶ生命保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2021年05月
松澤 登のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/15 | 芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立 | 松澤 登 | 研究員の眼 |
| 2025/10/09 | ソニーのパーシャル・スピンオフ-ソニーフィナンシャルの分離・上場 | 松澤 登 | 研究員の眼 |
| 2025/09/18 | 欧州委員会、Googleに制裁金-オンライン広告サービス市場での支配力濫用 | 松澤 登 | 研究員の眼 |
| 2025/09/12 | スマホ競争促進法の指針-Digital Markets Actとの比較 | 松澤 登 | 基礎研レポート |
新着記事
-
2025年10月15日
IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 -
2025年10月15日
中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -
2025年10月15日
芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立 -
2025年10月15日
英国雇用関連統計(25年9月)-週平均賃金は前年比5.0%まで再び上昇 -
2025年10月14日
中国の貿易統計(25年9月)~輸出、輸入とも加速。対米輸出は減少が続く
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【米国でのiPhone競争法訴訟-司法省等が違法な独占確保につき訴え】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
米国でのiPhone競争法訴訟-司法省等が違法な独占確保につき訴えのレポート Topへ

















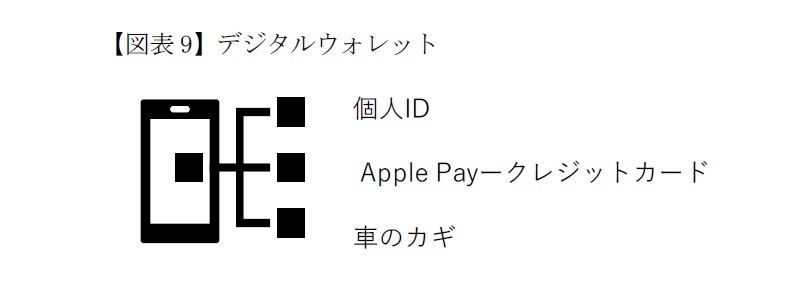

 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




