- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 経済 >
- 経済予測・経済見通し >
- 2019・2020年度経済見通し(19年5月)
2019年05月21日
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
1.2019年1-3月期は年率2.1%のプラス成長も、内容は悪い
2019年1-3月期の実質GDP(1次速報値)は、前期比0.5%(前期比年率2.1%)と2四半期連続のプラス成長となった。
中国をはじめとした海外経済の減速を背景に輸出は前期比▲2.4%の減少となったが、輸入が前期比▲4.6%と輸出以上に落ち込んだため、外需寄与度は前期比0.4%(年率1.6%)と4四半期ぶりに成長率の押し上げ要因となった。一方、国内需要は、2018年度補正予算の執行が本格化した公的固定資本形成(前期比1.5%)、消費税率引き上げ前の駆け込み需要が一部で見られた住宅投資(前期比1.1%)が増加し、民間在庫変動も前期比・寄与度0.1%のプラスとなったが、民間消費(前期比▲0.1%)、設備投資(同▲0.3%)が減少したため、前期比0.1%とほぼ横ばいにとどまった。
2019年1-3月期は潜在成長率を大きく上回る高成長となったが、その主因は国内需要の低迷を反映した輸入の減少と最終需要の弱さに起因する在庫の積み上がりによるもので、内容は悪い。
2018年度の実質GDPは0.6%と4年連続のプラス成長となったが、2017年度の1.9%からは大きく減速した。実質GDP成長率に対する寄与度を内外需別にみると、民間消費、設備投資などの国内需要は0.7%と一定の底堅さを維持したが、輸出の伸びが大きく鈍化し外需が▲0.1%と5年ぶりのマイナス寄与となった。
中国をはじめとした海外経済の減速を背景に輸出は前期比▲2.4%の減少となったが、輸入が前期比▲4.6%と輸出以上に落ち込んだため、外需寄与度は前期比0.4%(年率1.6%)と4四半期ぶりに成長率の押し上げ要因となった。一方、国内需要は、2018年度補正予算の執行が本格化した公的固定資本形成(前期比1.5%)、消費税率引き上げ前の駆け込み需要が一部で見られた住宅投資(前期比1.1%)が増加し、民間在庫変動も前期比・寄与度0.1%のプラスとなったが、民間消費(前期比▲0.1%)、設備投資(同▲0.3%)が減少したため、前期比0.1%とほぼ横ばいにとどまった。
2019年1-3月期は潜在成長率を大きく上回る高成長となったが、その主因は国内需要の低迷を反映した輸入の減少と最終需要の弱さに起因する在庫の積み上がりによるもので、内容は悪い。
2018年度の実質GDPは0.6%と4年連続のプラス成長となったが、2017年度の1.9%からは大きく減速した。実質GDP成長率に対する寄与度を内外需別にみると、民間消費、設備投資などの国内需要は0.7%と一定の底堅さを維持したが、輸出の伸びが大きく鈍化し外需が▲0.1%と5年ぶりのマイナス寄与となった。
(景気動向指数の基調判断は「悪化」へ)
5/13に公表された内閣府の「景気動向指数」では、2019年3月のCI一致指数が前月差▲0.9ポイントの低下となり、CI一致指数の基調判断が、それまでの「下方への局面変化」から、景気後退の可能性が高いことを示す「悪化」へと下方修正された。
景気動向指数のCI一致指数によって基調判断が行われるようになった2008年4月以降、基調判断が「悪化」になったことは2回あるが、いずれも事後的に景気後退と認定されている。さらに、筆者が内閣府の「CIによる景気の基調判断の基準」を用いて、現行のCI一致指数が存在する1985年1月から2008年3月までの基調判断を行ったところ、「悪化」となった6回(第10循環~第15循環)の全てで景気後退となっていることが確認された。
5/13に公表された内閣府の「景気動向指数」では、2019年3月のCI一致指数が前月差▲0.9ポイントの低下となり、CI一致指数の基調判断が、それまでの「下方への局面変化」から、景気後退の可能性が高いことを示す「悪化」へと下方修正された。
景気動向指数のCI一致指数によって基調判断が行われるようになった2008年4月以降、基調判断が「悪化」になったことは2回あるが、いずれも事後的に景気後退と認定されている。さらに、筆者が内閣府の「CIによる景気の基調判断の基準」を用いて、現行のCI一致指数が存在する1985年1月から2008年3月までの基調判断を行ったところ、「悪化」となった6回(第10循環~第15循環)の全てで景気後退となっていることが確認された。
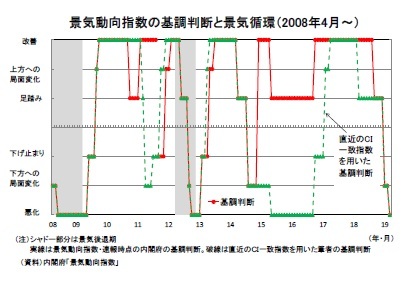 ただし、消費税率引き上げ後の2014年8月から11月にかけて、CI一致指数の基調判断は「下方への局面変化」となった後、12月に「改善」へと上方修正され、「悪化」となることは回避されたが、この基調判断は当時のCI一致指数を基にしたものである。CI一致指数は、鉱工業指数の基準改定、毎月勤労統計の再集計など採用系列の改訂に伴い過去に遡って改訂されている。筆者が直近のCI一致指数を基に改めて基調判断を行ったところ、2014年8月から2015年4月まで「下方への局面変化」が続いた後、2015年5月から2016年9月まで「悪化」という結果となった。このことは、消費税率引き上げ後の停滞期が景気後退と認定されるかどうか微妙な局面であったことを示している。その一方で、基調判断が「悪化」に下方修正されたとしても、それがそのまま景気後退に直結する訳ではないという見方もできる。
ただし、消費税率引き上げ後の2014年8月から11月にかけて、CI一致指数の基調判断は「下方への局面変化」となった後、12月に「改善」へと上方修正され、「悪化」となることは回避されたが、この基調判断は当時のCI一致指数を基にしたものである。CI一致指数は、鉱工業指数の基準改定、毎月勤労統計の再集計など採用系列の改訂に伴い過去に遡って改訂されている。筆者が直近のCI一致指数を基に改めて基調判断を行ったところ、2014年8月から2015年4月まで「下方への局面変化」が続いた後、2015年5月から2016年9月まで「悪化」という結果となった。このことは、消費税率引き上げ後の停滞期が景気後退と認定されるかどうか微妙な局面であったことを示している。その一方で、基調判断が「悪化」に下方修正されたとしても、それがそのまま景気後退に直結する訳ではないという見方もできる。
(CI一致指数以外の動き)
正式な景気の山谷の判定(景気基準日付)は、景気動向指数研究会の議論を踏まえて、経済社会総合研究所長が設定する。景気循環の判断は、基本的には(1)景気動向指数(一致指数)の各採用系列から作られるヒストリカルDI(波及度)に基づいて行われるが、それに加えて(2)量的な変化、(3)拡張・後退期間について検討し、併せて(4)参考指標(実質GDP、日銀短観等の景況感)の動きを確認することとしている。
2014年4月以降の停滞期が景気後退と認定されなかったのは、期間の長さは十分だったものの、波及度(ヒストリカルDIがゼロ%近傍まで下降)、量的な変化(CIの下降率)が不十分で、参考指標(実質GDP、日銀短観)が比較的堅調な動きを示していたためである1。
したがって、2018年秋以降の景気停滞が事後的に景気後退となるかどうかは、景気の落ち込みが比較的軽微だった2012年4月以降の後退期、2014年4月以降の停滞期における経済指標の動きがひとつの目安となるだろう。
まず、波及度については、一致指数9系列のうち鉱工業生産をはじめとした過半数の系列が2018年10月までにピークアウトしている可能性がある。ただし、直近(2019年3月)の水準がピーク時に近い系列があること、有効求人倍率は直近(2019年3月)がピークとなっていることなどから、現時点で波及度が十分との判断はできない。
次に、量的な変化については、2018年10月を景気の山の候補とした場合、2019年3月までのCI一致指数の下落率は▲4.1%である。第10循環の後退局面(1985年6月~1986年11月:▲3.3%)より下落幅は大きいものの、第15循環の後退局面(2012年3月~2012年11月:▲6.2%)、2014年4月以降の停滞期(2014年3月~2015年12月2:▲6.7%)より小さい。現時点で量的な変化は十分とは言えない。
景気後退期間の目安は、「景気の山(谷)が、直前の谷(山)から5ヵ月以上経過、かつ前の景気循環の山(谷)から15ヵ月以上経過」となっている。2018年10月以前にピークをつけた系列のボトムが2019年3月以降になった時点でこの条件は満たすことになる(前の景気の谷(2012年11月)からの期間はすでに十分)。
最後に参考指標の動きを確認すると、2018年10月を景気の山の候補とした場合、実質GDPは2018年10-12月期が前期比年率1.6%、2019年1-3月期が同2.1%と潜在成長率を上回る高い伸びとなっている。日銀短観については、大企業・全産業の業況判断DIは2017年12月調査の+25をピークに低下傾向が続き、2019年3月調査では+17となった。この間の低下幅(▲8)は第15循環(▲4)よりは大きいものの、2014年4月以降の停滞期(▲9)や、第14循環以前よりも小さい。さらに、過去の景気後退局面ではいずれもDIの水準がマイナスに沈んでいるが、直近の水準は大幅なプラスを維持している。
鉱工業生産、実質GDP、日銀短観の業況判断DIなどの主要経済指標が4-6月期に上向けば、景気後退が回避される可能性が高くなるだろう。
正式な景気の山谷の判定(景気基準日付)は、景気動向指数研究会の議論を踏まえて、経済社会総合研究所長が設定する。景気循環の判断は、基本的には(1)景気動向指数(一致指数)の各採用系列から作られるヒストリカルDI(波及度)に基づいて行われるが、それに加えて(2)量的な変化、(3)拡張・後退期間について検討し、併せて(4)参考指標(実質GDP、日銀短観等の景況感)の動きを確認することとしている。
2014年4月以降の停滞期が景気後退と認定されなかったのは、期間の長さは十分だったものの、波及度(ヒストリカルDIがゼロ%近傍まで下降)、量的な変化(CIの下降率)が不十分で、参考指標(実質GDP、日銀短観)が比較的堅調な動きを示していたためである1。
したがって、2018年秋以降の景気停滞が事後的に景気後退となるかどうかは、景気の落ち込みが比較的軽微だった2012年4月以降の後退期、2014年4月以降の停滞期における経済指標の動きがひとつの目安となるだろう。
まず、波及度については、一致指数9系列のうち鉱工業生産をはじめとした過半数の系列が2018年10月までにピークアウトしている可能性がある。ただし、直近(2019年3月)の水準がピーク時に近い系列があること、有効求人倍率は直近(2019年3月)がピークとなっていることなどから、現時点で波及度が十分との判断はできない。
次に、量的な変化については、2018年10月を景気の山の候補とした場合、2019年3月までのCI一致指数の下落率は▲4.1%である。第10循環の後退局面(1985年6月~1986年11月:▲3.3%)より下落幅は大きいものの、第15循環の後退局面(2012年3月~2012年11月:▲6.2%)、2014年4月以降の停滞期(2014年3月~2015年12月2:▲6.7%)より小さい。現時点で量的な変化は十分とは言えない。
景気後退期間の目安は、「景気の山(谷)が、直前の谷(山)から5ヵ月以上経過、かつ前の景気循環の山(谷)から15ヵ月以上経過」となっている。2018年10月以前にピークをつけた系列のボトムが2019年3月以降になった時点でこの条件は満たすことになる(前の景気の谷(2012年11月)からの期間はすでに十分)。
最後に参考指標の動きを確認すると、2018年10月を景気の山の候補とした場合、実質GDPは2018年10-12月期が前期比年率1.6%、2019年1-3月期が同2.1%と潜在成長率を上回る高い伸びとなっている。日銀短観については、大企業・全産業の業況判断DIは2017年12月調査の+25をピークに低下傾向が続き、2019年3月調査では+17となった。この間の低下幅(▲8)は第15循環(▲4)よりは大きいものの、2014年4月以降の停滞期(▲9)や、第14循環以前よりも小さい。さらに、過去の景気後退局面ではいずれもDIの水準がマイナスに沈んでいるが、直近の水準は大幅なプラスを維持している。
鉱工業生産、実質GDP、日銀短観の業況判断DIなどの主要経済指標が4-6月期に上向けば、景気後退が回避される可能性が高くなるだろう。
1 詳細は第17回景気動向指数研究会「資料1 第15循環の景気の谷以降の状況について」(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/170615siryou1.pdf)を参照。
2 景気の山谷がないため、ヒストリカルDIが50%を下回る期間を対象とした下落率。
(輸出の減少傾向が鮮明に)
景気の牽引役となってきた輸出は、世界経済の減速を受けて2018年に入り増加ペースが鈍化した後、2018年度末にかけて減少した。
景気の牽引役となってきた輸出は、世界経済の減速を受けて2018年に入り増加ペースが鈍化した後、2018年度末にかけて減少した。
輸出の先行きを展望すると、米国は2018年の実質GDP成長率が2.9%となり、2017年の2.2%から加速したが、歳出拡大の時限措置終了、減税による押し上げ効果の減衰、保護主義的な通商政策による下押しなどから、2019年が2.6%、2020年が1.8%と徐々に減速すると予想している。また、2018年後半には前期比年率0%台まで成長率が低下したユーロ圏は、2019年1-3月期には同1.6%といったん持ち直したが、4-6月期以降は1%程度の成長へ減速することを見込んでおり、景気対策の効果などから2018年中の減速傾向に歯止めがかかりつつある中国も、米中貿易摩擦が再び激化しつつあることもあり成長ペースの加速は期待できないだろう。
日本の輸出が世界貿易量以上に落ち込んでいる一因は、日本が比較優位を持つIT関連需要が世界的に急速に縮小していることである。
日本の輸出が世界貿易量以上に落ち込んでいる一因は、日本が比較優位を持つIT関連需要が世界的に急速に縮小していることである。
(底堅さを維持する国内需要)
輸出の減少を受けて鉱工業生産が大きく落ち込んでいるにもかかわらず、日本経済全体が落ち込んでいないのは個人消費、設備投資などの国内需要が一定の底堅さを維持しているためである。2019年1-3月期のGDP統計では、外需(純輸出)が大幅なプラスとなる一方、国内需要はほぼ横ばいにとどまったが、四半期毎の振れを均すために前年比で見ると、2018年7-9月期以降は外需のがマイナスを国内需要のプラスがカバーする形となっている。
外需が大きく悪化する一方で国内需要が底堅さを維持していることは企業の景況感にも表れている。日銀短観の業況判断DIは輸出の影響を強く受ける製造業が大きく悪化する一方、国内需要との連動性が高い非製造業は高水準横ばい圏で踏みとどまっている。
輸出の減少を受けて鉱工業生産が大きく落ち込んでいるにもかかわらず、日本経済全体が落ち込んでいないのは個人消費、設備投資などの国内需要が一定の底堅さを維持しているためである。2019年1-3月期のGDP統計では、外需(純輸出)が大幅なプラスとなる一方、国内需要はほぼ横ばいにとどまったが、四半期毎の振れを均すために前年比で見ると、2018年7-9月期以降は外需のがマイナスを国内需要のプラスがカバーする形となっている。
外需が大きく悪化する一方で国内需要が底堅さを維持していることは企業の景況感にも表れている。日銀短観の業況判断DIは輸出の影響を強く受ける製造業が大きく悪化する一方、国内需要との連動性が高い非製造業は高水準横ばい圏で踏みとどまっている。
ただし、輸出の減少はいずれ国内需要にも波及する。国内需要の柱のひとつである設備投資は輸出との連動性が高く、すでに製造業では輸出の減少を受けて投資計画を先送りする動きがみられる。輸出の低迷が長引けば、企業収益の減少が雇用所得環境の悪化、国内需要の下押しにつながり、非製造業の設備投資抑制も抑制されるだろう。
(2019年05月21日「Weekly エコノミスト・レター」)
このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836
経歴
- ・ 1992年:日本生命保険相互会社
・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ
・ 2019年8月より現職
・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)
・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)
・ 2018年~ 統計委員会専門委員
斎藤 太郎のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |
| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |
| 2025/09/19 | 消費者物価(全国25年8月)-コアCPIは9ヵ月ぶりの3%割れ、年末には2%程度まで鈍化する見通し | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |
| 2025/09/17 | 貿易統計25年8月-関税引き上げの影響が顕在化し、米国向け自動車輸出が数量ベースで大きく落ち込む | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |
新着記事
-
2025年10月17日
EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -
2025年10月17日
日本における「老衰死」増加の背景 -
2025年10月17日
選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -
2025年10月17日
首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -
2025年10月17日
「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【2019・2020年度経済見通し(19年5月)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
2019・2020年度経済見通し(19年5月)のレポート Topへ

















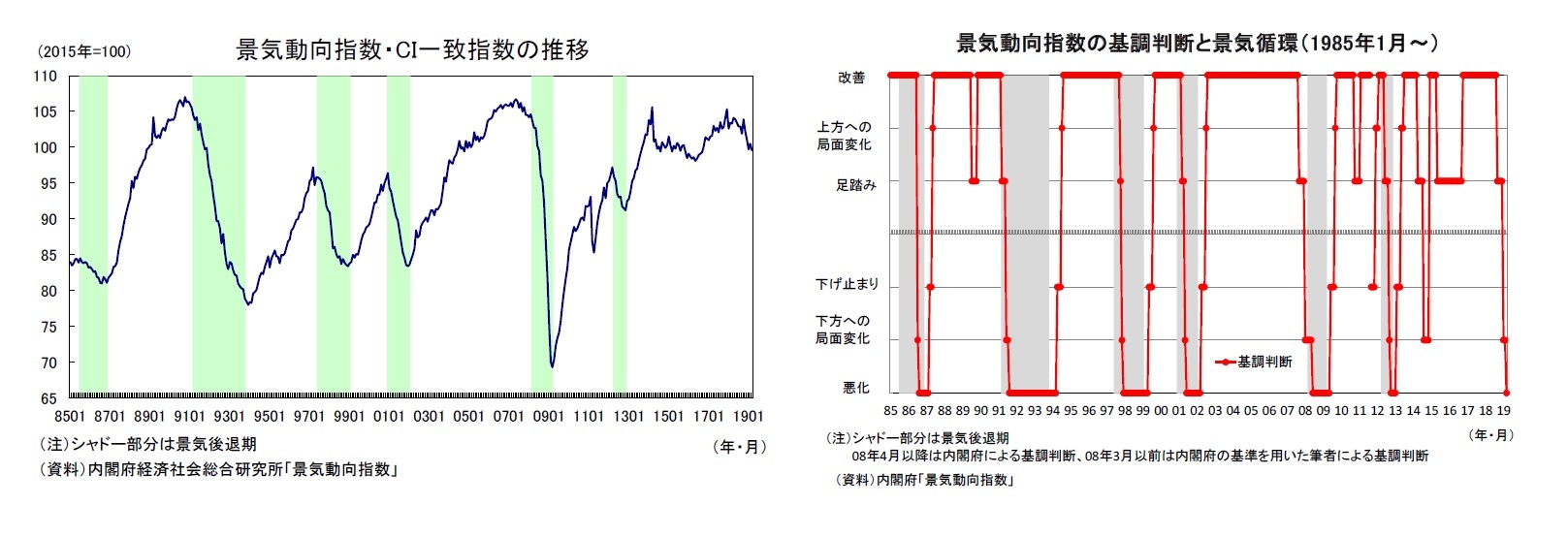
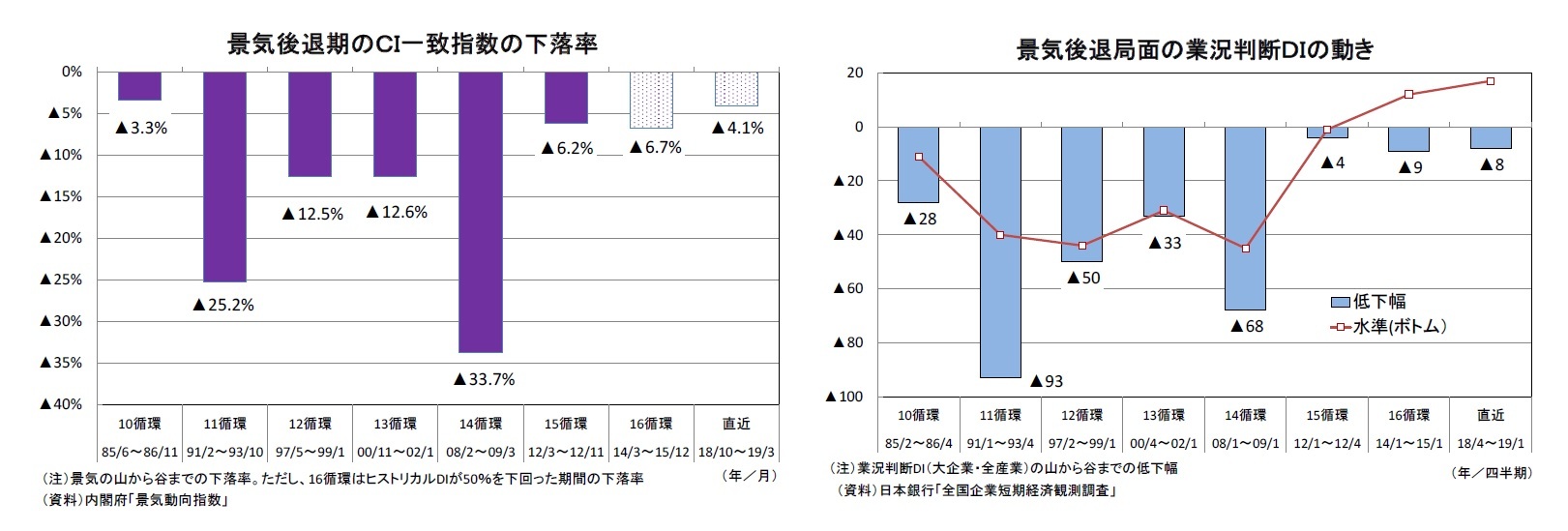
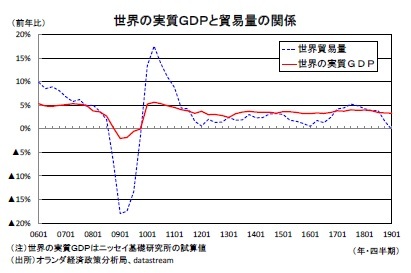
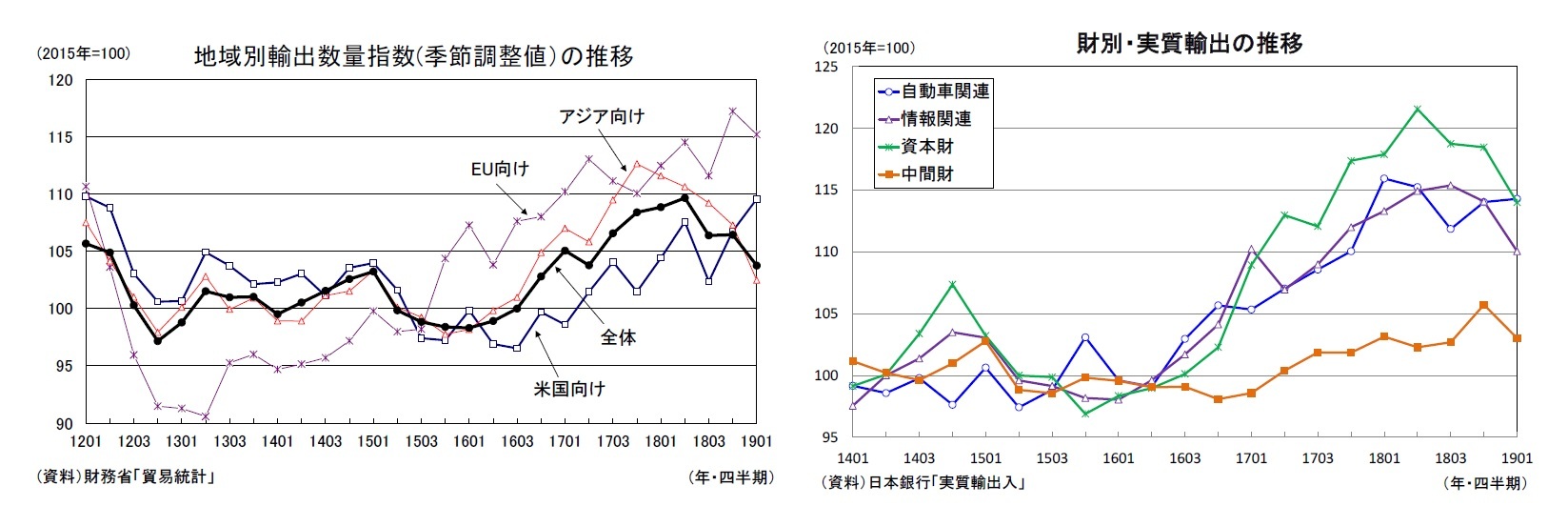
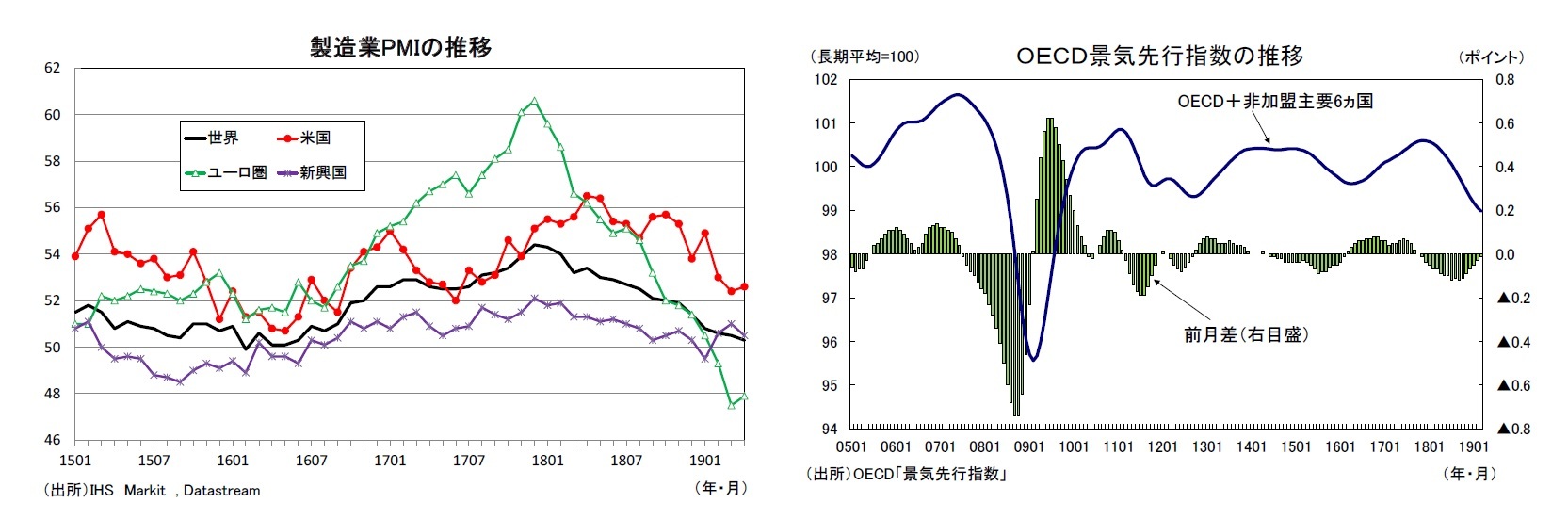
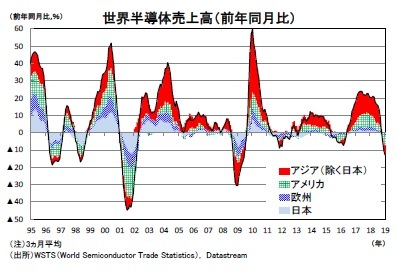
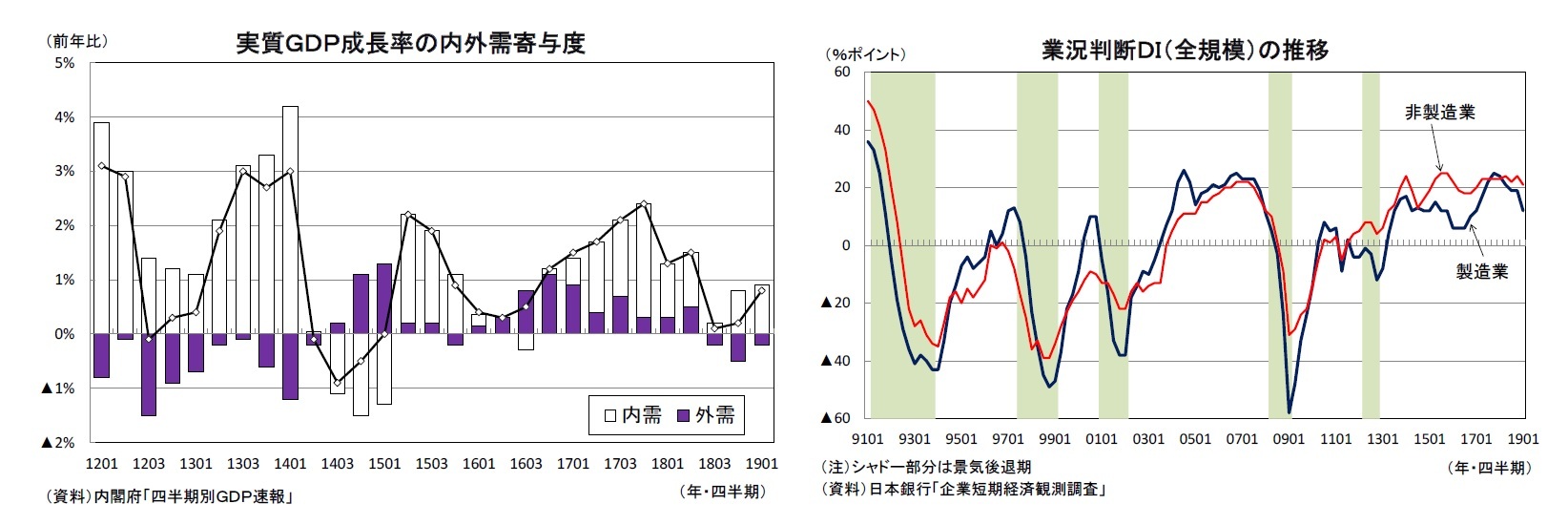
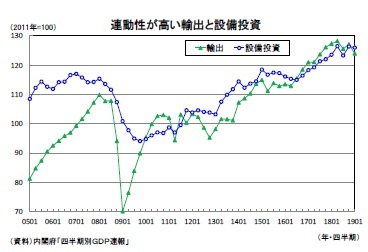

 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




