- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 経済 >
- 家計の貯蓄・消費・資産 >
- 資産市場の拡大を期待する日本と縮小を警戒する米国
コラム
2006年01月23日
| 1.65歳以上人口の割合:2055年まで上昇を続ける日本と2030年には頭打ちする米国 周知の通り、2005年における日本の総人口は前年比で減少に転じた。飢饉・戦乱や疫病の流行以外の原因によって、すなわち、少子高齢化を背景に総人口が減少するのは、日本の歴史が始まって以来おそらく初めての経験である。 実は、65歳以上人口が総人口に占める割合に関して、1980年代初頭まで先進国の中で最も低い水準にあったのは、日本である。しかし、日本の現在の数字は20%を超え、世界で最も高い国となっている。それほど、高齢化の進行が急だったのである。今後も、2015年に26.0%、2035年には30.9%と上昇を続け、ようやく2054年の36.0%でピークを迎える見込みである(国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口」による中位推計)。
このように高齢化が進行するといっても、65歳以上人口の割合が30年後に現在の日本並みの水準に達した後は安定化する米国と比べると、50年間にわたって上昇が続き、しかも、約2倍の水準に達する日本の場合、経済への影響度合いははるかに大きいだろう。 2.現在の家計貯蓄率:日本は2.8%、米国は1.8% 高齢化の進行がマクロ経済に及ぼす影響は多岐にわたると考えられるが、社会保障給付の増大と並んで想像しやすいのは、貯蓄率の低下である。 貯蓄とは、所得のうち現在の消費に使われずに、将来の消費原資に充てるために残された部分のことである。そして、マイナスの貯蓄とは、過去に蓄えられた資産の取り崩しによって、現在の所得を上回る消費が行われる際の超過部分に対応する。失業や引退によって労働所得がなくなった世帯では、消費の水準を従前より大幅に下げない限り、貯蓄率はマイナスにならざるを得ない。したがって、引退した高齢者世帯の割合が高まれば、社会全体の家計貯蓄率が低下するのも自然の成り行きである。 もちろん、失業や引退という「イベント」だけが世帯の貯蓄に影響する要因ではない。例えば、予期せざる資産価格の上昇が起きた場合、保有資産の増加は生涯所得の増加、言い換えると、生涯に消費可能な総額の増加に等しい効果を持つ。この場合、現在の可処分所得は変わらないから、この効果を拠り所として消費を増やせば、結果として計算される消費性向は上昇し、貯蓄率は低下することになる。今後の所得増加が楽観できる状況になった場合も、同様のことが言える。あるいはまた、価値観や嗜好という次元において、将来の消費よりも現在の消費を選好する世帯は、そうでない世帯よりも結果としての消費性向は高く、貯蓄率は低くなる。いずれにしても、社会全体の家計貯蓄率は多種多様な世帯が集計された結果としての貯蓄率であるから、社会を構成する世帯の多くが貯蓄率を低下させる経済環境にある場合や、現在を重視する選好を持った世帯が多い場合には、家計部門の貯蓄率は低位にとどまることになる。
まず、1970年代半ば以降の日本の家計貯蓄率の低下トレンドは高齢化の進行及び経済成長率の低下に見合うものである。ただし、先般発表された96年度以降の実績値に関して、7年連続低下の結果として累計8.7%もの下落となったことについては、高齢化進行や所得減少期の慣習効果のみでは十分な説得力を持たない。一方、90年代半ば以降の米国の家計貯蓄率の低下は、所得環境の好転と資産価格の上昇を背景にしたものと考えられる。また、65歳以上人口の割合が日本よりも低い米国の貯蓄率の方が常に低いのは、現在を重視する選好を持った家計が相対的に多いためであろう。真相は詳細な実証研究に委ねるしかないが、今後に関しては、高齢化進行の影響を強く受けるのは日本の方であろう。 ところで、家計貯蓄率が低下すれば、家計の保有資産の伸びも低下するという意味での直接的な効果は万国共通である。資産価格の変動がない場合、家計貯蓄率がプラスである限りは家計の資産残高は増えるが、貯蓄率がマイナスの状況下では資産残高は減少する。また、家計貯蓄率がプラスであっても、住宅投資など新規の実物資産取得に振り向けられる部分が非常に大きければ、金融資産の新規取得はマイナスにならざるを得ない。このように、家計貯蓄率は家計部門の資産規模や資産市場の成長を示す指標としても読むことができるのである。 3.ベビーブーマー退職後の資産市場:市場拡大を期待する日本と「マーケット・メルトダウン」を懸念する米国 家計部門の株式保有という文脈で考えると、高齢化の進行に伴って家計貯蓄率がマイナスにまで低下するかどうかだけではなく、数の上で影響力の大きい特定の年齢階層や世代が存在するかどうかも重要である。 この点に関して、米国では、これまでの株式市場を支えてきたのは引退前のべビーブーマーに負うところが小さくなく、ベビーブーマーが引退してしまうと株式需要は後退する可能性があるという見方が、様々な立場の人々の間で浸透している。特に、「マーケット・メルトダウン」とは、株価がとめどもなく下がっていき、市場が崩壊してしまうかもしれないという最も悲観的なシナリオを象徴する言葉である。そうなると考えているわけではないが、可能性のひとつとして警戒しているというところであろう。 しかも、「マーケット・メルトダウン」は市場関係者によってのみ論じられているのではなく、経済学者による研究も行われている。例えば、理論モデル上はベビーブーマー引退によって資産価格下落圧力がかかるとか、実証分析に基づく限りは、引退したからといって株式需要が急激に後退することはないとか、株価や債券価格の変動は人口の年齢構成変化によって説明できる部分は小さいというような内容である。米国からは聞こえてくるのは、ヒステリックな悲観論でも、手放しの楽観論でもない、理性的な議論である。 これに対して、団塊世代の退職を前にした日本では、株式市場の拡大と活性化という明るい可能性ばかりが強調され過ぎてはいないだろうか。もちろん、それを支える幾つかの根拠は確かにある。家計の年齢階層別の保有資産データを見ると、高齢者の方が株式を保有している世帯の割合は高いし、総資産に占める株式の割合も高い。証券化と規制緩和の流れの中で、金融商品が多様化し、市場性資産に対する家計のアクセシビリティは高まっている。十分な教育機会に恵まれ、自らと家族の幸福を大切にする団塊世代が引退した場合、第二の人生を豊かに過ごすために、資産運用には前向きな取組みをする公算が高い。 他方、資産保有額は退職金支払いを受けた直後がピークで、以後は消費資金に充当するための資産取り崩しが行われているという事実が引き合いに出されることは稀である。リスク性資産の保有割合は高齢者の方が高いといっても、資産総額が現役世代より大きいからリスク許容度が高いのか、純粋に年齢的要因だけを抽出した場合にもリスク許容度が高いのかも、不確かである。団塊世代に続く世代の中には、最も地価が高い時期に持家を取得して、その後の地価下落でバランスシートにダメージを負っている場合など、引退時に団塊世代ほどの純資産は持ち得ない世帯も含まれているはずである。そう考えると、団塊世代が現役の時の家計部門と団塊世代が引退した後の家計部門とを比較した場合、前者のリスク許容度の方が高いという可能性もないわけではないだろう。さらに、今後の高齢化の進展を考えるならば、家計貯蓄率がマイナスに転じ、家計の保有する資産規模自体が縮小する事態が起こらないとは言えないであろう。 今後の資産市場に対して、高齢化の度合いはさほど深刻とは思われない米国の方が慎重なのは、余裕のなせる業だろうか。それとも、日本での議論は、懸念材料の存在は十分に認識したうえで、明るい材料を生かす前向きの姿勢をとっているだけなのであろうか。 |
このレポートの関連カテゴリ
石川 達哉
研究・専門分野
公式SNSアカウント
新着レポートを随時お届け!日々の情報収集にぜひご活用ください。
新着記事
-
2024年04月30日
今週のレポート・コラムまとめ【4/23-4/26発行分】 -
2024年04月26日
ドイツの産業空洞化リスク-グローバル化逆回転はドイツへの逆風、日本への追い風か?- -
2024年04月26日
米GDP(24年1-3月期)-前期比年率+1.6%と前期から低下、市場予想の+2.5%も大幅に下回る -
2024年04月26日
滞留するふるさと納税 -
2024年04月26日
EUのDMA関連調査開始決定-GAFAそれぞれの問題を指摘
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2024年04月02日
News Release
-
2024年02月19日
News Release
-
2023年07月03日
News Release
【資産市場の拡大を期待する日本と縮小を警戒する米国】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
資産市場の拡大を期待する日本と縮小を警戒する米国のレポート Topへ


















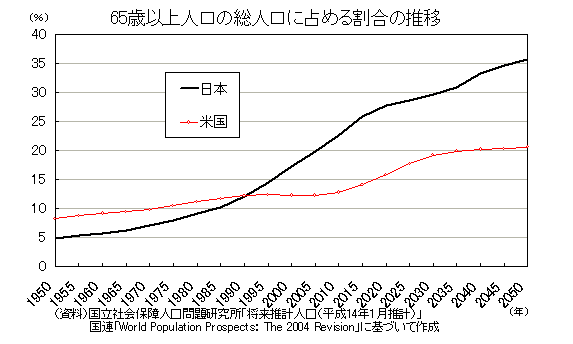
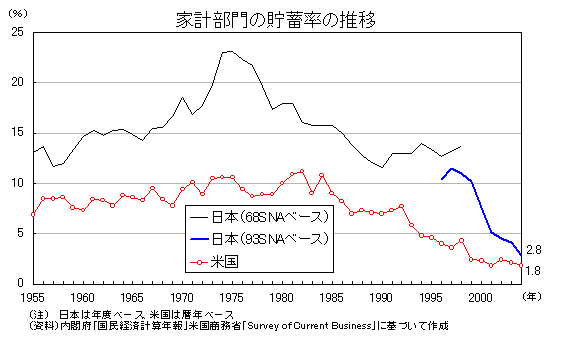

 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!





