- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 経済 >
- 欧州経済 >
- ECB政策理事会-PEPPは来年3月で終了か
2021年10月29日
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
(質疑応答(趣旨))
- 会議での最優先議題は何か。ユーロ圏のインフレ率が30年ぶりの高水準であり、インフレの見方について異なる評価が見られたか
- インフレ率は多くの時間と議論を費やしたテーマだった
- インフレ促進の要因はコロナ禍からの回復に関するものと、エネルギー価格に関するものの2種類に大別できる
- またドイツのVATというベース効果に関するものがあり、これは1月1日にはなくなる
- 上記2種類の要因について、2022年には次第に解消されるだろう信じるに足る充分な理由がある
- 市場の利上げ期待が高まっていることについて、エコノミストは市場が新しいフォワードガイダンスを消化していないと言うが、市場の来年までの利上げ期待はなぜ間違っているのか
- 我々は、市場が期待するように、現在、フォワードガイダンスの利上げの条件を満たしておらず、またすぐに満たされないと分析している
- 我々の見通しと分析が正しいという確信がある
- 世界を見ると、インフレの急上昇に対して金融引き締めをしはじめている。ユーロ圏のインフレ基調は他の先進国と本質的に異なるのか、それとも他の中央銀行が物価上昇に対して過剰反応をしているのか
- 同じ経済について話している訳ではないので、比較してはいけないものである
- 見通しもインフレの水準も異なっている
- 我々は、金利が実効的な下限にあるもとでは、我慢強くなければならない
- PEPPのペースについて、9月に10-12月期には適度に減速したペースにすることを決定したが、今月の週次データではそうなっていない。これは、政策引き締め期待に対応するものなのか、データをどう読めば良いのか
- 9月の決定は10月についての決定だった
- これはテーパリングではなく、昨年12月のコミットメントに基づいて良好な資金調達環境とインフレ見通しと見て決定されている
- ECBが債券購入を削減、終了して金利が再び上昇するというある種、正常化するための前提条件は何か
- 私の見解では、PEPPは22年3月に終了する見込みだが、何が通常の政策かということについては確信を持って言えない
- 利上げのための条件は、フォワードガイダンスに明確に示されているものの、現在の分析によればそれは満たされておらず、近い将来でもおそらく満たされない
- ドイツの経済研究センターの調査に関するもので、ECB理事会メンバーの加盟国の財政スタンスと金融政策に相関が見られるという、この結果についてどう感じるか
- ECBは独立しており、欧州の条約に縛られており、それは端的には1つの使命であり物価の安定である
- インフレ率と経済に影を落としている原材料不足とサプライチェーンの制約はいつまで続くと考えているか
- まず、供給制約はなくなるだろうと考えている
- 第2に、予想していたよりも少し長期化する可能性が高い
- 22年中には解決されるだろうが、22年1-3月期では解決されず、一部は年いっぱいかかると見られる
- 第3に、ドイツの見通しの再調整がそうだが、はじめは減少するものの、その後は増加が見込まれる
- インフレが一時的なものとならずに継続し、スタグフレーションになるリスクはあるか
- スタグフレーションには経済停滞が起きている必要があるが、見通し期間中にその兆候はみられない
- PEPPを3月に終了する予定だと言ったが、枠をすべて使わない可能性があるのか、その確率はどの程度か
- 現時点で、PEPPは3月に終了する予定であり、枠をすべて使うか否かは良好な資金調達環境次第で、3月までの数か月に決定する
- FRBは政策決定者の個人での運用に関する規定を厳格化したが、それについての見解を教えて欲しい、FRBの決定に照らして規則を変更する予定は
- 我々の倫理委員会と倫理担当者が、規則を、明確、透明で利害対立がないように見直しており、すべてのメンバーにより規則が順守、尊重されている
- 市場は早ければ来年末にも利上げを予想しているが、PEPPが3月に終了した後もPEPPの柔軟性を維持することはどれだけ重要か
- 我々の分析では、フォワードガイダンスの条件は満たされていない
- 現在のデータでは、賃金が持続的に上昇すると信じるに足る理由はなく、これが見られれば波及効果(second-round effect)が生まれ、分析を再評価するかもしれない
- PEPPを生み出すときには、物価安定の使命を果たすための、政策スタンスと伝達効果をもたらすために、必要な柔軟性を持つことができた
- 将来もそうすることができると確信している
- ECBが現行政策を維持し、米国と英国で金融引き締めが予想されているため、ユーロの下落圧力となる。ユーロ安が輸入インフレをもたらすことについて、議論されたか
- イングランド銀行やFRBの引き締めによる波及効果については議論しなかった
- 次回、今年最後の記者会見についてコロナ禍の終わりが近づいているという認識を示すために、対面で行って頂けますでしょうか
- 我々は、予防として1月末まで現行と同じ措置するようお願いしているので、私の希望としては22年の最初には物理的な出席ができるよう期待している
- 試算購入について、2%の目標を達成するには期間や量が重要なのか。一部の理事会メンバーは異なる見解を持っているように思うが
- 今回の理事会では議論されなかったが、過去に話題になったことはあり、正しく見解の多様性を捉えていると思う
- 量の方が期間より重要だという考えが支配的だと思うが、究極的な回答は出ていないと思う
- 欧州委員会が提案する銀行へのバーゼルIIIの提要を2025年に延期するという提案についてどう考えているか。非金融機関貸出など欧州の固有事項を考慮することは有用だと考えるか
- 私や同僚のSMMのアンドレア・エンリア氏が主張してきた時間軸でないことはその通りだった
- バーゼルIIIの適用は全ての地域・銀行で一貫、同期されることが良かったと思う
- 結論を急ぐのではなく、特徴的な欧州銀行が可能な限り、同期され一貫性のある仕組みに適応できるようしたい
- バイトマン氏の辞任について。最大加盟国の代表が、おそらく理事会の金融緩和策に不満を持って辞任することは健全なのか、解決策はあるのか
- 我々はバイトマン総裁と素晴らしい業務関係にあり、個人的にも良い関係にあった
- 彼が私や理事会の同僚に話したことには、あなたが辞任の理由としてほのめかしたことを示唆するものはなにもない
- フランスやドイツのような国がマルタやルクセンブルグと同じ1票しか持っていないのは公平なのか。GDPや人口規模に結びつける他の方法もある。
- 投票権のウェイトは、選択肢になく、欧州が作られてきた歴史の中にもない。ECBがこの特定問題への見解を示し、変えることもない
- 加盟国各国が発言権を持ち、意見を聞いてもらい、尊重されつつ、規模の大きい加盟国は金融政策の実行や決定についてより積極的で重要な役割を果たしていることは確かと言える
- フォワードガイダンスで、依然として低い金利について言及されているのはなぜか。今後段階的に取り除かれていくのか
- 状況に応じて高い金利にも低い金利にも言及され、理事会によって議論され、今後見直される事項である
- TLTROについて。12月の理事会前にTLTROⅢが終了するが、それが崖の端になるのか、それとも異なるTLTROへの移行があるのか。
- 崖の影響を避けるために出来る限りのことをすべきであると考えており、次回の理事会で議論する予定である
- 2年後の利上げを見込む市場の見通しはECBと異なっており、それはECBの意図を市場ではなく広範な経済に発信しているからではないか。なぜメッセージを聞く気がない期間に発信するのか
- 市場の期待と我々のフォワードガイダンスの分析は異なっており、利上げの時期について両者が断絶しているという指摘は正しく、反復し信念を維持することで究極的には伝わると考えている
- PEPPが3月に期限切れになると強調したが、ECBの購入策は削減されるのか、それとも代替としてAPPの増額に円滑に移行するのか
- PEPPの次に何が起こるかは次の12月の理事会で議論する予定である
- なぜ2022年中にインフレ率が低下すると確信しているのか
- ベース効果や供給制約はいずれ解消に向かう、エネルギー価格も過去の事例から学ぶならば安定し、いくらか下落する
- ボトルネックが長期化すれば賃金に影響し、波及効果について注視する必要があるが、現在の弛み(slack)の状況も鑑みる必要がある
- インフレ期待も固定されている
(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。
(2021年10月29日「経済・金融フラッシュ」)
このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1818
経歴
- 【職歴】
2006年 日本生命保険相互会社入社(資金証券部)
2009年 日本経済研究センターへ派遣
2010年 米国カンファレンスボードへ派遣
2011年 ニッセイ基礎研究所(アジア・新興国経済担当)
2014年 同、米国経済担当
2014年 日本生命保険相互会社(証券管理部)
2020年 ニッセイ基礎研究所
2023年より現職
・SBIR(Small Business Innovation Research)制度に係る内閣府スタートアップ
アドバイザー(2024年4月~)
【加入団体等】
・日本証券アナリスト協会 検定会員
高山 武士のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | ECB政策理事会-2会合連続で全会一致の据え置き決定 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 2025/09/12 | 欧州経済見通し-関税合意後も不確実性が残る状況は続く | 高山 武士 | Weekly エコノミスト・レター |
| 2025/09/11 | ロシアの物価状況(25年8月)-前年比の低下基調が継続、8%台前半に | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 2025/09/05 | トランプ関税後の貿易状況(25年9月更新版) | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
新着記事
-
2025年09月16日
インド消費者物価(25年9月)~8月のCPI上昇率は+2.1%に上昇、GST合理化でインフレ見通しは緩和 -
2025年09月16日
タイの生命保険市場(2024年版) -
2025年09月16日
外国人問題が争点化した背景-取り残されたと憤る層を包摂する政策を -
2025年09月16日
男性の育休取得の現状(2024年度)-過去最高の40.5%へ、産後パパ育休で「すそ野拡大」効果も -
2025年09月16日
今週のレポート・コラムまとめ【9/9-9/12発行分】
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【ECB政策理事会-PEPPは来年3月で終了か】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ECB政策理事会-PEPPは来年3月で終了かのレポート Topへ

















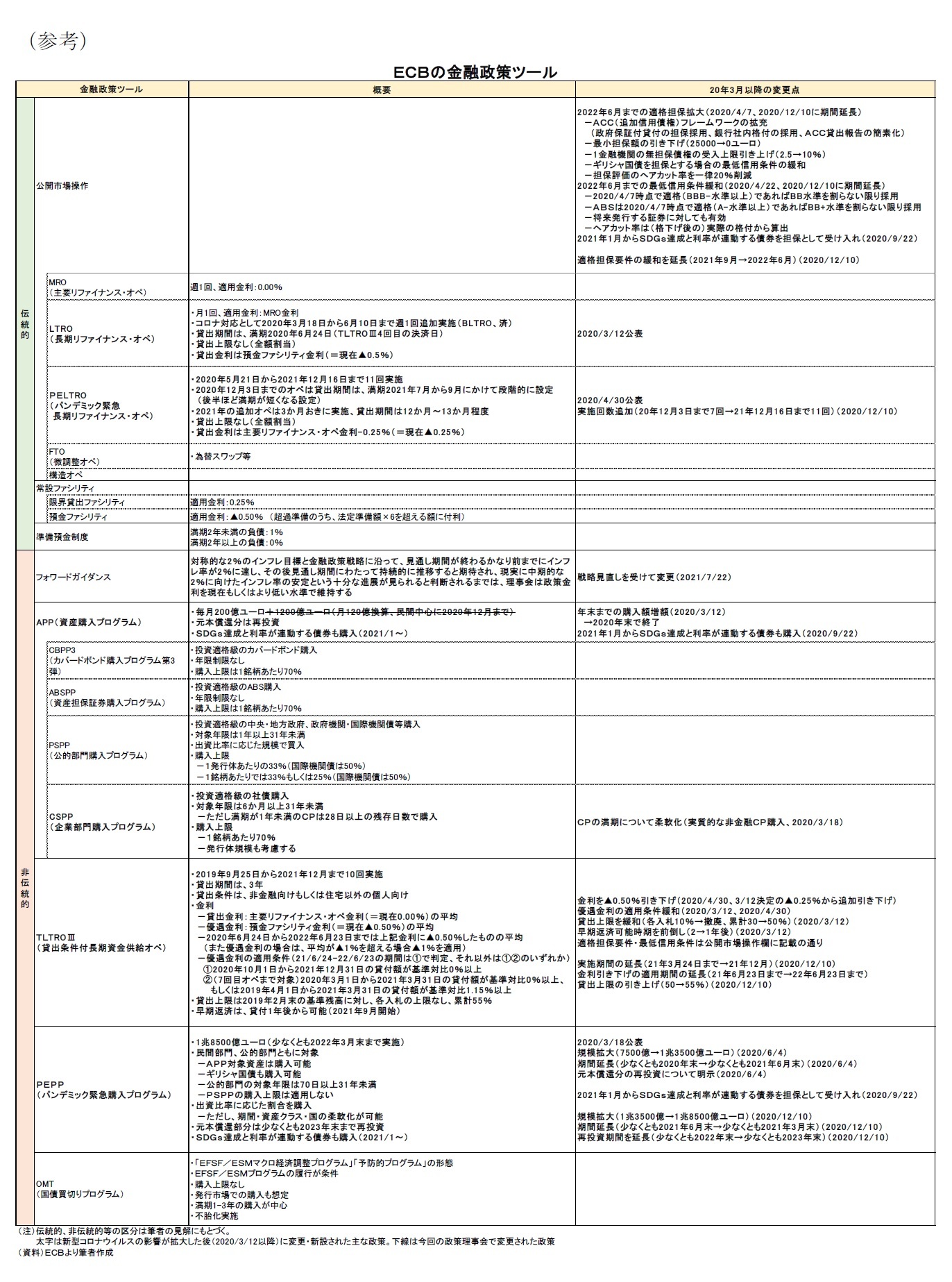

 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




