- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 経済 >
- 日本経済 >
- デフレ脱却宣言はいつ出るのか
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
政府は12/24に発表した12月の月例経済報告で、物価の判断を「底堅く推移している」とし、4年2ヵ月ぶりに「デフレ」の文言を削除した。ただし、日本経済がデフレに再び逆戻りするリスクを完全には排除できないことから、デフレ脱却宣言は見送った。
政府は2001年3月の月例経済報告でデフレの判断を行った後、2006年7月にはいったんデフレの文言を削除したが、「デフレ脱却宣言」を行う前にリーマン・ショックが発生し物価が大幅に下落したため、2009年11月以降は再びデフレという表現を使い続けてきた。
今度こそ「デフレ脱却宣言」は行われるのだろうか。その場合、それはいつ頃になるのだろうか。
政府は「デフレ脱却」の定義を「物価が持続的に下落する状況を脱し、再びそうした状況に戻る見込みがないこと」としており、判断に当たっては、「消費者物価指数」に加えて、「GDPデフレーター」、「単位労働コスト」、「需給ギャップ」を重視するとしている。
このうち、現時点ですでに上昇率がプラス圏に浮上しているのは消費者物価指数だけだが、前年比で大幅な下落が続いていたGDPデフレーターは2013年7-9月期にはマイナス幅が▲0.3%まで縮小しており、2013年度中にはプラスに転じる可能性が高い。また、「雇用者報酬/実質GDP」で表される単位労働コストは、賃金の伸び悩みを主因として2013年度中は下落が続きそうだが、2014年度に入ると企業業績の好調を受けた賃上げの実施が見込まれるため、上昇に転じることが予想される(図表1)。
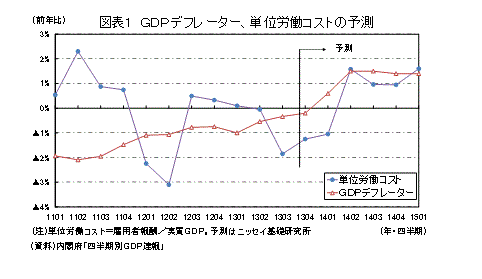
微妙なのは需給ギャップの動向だ。内閣府の試算によれば2013年7-9月期の需給ギャップ(=GDPギャップ)は▲1.6%となっている。依然としてマイナスだが、2013年に入り潜在成長率を上回る成長を続けたことで2012年後半の3%台からはマイナス幅が大きく縮小している。2013年度後半は消費税率引き上げ前の駆け込み需要が加わることで成長率が加速することが見込まれるため、2014年1-3月期の需給ギャップは約6年ぶりにプラス圏に浮上する可能性が高い。
問題は2014年度に入ってからだろう。当研究所では2014年4-6月期は駆け込み需要の反動を主因として大幅なマイナス成長となった後、7-9月期にはプラス成長に復帰すると予想している。ただし、消費税率引き上げに伴う実質所得低下の影響は2014年度を通して下押し圧力となるため、2013年度中のような高い成長は期待できないだろう。この結果、2013年度末にいったんプラスとなった需給ギャップは、2014年度入り後は再びマイナスの推移が続く可能性が高いと考えている(図表2)。
一方、12/21に発表された政府経済見通しでは、2014年度の実質GDP成長率を1.4%としており、当研究所の見通しよりもかなり強い。それでは、実質GDPが政府見通しに沿った動きとなった場合、先行きの需給ギャップはどうなるだろうか。
政府見通しは年度ベースの見通ししか示されていないため、日本経済センターの「ESPフォーキャスト調査」で集計されている民間エコノミストの平均的な予測値の四半期パターンを参考とし、2014年度の政府見通しを当研究所で四半期分割した上で2014年度末までの需給ギャップを試算した。
政府見通しに基づく試算値でも、需給ギャップは2014年1-3月期にプラスとなった後、4-6月期にはマイナスとなる。しかし、政府は2014年4-6月期の反動による落ち込みが小さく、7-9月期以降は比較的高めのプラス成長を予想していることが想定されるため、2014年度末にかけて需給ギャップがプラスに転じる姿となる(図表2)。
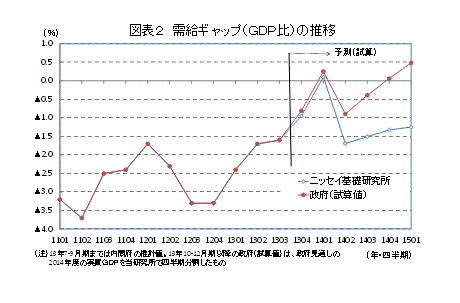
もちろん、これはあくまでも政府の年度見通しを当研究所で四半期分割した試算値であり、そもそも需給ギャップは定義や推計方法の違い等によってプラスマイナスの違いも含めて異なったものとなる。需給ギャップは相当の幅を持ってみるべき指標であるが、政府見通しが実現されれば、判断基準となる4指標の全てが2014年度中に「デフレ脱却」の条件を満たす可能性が高くなるということは言えるだろう。
ただし、「GDPデフレーター」、「単位労働コスト」、「需給ギャップ」はいずれもGDP関連指標であるため、消費者物価指数などの月次指標に比べて実績値の発表が遅いという難点がある。たとえば、需給ギャップが2014年10-12月期にプラスに転じた場合、それが判明するのは2015年2月になる。4指標に基づいて判断するとすれば、「デフレ脱却宣言」は早くても1年以上先のことになりそうだ。
(2013年12月26日「研究員の眼」)
このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836
- ・ 1992年:日本生命保険相互会社
・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ
・ 2019年8月より現職
・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)
・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)
・ 2018年~ 統計委員会専門委員
斎藤 太郎のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/24 | 消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |
| 2025/10/22 | 貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |
| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |
| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |
新着記事
-
2025年10月28日
試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -
2025年10月28日
地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -
2025年10月28日
東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -
2025年10月28日
今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -
2025年10月27日
大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【デフレ脱却宣言はいつ出るのか】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
デフレ脱却宣言はいつ出るのかのレポート Topへ


















 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




