- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- “サブプライム・ショック”の第二幕~実質住宅価格は12カ国で下落へ
コラム
2008年06月23日
米国金融機関の最新決算からは、サブプライムローン関連の損失が拡大していることが改めて確認されたが、OECDの「エコノミック・アウトルック」においては、「世界的な金融市場の混乱は最悪期を脱した」という見解が示されている。これは、証券化商品の保有額や評価損・実現損の規模が判らずに、信用不安が拡大した当初の状況とは異なり、事実が事実として把握され、問題の所在が明らかになっていることを評価し、市場への流動性供給も十分に行われていると判断したからであろう。
実際、緊急避難的な措置として政策金利の引き下げや市場への資金供給を行なってきたFRB(米国連邦準備制度理事会)やECB(欧州通貨銀行)の当局者は、それを打ち止めることを表明している。つまり、中央銀行にとっての優先的な政策課題は、原油など一次産品価格の上昇によるインフレ圧力の高まりに対処することに移ったということである。
実際、緊急避難的な措置として政策金利の引き下げや市場への資金供給を行なってきたFRB(米国連邦準備制度理事会)やECB(欧州通貨銀行)の当局者は、それを打ち止めることを表明している。つまり、中央銀行にとっての優先的な政策課題は、原油など一次産品価格の上昇によるインフレ圧力の高まりに対処することに移ったということである。
不幸なことに、こうした政策転換を前に、“サブプライム・ショック”の第二幕はすでに上がっている。各国の金融市場が証券化商品を通じて米国から間接的に影響を受ける局面から、国内に飛び火した要因から直接的な影響を受ける局面へと移っているのだ。
その要因とは、各国の住宅価格の下落である。一般物価上昇分を控除した実質ベースで見ると、統計が利用可能な先進17カ国のうち、90年代半ば以降の長期的な価格上昇を最近まで享受していたのが日本・韓国・ドイツ・スイスを除く13カ国、このうち、すでに価格下落へと転じた国はカナダ以外の12カ国にも及んでいる。昨年9月に「米国以外でも変調の兆しが見える住宅価格」と指摘した時には、実質ベースでも、価格下落が確認できたのはデンマークと米国のみであった。今や、当該リストには、英国・アイルランド・スペイン・フランス・オランダ・スウェーデン・ノルウェー・フィンランド・オーストラリア・ニュージーランドが加わり、12ヵ国に達している。この中には、最新の実質価格は直前の四半期と比べて低いが、前年同期と比べれば、まだ高いというケースも含まれているので、厳密には「横ばい、ないしは下落」と表現すべきかもしれない。しかし、永らく上昇が続いてきた状況とは、趨勢が一変している。
インフレ抑制のためとはいえ、こうした状況下での金融引き締めは、住宅価格を一段と下落させるリスクをはらんでいる。下落率が大きければ、購入資金の大半をローンに依存して住宅を取得した場合や、持家を担保とした借入れを行って、消費に用いた場合など、家計は債務超過状態に陥ってしまう。住宅価格が上昇を続けた過去10年の間に、各国の家計は、ほぼ例外なく、負債も大幅に増やしてきたからである。
しかも、2000年以降の実質価格上昇に関しては、米国の上昇幅はむしろ小さい方であり、「山高ければ、谷深し」の経験則が当てはまるならば、米国を上回る大幅な下落が起こる可能性のある国は少なくない。景気減速による所得減少や失業に直面すれば、債務超過に陥った家計がデフォルトする確率は更に高まる。しかも、債務超過には無縁の家計も含めて、資産としての住宅の価格下落は消費を抑制する要因として働く。
つまり、程度の差こそあれ、米国で起こったことは、潜在的には他の国でも起こり得る。注視すべき対象は、もはや、“サブプライム・ショック”に見舞われた金融機関の決算動向だけではないのだ。
その要因とは、各国の住宅価格の下落である。一般物価上昇分を控除した実質ベースで見ると、統計が利用可能な先進17カ国のうち、90年代半ば以降の長期的な価格上昇を最近まで享受していたのが日本・韓国・ドイツ・スイスを除く13カ国、このうち、すでに価格下落へと転じた国はカナダ以外の12カ国にも及んでいる。昨年9月に「米国以外でも変調の兆しが見える住宅価格」と指摘した時には、実質ベースでも、価格下落が確認できたのはデンマークと米国のみであった。今や、当該リストには、英国・アイルランド・スペイン・フランス・オランダ・スウェーデン・ノルウェー・フィンランド・オーストラリア・ニュージーランドが加わり、12ヵ国に達している。この中には、最新の実質価格は直前の四半期と比べて低いが、前年同期と比べれば、まだ高いというケースも含まれているので、厳密には「横ばい、ないしは下落」と表現すべきかもしれない。しかし、永らく上昇が続いてきた状況とは、趨勢が一変している。
インフレ抑制のためとはいえ、こうした状況下での金融引き締めは、住宅価格を一段と下落させるリスクをはらんでいる。下落率が大きければ、購入資金の大半をローンに依存して住宅を取得した場合や、持家を担保とした借入れを行って、消費に用いた場合など、家計は債務超過状態に陥ってしまう。住宅価格が上昇を続けた過去10年の間に、各国の家計は、ほぼ例外なく、負債も大幅に増やしてきたからである。
しかも、2000年以降の実質価格上昇に関しては、米国の上昇幅はむしろ小さい方であり、「山高ければ、谷深し」の経験則が当てはまるならば、米国を上回る大幅な下落が起こる可能性のある国は少なくない。景気減速による所得減少や失業に直面すれば、債務超過に陥った家計がデフォルトする確率は更に高まる。しかも、債務超過には無縁の家計も含めて、資産としての住宅の価格下落は消費を抑制する要因として働く。
つまり、程度の差こそあれ、米国で起こったことは、潜在的には他の国でも起こり得る。注視すべき対象は、もはや、“サブプライム・ショック”に見舞われた金融機関の決算動向だけではないのだ。
(2008年06月23日「研究員の眼」)
このレポートの関連カテゴリ
石川 達哉
石川 達哉のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2018/12/28 | 同床異夢の臨時財政対策債-償還費を本当に負担するのは国か、地方か? | 石川 達哉 | 研究員の眼 |
| 2018/07/13 | 「地方財源不足額」は本当に解消されているのか?―先送りされ続ける臨時財政対策債の償還財源確保 | 石川 達哉 | 基礎研レポート |
| 2017/08/31 | 再び問われる交付税特会の行方-地方財政の健全性は高まったのか? | 石川 達哉 | 基礎研レポート |
| 2017/07/03 | 増大する地方公共団体の基金残高 その2-実は拡大している積立不足!? | 石川 達哉 | 研究員の眼 |
新着記事
-
2025年10月15日
「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -
2025年10月15日
IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 -
2025年10月15日
中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -
2025年10月15日
芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立 -
2025年10月15日
英国雇用関連統計(25年9月)-週平均賃金は前年比5.0%まで再び上昇
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【“サブプライム・ショック”の第二幕~実質住宅価格は12カ国で下落へ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
“サブプライム・ショック”の第二幕~実質住宅価格は12カ国で下落へのレポート Topへ


















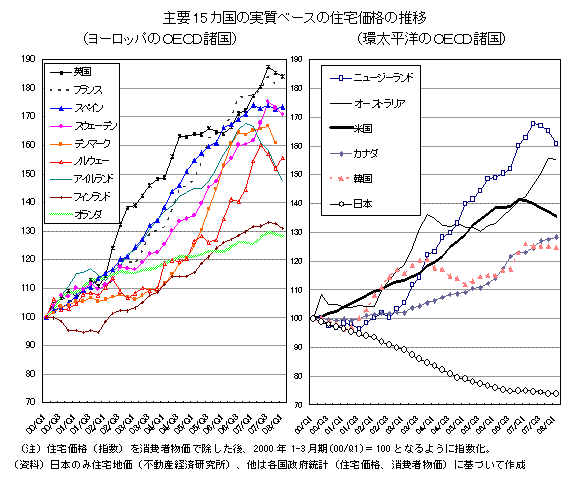

 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




