- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 経済 >
- 日本経済 >
- 日本版政府系ファンドは成功するか?
コラム
2007年12月10日
1.増大する政府系ファンド
中国は為替市場への介入で外貨準備が1兆5000億ドルに迫る水準にまで増加しており、これを運用する「中国投資有限責任公司」を設立した。資本金が2000億ドル(約23兆円)にものぼる巨大ファンドで、金融市場ではその動向が注目されている。
国が保有している外貨資産を運用する政府系ファンド(ソブリン・ウエルス・ファンド)は昔から、産油国の資金によるものやシンガポールの政府投資公社などが有名である。天然資源である原油はいずれ枯渇してしまうので、原油を輸出して得た資金を将来のために運用して増やす必要がある。産油国の資金は、昔からオイル・マネーと呼ばれて世界の金融市場に大きな影響を与えてきた。最近では、アジア通貨危機以来世界各国が外貨準備を多めに保有しようとしてきたこともあって、外貨準備が大きく増加しこれを運用する政府系ファンドが注目されるようになっている。世界の外貨準備の合計はIMFの統計では2007年6月末で5.7兆ドルにものぼる。政府系ファンドの影響が大きくなってきたことから、G7でも政府系ファンドの問題が議論されるようになっている。
国が保有している外貨資産を運用する政府系ファンド(ソブリン・ウエルス・ファンド)は昔から、産油国の資金によるものやシンガポールの政府投資公社などが有名である。天然資源である原油はいずれ枯渇してしまうので、原油を輸出して得た資金を将来のために運用して増やす必要がある。産油国の資金は、昔からオイル・マネーと呼ばれて世界の金融市場に大きな影響を与えてきた。最近では、アジア通貨危機以来世界各国が外貨準備を多めに保有しようとしてきたこともあって、外貨準備が大きく増加しこれを運用する政府系ファンドが注目されるようになっている。世界の外貨準備の合計はIMFの統計では2007年6月末で5.7兆ドルにものぼる。政府系ファンドの影響が大きくなってきたことから、G7でも政府系ファンドの問題が議論されるようになっている。
2.日本の外貨準備と政府系ファンド
日本の外貨準備は11月末現在で9701億8500万ドルとなり、中国には及ばないものの世界第二位となる巨額なものである。財務省は外貨準備の運用利回りを初めて公表したが、これによれば2002年度から2006年度までの5年間の利回りの平均は3.16%だった。この間の米国財務省証券(10年もの)の平均利回りが4.38%だったことを考えると、運用利回りは高いとは言えない。
外貨準備の原資は財務省証券を発行することによって賄われている。日本が現在のような低金利を続けている間は問題がないが、将来国内金利が上昇すれば大幅な逆鞘に陥る危険もある。これを避けるためには、できるだけ運用利回りを上げることが考えられる。運用の素人であるお役人に任せるよりは、運用のプロに任せた方が良い成果が得られるはずだということが、日本も政府系ファンドを作ってはどうかという考えの基にある。
またこの議論の背景には、ドルに偏りすぎている日本の外貨準備を分散させたいという思惑も見え隠れする。政府が運用している外貨準備の中身をドル資産から他の資産へと比重を移せば、すぐに衆知のこととなり国際金融市場に大きな影響を与えてしまう。しかしファンドにしてしまえば、運用の実態は分からなくなる。
しかし、現実にはそううまくは行かないだろう。日本の政府系ファンドが大量の資金をドルから他の通貨にシフトすれば、為替市場では需給が崩れてドルの下落が加速する。円高恐怖症の日本企業から円売り・ドル買い介入をすべきという声が高まり、外貨準備をファンドに移して分散させたはずのドル資産がまた増えてしまう可能性が高い。
また、収益をあげるためにはリスクを取る必要があるが、失敗すれば国民の資産を減らすことになる。運用をプロに任せるとは言うものの、失敗をしないように様々な制約を付けざるを得ない。結局、プロを雇っても自由には運用できず、失敗したときの言い訳ばかり考えて運用されるようになってしまうのではないか。
外貨準備の原資は財務省証券を発行することによって賄われている。日本が現在のような低金利を続けている間は問題がないが、将来国内金利が上昇すれば大幅な逆鞘に陥る危険もある。これを避けるためには、できるだけ運用利回りを上げることが考えられる。運用の素人であるお役人に任せるよりは、運用のプロに任せた方が良い成果が得られるはずだということが、日本も政府系ファンドを作ってはどうかという考えの基にある。
またこの議論の背景には、ドルに偏りすぎている日本の外貨準備を分散させたいという思惑も見え隠れする。政府が運用している外貨準備の中身をドル資産から他の資産へと比重を移せば、すぐに衆知のこととなり国際金融市場に大きな影響を与えてしまう。しかしファンドにしてしまえば、運用の実態は分からなくなる。
しかし、現実にはそううまくは行かないだろう。日本の政府系ファンドが大量の資金をドルから他の通貨にシフトすれば、為替市場では需給が崩れてドルの下落が加速する。円高恐怖症の日本企業から円売り・ドル買い介入をすべきという声が高まり、外貨準備をファンドに移して分散させたはずのドル資産がまた増えてしまう可能性が高い。
また、収益をあげるためにはリスクを取る必要があるが、失敗すれば国民の資産を減らすことになる。運用をプロに任せるとは言うものの、失敗をしないように様々な制約を付けざるを得ない。結局、プロを雇っても自由には運用できず、失敗したときの言い訳ばかり考えて運用されるようになってしまうのではないか。
3.求められる円高恐怖症の克服
実は変動相場制を採用している日本には、1兆ドル近くにものぼる規模の外貨準備を保有している必要性はない。将来の国内金利の上昇や為替レートの変動によるリスクを回避するために、本来は過剰な外貨準備を売却して政府の債務を削減すべきなのだ。現在のように1ドル110円近い水準まで円が上昇した後では、まさに後知恵と言われるだろうが、円安が1ドル120円台にまで進んだ状況で、ドルを売っておけばよかったのだ。しかし円高恐怖症に陥っている日本では、円高が起これば即円売り介入を求める声が出てくるものの、多少円安になったからと言って外貨を売るという発想はわいてこない。
2003年に年間30兆円にものぼる介入を行ったときには、日本経済をデフレスパイラルから救うための非常手段という意味があった。しかし、円高が起こるたびに介入でなんとかしようという発想の裏には、外需頼みで景気を支えようという考えがある。こうした外需頼みの回復は限界に達しているのではないか。そろそろ円高恐怖症を克服して、内需中心の経済成長を実現するための方策を真剣に模索しないと、いつまでたっても日本経済は「本格的な回復」という状態にはならないだろう。
2003年に年間30兆円にものぼる介入を行ったときには、日本経済をデフレスパイラルから救うための非常手段という意味があった。しかし、円高が起こるたびに介入でなんとかしようという発想の裏には、外需頼みで景気を支えようという考えがある。こうした外需頼みの回復は限界に達しているのではないか。そろそろ円高恐怖症を克服して、内需中心の経済成長を実現するための方策を真剣に模索しないと、いつまでたっても日本経済は「本格的な回復」という状態にはならないだろう。
(2007年12月10日「エコノミストの眼」)
櫨(はじ) 浩一 (はじ こういち)
櫨(はじ) 浩一のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2020/03/06 | 不安の時代ー過剰な貯蓄を回避する保険の意義 | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研マンスリー |
| 2020/02/27 | MMTを考える | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研レポート |
| 2020/02/07 | 令和の日本経済はどうなるか-経済予測の限界と意義 | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研マンスリー |
| 2020/01/31 | 不安の時代~過剰な貯蓄を回避する保険の意義~ | 櫨(はじ) 浩一 | エコノミストの眼 |
新着記事
-
2025年10月21日
今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】 -
2025年10月20日
中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -
2025年10月20日
ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -
2025年10月20日
家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -
2025年10月20日
縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【日本版政府系ファンドは成功するか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
日本版政府系ファンドは成功するか?のレポート Topへ


















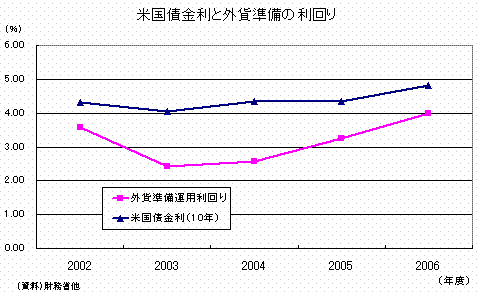

 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




