- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 経済 >
- アジア経済 >
- グローバルな金融環境の変化~試されるエマージング市場の対応力~
コラム
2006年06月05日
| 1.引き金はリスクマネー収縮への懸念 世界的な長期金利の低位安定と潤沢なリスクマネーの流入を背景に活況が続いたエマージング市場が、5月に一転して株、債券、通貨のトリプル安に見舞われた。 エマージング株式市場の代表的指数であるMSCI指数(ドル建て)は5月8日に2002年末比で201.8%高のピークをつけた後、同24日までに15.5%下落した。エマージング債券のリスク・プレミアムを示す米国債に対するスプレッド(利回り格差)も、5月1日のボトムの176.1bpから24日には222.8bpまで拡大した。 広く知られているとおり、今回のエマージング市場の調整は、米国、日本、欧州での株価の下落、高騰が続いた商品市況のピークアウト、米国債など低リスク資産の価格上昇と同時に進行した。欧州、日本の利上げ観測に加えて、世界のマネー・フローの中核で、製品の需要アブソーバーでもある米国の金融政策の先行き不透明感の強まり、物価上昇と景気失速への懸念が広がったことがきっかけで、「質への逃避」が生じたものと考えられる。 2003年以降、米金利の上昇懸念で市場に調整が加わる局面は2004年4~5月、2005年3~4月、2005年10月にもあった。今回の調整を、MSCI指数が5月8日から市場が一旦下げ止まった5月24日までとすると、過去3回に比べて進行のペースは速かったが、調整の幅は米国の利上げ開始が材料となった2004年4~5月を下回るものに留まった。
2.厳しさを増すファンダメンタルズへの評価 世界の株式市場で5月中のドル・ベースに換算した下げ幅が最も大きかったのはトルコだ。株価の13.7%の下落に加え、債券市場からの資本流出も加わり対ドル・レートも大幅に減価したことで、ドル・ベースの株価下落率は27.0%となった。 トルコは2000~2001年の金融危機以降、IMFによる管理とEU加盟という目標の下で、財政の健全化とインフレの抑制に成功、外資の流入も拡大するなど順調な回復を遂げてきた。しかし、高成長の持続と通貨リラの割高化で、経常収支は2005年にGDP比で6.4%と危機前を上回る水準に拡大、一桁台に達したインフレ率も2005年10月を底に上昇に転じていた。4月末に、昨年12月以降据え置かれてきた政策金利の引き下げが実施されたが、その後、4月のインフレ率が3月の8.8%から9.9%にさらに上昇、経常収支の拡大傾向も確認されたことなどが売り材料となった。 現地通貨建ての株価下落率では、エジプト(マイナス19.2%)、コロンビア(マイナス18.3%)、サウジアラビア(マイナス16.5%)、ドバイ(マイナス16.4%)、カタール(マイナス15.9%)など、近年株価が急伸し割高化が進んだ市場で大きいものとなった。日本からも株式投資が集中的に拡大したインド(注1)でも、代表的株価指数であるSENSEX指数が13.6%下落、資本流出に伴うルピー安も進んだため、ドル換算での下落率は16.6%となった。 インドの株式市場は、市場規模の厚み、高い成長率、規制緩和などを背景に外資が流入し、今年4月末までに株価は2002年末比で3.7倍、時価総額で4.7倍となり、東証の1割強に過ぎなかった時価総額は3割近くにまで拡大した(注2)。5月に入ってからも、10日まで8営業日連続で史上最高値を更新する過熱相場が続いていたが、グローバルな金融環境の変化とともに、海外投資家に対する課税が強化されるとの観測が広がったことで(注3)、外国人投資家が売り越しに転じ下げ幅が拡大した。 インドの場合も、2005年度(2005年4月~2006年3月)の成長率は8.4%と期待通りの高い成長を続けているが、その反面で経常赤字は過去の経済危機前(90年)を上回る水準に達し、そのファイナンスを証券投資など潜在的に逃げ足の速い資金に依存する度合いも高まっている。直近のデータは、成長加速の反面で、経常赤字はピークアウト、赤字の主因である貿易赤字の増勢は鈍化、競争力を持つITサービス輸出が拡大、直接投資の流入は増加するなど好材料も少なくないが、経済ファンダメンタルズに対する市場の目は従来よりも厳しさを増しているようだ。 3.試される環境変化への適応力 エマージング市場の当面の調整は、過去3回と同じく、深刻化しないとの見方が今のところは支配的だ。金融・為替政策の枠組みの改善、金融システムの健全化、対外債務構造の改善、外貨準備の積み増しによって金融環境変化への対応力は格段に向上している。長期的な成長力への期待の下方修正を必要とするような材料も見当たらないからだ。 しかし、エマージング諸国は押し並べて輸出依存度が高く、産油国や資源国、中国、韓国、台湾などアジアの一部を除き経常収支は赤字となっているため、成長の持続力は外部環境に大きく左右されざるを得ない。米国の金融政策は経済指標次第とされ見極めに時間を要する一方、超金融緩和政策を継続していた日本、欧州が金融政策正常化の前進が確実視される状況にあって、リスクマネーの収縮や世界景気の減速への懸念は燻り続ける。 選別の目が厳しさを増す中、エマージング諸国には従来以上に手堅い政策運営が求められることになろう。
|
(2006年06月05日「エコノミストの眼」)

03-3512-1832
経歴
- ・ 1987年 日本興業銀行入行
・ 2001年 ニッセイ基礎研究所入社
・ 2023年7月から現職
・ 2015~2024年度 早稲田大学商学学術院非常勤講師
・ 2017年度~ 日本EU学会理事
・ 2017~2024年度 日本経済団体連合会21世紀政策研究所研究委員
・ 2020~2022年度 日本国際フォーラム「米中覇権競争とインド太平洋地経学」、
「欧州政策パネル」メンバー
・ 2022~2024年度 Discuss Japan編集委員
・ 2022年5月~ ジェトロ情報媒体に対する外部評価委員会委員
・ 2023年11月~ 経済産業省 産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会 委員
・ 2024年10月~ 雑誌『外交』編集委員
・ 2025年5月~ 経団連総合政策研究所特任研究主幹
伊藤 さゆりのレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2025/09/30 | ドル離れとユーロ-地位向上を阻む内圧と外圧- | 伊藤 さゆり | |
| 2025/09/12 | 欧州経済見通し-関税合意後も不確実性が残る状況は続く | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |
| 2025/08/26 | 大砲かバターか-国防費の大幅引き上げに動く欧州の現実 | 伊藤 さゆり | 研究員の眼 |
| 2025/08/04 | 米EU関税合意-実効性・持続性に疑問符 | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |
新着記事
-
2025年11月04日
今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -
2025年10月31日
交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -
2025年10月31日
ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -
2025年10月31日
2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -
2025年10月31日
保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【グローバルな金融環境の変化~試されるエマージング市場の対応力~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
グローバルな金融環境の変化~試されるエマージング市場の対応力~のレポート Topへ

















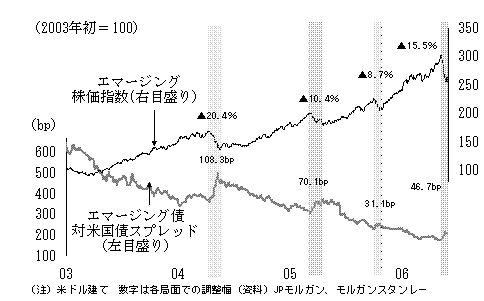

 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




