- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 経済 >
- 日本経済 >
- 赤字化する貿易・サービス収支
コラム
2004年10月25日
1.GNPは死なず 「くたばれGNP!」などというセリフを言おうものなら、それこそ年齢がバレてしまうだろう。経済学の教科書にはGNP(Gross National Product、国民総生産)はまだ残っているものの、新聞やテレビなどのマスコミにはGNPという用語は全く登場しなくなってしまった。それもそのはず、政府が発表しているGDP統計(国民経済計算)では、GNPという用語自体が無くなってしまっている。 GNPに替わって日本経済の規模を表す指標として現在使われているのは、ご承知のとおりGDP(Gross Domestic Product、国内総生産)である(この間の事情は2002年10月4日号の「エコノミストの眼」に詳しい)。しかし、「老兵は死なず、ただ消え去るのみ」と言ったのはマッカーサーだが(マッカーサーもそろそろ知らない人の方が多くなったかも知れない)、どっこいGNPはGNI(Gross National Income、国民総所得)」と名前を変えてはいるものの、ちゃんと生き残っている。 2.日本は世界一の金持ち GDPとGNI(GNP)の違いで、最も大きな要因は、日本が海外に持っている資産からの収入がGNIには入るが、GDPには含まれないことだ。2002年度では、GDPは497.6兆円であるのに対してGNIは505.7兆円と、その差は8兆円あまりもある。これは、長年日本経済が経常収支の黒字を続けたために、それが対外資産として積み上がり、その資産から生じる利子や配当などの所得が増加してきたためだ。 2003年末の時点で、日本が海外に持っている資産は385.5兆円、一方負債の方は、212.7兆円で、差し引き172.8兆円の純資産がある。日本は世界一の金持ちなのである。今後も日本経済は経常収支が黒字という状況が続くと予想されるので、日本の対外資産はさらに膨らんでいく。そして、対外資産から生じる所得も増加していき、GDPとGNIの差はさらに拡大していくことが見込まれる。GNPは単に名前を変えて生き残っただけではなく、GDPとGNI(GNP)の違いは、これからの日本経済にとって大きな意味を持つようになるはずである。 3.消える貿易・サービス収支の黒字 経常収支の黒字の存在は、長年にわたって円高傾向が続いている最も大きな要因である。このまま円高傾向が続けば、次第に日本からの輸出は厳しくなって輸入が増加していくが、経常収支が黒字なので円高傾向はなかなか終わらないだろう。いずれは輸入が輸出を上回って、貿易・サービス収支が赤字になるはずだ。後10年もたてば、日本の経常収支黒字の中身は、日本が海外にもっている資産からの所得だけになり、貿易・サービス収支は赤字化してしまうだろう。 貿易・サービス収支の黒字が消えてなくなる過程では、GDPで計られる日本の経済成長率は、外需のマイナス寄与分だけ低下する。日本経済は、ここまで輸出主導で経済成長を続けてきたが、将来はむしろ貿易が経済成長の足を引っ張る形になるはずである。
4.本当に怖いのは円高より円安 我々の発想も大きな転換を迫られる。生産の拡大は消費を拡大してより豊かな生活を送るために必要なだけなのだから、問題なのは生産の規模を示すGDPではなくて、財産所得も含めたGNIの方である。家計にたとえれば、所得収支の黒字は、預貯金の利子や株の配当など財産所得が多いことを意味している。財産所得が多ければ、働いて得る月給が少なくても豊かな生活が送れて、しかも財産は増えてゆくということである。 貿易・サービス収支の赤字は、毎年働いて稼ぐお金以上にモノが買えて、サービスも享受できているということだ。それでいて経常収支は黒字なのだから、日本が海外に持っている財産は増えていく。生産者の観点から貿易・サービス収支の赤字化を見れば大変な時代なのだが、消費者の観点から見れば、これは幸せな時代なのだ。 むしろ本当に問題なのは、その先に来る変化であろう。高齢化がさらに進んだ21世紀半ばになると、所得収支の黒字では貿易・サービス収支の赤字が賄えなくなり、経常収支が赤字化する時代がやってくる可能性が高い。日本は、海外に持っている資産を食い潰していくことになり、長く続いた円高も完全に終わりを告げて、円安に転じる日が来るはずである。輸出がしやすくなり輸入は難しくなるので、それは生産者にとっては良い知らせかも知れないが、消費者にとっては決して明るい知らせではないだろう。 |
(2004年10月25日「エコノミストの眼」)
櫨(はじ) 浩一 (はじ こういち)
櫨(はじ) 浩一のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2020/03/06 | 不安の時代ー過剰な貯蓄を回避する保険の意義 | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研マンスリー |
| 2020/02/27 | MMTを考える | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研レポート |
| 2020/02/07 | 令和の日本経済はどうなるか-経済予測の限界と意義 | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研マンスリー |
| 2020/01/31 | 不安の時代~過剰な貯蓄を回避する保険の意義~ | 櫨(はじ) 浩一 | エコノミストの眼 |
新着記事
-
2025年10月21日
選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -
2025年10月21日
連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を -
2025年10月21日
インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 -
2025年10月21日
中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) -
2025年10月21日
今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【赤字化する貿易・サービス収支】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
赤字化する貿易・サービス収支のレポート Topへ


















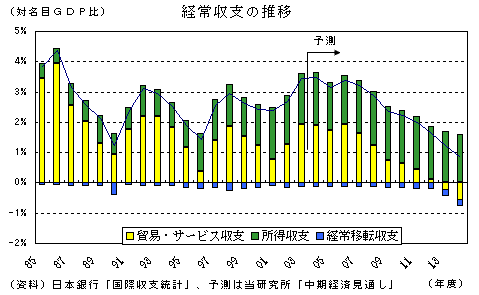

 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




