- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 経済 >
- 日本経済 >
- うるう年の経済効果
コラム
2004年01月26日
| 1.今年は四年に一度のうるう年 今年は四年に一度のうるう年である。前回のうるう年はコンピューターの2000年問題が重なったこともあり大きな混乱が生じた(*)が、今回はそのようなことはなさそうだ。しかし、日数が平年よりも一日多いことにより経済活動の水準が嵩上げされるという、うるう年特有の事象は今回も必ず発生する。 (*)コンピューターが西暦年号を下二桁だけで管理していたため、西暦2000年を1900年と認識して誤作動を起してしまう恐れがあったという問題。さらに、うるう年の規則は「西暦年数が4で割り切れる年は原則としてうるう年だが、例外として100で割り切れる年は平年とする。さらに例外として400で割り切れる年はうるう年とする」となっており、前回のうるう年は例外のさらに例外が適用されるものだったため、コンピューターの混乱も予想された。 2.日数増により押し上げられる1-3月期の個人消費 まず、うるう年による1日の増加分がどのくらいのインパクトを持つかを単純に計算してみると、年間では1/365=0.3%、四半期(1-3月期)では1/90=1.1%、月間(2月)では1/28=3.6%ということになる。1年間で均してしまえばそれほど大きなものとは言えないが、四半期、月間では無視できない大きさと言えるだろう。 もちろん、日数が多くなるといっても経済活動全てに影響があるという訳ではない。たとえば、企業の設備投資について言えば、ほとんどの企業は年間(あるいは半期、四半期)単位で設備投資額を計画しているため、日数が一日多いからといってその分設備投資が増えるということにはならないだろう。 逆に、個人消費は少なからず日数の影響を受ける。たとえば、人は毎日食べたり飲んだりするので、日数が増えればその分だけ食費が増えると考えられる。一方、家賃、定期代、駐車場代などのように月極めで毎月の支払額が決まっているものについては、日数は関係ないはずだ。 そこで、「家計調査(総務省統計局)」を用いて消費支出全体に占める月極め払いとそれ以外の割合を求め、月極め払い以外の項目だけ日数の影響を受けるとして試算すると、日数の増加により個人消費は2月は2.6%、1-3月期は0.8%、年間(2004年あるいは2003年度)では0.2%押し上げられるという結果になる。GDPに占める個人消費の割合は6割弱だから、GDPは1-3月期は0.4%、年間(2004年あるいは2003年度)では0.1%押し上げられることになる。 年間を通しての効果はそれほど大きなものではないが、四半期あるいは月次で考えると目に見える影響が出てくることは確実である。特に、個人消費関連統計の2月分に関しては、発表される数字を額面通りに受け取ってしまうと、実力を過大評価してしまうことになる。前年比で見る場合には3%弱程度割り引いて見ることが必要だろう。 3.うるう年効果による高成長は過去の話 このように、うるう年で日数が多いことが1-3月期の経済活動の水準を嵩上げすることは確実だが、それによって1-3月期は高成長が期待できるのだろうか。 残念ながら答えは否である。確かに、GDPの実額は押し上げられるので前年比の伸びは高くなる。しかし、GDP統計で最も注目される前期比(季節調整済)成長率はうるう年の影響で高まることはない。 これまでうるう年の1-3月期といえば、いつも極端な高成長となり波紋をよんだものである。前回のうるう年(2000年1-3月期)の実質GDP成長率は、前期比2.4%(年率10.0%)、前々回(96年1-3月期)は前期比3.0%(年率12.7%)であった(いずれも発表当時の数値)。景気の実勢が比較的強かったこともあるが、当時のGDP統計は季節調整でうるう年の影響が除去されていなかったことも高成長の一因であった。 しかし、その後内閣府は季節調整の方法を改め、現在ではうるう年を考慮した季節調整法を用いている。日数が多いことによって個人消費が増えたとしても、季節調整をかければその影響が除去されるようになっている。うるう年のおかげで1-3月期が高成長になるというのは、実はもはや過去の話なのである。 |
(2004年01月26日「エコノミストの眼」)

03-3512-1836
経歴
- ・ 1992年:日本生命保険相互会社
・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ
・ 2019年8月より現職
・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)
・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)
・ 2018年~ 統計委員会専門委員
斎藤 太郎のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |
| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |
| 2025/09/19 | 消費者物価(全国25年8月)-コアCPIは9ヵ月ぶりの3%割れ、年末には2%程度まで鈍化する見通し | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |
| 2025/09/17 | 貿易統計25年8月-関税引き上げの影響が顕在化し、米国向け自動車輸出が数量ベースで大きく落ち込む | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |
新着記事
-
2025年10月16日
EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- -
2025年10月16日
再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ -
2025年10月15日
インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -
2025年10月15日
「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -
2025年10月15日
IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【うるう年の経済効果】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
うるう年の経済効果のレポート Topへ

















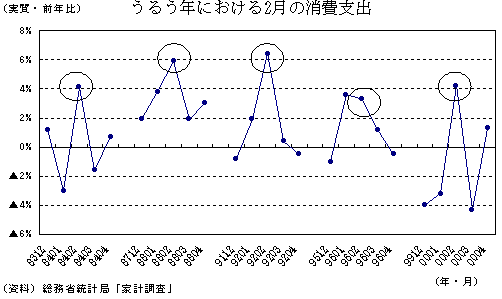

 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




