- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 金融・為替 >
- 金融政策 >
- マイナス金利の影響~私たちのくらしはどう変わる?
コラム
2016年02月09日
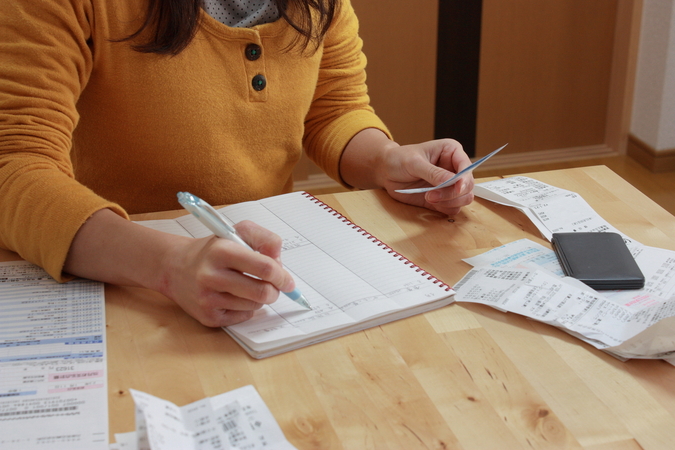
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
借りた物は返す。通常はお礼に粗品などを添えて返すこともあるだろう。お金を借りた人は利息を付けて返すのが普通である。マイナス金利ではお金を借りた人が利息を受け取る。つまり、お金を借りても全額は返さなくて良いことになる。
ついに日本でもマイナス金利が導入された。導入されてから10日あまり経過するが、その影響は様々なところで現れ始めている。銀行では定期預金や普通預金金利の引き下げが相次いでいる。証券会社等で預金に近い性質を持つMMFは売り止めになり、更に一部では運用を停止して資金を返却するところもある。個人向けに販売されている国債は、金利に下限がない方式のものについては手数料控除後でマイナス金利になるため募集が中止された。住宅ローン金利も引き下げられている。そして、10年長期国債金利もついにマイナスに突入した。
マイナス金利政策は、これまでの金融政策(量的・質的金融緩和)と性質が大きく異なると考えられる。これまで日銀は国債を大量に購入していたものの、そのお金は金融機関が日銀当座預金に預けるため結局日銀に戻ってきていた。日銀当座預金には0.1%の利息が付くため、金融機関はそれより低い利回りの国債で運用するよりも、日銀に預ける方が有利だった。今回はこの日銀当座預金の利率を-0.1%にするということなので、金融機関は国債売却資金を日銀に預けると損してしまう。そのため、別の方法で運用しなければならなくなった。これまで日銀に預けるよう誘導されていた資金が、逆に日銀に預けないように誘導される。いわば180度逆の方向に動かなければならなくなった。
金融機関はマイナス金利を避けるために、現金で持っていれば良いかというとそうでもない。日銀は全ての当座預金にマイナス金利を適用するのではなく、残高に応じて3段階(+0.1%、0%、-0.1%)の金利を適用している。金融機関の現金保有額が大きく増加した場合、その分は日銀当座預金に預けていると見なされ、日銀がプラス付与している当座預金金利にマイナス金利が適用される。つまり、金融機関が現金保有額を増やすと、実質的にマイナス金利が適用されてしまう。金融機関は現金以外の方法で資金を運用する必要に迫られている。こうなると、金融機関の収益は圧迫され私たちが銀行に預ける普通預金もマイナス金利になる可能性がある。そのため、日銀はマイナス金利が適用される残高を一定の範囲内(10~30兆円)に限定する考えである。金融機関の収益をできるだけ圧迫せず、国債金利のみをマイナスに誘導しようとしている。
マイナス金利政策は、金利そのものを直接下方に誘導するため、金利低下効果は非常に大きい。実際にマイナス金利政策が導入されてから、国債金利は今回の金利引き下げ分(+0.1%と-0.1%の差)0.2%分がほぼそのまま低下している。今後、日銀がマイナス幅を拡大すれば、国債金利のマイナス幅も更に拡大すると考えられる。
このようにマイナス金利政策は、金利そのものを狙い通り低下させているが、それが需要拡大につながるかどうかは不明である。また、金利が海外との比較で相対的に低くなり、円が流出するため円安になるとの見方もあったが、現在はマイナス金利導入時よりも円高になっている。
マイナス金利政策は、住宅ローンや預金金利など私たちの生活に直接的な影響を及ぼすが、今後更に影響が拡がる恐れもある。既に大企業の普通預金から手数料を取ることを検討している金融機関がある。欧州ではマイナス金利で金融機関の収益が圧迫されるため、住宅ローン金利が逆に上昇する例がある。個人の預金金利をマイナスにしないため、それを維持するための損失をローンの債務者に転嫁している。マイナス金利は私たちも始めての経験であるが、今後も様々な動きが出てくる可能性があり、その動向に対応していかなければならない。
ついに日本でもマイナス金利が導入された。導入されてから10日あまり経過するが、その影響は様々なところで現れ始めている。銀行では定期預金や普通預金金利の引き下げが相次いでいる。証券会社等で預金に近い性質を持つMMFは売り止めになり、更に一部では運用を停止して資金を返却するところもある。個人向けに販売されている国債は、金利に下限がない方式のものについては手数料控除後でマイナス金利になるため募集が中止された。住宅ローン金利も引き下げられている。そして、10年長期国債金利もついにマイナスに突入した。
マイナス金利政策は、これまでの金融政策(量的・質的金融緩和)と性質が大きく異なると考えられる。これまで日銀は国債を大量に購入していたものの、そのお金は金融機関が日銀当座預金に預けるため結局日銀に戻ってきていた。日銀当座預金には0.1%の利息が付くため、金融機関はそれより低い利回りの国債で運用するよりも、日銀に預ける方が有利だった。今回はこの日銀当座預金の利率を-0.1%にするということなので、金融機関は国債売却資金を日銀に預けると損してしまう。そのため、別の方法で運用しなければならなくなった。これまで日銀に預けるよう誘導されていた資金が、逆に日銀に預けないように誘導される。いわば180度逆の方向に動かなければならなくなった。
金融機関はマイナス金利を避けるために、現金で持っていれば良いかというとそうでもない。日銀は全ての当座預金にマイナス金利を適用するのではなく、残高に応じて3段階(+0.1%、0%、-0.1%)の金利を適用している。金融機関の現金保有額が大きく増加した場合、その分は日銀当座預金に預けていると見なされ、日銀がプラス付与している当座預金金利にマイナス金利が適用される。つまり、金融機関が現金保有額を増やすと、実質的にマイナス金利が適用されてしまう。金融機関は現金以外の方法で資金を運用する必要に迫られている。こうなると、金融機関の収益は圧迫され私たちが銀行に預ける普通預金もマイナス金利になる可能性がある。そのため、日銀はマイナス金利が適用される残高を一定の範囲内(10~30兆円)に限定する考えである。金融機関の収益をできるだけ圧迫せず、国債金利のみをマイナスに誘導しようとしている。
マイナス金利政策は、金利そのものを直接下方に誘導するため、金利低下効果は非常に大きい。実際にマイナス金利政策が導入されてから、国債金利は今回の金利引き下げ分(+0.1%と-0.1%の差)0.2%分がほぼそのまま低下している。今後、日銀がマイナス幅を拡大すれば、国債金利のマイナス幅も更に拡大すると考えられる。
このようにマイナス金利政策は、金利そのものを狙い通り低下させているが、それが需要拡大につながるかどうかは不明である。また、金利が海外との比較で相対的に低くなり、円が流出するため円安になるとの見方もあったが、現在はマイナス金利導入時よりも円高になっている。
マイナス金利政策は、住宅ローンや預金金利など私たちの生活に直接的な影響を及ぼすが、今後更に影響が拡がる恐れもある。既に大企業の普通預金から手数料を取ることを検討している金融機関がある。欧州ではマイナス金利で金融機関の収益が圧迫されるため、住宅ローン金利が逆に上昇する例がある。個人の預金金利をマイナスにしないため、それを維持するための損失をローンの債務者に転嫁している。マイナス金利は私たちも始めての経験であるが、今後も様々な動きが出てくる可能性があり、その動向に対応していかなければならない。
(2016年02月09日「研究員の眼」)
千田 英明
千田 英明のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2017/03/07 | マイナス金利下における国内債券運用 | 千田 英明 | 基礎研レポート |
| 2016/11/04 | マイナス金利で見直される個人向け国債 | 千田 英明 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 2016/10/17 | 収穫の秋、運用では種まきの秋 | 千田 英明 | 研究員の眼 |
| 2016/06/28 | マイナス金利下でも長期投資でプラス利回りへの道が見えてくる~RMBS投資とは~ | 千田 英明 | 研究員の眼 |
新着記事
-
2025年10月14日
中国の貿易統計(25年9月)~輸出、輸入とも加速。対米輸出は減少が続く -
2025年10月14日
ロシアの物価状況(25年9月)-低下が続くが、足もとインフレ圧力の強まりも -
2025年10月14日
今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】 -
2025年10月10日
企業物価指数2025年9月~国内企業物価の上昇率は前年比2.7%、先行きは鈍化予想~ -
2025年10月10日
中期経済見通し(2025~2035年度)
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【マイナス金利の影響~私たちのくらしはどう変わる?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
マイナス金利の影響~私たちのくらしはどう変わる?のレポート Topへ



















 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




