- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 女性にまつわる変化といくつかの政策ギャップ-政策の主対象は既婚・子あり・正規雇用だが、未婚・非正規が増加
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
1―はじめに
政府の成長戦略や少子化対策などにおける女性の活躍促進施策を眺めると、その主対象は既婚で子どものいる女性のように見える。しかし、未婚化や少子化の進行、非正規雇用者の増加等により、実は政策の主対象ではない層が増加している。近年の女性にまつわる変化を見ると、政策と実態にはズレがあるようだ。
2―女性にまつわる変化
1│就業率の上昇、出産後は退職
ひと昔前は寿退職などと言われ、結婚後に仕事を離れる女性が多かったが、近年では大学進学率の上昇等を背景に、結婚後も働き続ける女性が増えている。30歳前後の有配偶女性の就業率は、この10年で1割程度も上昇している1。
しかし、依然として、出産後の女性の就業継続率は低い。子どもの出生年別に第1子出産前後の妻の就業経歴をみると、直近でも就業継続者は出産前有職者の4割に満たない(図1)。また、就業継続率は、実はわずかに低下している。子どもの生まれ年が1985~1989年では39.1%だが、2005~2009年では37.9%である。
就業継続状況は雇用形態で大きく異なる(図2)。「正規職員」の就業継続率は上昇傾向にあり、直近で約半数だが、「パート等」では直近で2割に満たず、育休取得率もごくわずかだ。
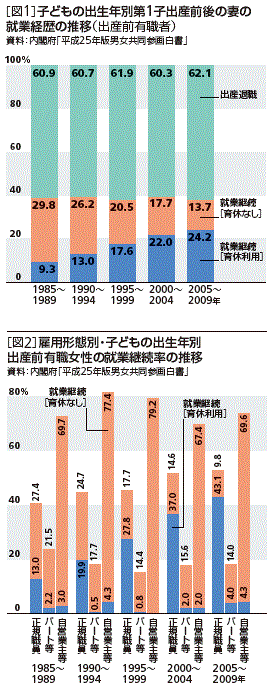
2│非正規雇用者の増加
近年、子育て期の女性で非正規雇用者が増加している。雇用者に占める非正規雇用者の割合は1990年代半ばから上昇し、現在、女性では15~24歳の53.6%、25~34歳の41.4%、35~44歳の54.6%を占める。正規雇用者の就業継続率が上昇しても、非正規雇用者では就業継続率が依然として低いことが、女性全体の就業継続率が伸びない背景にあるようだ。
なお、非正規雇用者でも育休を取得できるが、(1)同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること、(2)子の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれること等2の条件を満たす必要がある。(2)は人材に余裕のない企業では確約することが難しい。このことが、非正規雇用女性で育休取得率や就業継続率が低い背景にあるのだろう。
3│未婚化、晩婚化、晩産化の進行
ひと昔前は30代の大半が既婚だったが、未婚化が進行し、現在、30代前半の女性34.5%、男性47.3%、30代後半の女性23.1%、男性35.6%が未婚だ3。生涯未婚率も上昇し、女性の10人に1人、男性の5人に1人は生涯未婚だ。
晩婚化も進行し、2012年の平均初婚年齢は女性29.2歳、男性30.8歳、女性の第1子平均出生年齢は2011年に30歳を超えた(2012年は30.3歳)4。
4│少子化の進行~夫婦の子ども数は大きくは変わらない
未婚化・晩婚化、晩産化を背景に少子化も進行している。合計特殊出生率は1975年に2.0を下回った後、低下傾向が続き、2012年では1.41である。
ところで、合計特殊出生率は15~49歳の全ての女性を対象に計算している。子どものいる女性だけでなく、子どものいない女性や未婚女性も含んでいる5。よって、婚外子が少なく、未婚化が進行している日本では未婚者の影響が大きくあらわれる。
未婚者を除いた夫婦の状況をみると、夫婦の最終的な平均子ども数(完結出生児数)は、直近調査で2人をわずかに下回っているものの、1970年代から最近までおおむね2人程度で推移している(図3)。
完結出生児数を算出する対象は、結婚持続期間が15~19年の夫婦であり限定的だが、より結婚持続期間が短い夫婦の子ども数をみても、合計特殊出生率の推移よりも緩やかである6。より詳細な分析は必要だが、少子化の背景には、晩婚化・晩産化によって夫婦の子ども数が減ったことだけではなく、未婚化の影響も大きい7。
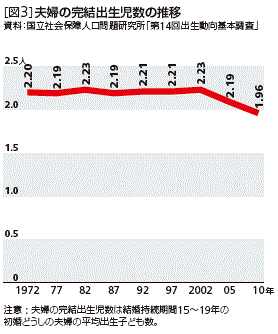
3―政策とのいくつかのギャップ
1│成長戦略「女性の活躍」におけるギャップ~既婚で子どものいる女性が主対象、正規・非正規による格差も
成長戦略では女性の活躍促進施策として、特に「待機児童の解消」「女性役員・管理職の増加」「職場復帰・再就職の支援」「子育て後の起業支援」を掲げているが、「女性役員・管理職の増加」を除くと、いずれも既婚で子どものいる女性を主な対象としている。成長戦略ではM字カーブの解消を喫緊の課題としているために、もともと就業率の高い未婚女性は対象外とし、離職者の多い出産期以降の女性を対象としているのかもしれない。しかし、これまで述べてきた通り、現在、未婚女性が増えており、現在は政策の主対象ではない層が増加している。
「女性役員・管理職の増加」についても、現在増えている非正規雇用者では役員や管理職を望みにくい。また、非正規雇用者は育休を取得し難いため、育休関連の施策(育休3年、育休復帰支援など)の恩恵を受けにくく、保育園利用についても不利な立場になりやすい8。保育所数や保育士数を増やすことで一定の効果は望めるだろうが、これだけ非正規雇用者が多い状況を見ると、平行して雇用形態による不利感を是正する必要もあるだろう
2│少子化対策におけるギャップ~未婚者への対策の薄さ、正規・非正規による格差も
少子化には未婚化の影響も大きいが、政府の少子化対策白書をみると、未婚化の解消につながる対策はごく一部であり、大半が既婚夫婦に向けたものだ。
未婚化の背景の1つには経済環境の厳しさがあるが、未婚者が該当する少子化対策としては、非正規雇用者の雇用の安定化や若年層のキャリア支援がある。しかし、非正規雇用者対策は若年層に限った話ではない。仮に、非正規から正規への雇用転換を図る際、非正規雇用者の中で競争がうまれるとすると、経験の少ない若年層は不利である。 既婚者や子どものいる家庭に向けた少子化対策では対象が具体的なものが多いことを鑑みると(児童手当や公立高校無償制度、妊婦検診・出産費用・不妊治療費の軽減、待機児童の解消、幼児教育や保育の質の向上、放課後対策、小児医療の充実、ひとり親家庭の支援、特に支援が必要な子どもへの支援、ワーク・ライフ・バランスの充実など)、直接的に若年未婚者を救済する措置があってもよいのではないだろうか。
また、既婚者あるいは子どものいる家庭であれば、必ず少子化対策の恩恵を受けられるわけではない。前項同様、非正規雇用者では育休関連の施策や保育園利用において恩恵を受けにくい。
政策により、更なる格差を生み出すことはあってはならないため、より踏み込んだ追加対策が必要である。
(2014年06月06日「基礎研マンスリー」)
このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1878
- プロフィール
【職歴】
2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社
2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用
2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門
2021年7月より現職
・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)
・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)
・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)
・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)
・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)
・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)
・総務省「統計委員会」委員(2023年~)
【加入団体等】
日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、
生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society
久我 尚子のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える | 久我 尚子 | 基礎研レポート |
| 2025/10/27 | 大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |
| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |
| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |
新着記事
-
2025年11月07日
次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 -
2025年11月07日
個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -
2025年11月07日
中国の貿易統計(25年10月)~輸出、輸入とも悪化。対米輸出は減少が続く -
2025年11月07日
英国金融政策(11月MPC公表)-2会合連続の据え置きで利下げペースは鈍化 -
2025年11月06日
世の中は人間よりも生成AIに寛大なのか?
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【女性にまつわる変化といくつかの政策ギャップ-政策の主対象は既婚・子あり・正規雇用だが、未婚・非正規が増加】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
女性にまつわる変化といくつかの政策ギャップ-政策の主対象は既婚・子あり・正規雇用だが、未婚・非正規が増加のレポート Topへ


















 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




