- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 経済 >
- 家計の貯蓄・消費・資産 >
- 反転の可能性高まる先進国の住宅価格と家計貯蓄率の趨勢
コラム
2008年02月18日
内閣府から先般公表された「国民経済計算確報 ストック編」によると、2006年末における日本の土地の時価総額は1990年以来実に16年ぶりに対前年比上昇に転じて、1,228兆円となった。このうちの6割は家計が所有しており、土地に家屋などを合わせた実物資産保有額は988兆円と、家計可処分所得の3.36倍に相当する大きさとなっている。
しかし、日本の家計が保有する実物資産の可処分所得比は、国際的には、決して高いとは言えない。8倍のスペインを筆頭に、5倍を超える国が7カ国も存在するからである。日本の家計貯蓄率が国際的に高いと言えないことは多くの人が知るところとなっているが、ほぼ同じことがストック面、特に実物資産の大きさにも当てはまるのである(注)。日本では地価下落が15年間も止まらなかったが、その間に、多くの先進国で住宅価格上昇が続いてきたからである。
しかし、日本の家計が保有する実物資産の可処分所得比は、国際的には、決して高いとは言えない。8倍のスペインを筆頭に、5倍を超える国が7カ国も存在するからである。日本の家計貯蓄率が国際的に高いと言えないことは多くの人が知るところとなっているが、ほぼ同じことがストック面、特に実物資産の大きさにも当てはまるのである(注)。日本では地価下落が15年間も止まらなかったが、その間に、多くの先進国で住宅価格上昇が続いてきたからである。
正確な因果関係を述べれば、先進国の住宅価格上昇が続いてきたことで、家計が保有する住宅資産の大きさやマクロ経済に対するその影響力について、近年高い関心が向けられるようになり、国際的に比較可能な統計が作成されるようになったことによって、事実が明らかになったと言うべきかもしれない。
興味深いのは、90年代半ば以降、地価や住宅価格の継続的な上昇が起きた国の中で家計貯蓄率が低下しなかった国は、フランスのみであるという点である。ドイツやスイスは、住宅価格上昇が起こらなかった日本以外の先進国という意味で稀有な存在だが、家計貯蓄率の低下傾向も観察されないという点では整合的である。これに対して、フランスとは逆に、地価は上昇しなかったのに、家計貯蓄率が大幅に低下した国は日本のみである。
興味深いのは、90年代半ば以降、地価や住宅価格の継続的な上昇が起きた国の中で家計貯蓄率が低下しなかった国は、フランスのみであるという点である。ドイツやスイスは、住宅価格上昇が起こらなかった日本以外の先進国という意味で稀有な存在だが、家計貯蓄率の低下傾向も観察されないという点では整合的である。これに対して、フランスとは逆に、地価は上昇しなかったのに、家計貯蓄率が大幅に低下した国は日本のみである。
つまり、名前を挙げなかった先進国においては、程度の差こそあれ、住宅価格上昇による資産効果で消費が促進され、家計貯蓄率の低下が進んできた可能性が高い。これまでの実証研究によると、消費に対する住宅の資産効果は数年間をかけて徐々に浸透してきたという説が有力である。
こうした住宅価格と家計貯蓄率の国際的な趨勢にも転機が訪れようとしている。
当コラムにおいて、昨年9月に「米国以外でも変調の兆しが見える住宅価格」を執筆した折は、「一国全体(平均)の実質住宅価格下落」が確認されたのは米国とデンマークのみであったが、今やアイルランドが加わり、更に、季節調整済み指数で見れば、英国にも当てはまる。スペインやオランダでは、住宅価格の上昇は続いているものの、上昇率自体は大幅に低下している。
過去の実績と照らし合わせると、国によって差があるものの、実質ベースの住宅価格は平均5年半の上昇局面が続いた後に、平均4年半の下落局面が訪れている。景気循環と比べると、山は高く、谷は深い。しかも、ほとんどの国において、今回の上昇局面の長さは既に過去の平均を大きく上回っている。
これまでの上昇局面から下落局面への転換には、多くの場合、金利上昇が絡んでいる。今回は、単純な意味での金利上昇は当てはまらないが、サブプライムローン問題を背景に、借り手の信用度に応じた要求プレミアムの上昇が起きている。つまり、下落トレンドへと転じる国が今後増えてもおかしくない状況は整いつつある。
そして、もし、住宅価格が国際的に下落局面入りすれば、国によって程度の差はあれ、消費に対する負の資産効果が働く可能性が高い。その結果、家計貯蓄率も反転上昇するだろう。
こうした国際的な動向に対して、直接的には「蚊帳の外」と言える日本も、欧米諸国が深刻な景気後退に陥れば、輸出の減少を通じた影響は免れない。何とも皮肉なことであるが、日本の地価下落が止まったら、今度は他国の住宅価格動向を心配しなければならない訳である。
(注) ここでの記述はマクロレベルでの比較結果に基づいている。世帯レベルでの比較に関しては、拙稿「国際比較で見る1世帯当たりの資産と負債」(「経済調査レポート」No.2007-06)を参照されたい。
こうした住宅価格と家計貯蓄率の国際的な趨勢にも転機が訪れようとしている。
当コラムにおいて、昨年9月に「米国以外でも変調の兆しが見える住宅価格」を執筆した折は、「一国全体(平均)の実質住宅価格下落」が確認されたのは米国とデンマークのみであったが、今やアイルランドが加わり、更に、季節調整済み指数で見れば、英国にも当てはまる。スペインやオランダでは、住宅価格の上昇は続いているものの、上昇率自体は大幅に低下している。
過去の実績と照らし合わせると、国によって差があるものの、実質ベースの住宅価格は平均5年半の上昇局面が続いた後に、平均4年半の下落局面が訪れている。景気循環と比べると、山は高く、谷は深い。しかも、ほとんどの国において、今回の上昇局面の長さは既に過去の平均を大きく上回っている。
これまでの上昇局面から下落局面への転換には、多くの場合、金利上昇が絡んでいる。今回は、単純な意味での金利上昇は当てはまらないが、サブプライムローン問題を背景に、借り手の信用度に応じた要求プレミアムの上昇が起きている。つまり、下落トレンドへと転じる国が今後増えてもおかしくない状況は整いつつある。
そして、もし、住宅価格が国際的に下落局面入りすれば、国によって程度の差はあれ、消費に対する負の資産効果が働く可能性が高い。その結果、家計貯蓄率も反転上昇するだろう。
こうした国際的な動向に対して、直接的には「蚊帳の外」と言える日本も、欧米諸国が深刻な景気後退に陥れば、輸出の減少を通じた影響は免れない。何とも皮肉なことであるが、日本の地価下落が止まったら、今度は他国の住宅価格動向を心配しなければならない訳である。
(注) ここでの記述はマクロレベルでの比較結果に基づいている。世帯レベルでの比較に関しては、拙稿「国際比較で見る1世帯当たりの資産と負債」(「経済調査レポート」No.2007-06)を参照されたい。
(2008年02月18日「エコノミストの眼」)
このレポートの関連カテゴリ
石川 達哉
石川 達哉のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2018/12/28 | 同床異夢の臨時財政対策債-償還費を本当に負担するのは国か、地方か? | 石川 達哉 | 研究員の眼 |
| 2018/07/13 | 「地方財源不足額」は本当に解消されているのか?―先送りされ続ける臨時財政対策債の償還財源確保 | 石川 達哉 | 基礎研レポート |
| 2017/08/31 | 再び問われる交付税特会の行方-地方財政の健全性は高まったのか? | 石川 達哉 | 基礎研レポート |
| 2017/07/03 | 増大する地方公共団体の基金残高 その2-実は拡大している積立不足!? | 石川 達哉 | 研究員の眼 |
新着記事
-
2025年10月23日
御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1) -
2025年10月23日
EIOPAがソルベンシーIIのレビューに関する技術基準とガイドラインのセットの新たな協議を開始等 -
2025年10月23日
中国:25年7~9月期GDPの評価-秋風索莫の気配が漂う中国経済。内需の悪化により成長率は減速 -
2025年10月23日
パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 -
2025年10月22日
高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【反転の可能性高まる先進国の住宅価格と家計貯蓄率の趨勢】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
反転の可能性高まる先進国の住宅価格と家計貯蓄率の趨勢のレポート Topへ


















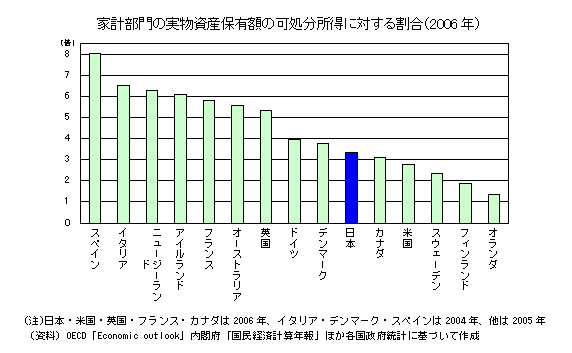
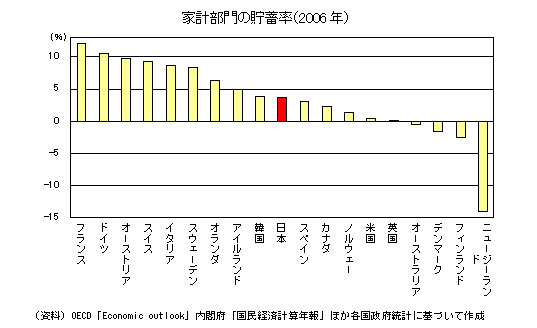

 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




