- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 経済 >
- 欧州経済 >
- 欧州中央銀行の次の一手を考える
コラム
2005年12月05日
| 1.ユーロ相場は対ドル安、対円高が進行 12月1日、欧州中央銀行(ECB)が2年6カ月にわたり2%に据え置いてきた政策金利の25bpの引き上げを決めた。およそ7年という短いECBの金融政策の歴史で利上げは5年ぶりのことだ。 外国為替市場では、ECBの利上げ後も、対ドルでのユーロ安には大きな変化は見られない一方、円安ドル高が進行したため、対円ではユーロ高が進行した。ユーロの対ドル相場の1ドル=1.17ユーロという現在の水準は最高値圏にあった昨年末に比べ16%減価しているが、対円レートは、1ユーロ=141円台で最高値圏にある(図表)。
こうした動きは、2004年6月以降の米FRBの連続利上げで拡大した欧米間の金利差が、当面大きくは縮小することはない一方、政治サイドからの牽制で量的金融緩和の早期解除観測が後退している日本との比較では、ユーロ圏の超金融緩和政策の修正のスピードが速いという市場の見方を反映したものだ。1日の理事会後の記者会見でも、トリシェ総裁は「事前に連続的な利上げを決めることはない」と従来から用いてきた表現でFRB流の連続利上げは否定したが、今回の利上げは「金融緩和の修正」であり、今後も「物価の安定に対するリスクを注視する」として追加利上げに含みを持たせた。ECBの次の一手がどのような幅とタイミングで打ちだされるのか、ユーロ相場の決定要因として目が離せない状況となっている。 2.次の一手に求められる十分な理由付け 今回の利上げは、景気回復に伴うインフレ・リスクの高まりを受けて、10月以降、地ならしに動いたECBに対して各国政府、さらに国際機関からもけん制が相次ぐ中で行なわれた。追加利上げに対する抵抗は一段と強まると見られるため、ECBは次の一手に際して、今回以上にデータ面での裏付けと十分な理由付けを求められるであろう。 今回の場合、利上げを見送るべきとの主張の論拠は以下のようなものであった。まず、物価の現状判断と上振れリスクについては、「消費者物価の上昇は原油価格の動向が直接的に影響」しているもので、エネルギー、食料を除いたコア・インフレ率が直近でも1.4%と落ち着いており、「二次的影響の兆候は見られない」(ルクセンブルグ・ユンケル財務相)、「すでに低下しつつある」(オランダ・ツァルム財務相、スペイン・ソルベス財務相)ため、ECBの警戒は過大と評価した。その一方、景気については、回復の初期段階にあり、先行きには「原油価格のさらなる上昇と世界的不均衡の急激、かつ、無秩序な調整というリスクが存在」する(IMFラト理事、欧州委員会アルムニア経済・金融担当委員)ため、「回復の足取りが十分なものとなり、底堅さを増すまで少なくとも数四半期は金融引締めを見合わせるべき」(OECD,”EonomicOutlook、November2005”)とされた。 こうした議論に対して、政策理事会後の記者会見でトリシェ総裁が示したECBの公式の見解は、以下のようなものだ。まず、物価の現状と短期的な見通しについては、物価上昇率は9月2.6%→10月2.5%→11月2.4%と低下しているが、2%以下でその近辺(below, but close to ,2%)という政策目標を上回っており、物価上昇の原因である「エネルギー価格の上昇は世界的な需要増によるもの」であるため、「当面高止まる」との見方を示した。また、ユーロ圏におけるインフレ・リスクの小ささを示す指標として取り上げられるコア・インフレ率は、「ユーロ圏では多くの場合、総合指数に遅行して上昇する傾向見られる」とし、「エネルギーを物価指数から除いて考えることは、製造業製品など国際的に取引されているその他の財を除くのと同じように不適切」として、総合指数重視の姿勢を強調した。そして、ユーロ圏が現在直面するインフレ圧力として、「価格設定や賃金上昇を通じた原油高の二次的影響」、「公共料金や間接税引き上げ」、さらに「過剰流動性からくる住宅市場の価格動向」を注視する必要があるとした。 うち原油高の二次的影響については、ECBも月報の最新号(11月号)で「労働市場が軟調であるため賃金上昇率は抑制された状況が当面は続く」、「製品価格への転嫁はグローバルな競争激化の中で抑制されている」と据え置き派と同様の判断を示している。政策対応に対する結論の違いは、ECBが「リスクが顕現化するまで待っていては手遅れになる」と考え、「中長期的なインフレ期待の安定を確保する」ために予防的な対応が必要と判断したことによる。 その一方、据え置き派が懸念を示した景気の先行きについては、ECBの見方は、「良好な外部環境による輸出の拡大」、「低金利、高収益に支えられた設備投資の拡大」、さらに「所得の伸びに支えられて個人消費も回復」が見込まれるという楽観的なものだ。下振れリスクとして「原油価格の上振れ、世界的不均衡、消費者マインドの弱さ」の存在を認めながら、「名目、実質ともに金利は非常に低い状態が続く」ため、「経済活動と雇用創出をサポートする」として、利上げが景気の腰折れにつながるとの見方を否定している。 3.1~3月期の25bpの利上げ後、据え置きの可能性も ECBはこれまでも2%という歴史的、例外的低水準の政策金利の引き上げによる金融政策正常化の道筋を探ってきた。7~9月期に域内全域でプラス成長が定着、物価を巡るリスクも上振れで一致し環境が整ったことで、ようやく第一歩を踏み出すことができた(Weeklyエコノミストレター2005.11.18「ユーロ圏-整いつつある利上げの環境-」)。今回の利上げの影響は、ユーロ安という環境もあり、据え置き派が懸念するほどの広がりはもたず、むしろ、ECBが口先だけに留めざるを得なかった原油高の二次的影響やスペイン、アイルランドなどの国々での住宅ブームの行き過ぎへの警戒を行動で示した意義の方が大きいと言えるだろう。 しかし、ユーロ圏並びに世界経済の環境は、2006年中に政策金利を中立と見られる3%台まで引き上げるようなスピードでの調整を許容しうる状況にもない。景気停滞を脱したばかりのドイツなどユーロ圏主要国の外需依存の高さや企業部門の回復の家計への波及の鈍さに鑑みると、高成長国の住宅市場過熱などの問題にターゲットを絞って政策を運営することは難しい。ECBが利上げを急ぐことには、為替相場におけるユーロ安基調の修正や、12月2~3日にロンドンで開催された7カ国(G7)財務相・中央銀行総裁会議でもリスク要因として議論された世界的な長期金利の上昇とグローバルなマネーフローの変化の引き金となり、ユーロ圏に跳ね返ってくるおそれもある。 直近までの先行指標の推移を見る限り、ユーロ圏では少なくとも来年1~3月期は景気の回復基調が持続、原油高の影響による物価の高止まりも続く見通しだ。この段階で25bpの追加利上げが行なわれる可能性は高いだろう。その後は、米国経済の持続力や金融政策の展開など外部環境の不確実要因が増える中、ECBが様子見姿勢に回帰することも十分に考えられよう。 |
(2005年12月05日「エコノミストの眼」)

03-3512-1832
経歴
- ・ 1987年 日本興業銀行入行
・ 2001年 ニッセイ基礎研究所入社
・ 2023年7月から現職
・ 2015~2024年度 早稲田大学商学学術院非常勤講師
・ 2017年度~ 日本EU学会理事
・ 2017~2024年度 日本経済団体連合会21世紀政策研究所研究委員
・ 2020~2022年度 日本国際フォーラム「米中覇権競争とインド太平洋地経学」、
「欧州政策パネル」メンバー
・ 2022~2024年度 Discuss Japan編集委員
・ 2022年5月~ ジェトロ情報媒体に対する外部評価委員会委員
・ 2023年11月~ 経済産業省 産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会 委員
・ 2024年10月~ 雑誌『外交』編集委員
・ 2025年5月~ 経団連総合政策研究所特任研究主幹
伊藤 さゆりのレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2025/09/30 | ドル離れとユーロ-地位向上を阻む内圧と外圧- | 伊藤 さゆり | |
| 2025/09/12 | 欧州経済見通し-関税合意後も不確実性が残る状況は続く | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |
| 2025/08/26 | 大砲かバターか-国防費の大幅引き上げに動く欧州の現実 | 伊藤 さゆり | 研究員の眼 |
| 2025/08/04 | 米EU関税合意-実効性・持続性に疑問符 | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |
新着記事
-
2025年11月04日
今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -
2025年10月31日
交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -
2025年10月31日
ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -
2025年10月31日
2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -
2025年10月31日
保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【欧州中央銀行の次の一手を考える】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
欧州中央銀行の次の一手を考えるのレポート Topへ

















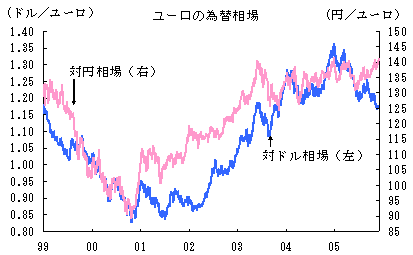

 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




