- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 経済 >
- 日本経済 >
- GDP統計の空白問題
コラム
2005年01月24日
1. 実質GDPは連鎖方式へ GDP統計は、昨年12月に公表された2004年7-9月期の2次速報値から、実質化の手法がそれまでの固定基準年方式(以下、旧方式)から連鎖方式へと変更された。 連鎖方式による2003年度の実質GDP成長率は、旧方式の3.2%から1.9%へと大きく低下した。名目成長率は変わらなかったが、旧方式に比べ、GDPデフレーターのマイナス幅が縮小したためである。旧方式では、最近のGDPデフレーターには下方バイアスがあり、2003年度の実質成長率はかなり嵩上げされている、という指摘が多かった。そのため、連鎖方式による実質成長率はより実態に近い数字に改められたということも含め、概ね好意的に受け止められている。 2. 1994年以降しか存在しない連鎖方式の実質GDP しかし、ここではあえて、新方式が導入されたことに伴う影の部分を指摘したい。それはGDP統計の空白問題である。 GDP統計は最近の動きばかりに目を奪われがちだが、過去のデータも非常に重要である。ところが、連鎖方式の実質GDPが公表されているのは1994年以降に限られている。1993年以前の実質GDPは旧方式のものしか存在しない、いわば空白期間となっているのだ。 現状では、実質GDPを使って経済分析をしようとすると、94年以降のデータしかないことが大きな支障となる。94年といえばバブル崩壊直後の景気後退が終了した時期にあたる。中長期的な分析をしようとした場合、それ以降のデータだけではとても足りない。93年以前の実質GDPは旧方式のデータを使わざるをえないが、これをそのまま使うと、93年と94年の間に大きな断層が生じてしまう。連鎖方式と旧方式では実質値の基準となる年が異なっている(連鎖方式は2000年、旧方式は1995年)こともあり、両系列の水準も違うからである。この断層を調整しようとすれば、利用者が両系列を接続する必要があるが、これには手間がかかる上、接続の仕方によっては利用者によって違うデータを用いることになる可能性がある。その結果、場合によっては同じ分析をしているにもかかわらず、異なる結論が導き出されてしまう恐れすらある。これは非常に深刻な問題だ。 内閣府によれば、93年以前の遡及推計の予定はまだ決まっていないということであるが、このような空白期間は一刻も早く解消すべきである。
また、例年は年末までに内閣府から前年(度)の国民経済計算の確報が公表されるが、今回はそれが大幅に遅れているという問題点も指摘できる。昨年末までに公表されたのは一般政府部門の部門別勘定等、一部の項目だけであった。年明け以降、国民所得、制度部門別所得支出勘定、経済活動別(産業別)GDP等が公表されたが、現時点(1/24)でもまだ、制度部門別資本調達勘定、ストック系列といった重要な項目が未公表となっている。このため、たとえば、近年、本来資金不足であるはずの企業部門が、資金余剰となっている(制度部門別資本調達勘定のデータ)ことが問題となっているが、このことは国民経済計算では2年近く前の2002年度までしか確認できない。また、地価の下落などから2002年まで5年連続で減少していた国富が、2003年にどうなったのかも気になるところである。 連鎖方式という新しい手法の導入で作業負荷が増えたことが、確報推計作業の遅れにつながっていると推察される。 4. 過去にも起こったGDP統計の空白問題 GDP統計の見直しに伴ってデータに空白が生じたのは、実は今回に限ったことではない。最近では、2000年秋に基準改定(90年基準→95年基準)と68SNAから93SNAへの移行(注)が同時に実施された時の例が挙げられる。それ以前のGDP統計は、支出系列などの主要項目は1955年以降、ストック系列は1969年以降のデータが存在したが、93SNAへの移行に伴い、支出系列は1980年以降、それ以外の系列は1990年以降と、データの存在期間が一気に縮まってしまったのである。支出系列以外の1980~1989年のデータは2004年になってようやく公表された。 また、2002年8月にGDP速報の推計方法が大きく変更された際にも、GDP統計にある種の空白が生じた。当初、新しい方式で推計された計数が正式な公表値とされたのは2000年1-3月期以降だけで、それ以前は古い方式で推計された計数が正式な公表値とされていたのである。99年10-12月以前について、正式な公表値が新推計方法によるものとなったのは、移行から1年以上が経過した2003年12月のことであった。 5. 望まれる空白期間の解消 GDP統計の見直しが行われるたびに、こうした空白期間が生じてしまうのは、GDP統計を作成するための体制が十分に整っていないことも一因ではないか。連鎖方式の導入は、経済実態を正確に把握する上で正しい選択だったことに異論はないが、93年以前の系列が公表されていないことや、2003年度確報の公表が遅れていることからすると、新しい方法を導入するにあたっては、体制の強化が必要だったのではないだろうか。 GDP統計は、国内の経済活動を包括的かつ整合的にとらえることができる、唯一の重要な経済統計である。このような重要統計に空白期間が生じてしまうことは、非常に大きな問題である。 今年の秋には、5年に1度の基準改定(95年基準→2000年基準)が予定されている。統計利用者としては、現在空白となっている期間のデータが早く公表されること、基準改定に伴って新たな空白期間が生まれないことを願うばかりである。 (注)1993年に国際連合が1968年以来、25年ぶりに新しいSNA体系の基準を勧告したことに伴い、日本の国民経済計算の体系も2000年10月に68SNAから93SNAへ移行した。 |
(2005年01月24日「エコノミストの眼」)

03-3512-1836
経歴
- ・ 1992年:日本生命保険相互会社
・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ
・ 2019年8月より現職
・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)
・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)
・ 2018年~ 統計委員会専門委員
斎藤 太郎のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |
| 2025/10/31 | 鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |
| 2025/10/31 | 雇用関連統計25年9月-女性の正規雇用比率が50%に近づく | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |
| 2025/10/30 | 潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 | 斎藤 太郎 | 基礎研レポート |
新着記事
-
2025年11月04日
今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -
2025年10月31日
交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -
2025年10月31日
ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -
2025年10月31日
2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -
2025年10月31日
保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【GDP統計の空白問題】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
GDP統計の空白問題のレポート Topへ

















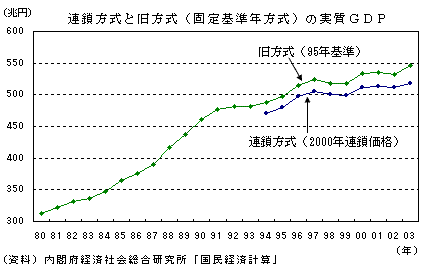

 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




