- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 経済 >
- アジア経済 >
- アジアとの経済連携の強化~欧州統合の経験が示唆すること~
コラム
2003年09月08日
| 1.FTA加速論の背景 日本はアジア諸国との自由貿易協定(以下、FTA)締結を急ぐべきとの声が高まっている。背景には、90年代以降、世界各国で世界貿易機関(WTO)による多国間協定を補完するものとしてFTAの締結が急増したことがある(図表)。 欧州ではすでに高い次元の統合が実現、2004年5月には中東欧など10カ国が欧州連合(EU)に加盟、統合は地域的にも拡大する。米州では94年の北米自由貿易協定(以下、NAFTA)の成立に続き、2005年1月の妥結を目指し、南北アメリカを統合する米州自由貿易協定(FTAA)の交渉が進められている。FTA締結の動きが相対的に低調であったアジアでも、東南アジア諸国連合(以下、ASEAN)の中継貿易基地・シンガポールが域内・域外とのFTA締結に積極的に取り組んでいるほか、韓国もチリとFTAを締結、中国もASEANとのFTA実現に動きだすなどFTAへの気運が盛り上がりを見せている。 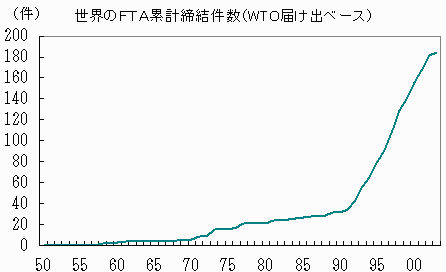 FTA加速論は、直接的には、FTAの広がりで参加のベネフィットとともに、参加しない不利益が強く意識されるようになったことによるものだ。メキシコがNAFTAに続き、2000年にはEUとFTAを締結、日本企業が不利益を被ったことは大きな教訓となっている。今後、ASEAN-中国のFTAが実現すれば、両地域を軸に、クロスボーダーな生産・物流ネットワークを築いている日本企業にとっては拠点の効率化などを通じてベネフィットを享受する余地が生まれる。しかし、日本のFTA推進が遅れをとれば、日本国内の産業空洞化を招くばかりでなく、将来のアジア域内の経済連携強化のためのルール作りへの影響力低下にもつながることが危惧されるのである。 2.アジア地域統合戦略への欧州からの示唆 日本の実際の取り組みは、2002年11月に初の二国間FTAである「日シンガポール新時代経済連携協定」が発効、メキシコ、チリの他、韓国、台湾、タイ、フィリピン、ASEANとのFTAについて協議・検討している段階にある。平成15年版の「通商白書」では、こうした取り組みを、「日中韓やASEAN+3へと広げ、また台湾・香港との連携にも結び付け、より広い東アジア大の地域的経済統合を実現していくことが、今後の戦略的課題」として、統合推進への意思が示された。 日本が、こうした地域統合戦略の実現の道筋を模索する際、統合の深さと地域的な広がりの両面で先進している欧州統合の経験からは多くの示唆を得ることになるだろう。ここでは2つの基本的なポイントを挙げておきたい。 第1に、一定の深さと広がりをもつ統合の実現には長い時間を要することと、その間、国家主権の制限を伴う統合へのダイナミズムを維持するには、統合の必然性とベネフィットに対する意識の共有が必要となることだ。EUの場合、通貨統合の実現、市場統合への中東欧の参加までに50年もの歳月を要した。地域統合は平和と安定の確保に資するという政治的な意思が共有されたことが、経済的なベネフィットへの期待感以上に、欧州統合の原動力として重要な役割を果たしてきた。 アジアにおける経済連携の枠組みは、東アジア自由貿易協定(EAFTA)といった形で、事実上の域内分業のネットワークが広がっている範囲をカバーし、関税・非関税障壁の撤廃のみならず、カネ、ヒト、サービスの移動を円滑化する協定も盛り込まれることが理想である。しかし、アジアの現状と照らし合わせれば、これが容易に達成できる目標でないことが明らかだ。中国は2001年12月にWTO加盟を果たしたばかりで、WTOルールとの整合化のための市場開放、投資環境改善を進めている段階にある。ASEANではASEAN自由貿易地域(AFTA)の関税引き下げ計画は履行されたが、手続きの煩雑さやルール執行の不統一などの問題が残されており、FTAの推進意欲も履行能力も国毎に温度差がある。IT分野の工程間分業に欠くことのできない台湾の参加には政治的な障害が存在する。時間をかけて、これらの障害を乗り越え、FTA網の拡充などを経て、最終的に地域統合の実現に至るには、持続する政治的な強い意思が求められるのである。 日本国内においても、アジアとの連携強化で構造調整にはずみをつけ、アジア市場における存在意義を確立することが、経済的な繁栄を維持する有効な方策となることへの国民的なコンセンサス作りが必要であろう。 第2に、広い分野にわたる統合の実現は、通貨の障壁を取り除く必然性を高めることから、通貨面での政策協調についても検討していく必要があるということだ。欧州の統合は関税同盟から市場統合へと段階的なステップを踏んだが、93年の市場統合の完成で、域内における為替の障壁が市場統合の実効性を妨げる要因として強く認識されるようになり、通貨統合を後押しすることになった。その後、比較的短い期間で通貨統合が達成された背景には、70年代以降、通貨面での域内政策協調が試みられていたことがあった点も忘れてはならない。 アジアでは、通貨危機を教訓に、二国間で通貨急落時に介入通貨を融通し合うスワップ協定を締結する動きが広がった。通貨危機の本質的な原因は、設備投資のための資金を、短期の外貨資金で調達することで生じる「期間と通貨のミスマッチ」という金融構造上の問題であったが、この問題への有効な対策となるアジア債券市場育成構想も動きだそうとしている。アジアは、発展段階の格差が大きく、為替制度や金融政策運営の方針も様々で、単一金融政策が機能する前提となる自由な資本取引や金融システムの健全性といった条件も満たされていない国が少なくない。現時点ではアジアにおける単一通貨の導入は現実的ではなく、二国間のFTA交渉とそのネットワーク化が優先課題となる。しかし、同時に、域内為替レート安定化の方策について協議を重ね、段階的に政策協調の仕組みを整えることもまた重要なのである。 |
(2003年09月08日「エコノミストの眼」)

03-3512-1832
経歴
- ・ 1987年 日本興業銀行入行
・ 2001年 ニッセイ基礎研究所入社
・ 2023年7月から現職
・ 2015~2024年度 早稲田大学商学学術院非常勤講師
・ 2017年度~ 日本EU学会理事
・ 2017~2024年度 日本経済団体連合会21世紀政策研究所研究委員
・ 2020~2022年度 日本国際フォーラム「米中覇権競争とインド太平洋地経学」、
「欧州政策パネル」メンバー
・ 2022~2024年度 Discuss Japan編集委員
・ 2022年5月~ ジェトロ情報媒体に対する外部評価委員会委員
・ 2023年11月~ 経済産業省 産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会 委員
・ 2024年10月~ 雑誌『外交』編集委員
・ 2025年5月~ 経団連総合政策研究所特任研究主幹
伊藤 さゆりのレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 新たな局面に入るロシア制裁・ウクライナ支援 | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |
| 2025/09/30 | ドル離れとユーロ-地位向上を阻む内圧と外圧- | 伊藤 さゆり | |
| 2025/09/12 | 欧州経済見通し-関税合意後も不確実性が残る状況は続く | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |
| 2025/08/26 | 大砲かバターか-国防費の大幅引き上げに動く欧州の現実 | 伊藤 さゆり | 研究員の眼 |
新着記事
-
2025年11月07日
フィリピンGDP(25年7-9月期)~民間消費の鈍化で4.0%成長に減速、電子部品輸出は堅調 -
2025年11月07日
次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 -
2025年11月07日
個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -
2025年11月07日
中国の貿易統計(25年10月)~輸出、輸入とも悪化。対米輸出は減少が続く -
2025年11月07日
英国金融政策(11月MPC公表)-2会合連続の据え置きで利下げペースは鈍化
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【アジアとの経済連携の強化~欧州統合の経験が示唆すること~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
アジアとの経済連携の強化~欧州統合の経験が示唆すること~のレポート Topへ


















 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




