- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 経済 >
- 日本経済 >
- 難しい経済見通しの評価
コラム
2001年12月03日
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
1.経済見通しをどう評価すべきか
今年も新年度の経済見通しの季節がやってきた。12月は毎年50以上の民間機関で新年度の経済見通しの発表が行われ、その予測数値が新聞紙上をにぎわすことになる。政府も新年度の予算編成に合わせて「経済見通しと経済運営の基本的態度」という形で実質GDP成長率などの予測を策定するが、これも世間の注目度は非常に高い。しかし、経済見通しの注目度の高さに比べて、その見通しが当たったかどうかといった評価については関心をもたれることが少ない。実績値が出る頃にはかなり昔に発表された経済見通しなど皆忘れてしまっているということもあるだろうが、経済見通しの評価の仕方が難しいこともその理由のひとつだろう。
経済成長率の予測を実績と比較する場合に意外に大きな問題は、いつ時点の「実績値」を使うかということである。GDP統計は数多くの基礎統計を加工することによって推計されたものであるため、基礎統計の追加や、推計方法の変更等によって修正が繰り返され、そのたびに経済成長率の実績が変わってしまうからだ。
年度の経済成長率は、まず「速報値」が翌年の6月に発表される。同じ年の12月には速報値が「確報値」に改定され、その1年後の12月には「確確報値」へと改定される。さらに、5年に1度の基準年の改定により過去の数字が一斉に改定されるほか、昨年のようにSNA 体系の改訂が行われた場合には、GDPの定義の変更も伴うため過去の数字が大幅に修正される。
経済成長率の予測を実績と比較する場合に意外に大きな問題は、いつ時点の「実績値」を使うかということである。GDP統計は数多くの基礎統計を加工することによって推計されたものであるため、基礎統計の追加や、推計方法の変更等によって修正が繰り返され、そのたびに経済成長率の実績が変わってしまうからだ。
年度の経済成長率は、まず「速報値」が翌年の6月に発表される。同じ年の12月には速報値が「確報値」に改定され、その1年後の12月には「確確報値」へと改定される。さらに、5年に1度の基準年の改定により過去の数字が一斉に改定されるほか、昨年のようにSNA 体系の改訂が行われた場合には、GDPの定義の変更も伴うため過去の数字が大幅に修正される。
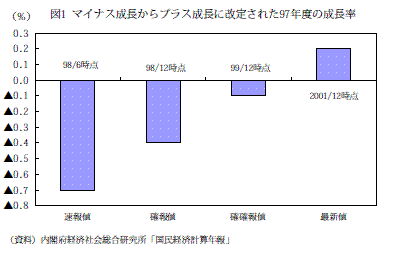 たとえば、97年度の実質GDP成長率は最初に発表された98年6月時点では、前年比▲0.7%のマイナス成長であった。しかし、その後確報値、確確報値と上方修正され、昨年10月に基準改定と93SNA への移行による修正が行われた結果、ついには0.2%のプラス成長へと転じることになった(図1)。
たとえば、97年度の実質GDP成長率は最初に発表された98年6月時点では、前年比▲0.7%のマイナス成長であった。しかし、その後確報値、確確報値と上方修正され、昨年10月に基準改定と93SNA への移行による修正が行われた結果、ついには0.2%のプラス成長へと転じることになった(図1)。そのため、速報段階では予測が当たっていたとしても、実績値が確報値に改定されることによりはずれてしまったり、その逆のことも起きたりするのである。
GDP統計は、速報値よりも確報値のほうがより正確なものになっていると考えれば、経済見通しの評価には最新の実績値を用いるべきということになる。しかし、経済見通しを作成している立場からすればいったん発表された実績値が改定されることまで考慮して予測をするなど無理な話だろう。
2.来年度の経済見通しのポイント
ここで、あえて現時点における最新の実績値と、90年以降の政府、民間機関(平均)の実質GDP成長率の予測(前年12月時点)を比較してみると、図2のようになる。
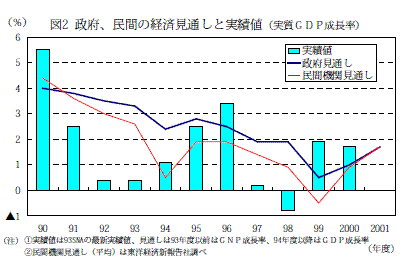 一般的に言われているように、総じて政府のほうが民間よりも楽観的な見通しになっているが、政府見通しは単なる予測と違って政策目標的な意味合いが含まれているからだろう。90年以降の予測値と実績値の年平均の乖離幅(単純絶対誤差)は政府1.6%、民間1.4%となっている。つまり、政府見通しも民間見通しも毎年平均して1%以上は間違うということである。この誤差を大きいと考えるか小さいと考えるかは意見が分かれるところだろうが、実績値自体が1%も改定されることがあることを考慮する必要があるだろう。
一般的に言われているように、総じて政府のほうが民間よりも楽観的な見通しになっているが、政府見通しは単なる予測と違って政策目標的な意味合いが含まれているからだろう。90年以降の予測値と実績値の年平均の乖離幅(単純絶対誤差)は政府1.6%、民間1.4%となっている。つまり、政府見通しも民間見通しも毎年平均して1%以上は間違うということである。この誤差を大きいと考えるか小さいと考えるかは意見が分かれるところだろうが、実績値自体が1%も改定されることがあることを考慮する必要があるだろう。これから続々と経済見通しが発表されることになるが、GDP統計の精度を考えれば、経済成長率の予測においてはコンマいくつの違いに本質的な意味はない。むしろ、見通しの前提になっている財政、金融政策の違い、各需要項目動向についての見方の違い、景気局面の転換時期についての見方の違い、などに目をむけるべきであろう。
あえて、数字を見る上のポイントを挙げるとすれば、来年度の成長率が今年度の成長率よりも高くなると見るか低くなると見るかではないか。成長率の数値自体は統計が改定されるたびに修正されるのであまりあてにならないが、ある年度の成長率が前年度よりも高かったか低かったかは実はほとんど変わることがない。たとえば、97、98年度の成長率は統計の改定によってともに大きく上方修正されたが、98年度の成長率が97年度の成長率よりも低いという関係は速報値が発表された時から現在まで変わっていないのである。成長率が前年度よりも高くなるか低くなるかが当たる確率は2分の1であるが、実際には政府、民間とも6割程度の確率でしか的中しておらず、これを当てるだけでもそれなりに意味があることだろう。
今年度のマイナス成長が確実となった中では、政府、民間各社が来年度の成長率のマイナス幅が今年度よりもさらに拡大すると予測するのか、それとも縮小する(あるいはプラス成長に転じる)と予測するのか、が注目点のひとつになるだろう。
(2001年12月03日「エコノミストの眼」)
このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836
経歴
- ・ 1992年:日本生命保険相互会社
・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ
・ 2019年8月より現職
・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)
・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)
・ 2018年~ 統計委員会専門委員
斎藤 太郎のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/22 | 貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |
| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |
| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |
| 2025/09/19 | 消費者物価(全国25年8月)-コアCPIは9ヵ月ぶりの3%割れ、年末には2%程度まで鈍化する見通し | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |
新着記事
-
2025年10月22日
高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 -
2025年10月22日
貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに -
2025年10月22日
米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 -
2025年10月21日
選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -
2025年10月21日
連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【難しい経済見通しの評価】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
難しい経済見通しの評価のレポート Topへ


















 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




