- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 不動産 >
- 土地・住宅 >
- 宴(うたげ)の後に ・・・ 先進国の住宅価格はどこまで下がるのか?
コラム
2008年07月31日
公的資金注入を柱とする住宅金融公社の支援法案が米国で可決されたが、土地バブル崩壊後の日本における住専問題を思い起こした人は少なくないだろう。デフォルトリスクの高い低所得者に対する住宅ローン債権の証券化は米国特有のものとしても、地価や住宅価格の上昇が続く場合にしか債権回収が確保できないような形の融資が行われた場合には、価格反落時に金融機関が巨額の損失を被ることや、それに伴って深刻な金融危機が起きる可能性があることについては、米国に限定されないはずである。
実際、政府の住宅価格統計が利用可能な先進国に限れば、カナダを除くほぼすべての国で実質住宅価格は横ばいか下落に転じている(拙稿「サブプライム・ショック”の第二幕~実質住宅価格は12カ国で下落へ」)。今回は、この下落が一時的なものにとどまらず、趨勢的に持続するかどうか、下落が持続した場合に下落幅はどの程度の大きさになるかについて考えてみたい。
まず、これまで続いてきた住宅価格上昇は90年代半ば以降に始まったものであり、1970年代以降の先進18カ国について分析したOECDの研究によると、実質価格の上昇が一定期間持続するという意味でのブームは、それ以前にも39ケースある。この6割に相当する23ケースにおいては、間隔をおくことなしに、上昇局面に続いて、大幅な下落を伴う持続的な下降局面(バスト:破裂、破滅)が訪れている。
上昇局面の後の下降局面が終った時に、上昇分の1/2が残っているのは、このうちの1ケースのみである。それどころか、23ケース中の9ケースにおいて、下落が止まるまでの間に上昇分のすべてが失われている。単純に平均すると、上昇と下降の1サイクルを経た後の実質住宅価格は当初の水準よりも6%高いに過ぎない。90年代以降続いてきた日本の実質住宅地価(注)の下落は完全には終わっていないため、上記の23ケースには含まれていないが、下降局面に先立つ上昇局面の始まった77年9月の水準と現在の水準がほぼ等しいという事実は、驚くほどのことではないことになる。
長期的に見ると、住宅価格を一般物価で除した実質価格の水準は、一定の範囲にとどまるということである。そもそも、住宅価格は家賃、正確には持家の帰属家賃を実質金利で除した水準に決まるはずである。そして、長期的には、家賃の上昇率と一般物価の上昇率はほぼ同等であるので、実質金利が変動しなければ、住宅価格の上昇率も一般物価上昇率にほぼ一致し、実質住宅価格は一定の値をとることになる。短期的には名目金利や住宅価格の期待上昇率が変動するため、現実の実質金利は変動し、それを反映した住宅の実質価格の上昇・下落が起こるということである。このとき、実質金利がランダムに変化するのではなく、しばらくの間は低下や上昇を続けつつも、一定範囲での変動にとどまるということであれば、実質住宅価格には上昇が続く期間と下落が続く期間が訪れるが、水準は一定範囲に収まるという現象の説明がつく。住宅価格を実質ベースで見ることの重要性はここにある。
ちなみに、今回のブームでは、米国のピーク時までの上昇率は58%であったが、アイルランド・英国・ノルウェー・デンマーク・スウェーデン・フランス・スペイン・オランダ・オーストラリア・ニュージーランドの10か国はそれを上回っている。経験則に従えば、下落趨勢が定着して下降局面入りする確率は6割あり、下降局面入りした場合には大幅な下落が起きる可能性が高いことを心に留めておくべきだろう。
実際、政府の住宅価格統計が利用可能な先進国に限れば、カナダを除くほぼすべての国で実質住宅価格は横ばいか下落に転じている(拙稿「サブプライム・ショック”の第二幕~実質住宅価格は12カ国で下落へ」)。今回は、この下落が一時的なものにとどまらず、趨勢的に持続するかどうか、下落が持続した場合に下落幅はどの程度の大きさになるかについて考えてみたい。
まず、これまで続いてきた住宅価格上昇は90年代半ば以降に始まったものであり、1970年代以降の先進18カ国について分析したOECDの研究によると、実質価格の上昇が一定期間持続するという意味でのブームは、それ以前にも39ケースある。この6割に相当する23ケースにおいては、間隔をおくことなしに、上昇局面に続いて、大幅な下落を伴う持続的な下降局面(バスト:破裂、破滅)が訪れている。
上昇局面の後の下降局面が終った時に、上昇分の1/2が残っているのは、このうちの1ケースのみである。それどころか、23ケース中の9ケースにおいて、下落が止まるまでの間に上昇分のすべてが失われている。単純に平均すると、上昇と下降の1サイクルを経た後の実質住宅価格は当初の水準よりも6%高いに過ぎない。90年代以降続いてきた日本の実質住宅地価(注)の下落は完全には終わっていないため、上記の23ケースには含まれていないが、下降局面に先立つ上昇局面の始まった77年9月の水準と現在の水準がほぼ等しいという事実は、驚くほどのことではないことになる。
長期的に見ると、住宅価格を一般物価で除した実質価格の水準は、一定の範囲にとどまるということである。そもそも、住宅価格は家賃、正確には持家の帰属家賃を実質金利で除した水準に決まるはずである。そして、長期的には、家賃の上昇率と一般物価の上昇率はほぼ同等であるので、実質金利が変動しなければ、住宅価格の上昇率も一般物価上昇率にほぼ一致し、実質住宅価格は一定の値をとることになる。短期的には名目金利や住宅価格の期待上昇率が変動するため、現実の実質金利は変動し、それを反映した住宅の実質価格の上昇・下落が起こるということである。このとき、実質金利がランダムに変化するのではなく、しばらくの間は低下や上昇を続けつつも、一定範囲での変動にとどまるということであれば、実質住宅価格には上昇が続く期間と下落が続く期間が訪れるが、水準は一定範囲に収まるという現象の説明がつく。住宅価格を実質ベースで見ることの重要性はここにある。
ちなみに、今回のブームでは、米国のピーク時までの上昇率は58%であったが、アイルランド・英国・ノルウェー・デンマーク・スウェーデン・フランス・スペイン・オランダ・オーストラリア・ニュージーランドの10か国はそれを上回っている。経験則に従えば、下落趨勢が定着して下降局面入りする確率は6割あり、下降局面入りした場合には大幅な下落が起きる可能性が高いことを心に留めておくべきだろう。
(注) 全国市街地価格指数(日本不動産研究所)÷消費者物価指数(総務省)
(2008年07月31日「研究員の眼」)
このレポートの関連カテゴリ
石川 達哉
石川 達哉のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2018/12/28 | 同床異夢の臨時財政対策債-償還費を本当に負担するのは国か、地方か? | 石川 達哉 | 研究員の眼 |
| 2018/07/13 | 「地方財源不足額」は本当に解消されているのか?―先送りされ続ける臨時財政対策債の償還財源確保 | 石川 達哉 | 基礎研レポート |
| 2017/08/31 | 再び問われる交付税特会の行方-地方財政の健全性は高まったのか? | 石川 達哉 | 基礎研レポート |
| 2017/07/03 | 増大する地方公共団体の基金残高 その2-実は拡大している積立不足!? | 石川 達哉 | 研究員の眼 |
新着記事
-
2025年10月17日
EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -
2025年10月17日
日本における「老衰死」増加の背景 -
2025年10月17日
選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -
2025年10月17日
首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -
2025年10月17日
「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【宴(うたげ)の後に ・・・ 先進国の住宅価格はどこまで下がるのか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
宴(うたげ)の後に ・・・ 先進国の住宅価格はどこまで下がるのか?のレポート Topへ


















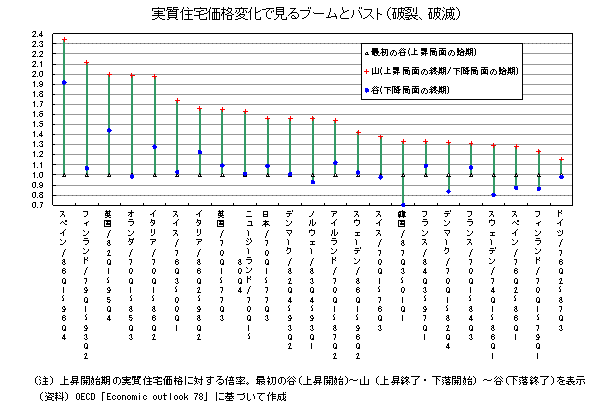

 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




