- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 資産運用・資産形成 >
- 株式 >
- これからの時代の責任投資-PRI in Person 2022バルセロナ大会の模様-
これからの時代の責任投資-PRI in Person 2022バルセロナ大会の模様-

日本生命保険相互会社 木村 武*、高瀬俊史、德重亨、林宏樹、三木さやか

* PRI(国連責任投資原則)理事
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
1―― PRI in a Changing World
PiPバルセロナ大会を総括するうえで見逃してはならないポイントは、PRIが2022年夏から(2023年初にかけて)署名機関に対し「PRI in a Changing World」というコンサルテーションを行っていることである。署名機関との対話を通して、今後の責任投資の方向性について指針をたてるための調査である。同コンサルテーションにおけるキーワードの一つが“sustainability outcome”である。
SDGsやパリ協定などのグローバル目標が設定される一方、実社会の現状(real world outcome)とこれら目標との乖離が広がっており、投資家としてこのギャップにどう対応すべきか、という問いかけである。すなわち、投資家は、ギャップを縮小するよう、“sustainability outcome”の形成に能動的に努めるべきか否かということである。
PiPバルセロナ大会でのPRI 関係者(理事やCEO、モデレーター)のスピーチにおいて、“shape real world/sustainability outcomes”はキーワードの一つになっていた。責任投資において“shape outcomes”を目指すことは、ESGインテグレーションとは異なるものである。ESGインテグレーションは、将来の実社会を所与としたうえで、そこから発生するリスクと機会を投資プロセスに組み込むという、いわば受け身(passive)の投資スタンスである。一方、“shape outcomes”は、実社会に対してポジティブなインパクトを及ぼす、あるいはネガティブなインパクトを削減することにより、将来を変えようという能動的(active)な投資スタンスである。インパクト投資はその一例だが、PRIの考える“shape outcomes”を目的とした投資はより広義の概念であり、(インパクト投資ファンド以外を含む)ポートフォリオ全体のコア戦略・運用哲学として、“sustainability outcome/impact”を考慮しようというものである。
―― 「ESGのリスクと機会」と「sustainability outcome(SDGs-aligned outcome)」の間には、継続的なフィードバック・サイクルが存在することが想定される。ESGの課題は投資家のリスクと機会を生み出し、投資家の行動は実社会のアウトカムを形成し、それがESGのリスクと機会という形でポートフォリオにフィードバックされる。このため、投資家がoutcome/impactを重視することは、投資リターンの追求を犠牲にするものでは必ずしもなく、両立し得るものである。
PRI署名機関は、6つの責任投資原則の遵守を求められるが、その原則の中には、“sustainability outcome/impact”という言葉は一切あらわれない。これは、PRIが設立された(すなわち、6つの原則が設定された)のが2006年であり、SDGsやパリ協定などのグローバル目標が設定されたのは2015年、“sustainability outcome/impact”という概念をPRIが議論するようになったのは2016~2017年頃から、という時系列が関係している。
PRIはUNEP-FI、Generation Foundationとともに、英国のフレッシュフィールズ法律事務所に委託した調査レポート「A Legal Framework for Impact」を2021年7月に公表している。同レポートは、(法域や投資家のタイプによって違いはあるが)一般には、“sustainability outcome/impact”を投資プロセスに考慮することが受託者責任に反しないことを指摘している。同レポートは、責任投資における“shape outcomes”の理論的支柱であり、その主著者であるDavid Rouchは、今回のバルセロナ大会(とその前日に開催されたSustainable Finance Policy Conference 2022)のセッションに2回登壇した。
2―― Be Ambitious
3―― Priority Issues
全体会合のほか、多くの分科会で、トランジションに関する議論がなされた。印象に残った登壇者の主張や論点は以下の通り。
- IEA(国際エネルギー機関)のBirol事務局長は、科学者やエネルギー業界の中で1.5℃目標の実現は不可能という見解も出てきていることについて、「困難を伴うものの、1.5℃の削減目標が達成不能とは思わない(I don’t buy that 1.5 degrees is dead.)」と発言。ネットゼロ実現に向けて各国が様々な取組みを進めているが、最も重要なことはエネルギー安全保障、気候変動へのコミットメント、産業政策と指摘。
- 「サステナ領域の国際的な取組みの動きが、ロシア・ウクライナの紛争によって後退することはない(no backsliding)」というメッセージがCOP27や米中首脳が会談したG20で発信されたことを前向きに捉えている、とのコメントがあった。また、欧州では、例えばポーランドの市民にとってEUのロシア制裁に従うことは、すぐ隣国に位置するサプライヤーからの供給がストップすることになり、コスト面では手痛いが、絶対に必要な措置(absolutely necessary)であり、むしろ地政学上の変化が汎欧州レベルでのサステナ領域における市民の連帯強化につながっているとの指摘があった。
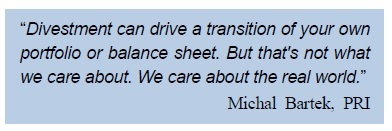
- ダイベストメントに関しては、「実体経済を変えることが重要であり、ダイベストメントは優先すべき手段とは言えない」、「投資の持ち分を失うことで企業に変革を促す影響力を失うデメリットの方が大きい」など、有効な手段とはいえない、とする見解が中心であった。分科会参加者(100名程度)を対象に実施されたアンケートでも、「ダイベストメントは有効ではない」との回答が過半を占めた。ダイベストメントに関しては、「実体経済を変えることが重要であり、ダイベストメントは優先すべき手段とは言えない」、「投資の持ち分を失うことで企業に変革を促す影響力を失うデメリットの方が大きい」など、有効な手段とはいえない、とする見解が中心であった。分科会参加者(100名程度)を対象に実施されたアンケートでも、「ダイベストメントは有効ではない」との回答が過半を占めた。
- ネットゼロに向けたトランジションの促進において、エンゲージメントが最も有効な手段というのが投資家のコンセンサス。投資家として、企業の目標策定を後押しするだけでなく、企業が2050年から逆算してどのような戦略を持っているのか、目標達成のためのインセンティブ付けやガバナンス体制はどうか、などネットゼロ実現に向けた企業の具体策をエンゲージメントの中で確認することが重要、との指摘が聞かれた。
- また、実体経済のネットゼロを進めていく上では、上場企業だけでなく未上場企業も含めて状況を捉えることが重要との指摘も。
- 脱炭素はグリーンファイナンスだけでは実現できず、トランジション・ファイナンスやイノベーション・ファイナンスが不可欠との指摘があったほか、排他的で極端な画一的アプローチでは反ESGを煽る可能性があるため、地域の特性を捉えたアプローチの重要性も指摘された1。また、脱炭素に向けて新興国のトランジションが極めて重要であり、先進国の失敗を繰り返さないためにも包括的なアプローチの必要性が指摘された。
- トランジションの進め方については、日本と欧州の間に溝があることを印象付ける場面もみられた。日本の登壇者から、多排出セクターのトランジションをサポートする過程では一時的にGHG(温室効果ガス)が増加することもあり得る、との発言――日本でしばしば見受けられる考え方――に対して、PRIのモデレーターから、なぜそのようなことが起き得るのか具体的に説明して欲しい、と再質問があった。トランジションの過程でfinanced emissionsが一時的に増加する可能性に言及した欧米の投資家はみられなかった。
1 Responsible Investor, “Anti-ESG movement could spread beyond the US, PRI board member warns —Speaking at PRI in Person at Barcelona, Nippon Life’s Kimura warned against a ‘one size fits all’ approach to decarbonization—”, 30 November 2022.
大会2日目の全体会合で、PRIのDavid Atkin CEOが、人権に関する協働エンゲージメント「Advance」の発足を発表。同イニシアティブを通じて、投資家が協働で企業と対話する内容として、(1)人権リスクに対処すること、(2)ロビー活動を行う際には人権尊重との平仄をとること、(3)国連の「ビジネスと人権の指導原則」に則ること、を挙げた。
登壇者の主な発言は以下の通り。
- 人権リスクが顕在化すれば、投資先企業の不買運動やレピュテーションの悪化、賠償金や罰金の発生などを通して、企業価値に深刻な影響が及ぶ。
- 一方、それが故に――人権問題が明るみに出るとメディア等から非常に厳しい反応を受けるために――、企業側がサプライチェーンも含めた人権問題を正直に語ってくれないケースがある。
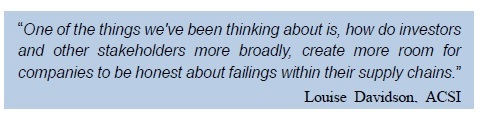
- 投資家は、対話を通じて、企業が人権問題に関して正直に語るインセンティブを醸成する必要がある(枠囲み発言参照)。
- この点、豪のリオ・ティント(鉱業・資源の多国籍企業)は、2022年に組織内の人種差別やセクハラに関する報告書を公開した。中身は課題山積であったが、人権問題を解決するために行動しようとしている企業のこうした動きを投資家はポジティブに受け入れる必要がある。
- 投資家は、全資産のデューデリジェンスに人権を組み込み、そして、企業分析において人権をリスクとして捉えるだけではなく、企業が人権リスクに対しどのように対応しているかを対話の中で確認し、それらを情報開示していくことが重要。
- このほか、人権デューデリジェンスに必要な詳細なデータが不足していることが、大きな課題(4.節で後述)。
PiPバルセロナ大会から生物多様性に関する国際会議COP15(12月5日からモントリオールで開催)への橋渡し役として、TNFDのGoldner事務局長がバルセロナ大会最終日の最後の全体会合に登壇。
主な発言内容は以下の通り。
- モントリオールで開かれるCOP15は、生物多様性の領域にとって(パリ協定が採択された2015年の気候変動COPのような)“The Paris Moment”になる。
- 世界経済フォーラムが発表した「気候変動の緩和と適応の失敗(Climate Change)」・「異常気象(Extreme Events)」・「生物多様性喪失(Nature Loss)」の世界三大リスクに対して、2023年がブレイクスルーの年になることを期待する。
- 再保険は、鉱山のカナリア(Canary in the mines)と言われるが、世界の大手再保会社の再保険料が、自然関連リスクのために30~50%も上昇している。
- G7/G20のリーダーたちはTNFDを組成して、世界中から20兆ドルのAUMを集めて「TNFDフォーラム」を立ち上げた。2023年9月にTNFDとしての提言を公表予定なので、PRI署名機関にぜひ市中協議に参加してもらいたい。
- Just Transition/Net Zero/Nature Positiveの三つの優先課題に、国際社会が結束して今こそ取組むべき時。
- 今こそ、金融機関が自然資本への投資を加速し、イノベーションカーブの先を行く絶好の機会であり、千載一遇の好機(Transformational Opportunity)である。
上記講演のほか、サーキュラーエコノミーの分科会でも、生物多様性・自然資本に関する言及がみられた。
(2023年01月11日「基礎研レポート」)
日本生命保険相互会社 木村 武*、高瀬俊史、德重亨、林宏樹、三木さやか
* PRI(国連責任投資原則)理事
新着記事
-
2025年10月27日
秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -
2025年10月27日
大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -
2025年10月27日
なぜ味噌汁は動くのか -
2025年10月24日
米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -
2025年10月24日
企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【これからの時代の責任投資-PRI in Person 2022バルセロナ大会の模様-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
これからの時代の責任投資-PRI in Person 2022バルセロナ大会の模様-のレポート Topへ


















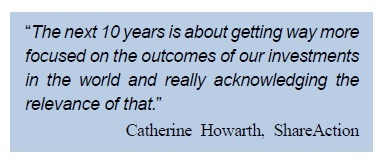
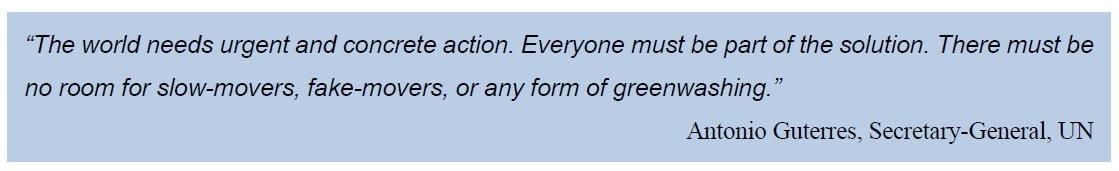
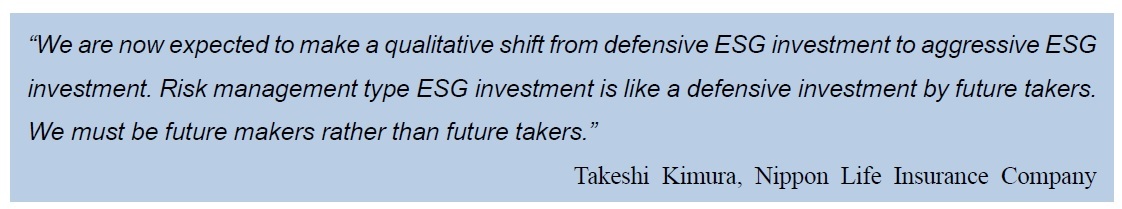
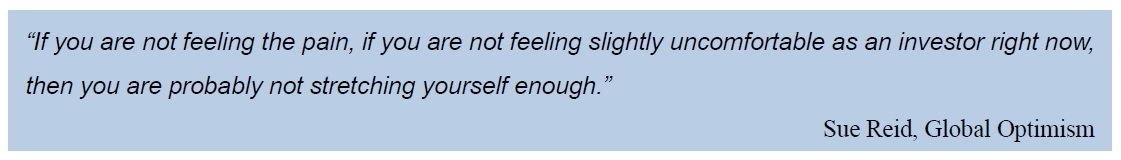
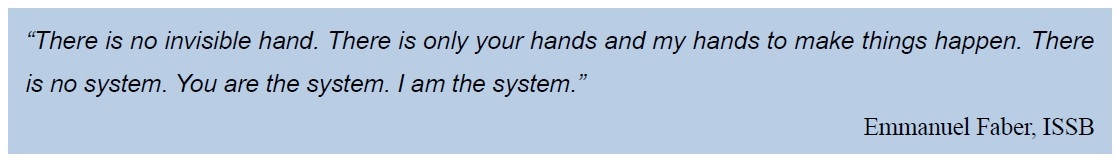
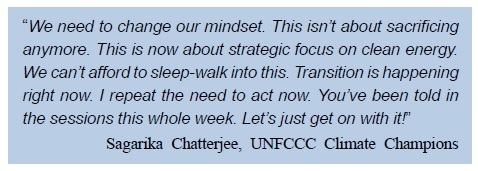
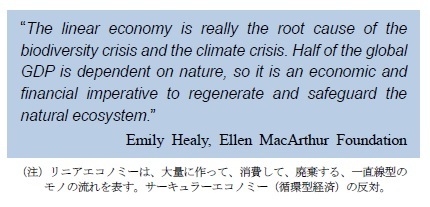

 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




