- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 暮らし >
- 芸術文化 >
- 2020年。全国で文化の祭典を
2018年03月28日
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
(2) 日本文化の発信だけではなく国際的な文化交流を
文化オリンピアードや文化プログラムの企画で、つい考えがちなのが、世界中から訪れる人たちに、日本の文化を発信しよう、地域の文化を体験してもらおう、という発想である。もちろん、そうした事業も重要だと思うが、東京以外の地域で実施する場合、少し冷静に考えた方が良いと思われる。
東京2020大会で初めて来日する観光客なら、京都や奈良など、著名な観光地も旅行しよう、ということになるかもしれない。しかし、よほど強いコンテンツでもない限り、オリンピック・パラリンピック競技の観戦にやって来る来日客が、文化イベントのために競技のない地方都市をわざわざ訪問する可能性は低いと考える方が現実的だろう。ロンドン2012文化オリンピアードの主要な事業を対象にした観客調査の結果でも22、海外からの観客が国内・地元を上回ったのは、バーミンガムで開催された世界初演の壮大なオペラのみである23。
しかし、東京2020大会は世界中のメディアが日本に注目する機会であることは間違いない。だとすれば、日本各地の文化をそのタイミングで国際的にアピールし、2021年以降のインバウンドにつなげるという戦略の方が現実的だと思われる。そのためにも、海外からの観光客に期待するより、文化プログラムとして海外のアーティストやクリエイターを招聘するなど国際交流に力を入れるべきではないか、というのがもう一つ指摘しておきたい点である。
ロンドン大会の例ばかり参照するのは気が引けるが、彼らの文化オリンピアードで注目すべき実績のひとつは、競技大会に参加した204のすべての国と地域からアーティストが参加したということである。日本からも蜷川幸雄や京都の劇団「地点」が招聘されてシェイクスピア作品を上演した。中には、競技にわずか数人のアスリートしか参加しない国や地域もあるはずだが、そうしたところからもアーティストが参加した、というのである。つまりロンドン2012大会には、オリンピック・パラリンピックという世界中が注目するチャンスを世界中のアーティストに提供しようというビジョンがあった。
この点は、東京2020大会もぜひ参考にすべきではないか。オリンピック・パラリンピック自体が、壮大な国際交流プロジェクトであることからも、海外との交流を視野に入れた文化プログラムをもっと実施すべきだと思うのである。
22 Institute of Cultural Capital, London 2012 Cultural Olympiad Evaluation Final Report, April 2013, p.126
23 シュトックハウゼンのオペラ「Mittwoch aus Lichit(光からの水曜日)」。作曲家が27年間を費やしたオペラ「光」の7部作のうち、この作品だけは一部のパートを除いて全曲上演されたことがなかった。宙に浮いたソリストの演奏、4機のヘリコプターに弦楽奏者が乗り込んで空中で共演する“ヘリコプターの四重奏”など、実現困難な要素が多数含まれていたためである。元工場で行われた5回の公演には、競技観戦に関係なく世界中のオペラファンが訪れたという。
文化オリンピアードや文化プログラムの企画で、つい考えがちなのが、世界中から訪れる人たちに、日本の文化を発信しよう、地域の文化を体験してもらおう、という発想である。もちろん、そうした事業も重要だと思うが、東京以外の地域で実施する場合、少し冷静に考えた方が良いと思われる。
東京2020大会で初めて来日する観光客なら、京都や奈良など、著名な観光地も旅行しよう、ということになるかもしれない。しかし、よほど強いコンテンツでもない限り、オリンピック・パラリンピック競技の観戦にやって来る来日客が、文化イベントのために競技のない地方都市をわざわざ訪問する可能性は低いと考える方が現実的だろう。ロンドン2012文化オリンピアードの主要な事業を対象にした観客調査の結果でも22、海外からの観客が国内・地元を上回ったのは、バーミンガムで開催された世界初演の壮大なオペラのみである23。
しかし、東京2020大会は世界中のメディアが日本に注目する機会であることは間違いない。だとすれば、日本各地の文化をそのタイミングで国際的にアピールし、2021年以降のインバウンドにつなげるという戦略の方が現実的だと思われる。そのためにも、海外からの観光客に期待するより、文化プログラムとして海外のアーティストやクリエイターを招聘するなど国際交流に力を入れるべきではないか、というのがもう一つ指摘しておきたい点である。
ロンドン大会の例ばかり参照するのは気が引けるが、彼らの文化オリンピアードで注目すべき実績のひとつは、競技大会に参加した204のすべての国と地域からアーティストが参加したということである。日本からも蜷川幸雄や京都の劇団「地点」が招聘されてシェイクスピア作品を上演した。中には、競技にわずか数人のアスリートしか参加しない国や地域もあるはずだが、そうしたところからもアーティストが参加した、というのである。つまりロンドン2012大会には、オリンピック・パラリンピックという世界中が注目するチャンスを世界中のアーティストに提供しようというビジョンがあった。
この点は、東京2020大会もぜひ参考にすべきではないか。オリンピック・パラリンピック自体が、壮大な国際交流プロジェクトであることからも、海外との交流を視野に入れた文化プログラムをもっと実施すべきだと思うのである。
22 Institute of Cultural Capital, London 2012 Cultural Olympiad Evaluation Final Report, April 2013, p.126
23 シュトックハウゼンのオペラ「Mittwoch aus Lichit(光からの水曜日)」。作曲家が27年間を費やしたオペラ「光」の7部作のうち、この作品だけは一部のパートを除いて全曲上演されたことがなかった。宙に浮いたソリストの演奏、4機のヘリコプターに弦楽奏者が乗り込んで空中で共演する“ヘリコプターの四重奏”など、実現困難な要素が多数含まれていたためである。元工場で行われた5回の公演には、競技観戦に関係なく世界中のオペラファンが訪れたという。
(3) 東京2020アーティスト・イン・レジデンス
そうした発想から、筆者が最近各地で提案しているのが、アーティスト・イン・レジデンスである。2020年の東京には200を超える国や地域からトップレベルのアスリートが集結する。であれば、東京以外の場所に同じだけの国と地域からアーティストを招いてはどうかというアイディアである。
アーティスト・イン・レジデンスは華やかな文化イベントとは対極にある事業だが、アーティストやクリエイターが地域に滞在して創作活動に取り組んだり、子どもたちや地域住民と交流したりすることで、国際的な相互交流と日本文化への理解が促進されることは間違いない。「平和」をテーマに日本のアーティストたちと共同制作に取り組む、といったことも可能だろう。
例えば、京都などを中心に関西広域連合の府県が手分けして実施したとすれば、東京圏と関西圏でスポーツと文化の祭典を同時開催できる。空き家を活用して京都の町屋への滞在を呼びかければ、世界中のアーティストから応募があるに違いない。あるいは九州の約230の市町村がそれぞれ一ヶ国からアーティストを招聘するというのも一案だ。2002年のワールドカップで大分県中津江村にカメルーン代表がキャンプをした時のことを記憶している方も多いだろう。その様子を思い起こせば、小さな町に海外からアーティストがやってくることのインパクトは容易に想像できる。
アーティストの選出は各国大使館や国際交流基金を経由して依頼する。滞在や制作に伴う経費は地元で負担することにして、日本までの渡航費を各国に協力してもらえば、さほど大きな経費はかからない。東京に滞在する海外メディアも、オリンピックの機会に自国からアーティストが招聘されているとなると、地方にも取材に訪れるだろう。
オリパラ教育の一環として、アーティストには地元の小中学校を訪問してワークショップを行ってもらう。そうすれば、競技大会中は地域をあげてアーティストの母国を応援するに違いない。海外メディアには、その様子はもちろん、アーティストと地域住民や子どもたちとの交流、町の文化や観光資源などを取材、報道してもらえば、翌年以降のインバウンドにつながる可能性もゼロではない。
政府の推進するホストタウンと連携すれば、地域を限定せず全国で展開することも可能だ。事前合宿の招致はハードルが高いことから、政府は競技大会終了後に選手がホストタウンを訪問する「事後交流」を後押ししているが、その場合でも大会前後の短い期間に限られる。それに対し、アーティスト・イン・レジデンスは競技期間に縛られる必要がない。例えば、聖火リレーのスタートする2020年春頃からパラリンピックの終了する9月上旬の間に、数週間から数ヶ月滞在してもらい、より長期の交流プログラムを行うことも可能だろう。
そうした発想から、筆者が最近各地で提案しているのが、アーティスト・イン・レジデンスである。2020年の東京には200を超える国や地域からトップレベルのアスリートが集結する。であれば、東京以外の場所に同じだけの国と地域からアーティストを招いてはどうかというアイディアである。
アーティスト・イン・レジデンスは華やかな文化イベントとは対極にある事業だが、アーティストやクリエイターが地域に滞在して創作活動に取り組んだり、子どもたちや地域住民と交流したりすることで、国際的な相互交流と日本文化への理解が促進されることは間違いない。「平和」をテーマに日本のアーティストたちと共同制作に取り組む、といったことも可能だろう。
例えば、京都などを中心に関西広域連合の府県が手分けして実施したとすれば、東京圏と関西圏でスポーツと文化の祭典を同時開催できる。空き家を活用して京都の町屋への滞在を呼びかければ、世界中のアーティストから応募があるに違いない。あるいは九州の約230の市町村がそれぞれ一ヶ国からアーティストを招聘するというのも一案だ。2002年のワールドカップで大分県中津江村にカメルーン代表がキャンプをした時のことを記憶している方も多いだろう。その様子を思い起こせば、小さな町に海外からアーティストがやってくることのインパクトは容易に想像できる。
アーティストの選出は各国大使館や国際交流基金を経由して依頼する。滞在や制作に伴う経費は地元で負担することにして、日本までの渡航費を各国に協力してもらえば、さほど大きな経費はかからない。東京に滞在する海外メディアも、オリンピックの機会に自国からアーティストが招聘されているとなると、地方にも取材に訪れるだろう。
オリパラ教育の一環として、アーティストには地元の小中学校を訪問してワークショップを行ってもらう。そうすれば、競技大会中は地域をあげてアーティストの母国を応援するに違いない。海外メディアには、その様子はもちろん、アーティストと地域住民や子どもたちとの交流、町の文化や観光資源などを取材、報道してもらえば、翌年以降のインバウンドにつながる可能性もゼロではない。
政府の推進するホストタウンと連携すれば、地域を限定せず全国で展開することも可能だ。事前合宿の招致はハードルが高いことから、政府は競技大会終了後に選手がホストタウンを訪問する「事後交流」を後押ししているが、その場合でも大会前後の短い期間に限られる。それに対し、アーティスト・イン・レジデンスは競技期間に縛られる必要がない。例えば、聖火リレーのスタートする2020年春頃からパラリンピックの終了する9月上旬の間に、数週間から数ヶ月滞在してもらい、より長期の交流プログラムを行うことも可能だろう。
(4) 圧倒的な市民参加プロジェクト
筆者がかねてから提案しているもう一つの具体的なアイディアは、年齢や障がいの有無に関係なく、あらゆる人々の市民参加を促すプロジェクトである。具体的なアイディアは次の3つだ。
【鳴り響け1,000万台のピアノ】
日本は世界に誇るピアノ大国である。2014年の全国消費実態調査によれば、ピアノ・電子ピアノの世帯普及率は24.7%、世帯数は5,175万だから1,000万台を優に超えるピアノが一般家庭に保有されていることになる。学校やホール・劇場、その他の公共施設や商業施設などを含めると、その数はさらに増えるだろう。
そのピアノを使って、開会式や閉会式にあわせ、テーマソングを全国で1,000万人が奏でる、というのがこのアイディアである。学校はもちろん、劇場やホール、公共施設等のピアノに加え、家庭で埃を被っているアップライトピアノも調律し直せば、自宅に居ながら誰もがピアノで東京2020大会に参加できる。オリパラ教育の一環として、2020年春から全国の小中学校の音楽の授業に取り入れる、というのはどうだろう。
【第九、250万人の熱唱】
2020年はベートーベンの生誕250年にあたる。パラリンピックの開会式や閉会式にあわせ、全国で250万人が第九を熱唱する、という案はどうだろうか。周知のとおり第九はベートーベンが聴力を完全に失ってから作曲された。いわば障がいのあるアーティストが生み出した歴史的作品である。
「歓喜の歌」を日本各地で熱唱し、スポーツと芸術の両面からパラリンピックの理念を世界中にアピールするというのがこのアイディアの狙いである。250万人は生誕250年の語呂合わせであるが、1万人の第九(大阪城ホール)、5,000人の第九(国技館)などが日本各地で開催されていることを考えると、あながち無理な数字ではないはずだ。
プロアマ問わず、全国のオーケストラに参加してもらい、アリーナや公共ホールなどで同時演奏する。大会主催都市の東京都から、64年の東京五輪を機に創設された東京都交響楽団が音頭を取って、全国に働きかけることはできないだろうか。
【日本縦断BON DANCE】
日本で参加型の文化催事で最大規模のものと言えば盆踊りだろう。最近では近藤良平・コンドルズの振り付けで毎年池袋西口公園で開催される「にゅ~盆踊り」、東日本大震災の後、音楽家の大友良英らが立ち上げたPROJECT FUKUSHIMAで始まった「納涼!盆踊り」など、現代アーティストが中心になって始まったものもある。
新旧合わせ、北から南まで日本中の盆踊りを東京2020大会の記念行事とし、子どもやお年寄りはもちろん、障がいの有無や性差、国籍など関係なく、誰もが盆踊りを楽しんでいる様子を世界に発信することを文化プログラムにしてはどうかというのがこのアイディアである。8月のお盆はオリンピックとパラリンピックのインターバルで、両者をつなぐイベントにもなるはずだ。
筆者がかねてから提案しているもう一つの具体的なアイディアは、年齢や障がいの有無に関係なく、あらゆる人々の市民参加を促すプロジェクトである。具体的なアイディアは次の3つだ。
【鳴り響け1,000万台のピアノ】
日本は世界に誇るピアノ大国である。2014年の全国消費実態調査によれば、ピアノ・電子ピアノの世帯普及率は24.7%、世帯数は5,175万だから1,000万台を優に超えるピアノが一般家庭に保有されていることになる。学校やホール・劇場、その他の公共施設や商業施設などを含めると、その数はさらに増えるだろう。
そのピアノを使って、開会式や閉会式にあわせ、テーマソングを全国で1,000万人が奏でる、というのがこのアイディアである。学校はもちろん、劇場やホール、公共施設等のピアノに加え、家庭で埃を被っているアップライトピアノも調律し直せば、自宅に居ながら誰もがピアノで東京2020大会に参加できる。オリパラ教育の一環として、2020年春から全国の小中学校の音楽の授業に取り入れる、というのはどうだろう。
【第九、250万人の熱唱】
2020年はベートーベンの生誕250年にあたる。パラリンピックの開会式や閉会式にあわせ、全国で250万人が第九を熱唱する、という案はどうだろうか。周知のとおり第九はベートーベンが聴力を完全に失ってから作曲された。いわば障がいのあるアーティストが生み出した歴史的作品である。
「歓喜の歌」を日本各地で熱唱し、スポーツと芸術の両面からパラリンピックの理念を世界中にアピールするというのがこのアイディアの狙いである。250万人は生誕250年の語呂合わせであるが、1万人の第九(大阪城ホール)、5,000人の第九(国技館)などが日本各地で開催されていることを考えると、あながち無理な数字ではないはずだ。
プロアマ問わず、全国のオーケストラに参加してもらい、アリーナや公共ホールなどで同時演奏する。大会主催都市の東京都から、64年の東京五輪を機に創設された東京都交響楽団が音頭を取って、全国に働きかけることはできないだろうか。
【日本縦断BON DANCE】
日本で参加型の文化催事で最大規模のものと言えば盆踊りだろう。最近では近藤良平・コンドルズの振り付けで毎年池袋西口公園で開催される「にゅ~盆踊り」、東日本大震災の後、音楽家の大友良英らが立ち上げたPROJECT FUKUSHIMAで始まった「納涼!盆踊り」など、現代アーティストが中心になって始まったものもある。
新旧合わせ、北から南まで日本中の盆踊りを東京2020大会の記念行事とし、子どもやお年寄りはもちろん、障がいの有無や性差、国籍など関係なく、誰もが盆踊りを楽しんでいる様子を世界に発信することを文化プログラムにしてはどうかというのがこのアイディアである。8月のお盆はオリンピックとパラリンピックのインターバルで、両者をつなぐイベントにもなるはずだ。
いずれの案も、どこか小さな市町村から始まり、徐々に賛同者を得て全国に広がっていくイメージである。これらのアイディアを紹介すると、多くの方が関心を示してくださるが、残念ながらまだ具体的に始めようというところは出てきていない。最初に手を挙げたところが、全国プロジェクトの創設者になれると思うのだが、いかがだろうか。
(2018年03月28日「基礎研レポート」)
吉本 光宏 (よしもと みつひろ)
吉本 光宏のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2023/07/11 | 個人寄付から社会を変える-新型コロナの経験を活かすために | 吉本 光宏 | ニッセイ基礎研所報 |
| 2023/06/07 | Achieving world peace through art and culture: A declaration at the Busan International Cultural Forum | 吉本 光宏 | 研究員の眼 |
| 2023/05/25 | 文化から平和を考える-釜山国際文化フォーラムに出席して | 吉本 光宏 | 研究員の眼 |
| 2022/11/22 | DON’T FOLLOW THE WIND-未だ終わらぬ東日本大震災と福島第一原発事故 | 吉本 光宏 | 研究員の眼 |
新着記事
-
2025年09月17日
ふるさと納税「お得競争」の終焉-ポイント還元の廃止で問われる「地域貢献」と「持続可能な制度」のこれから -
2025年09月17日
貿易統計25年8月-関税引き上げの影響が顕在化し、米国向け自動車輸出が数量ベースで大きく落ち込む -
2025年09月17日
「最低賃金上昇×中小企業=成長の好循環」となるか?-中小企業に託す賃上げと成長の好循環の行方 -
2025年09月17日
家計消費の動向(二人以上世帯:~2025年7月)-実質賃金改善下でも「メリハリ消費」継続、娯楽支出は堅調を維持 -
2025年09月16日
インド消費者物価(25年9月)~8月のCPI上昇率は+2.1%に上昇、GST合理化でインフレ見通しは緩和
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【2020年。全国で文化の祭典を】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
2020年。全国で文化の祭典をのレポート Topへ


















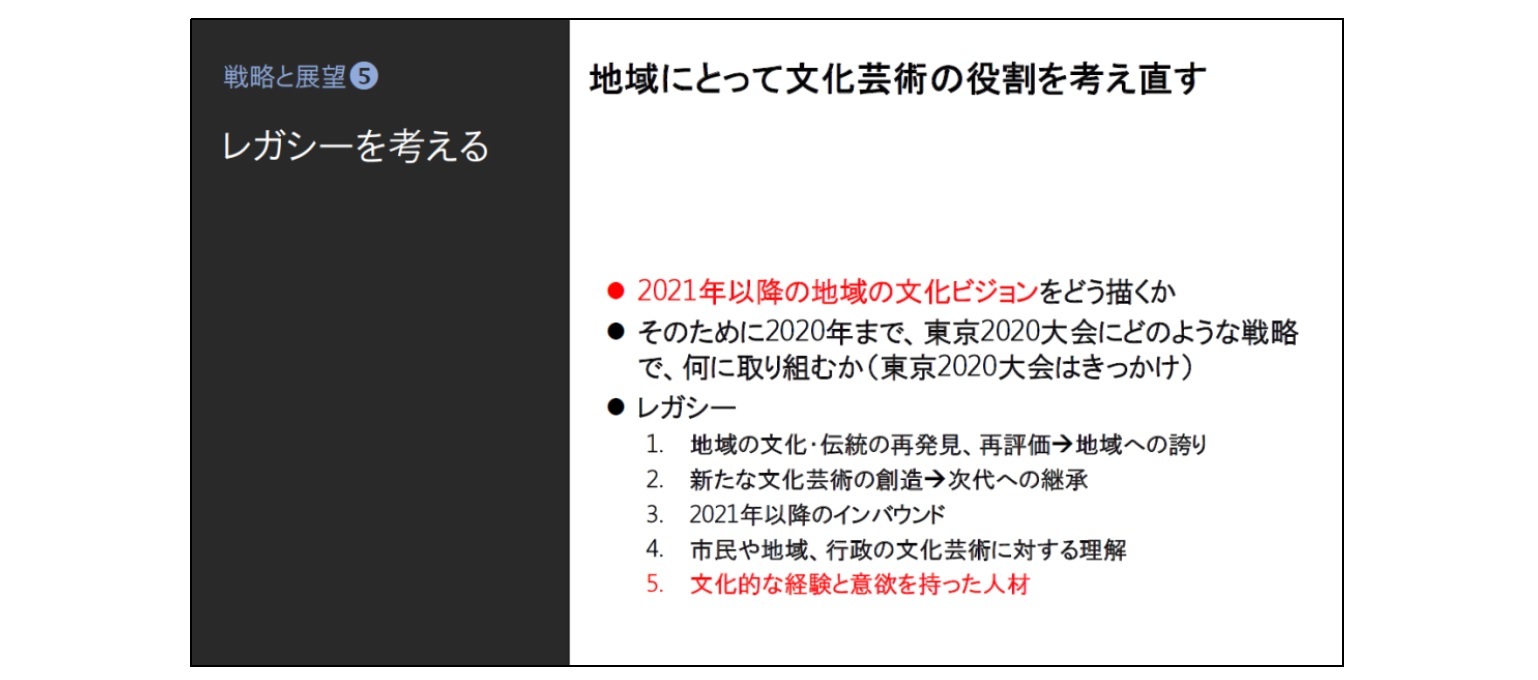

 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




