- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >
- 高齢者世帯の家計・資産 >
- 未婚と離婚の増加で変わる将来の高齢単身者
コラム
2008年08月20日
同居する家族の構成という意味で様々な形態の世帯がある中、最も数が多い世帯形態は、今のところは、夫婦と子から成る世帯である。しかし、近いうちにこれに代わると予想されているのが単身世帯である。主役交代が間近だと見られているのは、長寿化に伴って高齢単身者が増加するだけでなく、夫婦数自体も減っていくからである。実際、結婚しない人が増加を続ける一方で、離婚する人も同様に増え続けており、すでに夫婦の数は2001年をピークに減少に転じている。
その離婚に関して、特に注目されるのは、40歳代と50歳代の女性の動向である。離婚した後に再婚していない人(以下、離婚者と表記)が同世代の総人口に占める割合は、なんと8.1%にも達している。一方、同じ年齢階層の男性については、この割合は5.2%にとどまっている。各年齢階層における未婚者(1度も結婚したことのない人)の割合を男女間で比較すると、離婚者の割合とは逆に、男性の方が女性よりも大幅に高い。例えば、50歳代後半の未婚者の割合は、女性5.2%、男性9.8%と、こちらもショッキングな数字である。
未婚者と離婚者の割合を年齢階層間で比較すると、未婚者の割合は年齢とともに低下するのに対して、離婚者の割合は年齢とともに上昇する関係が、男女共通に見られる。しかし、加齢に伴う変化幅がそれぞれ微妙に異なるため、年齢階層別人口から未婚者、離婚者、死別者を除いた人の割合、すなわち、配偶者のいる人の割合が最も高い年齢階層は、男女で著しく異なっている。最も高いのは、男性の場合は、60歳代後半の85.3%であるのに対して、女性の場合は、年齢階層は50歳代前半、水準も80.9%でしかない。いずれにしても、現在の50歳代前半女性のグループは、他の年齢階層の女性と比べて配偶者がいる人の割合が最も高いために見過ごされやすいが、前述のとおり、離婚し、その後も再婚していない人の割合が最も高いグループでもあるのだ。
より正確な事実を知るため、同一世代内の未婚者の割合と離婚者の割合が年齢とともにどのように推移してきたのか、世代別に生涯の変化を歴史的に辿ってみると(後掲図表)、同一年齢階層における割合は、いずれも後に生まれた世代ほど高く、その上昇傾向に歯止めがかかっていないことが分かる。一方、現在の65歳以上の世代では、未婚者の割合も離婚者の割合も3%前後にとどまっており、配偶者のいる人の割合は62%、残り30%は配偶者と死別した人の割合である。つまり、現在の単身高齢者の大半は、夫か妻のいずれかが死亡するまで、夫婦、ないしは夫婦と子から成る世帯として長い間生活をともにしてきたものと考えられる。
世代間の違いという意味では、他にも重要な事実がある。1935年以前に生まれた世代は、男女ともに一定の年齢を過ぎると離婚者の割合が低下していくのに対して、1936年以降に生まれた世代については、そうした傾向が未だ見られないことである。1935年以前に生まれた世代に関しては、次のように考えられる。ひとつは、離婚した人が、高齢期を迎える前に再婚したという可能性である。もうひとつは、離婚した人は、夫婦ともに暮らす人ほどには長生きをしているケースが少ないという可能性である。そのような推測ができるのは、離婚者の割合を計算する際の分子と分母が同数減少すれば、算出された数字が低下するからである。
いずれにしても、現在の若年世代や中年世代が将来高齢に達した時の単身高齢者は、現在のように、高齢になってから配偶者と死別した人が大多数を占めるというのではなく、もともと結婚していない人や早くに離婚した人が相当数を占めることが予想される。
老後の生活という観点から見ると、見掛け上は同じ単身高齢者であっても、夫婦として過ごした期間が長いか、短いかによって、受給できる公的年金の金額(注)も、老後の生活に入るまでに蓄えることのできる資産の金額も、著しく異なるはずである。今後の社会保障制度改革に際しては、これまでの標準的なライフコースには収まらない未婚や離婚による単身高齢者が増えていく可能性も明示的に考慮に入れるべきであろう。
(注)夫婦期間が長い世帯に関しては、老齢厚生年金を受給していた人が死亡した後に、配偶者が自分自身の基礎年金のほかに遺族厚生年金を受給するケースを想定
その離婚に関して、特に注目されるのは、40歳代と50歳代の女性の動向である。離婚した後に再婚していない人(以下、離婚者と表記)が同世代の総人口に占める割合は、なんと8.1%にも達している。一方、同じ年齢階層の男性については、この割合は5.2%にとどまっている。各年齢階層における未婚者(1度も結婚したことのない人)の割合を男女間で比較すると、離婚者の割合とは逆に、男性の方が女性よりも大幅に高い。例えば、50歳代後半の未婚者の割合は、女性5.2%、男性9.8%と、こちらもショッキングな数字である。
未婚者と離婚者の割合を年齢階層間で比較すると、未婚者の割合は年齢とともに低下するのに対して、離婚者の割合は年齢とともに上昇する関係が、男女共通に見られる。しかし、加齢に伴う変化幅がそれぞれ微妙に異なるため、年齢階層別人口から未婚者、離婚者、死別者を除いた人の割合、すなわち、配偶者のいる人の割合が最も高い年齢階層は、男女で著しく異なっている。最も高いのは、男性の場合は、60歳代後半の85.3%であるのに対して、女性の場合は、年齢階層は50歳代前半、水準も80.9%でしかない。いずれにしても、現在の50歳代前半女性のグループは、他の年齢階層の女性と比べて配偶者がいる人の割合が最も高いために見過ごされやすいが、前述のとおり、離婚し、その後も再婚していない人の割合が最も高いグループでもあるのだ。
より正確な事実を知るため、同一世代内の未婚者の割合と離婚者の割合が年齢とともにどのように推移してきたのか、世代別に生涯の変化を歴史的に辿ってみると(後掲図表)、同一年齢階層における割合は、いずれも後に生まれた世代ほど高く、その上昇傾向に歯止めがかかっていないことが分かる。一方、現在の65歳以上の世代では、未婚者の割合も離婚者の割合も3%前後にとどまっており、配偶者のいる人の割合は62%、残り30%は配偶者と死別した人の割合である。つまり、現在の単身高齢者の大半は、夫か妻のいずれかが死亡するまで、夫婦、ないしは夫婦と子から成る世帯として長い間生活をともにしてきたものと考えられる。
世代間の違いという意味では、他にも重要な事実がある。1935年以前に生まれた世代は、男女ともに一定の年齢を過ぎると離婚者の割合が低下していくのに対して、1936年以降に生まれた世代については、そうした傾向が未だ見られないことである。1935年以前に生まれた世代に関しては、次のように考えられる。ひとつは、離婚した人が、高齢期を迎える前に再婚したという可能性である。もうひとつは、離婚した人は、夫婦ともに暮らす人ほどには長生きをしているケースが少ないという可能性である。そのような推測ができるのは、離婚者の割合を計算する際の分子と分母が同数減少すれば、算出された数字が低下するからである。
いずれにしても、現在の若年世代や中年世代が将来高齢に達した時の単身高齢者は、現在のように、高齢になってから配偶者と死別した人が大多数を占めるというのではなく、もともと結婚していない人や早くに離婚した人が相当数を占めることが予想される。
老後の生活という観点から見ると、見掛け上は同じ単身高齢者であっても、夫婦として過ごした期間が長いか、短いかによって、受給できる公的年金の金額(注)も、老後の生活に入るまでに蓄えることのできる資産の金額も、著しく異なるはずである。今後の社会保障制度改革に際しては、これまでの標準的なライフコースには収まらない未婚や離婚による単身高齢者が増えていく可能性も明示的に考慮に入れるべきであろう。
(注)夫婦期間が長い世帯に関しては、老齢厚生年金を受給していた人が死亡した後に、配偶者が自分自身の基礎年金のほかに遺族厚生年金を受給するケースを想定
(2008年08月20日「研究員の眼」)
このレポートの関連カテゴリ
石川 達哉
石川 達哉のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2018/12/28 | 同床異夢の臨時財政対策債-償還費を本当に負担するのは国か、地方か? | 石川 達哉 | 研究員の眼 |
| 2018/07/13 | 「地方財源不足額」は本当に解消されているのか?―先送りされ続ける臨時財政対策債の償還財源確保 | 石川 達哉 | 基礎研レポート |
| 2017/08/31 | 再び問われる交付税特会の行方-地方財政の健全性は高まったのか? | 石川 達哉 | 基礎研レポート |
| 2017/07/03 | 増大する地方公共団体の基金残高 その2-実は拡大している積立不足!? | 石川 達哉 | 研究員の眼 |
新着記事
-
2025年11月04日
今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -
2025年10月31日
交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -
2025年10月31日
ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -
2025年10月31日
2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -
2025年10月31日
保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【未婚と離婚の増加で変わる将来の高齢単身者】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
未婚と離婚の増加で変わる将来の高齢単身者のレポート Topへ


















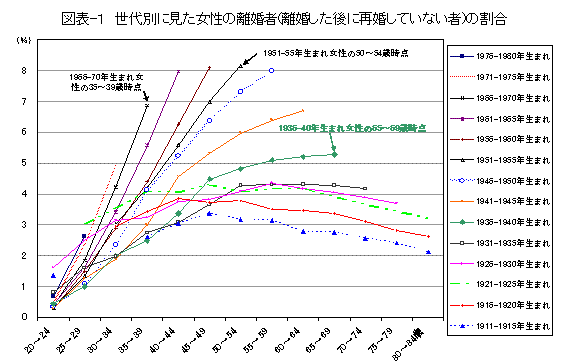
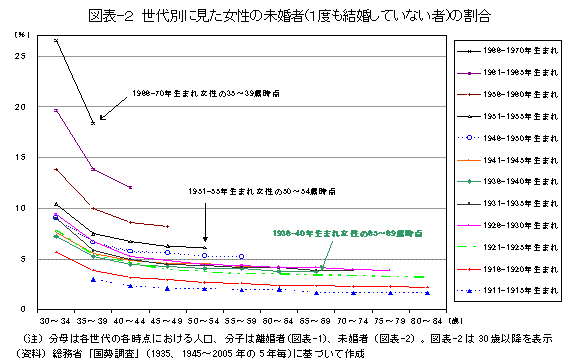

 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




