- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 暮らし >
- 消費者行動 >
- 持家志向の謎
| 1.土地に対して冷静になった日本の家計 まもなく、2004年1月1日時点での公示地価が公表される見込みである。アメニティの充実した総合ショッピングセンターのオープン、新公共交通システムや地下鉄の開通・路線延長などによって、利便性の向上した一部地域では地価上昇に転じている例外的なケースもあるだろうが、日本全体としては13年連続の地価下落という結果が想像される。日本とは対照的なのが米国・英国であり、株価が調整局面を迎えた2000年代入り後も、今日に至るまで不動産市場は好況を呈している。 実は、英国も、80年代後半の住宅(土地を含む、以下同様)の価格急騰と90年代初頭の大幅下落を経験しているが、住宅の名目価格は90年代半ばに底打ちし、実質価格も90年代後半から上昇に転じたのである。さらに、2000年代入り後は価格上昇率を高め、2003年半ばには名目ベースで20%を超える上昇率を記録したほどである。 最近では、価格上昇率自体はやや鈍化したものの、依然として上昇が続いているため、バブルやその崩壊の可能性が懸念されていることも事実である。それを認識したうえでも、市場性資産である住宅が価格上昇する時期も下落する時期も、長からぬ間隔で訪れるという歴史を積み重ねてきた英国には、ある種の羨望に似た感情を抱いてしまう。 日本においては、地価の持続的な下落から脱する、あるいは、社会としてこれを克服することが最重要課題のひとつであることは言うまでもないが、土地に対する国民の意識変化の中にはプラスの要素が確実に育まれているという点も見落としてはならない。 国土交通省が継続的に実施している「土地問題に関する国民の意識調査」によると、「土地は預貯金や株式などに比べて有利な資産か」という問いに対して、1988年においては「そう思う」と答えた人が2/3を占めていたが、2002年においてはその割合は1/3まで低下している。 興味深いのは「そうは思わない」という回答も1/3、残りの「どちらとも言えない」「わからない」という回答を合わせた割合も1/3あることである。「地価は絶対に下がらない」という土地神話が単に崩壊したというのではなく、資産としての土地の価格は不確実なもの、先行きを予見するのは困難であるという冷静な認識が浸透した結果と言えるであろう。 事実、土地を有利な資産と回答した人に限定して、その理由を聞いた結果においても、株式に厳し目の記述を採っている「価格変動リスクの大きい株式等と比べて、地価が大きく下落するリスクは小さい」という選択肢を理由に挙げている人は1割にとどまっている。最大(4割)の支持を集めている理由は「物理的に滅失しない」という選択肢であり、次点(2割)は「生産や生活に役立つ」という理由である。これらの理由の正当性には異を唱えようもあるまい。
2.されど変わらぬ持家志向
6割から7割という持家率の水準は、国際的に極めて標準的である。日本のほか、米国・英国・カナダ・オーストラリア・イタリア・ルクセンブルグ・ポルトガルなどがこの範囲に入っている。やや低めなのが、ドイツ・オランダ・デンマーク・スウェーデンなどの北ヨーロッパ系の国々である。 3.家計が潜在的に欲しているのは安くて広い借家 持家率の水準は国際標準の日本であるが、他国では考えられないような大きな問題が住宅市場には存在している。詳細なデータが利用できる日本・米国・英国・ドイツ・フランスについて、まず、戸当たり床面積を比較すると、持家・借家を総合した平均値では、日本のそれは決して低くない。しかし、借家の面積が著しく狭いのである。日本以外の国でも、借家の方が持家より狭い傾向は共通しているが、それでも借家にも持家の6~7割の床面積がある。4割に満たないのは日本だけである。
住宅は家計が直接消費することのできるサービス、すなわち、居住空間の提供という住宅サービスを生み出すことができる点では、金融資産とは決定的に異なる。価格変動という無視できないリスクを認識していても、広い借家がほとんど存在しない現状では、持家志向に傾くというのも極めて納得がいく判断である。 地価下落が続いてきた現在でも、年収と比べた持家の価額は、国際的に見て高い。だが、90年代半ば以降は、金融機関の住宅ローン貸出の積極化、低金利、住宅ローンに対する優遇税制の拡大という持家取得を促進する条件が重なった。それゆえ、雇用・所得環境がかつてないほど厳しくなった現在においても、多少背伸びをしてでもマイホーム取得に走る家計が少なくないのではなかろうか。住宅ローン設定時における返済計画期間の長さや借入資金の年収比を、米国や英国と比較すると、日本の家計はかなり大胆である。
もちろん、これらに対して、改善に向けた政策的対応がなされていない訳ではない。定期借地権制度、定期借家制度、住宅性能表示制度などの施行がそうである。定期借地権制度を利用した定期借地権付持家は、契約期間を限定することで安さと広さを実現できる。持家が一時的に空家になる場合など、定期借家制度を利用して賃貸住宅(借家)へ転用すれば、早期に広い借家を増加させることができる。住宅性能表示制度に基づいて建築方法や修理・改善の客観的事実を履歴情報として蓄積していけば、中古取引を阻害する「情報の非対称性」の問題を緩和できる。 これらに加えて望まれるのは、帰属家賃も考慮したうえでの持家新築と既存住宅の増改築や賃貸住宅の新築との税制上の中立性を実現することである。また、持家も含めて、家屋や土地の売却・取得・保有に課せられる様々な税は、この2年間の税制改正で軽減される見込みであるが、これまでが他の資産と比べて相対的に重課され過ぎてきたと言え、住宅固有の税は今なお残っている。「簡素・中立・公平」であれ、「簡素・活力・公正」であれ、住宅関連分野においても、その貫徹に向けた税制改革の推進を期待したい。そうすれば、広い借家が増え、背伸びし過ぎたローンで苦しむという意味での無理な持家志向も少なくなることであろう。 |
(2004年03月08日「エコノミストの眼」)
このレポートの関連カテゴリ
石川 達哉
石川 達哉のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2018/12/28 | 同床異夢の臨時財政対策債-償還費を本当に負担するのは国か、地方か? | 石川 達哉 | 研究員の眼 |
| 2018/07/13 | 「地方財源不足額」は本当に解消されているのか?―先送りされ続ける臨時財政対策債の償還財源確保 | 石川 達哉 | 基礎研レポート |
| 2017/08/31 | 再び問われる交付税特会の行方-地方財政の健全性は高まったのか? | 石川 達哉 | 基礎研レポート |
| 2017/07/03 | 増大する地方公共団体の基金残高 その2-実は拡大している積立不足!? | 石川 達哉 | 研究員の眼 |
新着記事
-
2025年10月24日
米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -
2025年10月24日
企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -
2025年10月24日
消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -
2025年10月24日
保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -
2025年10月23日
御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【持家志向の謎】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
持家志向の謎のレポート Topへ


















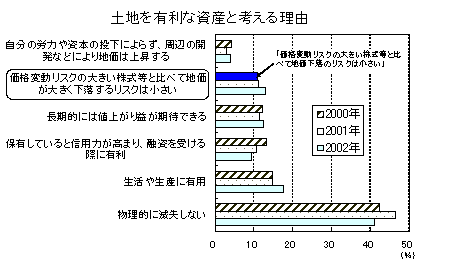
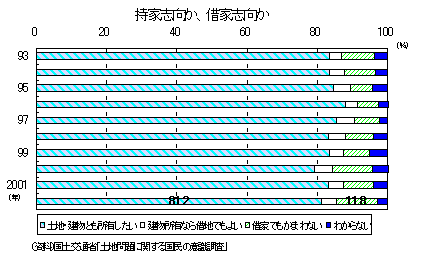
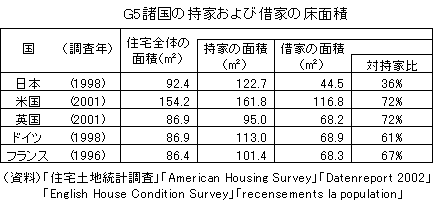
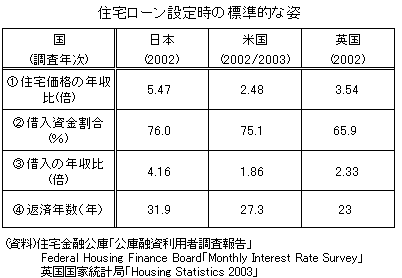

 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




