- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >
- 高齢者世帯の家計・資産 >
- 高齢化が家計貯蓄率に与える影響
コラム
2002年02月18日
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
1.国際的順位が下がった日本の家計貯蓄率
家計貯蓄率には様々な社会・経済要因が関係していると考えられる。これまでの実証研究からは、各国共通の要因として、人口構成、1人当たりの実質所得増加率、財政収支、失業率、インフレ率、消費者信用制度などの影響力が大きいことが明らかにされている。このうち、人口構成が重要な役割を果たしていることは想像に難くない。引退した高齢者の主たる収入は公的年金であり、生活資金はそれだけでは十分でないから、現役時代に貯えた資産を取り崩して使わざるを得ない。所得を上回る消費、すなわち、負の貯蓄を行うのが通常の高齢者の姿であり、そうした高齢者が人口に占める割合が高まれば、社会全体の貯蓄率は低下するからである。
90年代以降の日本に関しては、財政赤字の拡大と雇用環境の悪化が将来に備えて家計貯蓄を増やす方向に作用したため、高齢化による効果は一部相殺され、貯蓄率が顕著に低下しているわけではない。しかし、他の国々と比べて急速度で進んだ高齢化が家計貯蓄率に着実に影響を及ぼしていることは、「家計貯蓄率の国際的順位」の低下が十分に物語っている。
さらに重要なことは、高齢化の進行はこれから本格化することである。
90年代以降の日本に関しては、財政赤字の拡大と雇用環境の悪化が将来に備えて家計貯蓄を増やす方向に作用したため、高齢化による効果は一部相殺され、貯蓄率が顕著に低下しているわけではない。しかし、他の国々と比べて急速度で進んだ高齢化が家計貯蓄率に着実に影響を及ぼしていることは、「家計貯蓄率の国際的順位」の低下が十分に物語っている。
さらに重要なことは、高齢化の進行はこれから本格化することである。
2.老年従属人口比率が1%上昇すれば、家計貯蓄率は0.51%低下
1月末に国立社会保障・人口問題研究所が公表した「日本の将来推計人口(中位推計)」によると、65歳以上人口の割合は、2000年の17.4%から、2010年に22.5%、2020年には27.8%へと高まり、2050年に35.7%に達する見込みである。社会的な扶養負担を表す「老年従属人口比率(65歳以上人口÷15~64歳人口)」は、2000年25.5%、2010年35.2%、2020年46.4%、2050年66.5%と、上昇の一途をたどる。
この老年従属人口比率が1%上昇した場合に家計貯蓄率がどの程度変化するかに関しては、国際データを用いた実証研究・計測が積み重ねられており、-0.09%から-1.36%までの間の値が報告されている。筆者が最近行った研究で得た計測値「-0.51%」を単純に当てはめると、高齢化の効果のみで家計貯蓄率は2020年にマイナスに転じる試算結果となる(注)。ただし、他の条件を不変にしてである。
この老年従属人口比率が1%上昇した場合に家計貯蓄率がどの程度変化するかに関しては、国際データを用いた実証研究・計測が積み重ねられており、-0.09%から-1.36%までの間の値が報告されている。筆者が最近行った研究で得た計測値「-0.51%」を単純に当てはめると、高齢化の効果のみで家計貯蓄率は2020年にマイナスに転じる試算結果となる(注)。ただし、他の条件を不変にしてである。
(注) 詳細は石川達哉・矢嶋康次(2002)「家計の貯蓄行動と金融資産および実物資産」(当研究所『所報』Vol.21)を参照されたい。
3.家計貯蓄率の低下は好ましいことか、それとも、好ましくないことか?
過去30年間を顧みると、日本全体の貯蓄投資バランス、すなわち、経常収支の基調的黒字を支えてきたのは家計部門の貯蓄といっても過言ではない。家計貯蓄率が低下すれば、経常収支とその背後にある資本収支、さらには国際的な資金フローや実質為替レート、実質金利が変化する可能性が高い。その意味で、日本の家計貯蓄率の行方に対する国際的な注目度も高い。
しかし、誤解してはならないのは、家計貯蓄率は、「水準が高ければ良い、低ければ好ましくない」とか、逆に、「水準が高いのは好ましくないが、低いのは良い」という言い方が当てはまる性質のものではないことである。家計貯蓄率が低い状況、すなわち、現在の消費が重視される社会構造であれば、肝心なのは、それによって現在の生活が充実しているかどうか、また、十分なストックがすでに蓄積されているかどうかである。家計貯蓄率が高い状況、すなわち、将来への備えが重視される社会構造であれば、貯蓄が有効に投資されて、果実をもたらし将来の消費と生活の向上に役立てられるかどうかが問われなければならない。かりに、高齢化の進行によって将来の家計貯蓄率がマイナスになって、経常収支が赤字化したとしても、その時までに貯蓄を通じて積み立てられた資産によって充実した国民生活を送れる状況であれば、問題はないはずである。
貯蓄率の水準が高くても低くても、重要なのは、生活水準の向上に家計貯蓄が有効に使われているか、あるいは、有効に使えるような蓄積のされ方がなされているどうか、に尽きるであろう。
しかし、誤解してはならないのは、家計貯蓄率は、「水準が高ければ良い、低ければ好ましくない」とか、逆に、「水準が高いのは好ましくないが、低いのは良い」という言い方が当てはまる性質のものではないことである。家計貯蓄率が低い状況、すなわち、現在の消費が重視される社会構造であれば、肝心なのは、それによって現在の生活が充実しているかどうか、また、十分なストックがすでに蓄積されているかどうかである。家計貯蓄率が高い状況、すなわち、将来への備えが重視される社会構造であれば、貯蓄が有効に投資されて、果実をもたらし将来の消費と生活の向上に役立てられるかどうかが問われなければならない。かりに、高齢化の進行によって将来の家計貯蓄率がマイナスになって、経常収支が赤字化したとしても、その時までに貯蓄を通じて積み立てられた資産によって充実した国民生活を送れる状況であれば、問題はないはずである。
貯蓄率の水準が高くても低くても、重要なのは、生活水準の向上に家計貯蓄が有効に使われているか、あるいは、有効に使えるような蓄積のされ方がなされているどうか、に尽きるであろう。
(2002年02月18日「エコノミストの眼」)
このレポートの関連カテゴリ
石川 達哉
石川 達哉のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2018/12/28 | 同床異夢の臨時財政対策債-償還費を本当に負担するのは国か、地方か? | 石川 達哉 | 研究員の眼 |
| 2018/07/13 | 「地方財源不足額」は本当に解消されているのか?―先送りされ続ける臨時財政対策債の償還財源確保 | 石川 達哉 | 基礎研レポート |
| 2017/08/31 | 再び問われる交付税特会の行方-地方財政の健全性は高まったのか? | 石川 達哉 | 基礎研レポート |
| 2017/07/03 | 増大する地方公共団体の基金残高 その2-実は拡大している積立不足!? | 石川 達哉 | 研究員の眼 |
新着記事
-
2025年10月24日
企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -
2025年10月24日
消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -
2025年10月24日
保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -
2025年10月23日
御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1) -
2025年10月23日
EIOPAがソルベンシーIIのレビューに関する技術基準とガイドラインのセットの新たな協議を開始等
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【高齢化が家計貯蓄率に与える影響】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
高齢化が家計貯蓄率に与える影響のレポート Topへ


















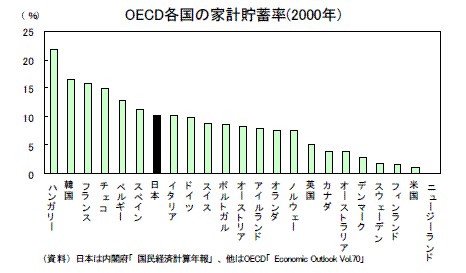
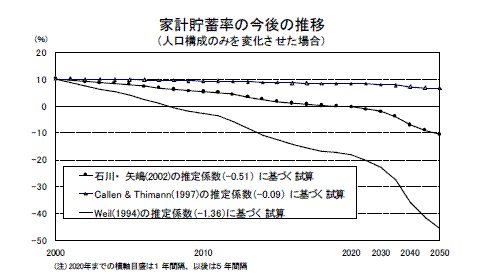

 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




