- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 経済 >
- 家計の貯蓄・消費・資産 >
- 前年度比で初めて減少した家計金融資産残高
コラム
2001年08月20日
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
1.減少に転じた2000年度の家計金融資産残高
2.土地取得の増加で縮小する家計の資金余剰
家計部門の資金余剰額とは、フローの貯蓄額から住宅や土地など実物資産の取得額を控除した収支尻に相当する。フローの貯蓄額は、可処分所得のうち消費に当てられなかった残余である。2000年度の資金余剰幅の大幅縮小に関して、直接の内訳を示す統計数値はまだ公表されていないが、要因的には、貯蓄が減少したか、実物資産への投資が増大したかのいずれかである。
所得・消費ともに伸び悩んでいる状況から判断すると、貯蓄側が大きく変動したとは考えにくい。つまり、実物資産への投資の増大が原因ということになる。しかし、住宅投資も好調とは言い難いから、土地の取得増大に原因を求めることができる。
実は、近年の土地取引に関しては、家計部門だけでなく、企業部門も含めて、大きな構造変化が生じている。
まず、過去50年間の農地・住宅地・商業地の面積の推移を見ると、農地が減り、住宅地・商業地が増えるという状況が続いている。農家が供給した土地をサラリーマン世帯や企業が取得するいうのがこれまでの基本的な構図である。部門別に見ると、商業地として土地を利用する企業は、永らく取得超過部門であった。農家とサラリーマン等の世帯を合わせた家計部門全体に関しては、土地の取得額より売却額の方が多かった。
所得・消費ともに伸び悩んでいる状況から判断すると、貯蓄側が大きく変動したとは考えにくい。つまり、実物資産への投資の増大が原因ということになる。しかし、住宅投資も好調とは言い難いから、土地の取得増大に原因を求めることができる。
実は、近年の土地取引に関しては、家計部門だけでなく、企業部門も含めて、大きな構造変化が生じている。
まず、過去50年間の農地・住宅地・商業地の面積の推移を見ると、農地が減り、住宅地・商業地が増えるという状況が続いている。農家が供給した土地をサラリーマン世帯や企業が取得するいうのがこれまでの基本的な構図である。部門別に見ると、商業地として土地を利用する企業は、永らく取得超過部門であった。農家とサラリーマン等の世帯を合わせた家計部門全体に関しては、土地の取得額より売却額の方が多かった。
しかし、90年代になって企業がリストラを進める中で土地の取得額を縮小し、遂には差し引きで土地の売却側に回ってしまったのである。一方、家計部門は99 暦年には取得超過部門に転じている。企業が売却した分は最終的にはサラリーマン世帯などの住宅地として購入されたことになる。住宅投資は横這いだから、土地を持っていない世帯の住宅・家屋と土地の取得が増え、土地を持っている世帯の住宅投資は減ったとものと考えられる。地価の下落によって住宅・家屋に対する土地の相対価格が下がり、家屋の取得に比べて土地の取得が相対的に進んだと言うこともできる。
土地の固定資産税に関する税務統計を見ると、個人納税者数が増加を続けるなかで、法人納税者数は2000年に減少に転じている。したがって、土地取引でも家計部門の購入超過が続いていると推測される。そして、それが家計部門の資金余剰を減らす要因として働いているはずである。
このように、家計部門の金融資産残高減少の背後には、実物資産取得の増加があり、企業部門を含めた土地取引の構造変化があることを見落としてはならないだろう。
土地の固定資産税に関する税務統計を見ると、個人納税者数が増加を続けるなかで、法人納税者数は2000年に減少に転じている。したがって、土地取引でも家計部門の購入超過が続いていると推測される。そして、それが家計部門の資金余剰を減らす要因として働いているはずである。
このように、家計部門の金融資産残高減少の背後には、実物資産取得の増加があり、企業部門を含めた土地取引の構造変化があることを見落としてはならないだろう。
(2001年08月20日「エコノミストの眼」)
このレポートの関連カテゴリ
石川 達哉
石川 達哉のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2018/12/28 | 同床異夢の臨時財政対策債-償還費を本当に負担するのは国か、地方か? | 石川 達哉 | 研究員の眼 |
| 2018/07/13 | 「地方財源不足額」は本当に解消されているのか?―先送りされ続ける臨時財政対策債の償還財源確保 | 石川 達哉 | 基礎研レポート |
| 2017/08/31 | 再び問われる交付税特会の行方-地方財政の健全性は高まったのか? | 石川 達哉 | 基礎研レポート |
| 2017/07/03 | 増大する地方公共団体の基金残高 その2-実は拡大している積立不足!? | 石川 達哉 | 研究員の眼 |
新着記事
-
2025年10月24日
米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -
2025年10月24日
企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -
2025年10月24日
消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -
2025年10月24日
保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -
2025年10月23日
御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【前年度比で初めて減少した家計金融資産残高】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
前年度比で初めて減少した家計金融資産残高のレポート Topへ


















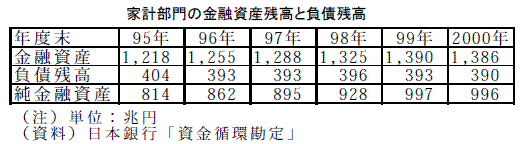
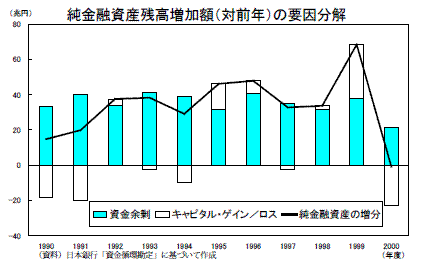
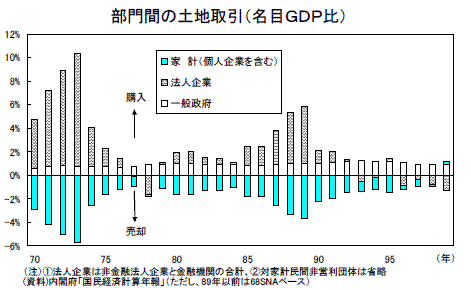

 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




