- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 経済 >
- 財政・税制 >
- 課税前後の所得不平等に想う
コラム
2003年10月06日
| 1.「見せかけの所得格差」に要注意 世の中も自分の暮らし向きもよい方向に進んでいると感じるとき、人が社会に対して抱く不満や不安の度合いは大きなものにはならないであろう。残念ながら、各種の世論調査の結果を見ると、現状はちょうどその正反対の状況にあると言わねばならない。社会全体の「パイ」が大きくなることが期待できないとき、関心は自ずとその分け方に向かうであろう。不満とは言わないまでも、分配のプロセスが公正なものか、結果としての分け前にそれなりの公平性が確保されているかという意味で、所得や賃金の不平等に対する人々の関心はきわめて高い。 もっとも、本当に所得格差が拡大しているのかどうかという事実認定には慎重な判断が求められる。たとえ、集計されたデータにおける所得格差が過去と比べて拡大している事実があったとしても、賃金には強い年功性が存在するため、年齢階層間の格差拡大によるものなのか、同一年齢階層内の格差拡大によるものなのか、いずれも拡大せずに単に各年齢階層の構成比が変化したことによるものかは、それだけでは定かではないからである。ひとつの時代には、異なったライフステージに位置する、異なった世代の家計が共存しているため、世帯総数における年齢構成変化によって、「見せかけの所得格差」が拡大しているように見える部分が存在することには注意しなければならない。 下図は、世帯人員が2人以上の勤労者世帯を年収の最も低い世帯から最も高い世帯を順番に並べて10のグループに区分した「十分位階級」毎の構成数について、世帯主の年齢階層別に内訳を見たものである。 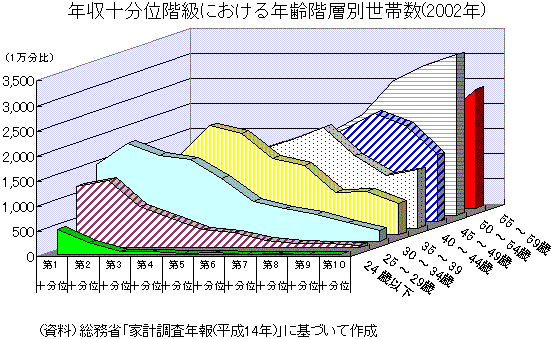 24歳以下の世帯に関しては、親と同居していて世帯主にはなっていない人や独立した世帯を形成していても単身である人が多いため、世帯数自体も少ないが、8割以上の世帯は年収水準が最も低い第1十分位か、第2十分位に属している。これに対して、平均賃金が全年齢階層の中で最も高い50~54歳の世帯については、その半数が第8十分位かそれ以上の階級に属している。逆から見ると、年収水準が最も高い第10十分位の世帯の1/3は50~54歳の階層によって占められている。 極論すれば、すべての年齢階層を対象にした所得階層別データでは、20歳代と30代前半の世帯が「低所得層」に分類され、50歳代が「高所得層」に分類されてしまう。同一年齢階層内、同一世代内の格差は確実に存在するが、それ以上に年齢階層間の水準の違いが目立ってしまうのである。年功的な賃金体系、年齢階層間の相対的な関係は過去数十年にわたって安定しており、上の年齢階層に移ることによって平均的な賃金水準が上がることは、これまでのところ、多くの人が経験してきたことであろう。その年齢階層間の相対関係が変わりつつあるのか、同一年齢階層内での格差が拡大しているかどうかは、各年齢階層毎のデータを見なければならない。つまり、すべての年齢階層が混在した所得階層別データを見ても、実際のところは若年層と中高年層の比較に終わってしまう可能性が高いのである。 世帯内の働き手の数に関しても、同様のことが当てはまる。有業人員が多ければ、結果としてその世帯の所得水準が高くなるのは当然である。実際、十分位で見た最高所得層の大半は有業人員2人の世帯によって占められている。もっとも、主たる稼ぎ手である世帯主の賃金水準が低いから、それを補うべく配偶者が働いているという場合もあるかもしれない。夫婦のどちらか一方が働いている年収600万円の世帯と夫婦2人で働いている年収700万円の世帯とでは、家事や余暇に割ける時間が異なるのに、所得のみで同列に比較をすることは意味が乏しいであろう。 2.それでも拡大している「真の所得格差」 真の所得格差を論ずるには、年齢階層、有業者数、所得階層という3次元の区分を持つデータを利用することが理想である。そのような理想的なデータは一般には公表されていないが、これに準ずるものが「標準世帯」、すなわち、有業人員1人、夫婦とこどもからなる4人家族の所得階層別データである。標準世帯の世帯主は「35~44歳」が過半を占めているため、年齢的な要素による「見せかけの所得格差」の影響が小さいからである。 もちろん、こうしたデータを見れば、所得格差が存在することが確認できる。問題は、5年前や10年前などの過去と比べて、格差が拡大しているかどうかである。家計が最終的に自由に使えるのは課税後の所得であるから、税制の介在によって所得不平等がどの程度緩和されているかという視点も重要である。人々が抱く不公平感は実態に見合ったものなのであろうか、それとも、錯覚に過ぎないのであろうか。これらの判定は、所得不平等度を示す客観的指標に基づいてなされるべきである。 下表は、各階層の所得水準とその世帯数に基づいて計測されるタイル尺度という客観指標を用いて、2002年、1997年、1992年における標準世帯の所得不平等度を課税前後で比較した結果である。課税前で見ても(表の(A)の時系列比較)、課税後で見ても((B)の時系列比較)、2002年における所得不平等度は5年前や10年前と比べて拡大している。もちろん、課税前後を比較すれば(同一年における(A)と(B)の比較)、累進所得税の効果で所得格差は縮小している。 しかし、累進税制が持つ所得再分配効果、格差縮小効果に関しては、所得不平等度が税制の介在によってどの程度緩和されているかという観点から評価されなければならないであろう。課税前後での不平等度の変化率を過去と比較すると(表の(C)の時系列比較)、その変化率、すなわち格差縮小効果は過去と比べて弱まっている。 課税後の所得不平等が拡大しているのは、課税前の所得格差が拡大しているうえ、税制の所得再分配効果も低下しているためであると言えるであろう。その両方の意味において、多くの人が感じている不公平感は決して根拠の乏しいものではないのである。 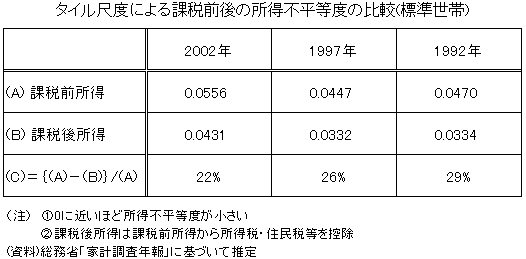 3.今後の税制・社会保障制度の改革に望まれること 人々の不公平感や閉塞感を解消するには、社会全体のパイそのものを大きくすること、そして、パイを公正に分けたうえで、結果としての分け前の格差が大きくなり過ぎないように、ある程度の再分配や保障を行うことのいずれもが必要であろう。 もちろん、これらをすべて満たすことは容易ではない。社会全体の成長率を高めるには、社会の構成員の能力や資源を出来る限り上手に活用することが不可欠である。パイの増大への貢献度に応じて分配が行われるということは、同一世代内で賃金格差が生じることを意味する。貢献したこと、成果をあげたことは正当に報いられなければならない。これに対して過度の再分配を行えば、貢献した人の意欲はそがれてしまう。 他方、誰しもが、常に貢献できるとは限らない。ほんのひと握りの人しか果実を享受できないとしたら、あるいは、偶発的な不運や個人の努力を超えた領域に属することが原因で十分な貢献ができなかった場合に、完全に蚊帳の外に置かれてしまうのであれば、安心して働く意欲も、チャレンジする積極性も湧いてこないかもしれない。また、そのような分配の仕方は社会的な公正・公平感には見合わないであろう。 政策論的に言えば、これらは資源配分における効率性と分配における公平性の問題に帰着する。その両方に重大な影響を及ぼすのが税制と社会保障制度である。税・社会保険料の負担と社会保障給付の問題は、家計の余暇と労働供給の選択、消費と貯蓄の選択と不可分であることを思い起こせばよい。前述の通り、効率性と公平性を両立することは一般的には困難だと考えられるが、現在の社会には効率性を犠牲にすることなく公平性を改善する余地、もしくは、公平性を犠牲にすることなく効率性を改善する余地が残されているはずである。あるいは、人々に不公平感や閉塞感を抱かせないように適正な所得再分配を行うことこそが効率性の改善につながる可能性もあるかもしれない。今後の税制改革ならびに社会保障制度改革に際しては、そうした点を含めて十分な検討が行われることを望みたい。 |
(2003年10月06日「エコノミストの眼」)
石川 達哉
石川 達哉のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2018/12/28 | 同床異夢の臨時財政対策債-償還費を本当に負担するのは国か、地方か? | 石川 達哉 | 研究員の眼 |
| 2018/07/13 | 「地方財源不足額」は本当に解消されているのか?―先送りされ続ける臨時財政対策債の償還財源確保 | 石川 達哉 | 基礎研レポート |
| 2017/08/31 | 再び問われる交付税特会の行方-地方財政の健全性は高まったのか? | 石川 達哉 | 基礎研レポート |
| 2017/07/03 | 増大する地方公共団体の基金残高 その2-実は拡大している積立不足!? | 石川 達哉 | 研究員の眼 |
新着記事
-
2025年10月16日
EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- -
2025年10月16日
再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ -
2025年10月15日
インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -
2025年10月15日
「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -
2025年10月15日
IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【課税前後の所得不平等に想う】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
課税前後の所得不平等に想うのレポート Topへ



















 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




