- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 経済 >
- 財政・税制 >
- 国民負担のあり方に求められる視点
コラム
2004年03月22日
| 1.増加する社会保障負担 経済財政諮問会議では、将来における潜在的な国民負担率(税+社会保障+財政赤字)を50%以内に抑制する、という目標を打ち出している。しかし、その一方では、少子高齢化や財政赤字の問題が深刻化するなかで、国民負担の増加を危惧する声も依然として大きい。 特に社会保障に対する負担については、年々増加する傾向が続いている。昨年末に議論された年金改革においても、保険料率がどこまで引き上げられるかに注目が集まり、最終的に年収の18.30%にまで保険料率を引き上げ、2017年度以降はそれを上限として料率が固定されるという形で決着している。 しかし社会保障負担の増加傾向は、年金だけによるものではない。今後は医療・介護・雇用など、年金以外の各社会保険料の引き上げも予定されており、医療や介護などを含めた社会保障の負担水準は、将来的にどこまで上昇するのか、引き続き懸念されるところである。 2.注目される社会保障の一体化改革 このなかで、負担の増加を抑制するための方策として注目されているのが、年金・医療・介護などの各社会保障制度を一体と捉え、横断的な改革を実施し、将来的な負担水準についても社会保障制度全体として考えいくという試みである。 従来、医療・年金等の各社会保障制度は、個別に制度改正や保険料引き上げが実施されてきた。しかし、その結果、近年では毎年何らかの社会保障制度改正が実施され、年々社会保障負担が増加するという状況が生じている。 さらに負担水準についても、厚生年金では上限が定められたが、それは医療や介護など、他の社会保障制度の水準との関係を考慮して決定されたものではない。社会保障制度全体での将来的な負担率が、どの程度の水準になるかについては依然として不透明なままである。そのため、それぞれの制度を一体として捉え、制度全体における負担の上限を設定するという発想は、社会保障負担を抑制するためには不可欠なものと言えるだろう。 3. 社会保障負担と税負担を一体として考える視点 ひるがえって、国民負担率を抑制するという観点から考えると、社会保障制度のみを一体として改革するだけでは十分とは言えまい。国民の負担には、言うまでもなく社会保障の他に税による負担もある。最近では定率減税の見直しや、消費税率の引き上げについても議論が活発化しており、ゆくゆくは国民の税負担増を伴う大規模な増税が実施される機運も高まりつつある。また、今後予定されている増税の一部が、社会保障給付の財源に充てられる可能性が高いことも注目すべき点である。 今回の年金改革では、年金保険料の水準を抑えるために、基礎年金の国庫負担割合が引き上げられることになったが、そのための財源は国民への増税という形で賄われることになる。これは保険料を抑制する代わりに、増税が実施されることとなり、いずれにしろ国民の負担が増加することに変わりはないものである。現在の社会保障制度は、保険料負担だけでなく税負担による影響も受けており、両者は完全に切り離して考えられるものではないだろう。 社会保障制度を一体として考えた結果、たとえ社会保障負担を抑制することに成功しても、その分、税負担が増加してしまえば、税と社会保障を合計した国民負担の抑制には繋がらない。国民負担の抑制に向けて、今後求められることは、社会保障負担と税負担を別個のものとして考えるのではなく、両者間の影響についても考慮し、国民が耐えられる全体の負担水準のなかで社会保障給付を実施していく、という視点ではないだろうか。 4. 政治の役割発揮が不可欠 そのためには、当然のことながら、税制と社会保障制度のあり方を一体として考えていく必要があり、省庁間の垣根を越えた連携が欠かせない。しかし、しばしば指摘されていることであるが、わが国では省庁間はもちろん、省内の各部局間においても縦割りで政策が立案されているのが実情である。ましてや、各省庁が一体となった改革となると、実現に向けたハードルは非常に高いと言わざるを得ない。しかも、負担と給付水準の関係について、広く国民各層のコンセンサスを得ていく最も困難で重要な作業も欠かせないのである。 それぞれの省庁、および官僚はあくまで各分野の専門家である。むしろ、これらの組織を超えた調整を行うことは、国民負担に係るコンセンサス形成とともに、すぐれて政治の役割であろう。まずは横断的な改革を可能とするための、政治のリーダーシップに期待したいところだ。 |
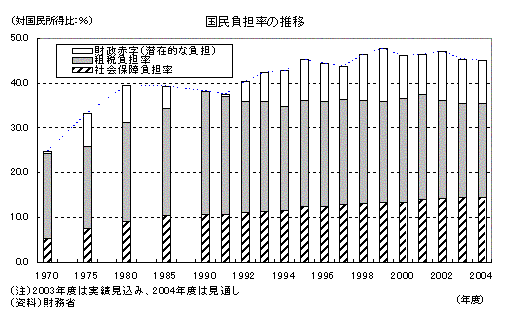 |
(2004年03月22日「エコノミストの眼」)
篠原 哲
篠原 哲のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2008/06/20 | 景気はピークを超えたか?~一致CIの要因分解 | 篠原 哲 | Weekly エコノミスト・レター |
| 2008/06/19 | 経済財政諮問会議(6月17日)~骨太素案、歳出抑制路線の継続を確認 | 篠原 哲 | 経済・金融フラッシュ |
| 2008/06/10 | 企業の保険料負担は誰のものか? | 篠原 哲 | 研究員の眼 |
| 2008/06/03 | 07年度一般会計税収実績:08年4月~07年度も暗雲漂う補正後予算の達成 | 篠原 哲 | 経済・金融フラッシュ |
新着記事
-
2025年10月29日
生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -
2025年10月29日
地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -
2025年10月28日
試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -
2025年10月28日
地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -
2025年10月28日
東宝の自己株式取得-公開買付による取得
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【国民負担のあり方に求められる視点】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
国民負担のあり方に求められる視点のレポート Topへ



















 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




