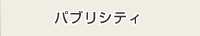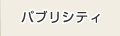- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- パブリシティ >
- 書籍出版
書籍出版
-

カーボン・ディスクロージャー ――企業の気候変動情報の開示動向
- 著者:
- 宝印刷株式会社総合ディスクロージャー研究所(監修) 村井秀樹/川村雅彦/鶴田佳史(編著)
- 出版社:
- 税務経理協会
- 発行年月:
- 2011年7月
- 定価:
- ¥2,835
- 研究員:
- 川村 雅彦
※当研究所川村雅彦が、第10章「気候変動にかかわるリスク・チャンス情報の両面開示」,終章「持続可能な社会の実現に向けて」を執筆。
今後一層高まることが予想されるステークホルダーからの気候変動情報の開示要求に対し,とるべき企業の対応を実例をもとに検証。学問領域と実務領域が融合した実務家必読書。
-

東日本大震災 復興への提言――持続可能な経済社会の構築
- 著者:
- 伊藤 滋・奥野 正寛・大西 隆・花崎 正晴(編)
- 出版社:
- 東京大学出版会
- 発行年月:
- 2011年7月
- 定価:
- ¥1,890
- 研究員:
-
矢嶋 康次
総合政策研究部
※当研究所矢嶋康次が、第II部「日本経済の課題――〔復興資金〕Sudden StopではなくGoing Concernを―今こそ、名目GDP連動国債を発行するとき」を一部執筆。
東日本大震災は,日本の経済社会が極めて脆弱な基盤のうえに成り立っていたことを白日のもとにさらした.価値観の根幹が揺らぐほどの衝撃のなか,われわれは何をなすべきなのか.経済学,都市論,産業論などの分野より,第一線の学識者50名がおくる,震災からの復興に向けた提言集。
-
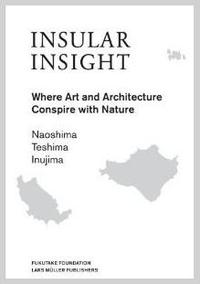
INSULAR INSIGHT――Where Arts and Architecture Conspire with Nature/島からの洞察――美術と建築が自然と共謀する場所
- 著者:
- Lars Müller and Akiko Miki(共編)
- 出版社:
- Lars Müller Publishers
- 発行年月:
- 2011年7月
- 定価:
- ¥5,434
- 研究員:
- 吉本 光宏
※当研究所、吉本光宏が“ISLANDS ENLIVENED BY ART: SEEKING AN UNKNOWN FUTURE COMMUNITY FROM THE PAST(アートの生命力が宿る島々:まだ見たこともない未来の故郷を求めて)”を執筆。
瀬戸内海の直島、豊島、犬島は、静寂と美の島々となった。そこでは20年以上にわたり、文化と自然の本質的な融合が行われ、世界中の首都の狂ったような生活に対するアンティテーゼが生み出されている。繊細なディテールから壮大なパノラマに至る写真、そして、世界的に著名な執筆者の洞察に満ちた小論は、このプロジェクトの創始者、福武總一郎のユニークな哲学を紹介している。現代美術と島々の自然環境が溶け合いながら変遷する姿を深くとらえた写真は興味深く、国際的に著名なアーティストの作品、そして安藤忠雄、妹島和世、西沢立衛などの建築が鮮やかに描かれる。
他の執筆者は、ペーター・スローターダイク、ナヤン・チャンダ、ジャン-ユベール・マルタン、イヴ・ブラウ、吉見俊哉。 -

日本経済が何をやってもダメな本当の理由
- 著者:
- 櫨(はじ) 浩一(著)
- 出版社:
- 日本経済新聞出版社
- 発行年月:
- 2011年6月
- 定価:
- ¥1,995
- 研究員:
- 櫨(はじ) 浩一
※当研究所、櫨(はじ)浩一が執筆。
はるか昔に先進工業国になったのに、貧しかった時代の生産優先の発想から脱却できない日本。供給力ではなく消費の不足こそが長期低迷の原因だ! 日本経済の呪縛を糾し、真の豊かさ実現への道を示す。
この20年余、日本経済が何をやっても浮上できないのは、そもそも我々の考え方が間違っているからではないのか――。日本経済をめぐる様々な議論の誤りを明快に指摘する、目から鱗の日本経済論です! -
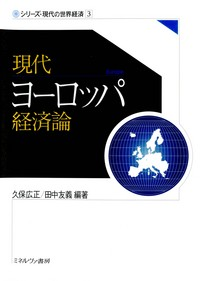
シリーズ・現代の世界経済3 現代ヨーロッパ経済論
- 著者:
- 久保 広正/田中 友義(編著)
- 出版社:
- ミネルヴァ書房
- 発行年月:
- 2011年4月
- 定価:
- ¥3,360
- 研究員:
-
伊藤 さゆり
経済研究部
※当研究所、伊藤さゆりが第II部第6章『 EUの雇用戦略 』を執筆。
世界に大きな影響を与えるヨーロッパ経済の中で、拡大と深化を続けるEU。世界経済の動向をつかむためには、ヨーロッパ経済の歩みと将来を学ばなければならない。
本書は、地域統合までのプロセス、通貨統合、社会保障と雇用問題、環境政策、中・東諸国やアジアとの関係など、激変するEUの最新経済動向を多くの側面から解説し、あわせてヨーロッパ経済の先行きや直面する課題とその処方箋を分析する。リーマン・ショックによる世界金融危機やギリシャ財政危機を乗り越え、確かな統合へと向かう道を探る入門書。 -
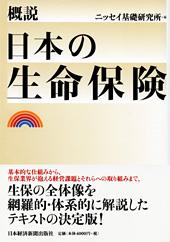
概説 日本の生命保険
- 著者:
- ニッセイ基礎研究所(編)
- 出版社:
- 日本経済新聞出版社
- 発行年月:
- 2011年4月
- 定価:
- ¥4,200
- 研究員:
- 松岡 博司
※当研究所、松岡博司が執筆。
規制緩和・自由化の進展、グローバル競争の激化、少子高齢化による契約数の減少――。大きな環境変化にさらされる生命保険の、基本的な仕組みから社会的な機能・役割、今後の業界動向まで解説する本格的テキスト。
専門用語を極力避けた平易な記述と豊富な表やグラフで初学者にも最適な一冊です。 -
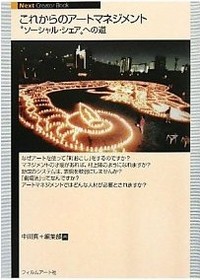
これからのアートマネジメント-“ソーシャル・シェア”への道
- 著者:
- 中川 真/フィルムアート社編集部(編)
- 出版社:
- フィルムアート社
- 発行年月:
- 2011年4月
- 定価:
- ¥1,785
- 研究員:
※当研究所、大澤寅雄が「アートマネジメントの思想」「アートマネジメントへの質問」を一部執筆。
ますます求められるアートマネジメントの仕事は多種多様。企業、学校、福祉、街の中のいたる場所で行なわれるアーツは、既存の考え方やシステムを打ち崩し、人と人、人と社会の新しい関係を創造します。
本書は、社会におけるアートの存在について、ダイナミックに捉えなおしながら、ダンス、美術、音楽、演劇など多様なジャンルの第一線で活躍中の著者たちが、アートマネジメントにおける大切な考え方や実践論を語ります。 -
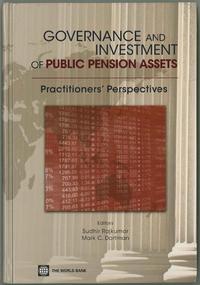
Governance and Investment of Public Pension Assets - A Practitioners' Perspectives
- 著者:
- Sudhir Rajkumar/Mark C. Dorfman(編)
- 出版社:
- THE WORLD BANK
- 発行年月:
- 2010年11月
- 定価:
- ¥3,395
- 研究員:
- 臼杵 政治
※当研究所、臼杵政治が"Lessons from Defined-Benefit Pension Funds in Japan","Making Investment Policy Consistent with Overall Pension Plan Design : Japan's GPIF"を執筆。
-
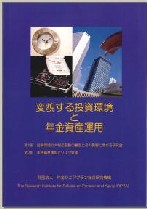
変貌する投資環境と年金資産運用
- 著者:
- 財団法人年金シニアプラン総合研究機構(編)
- 出版社:
- 財団法人年金シニアプラン総合研究機構
- 発行年月:
- 2010年7月
- 定価:
- ¥2,310
- 研究員:
- 櫨(はじ) 浩一
※当研究所、櫨(はじ)浩一が第1部第1章『世界的金融危機と今後の投資環境』を執筆。
投資環境の激変に対して、わが国を代表する各分野の専門家の様々な角度からの分析と示唆に富む意見等を取りまとめた【第1部 投資環境の大幅な変動の要因とその影響に関する研究会】と、財団法人年金シニアプラン総合研究機構の研究を基礎に、年金資産運用における考え方を体系的な解説書として編集した【第2部 年金資産運用とリスク管理】からなる年金資産運用の実践書。
-

創造性が都市を変える-クリエイティブシティ横浜からの発信-
- 著者:
- 横浜市/鈴木 伸治(編著)
- 出版社:
- 学芸出版社
- 発行年月:
- 2010年3月
- 定価:
- ¥2,100
- 研究員:
- 吉本 光宏
※当研究所、吉本光宏が第2章-01「アートを起点とした地域のイノベーションに向けて-創造界隈、そしてアートイニシアティブの意味するもの」を執筆。
グローバル経済に呑み込まれず、我が都市らしさを起点に、市民一人一人の創造性を高め、成長一辺倒とは異なる真の豊かさをいかに創ってゆくのか。ピーター・ホール、ジャン・ルイ・ボナン、福原義春、吉本光宏、篠田新潟市長、林横浜市長ら、世界の論客とリーダーが、芸術、産業、まちづくりの視点から創造都市を熱く語る。
研究員の紹介
-

井出 真吾
急上昇した日本株に潜む落とし穴~コロナ禍の成功体験は再現するか~
【株式市場・株式投資・マクロ経済・資産形成】 -

斎藤 太郎
雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化
【日本経済】 -

天野 馨南子
【少子化対策データ考】コロナ時の若年移動抑制で大阪府が非少子化1位へ
【人口動態に関する諸問題】 -

-

-

伊藤 さゆり
ドル離れとユーロ-地位向上を阻む内圧と外圧-
【欧州の政策、国際経済・金融】
コンテンツ紹介
-
レポート
-
受託実績・コンサルティング
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る