- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 対価の柔軟化を利用した中小企業M&Aの活性化への期待
コラム
2007年09月03日
1.増加する中小企業のM&A
新聞紙上を賑わすM&A案件は大企業間のものが中心であり、M&Aは大企業の問題と考える方も多いかと思われるが、現実には中小企業のM&Aは非常に多くかつ着実に増加している。例えば、レコフの調査によると未上場企業(≒中小企業)のM&Aは全体の7割を超え、過去5年間で約70%増加している(図表1)。しかも、レコフの調査は新聞や雑誌等の公表データをもとに収集されているため、小規模な案件は調査にカバーされていない。中小企業のM&Aの実態は図表1が示す以上に多いと推測される。
中小企業のM&Aが増加しているのは、いくつかの理由がある。第1は中小企業の経営者の高齢化である。多くの中小企業は後継者が見つからない「後継者問題」に直面している。これまでは、子供に後を継がせることで事業の承継が図られてきたが、最近では子供に跡を継がせない、あるいは子供が跡を継がないケースが増えているためである。前者は、経営環境が厳しさを増す中で、子供の経営手腕を危惧する経営者が増加しているためであり、後者は、経営者の厳しい労働環境を見て、生活の安定している勤労者の途を子供が選択するという理由によるものと考えられる。子供以外への承継としては、有能な従業員への承継も考えられるが、従業員には事業を買い取るための資金が不足するという問題があり実際のケースは少ない。この後継者問題を解決する方法としてM&Aが注目され、実際に活用されている。
第2は買い手側の問題である。M&Aが頻発するなかで、経営者にとってM&Aが特殊な経営手段ではなく、一般的な経営手段として認知されるようになったことである。この変化によって、中小企業間のM&Aのみならず、有用な経営資源を有する中小企業を大企業がM&Aによって取得することも珍しくなくなった。
第3は、中小企業M&Aが増加するなかで、その仲介ビジネスに金融機関などが注力し始めたことである。これまでは売り手と買い手の情報をマッチングさせることが難しかったが、仲介ビジネスの成長はその壁を取り払った。
第4点として、政府が中小企業の事業の承継に注力し始めていることが挙げられる。中小企業のM&Aを活発化させるために低利融資を設けるほか、M&Aに関するコンサルティング活動を積極化している。
中小企業のM&Aが増加しているのは、いくつかの理由がある。第1は中小企業の経営者の高齢化である。多くの中小企業は後継者が見つからない「後継者問題」に直面している。これまでは、子供に後を継がせることで事業の承継が図られてきたが、最近では子供に跡を継がせない、あるいは子供が跡を継がないケースが増えているためである。前者は、経営環境が厳しさを増す中で、子供の経営手腕を危惧する経営者が増加しているためであり、後者は、経営者の厳しい労働環境を見て、生活の安定している勤労者の途を子供が選択するという理由によるものと考えられる。子供以外への承継としては、有能な従業員への承継も考えられるが、従業員には事業を買い取るための資金が不足するという問題があり実際のケースは少ない。この後継者問題を解決する方法としてM&Aが注目され、実際に活用されている。
第2は買い手側の問題である。M&Aが頻発するなかで、経営者にとってM&Aが特殊な経営手段ではなく、一般的な経営手段として認知されるようになったことである。この変化によって、中小企業間のM&Aのみならず、有用な経営資源を有する中小企業を大企業がM&Aによって取得することも珍しくなくなった。
第3は、中小企業M&Aが増加するなかで、その仲介ビジネスに金融機関などが注力し始めたことである。これまでは売り手と買い手の情報をマッチングさせることが難しかったが、仲介ビジネスの成長はその壁を取り払った。
第4点として、政府が中小企業の事業の承継に注力し始めていることが挙げられる。中小企業のM&Aを活発化させるために低利融資を設けるほか、M&Aに関するコンサルティング活動を積極化している。
2.さらなる活性化が期待される中小企業M&A
事業承継を目的とする中小企業のM&Aの主たる目的は、会社の売却によって資金を回収することである。このため、これまでは現金が得られる株式譲渡あるいは事業譲渡が主に利用されてきた。合併、株式交換、会社分割といった方法は、売却の対価が買い手の会社の株式となるため、中小企業が買い手の場合、換金が難しい未上場株式を取得することになり処分に困るためである。
しかし、今年5月からのM&Aの対価の柔軟化によって、株式に代えて現金などの支払いが認められることになった。これにより中小企業のM&Aの形態の多様化が可能となった。現金による合併はもちろん、上場親会社の株式を用いた中小企業間の三角合併も可能となった。また、会社の一部を現金の対価によって分割することも可能となった。こうした、利用可能なM&A手法の増加は、中小企業にとってより大きな効果を持つと考えられる。先述のように中小企業のM&Aは増加しているが、M&Aの条件が折り合わず廃業に追い込まれたケースも少なくないと考えられるからである。多様化したM&A手法は、後継者不足に悩む中小企業の選択肢を広げ、円滑な事業承継を図っていくことを可能にすると考えられる。また、国民経済の視点から見ても、円滑な事業承継によって資産の有効活用が図られることは望ましいことと思われる。M&Aの対価の柔軟化を利用した、中小企業M&Aのさらなる活性化が期待されるところである。
しかし、今年5月からのM&Aの対価の柔軟化によって、株式に代えて現金などの支払いが認められることになった。これにより中小企業のM&Aの形態の多様化が可能となった。現金による合併はもちろん、上場親会社の株式を用いた中小企業間の三角合併も可能となった。また、会社の一部を現金の対価によって分割することも可能となった。こうした、利用可能なM&A手法の増加は、中小企業にとってより大きな効果を持つと考えられる。先述のように中小企業のM&Aは増加しているが、M&Aの条件が折り合わず廃業に追い込まれたケースも少なくないと考えられるからである。多様化したM&A手法は、後継者不足に悩む中小企業の選択肢を広げ、円滑な事業承継を図っていくことを可能にすると考えられる。また、国民経済の視点から見ても、円滑な事業承継によって資産の有効活用が図られることは望ましいことと思われる。M&Aの対価の柔軟化を利用した、中小企業M&Aのさらなる活性化が期待されるところである。
(2007年09月03日「エコノミストの眼」)
このレポートの関連カテゴリ
小本 恵照
小本 恵照のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2009/03/25 | 環境問題とCSRに取り組む日本企業 | 小本 恵照 | 基礎研マンスリー |
| 2009/02/25 | ニッセイ景況アンケート調査結果-2008年度下期調査 | 小本 恵照 | ニッセイ景況アンケート |
| 2009/01/26 | 中小小売業の現状と今後の経営のあり方 | 小本 恵照 | 基礎研マンスリー |
| 2008/12/02 | 中小小売業に求められる企業家精神 | 小本 恵照 | 研究員の眼 |
新着記事
-
2025年10月24日
米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -
2025年10月24日
企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -
2025年10月24日
消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -
2025年10月24日
保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -
2025年10月23日
御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【対価の柔軟化を利用した中小企業M&Aの活性化への期待】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
対価の柔軟化を利用した中小企業M&Aの活性化への期待のレポート Topへ


















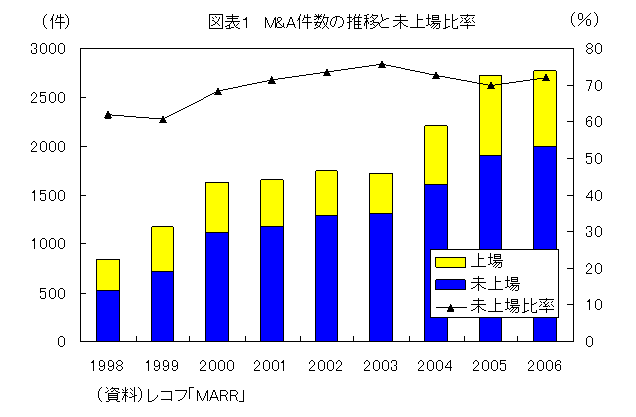

 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




