- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 経営・ビジネス >
- 企業経営・産業政策 >
- 純粋持株会社の課題とは何か
コラム
2004年05月24日
| 1.増加する「企業組織再編型」の純粋持株会社 純粋持株会社は、1947年以来独占禁止法によって永らく設立が禁止されてきたが、1997年の改正によって設立が可能となった。解禁から6年以上経過し、純粋持株会社へ組織を移行させる企業が徐々に増加しているが、その移行形態は大きく二つに大別される。 一つは従来の合併に代え、共同で純粋持株会社を設立し経営統合を行う「合併代替型」である。日本興業銀行、富士銀行、第一勧業銀行によるみずほフィナンシャルグループの設立や、川崎製鉄とNKKによるJFEホールディングスの設立などが代表的な例である。 もう一つは、純粋に既存の企業組織を変更させるもので、従来の事業部制やカンパニー制を分社化によって純粋持株会社に移行させる「企業組織再編型」である。前者の合併代替型は、1990年代後半からの大きな産業再編のうねりの中で、金融機関や素材型製造業を中心に、2000年代初頭にかけ多くの事例がみられたが、産業再編が一段落したこともあり、その利用はやや下火となってきている。 一方、後者の企業組織再編型は利用例が増加している。今年4月には、マルハ、メガチップ、フランスベッドなどが純粋持株会社に移行し、6月に丸石自転車、8月にグッドウィル・グループ、9月に梅の花、10月にコクヨとエイベックス、さらに来年4月には阪急電鉄が移行を決定するなど、純粋持株会社へ移行を表明する企業が相次いでいる。企業名を見る限り、業種や規模の大小にはあまり関係はなく純粋持株会社化が進んでいるようにみえる。では、増加している企業組織再編のための純粋持株会社化の目的と課題は何であろうか。
まず、合併代替型の純粋持株会社化の目的は明白である。他企業と一体化することによって規模の拡大を達成することが第一義としてあり、合併では組織結合の摩擦が大きいため、緩やかな統合が可能となる共同持株会社を利用しようというわけである。 一方、企業組織再編型の純粋持株会社化は、企業グループの組織運営の効率化を目指すものといえる。1990年代から2000年代初頭にかけ、各企業は子会社・関連会社を中心とする不採算事業の整理を進め、企業グループとしてのコア事業を次第に明確化してきた。こうして、輪郭の明確となったグループ経営の効率化に眼を向ける余裕が、それぞれの企業に出始めたことが関係していると考えられる。 ちなみに、純粋持株会社への移行企業および移行決定企業のプレスリリースからその目的を拾ってみると、
ここからは、純粋持株会社への移行によって、(1)迅速な意思決定をし、(2)責任・権限の明確化を図り、(3)個別事業の競争力の強化につなげようという、企業の意思がはっきりと読み取れる。 3.経営者が純粋持株会社という「器」を活かしきれるかが課題 実際に純粋持株会社化した企業の組織運営はどうなのであろうか。1999年という解禁から比較的早期に持株会社化したNTTをみると、グループ各社が同一事業で競合する場面がみられるなど、必ずしもグループとしての求心力が働いていないという評価が聞かれる。また、同時期に純粋持株会社に移行したソフトバンクは、ブロードバンド事業で厳しい業績が続いている。 一方で、2001年に純粋持株会社に移行した服飾のヤマノホールディング・コーポレーションは、持株会社の利点を利用して積極的なM&Aによる事業拡大を進め、業績も堅調に推移している。また、昨年7月に純粋持株会社に移行したサッポロホールディングスの岩間社長は、その効果を問われ、「分社化した各事業会社に自立しなければという意識が強烈に出てきた。」と述べ、移行による影響が出始めていることを示唆している。 こうした事例は、純粋持株会社という「器」を創ることが、直ちに業績の改善につながるわけではないことを示しているといえる。言い換えると、純粋持株会社という器に応じたマネジメントができないとその利点は発揮されないということである。先に述べたように、純粋持株会社は迅速な意思決定と責任・権限の明確化を主たる目的に設立されるが、そこでは、各事業会社の自立性を伸ばすと同時にグループとしての求心力を強めるという、微妙なバランスの達成が求められるのである。求心力を強めすぎると、各事業会社の社長は純粋持株会社の意向を窺い、独立した企業のトップとしてのリーダーシップが十分に発揮されなくなる恐れがある。いわば、実質的に従来の事業部制やカンパニー制と変わらない経営となってしまう。一方、自立性を伸ばすことに注力しすぎると、各事業会社間で事業の重複が生じるといった、グループとしての一貫性に欠けた事業展開が進められ、無秩序な分社化に陥ってしまうリスクが生じる。純粋持株会社の成功は、純粋持株会社の経営者が、自立性を促進しつつ求心力を維持するという、高度なバランス感覚を発揮できるかどうかにかかっているといえよう。 |
(2004年05月24日「エコノミストの眼」)
小本 恵照
小本 恵照のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2009/03/25 | 環境問題とCSRに取り組む日本企業 | 小本 恵照 | 基礎研マンスリー |
| 2009/02/25 | ニッセイ景況アンケート調査結果-2008年度下期調査 | 小本 恵照 | ニッセイ景況アンケート |
| 2009/01/26 | 中小小売業の現状と今後の経営のあり方 | 小本 恵照 | 基礎研マンスリー |
| 2008/12/02 | 中小小売業に求められる企業家精神 | 小本 恵照 | 研究員の眼 |
新着記事
-
2025年10月21日
選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -
2025年10月21日
連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を -
2025年10月21日
インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 -
2025年10月21日
中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) -
2025年10月21日
今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【純粋持株会社の課題とは何か】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
純粋持株会社の課題とは何かのレポート Topへ


















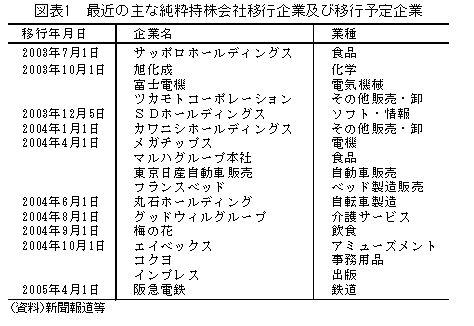

 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




