- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- ECB政策理事会-PEPP購入ペースの減速を決定
2021年09月10日
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
(リスク評価)
(金融・通貨環境)
(結論)
(質疑応答(趣旨))
- 我々は経済見通しへのリスクは総じて中立的(balanced)と見ている
- 消費者の景況感がより良くなり、予想以上に貯蓄を減らせば経済活動が予想を上回る可能性がある
- コロナ禍の状況が急速に回復することで、想定以上に力強さが見られる可能性もある
- しかし供給制約が長期化し、賃金上昇率にも影響すれば、価格上昇圧力はより持続的なものになる可能性がある
- 同時にコロナ禍の深刻化すれば、経済見通しは悪化し、経済再開の遅れや供給制約が予想されてより長期化し、生産を抑制すると見られる
(金融・通貨環境)
- 成長率とインフレ率の回復は経済の全部門における良好な資金調達環境に依存している
- 市場金利は夏の期間中は緩和されていたが、最近は上昇している
- 総じて経済の資金調達環境は引き続き良好なである
- 企業や家計に対する貸出金利は歴史的な低水準にある
- 家計への貸出は底堅く、特に住宅購入需要が強い
- 企業への貸出は鈍化しているが、主に企業がすでにコロナ禍の第一波で借入を増やした結果、十分に資金があるためだといえる
- 彼らは潤沢な現預金を保有しており、内部留保も増やしているため、外部からの資金調達需要は低下している
- 大企業では社債発行が銀行借入より魅力的な代替手段となっている
- 銀行の健全な財務状況(balance sheets)が十分な信用供給を引き続き可能にしている
- しかしながら、多くの企業や家計はコロナ禍中に多くの債務を負った
- 経済見通しの悪化は金融の健全性を脅かす可能性がある
- これは銀行の財務状況の質も悪化させる可能性がある
- 政策による支援により、財務状況の疲弊と資金調達環境の厳格化が互いに強まることを防ぐことは引き続き必要不可欠である
(結論)
- 要約すれば、ユーロ圏経済は明確に回復している
- しかし回復のスピードは、引き続きコロナ禍とワクチン普及の進展に依存している
- 足もとのインフレ率の上昇は大部分が一時的と見られ、物価上昇圧力の基調は緩やかな増加にとどまる
- 中期的なインフレ見通しの若干の改善と現在の資金調達環境により、PEPPでのネット資産購入を適度に減速したペースにしても良好な資金調達環境を維持できるだろう
- 我々の政策手段はフォワードガイダンスの変更を含めて、経済の強固な回復と、究極的には2%のインフレ目標の達成を支援するものである
(質疑応答(趣旨))
- 理事会メンバーの何人かはPEPPの終了が近いことを示唆しているが、今回の決定は方向転換と見なせるのか
- 今回の決定は、枠組み通りインフレ見通しと資金調達環境の双方を勘案して決定した事項である
- 今回の決定は、枠組み通りインフレ見通しと資金調達環境の双方を勘案して決定した事項である
- 今回の決定にどれほど自信を持っているか。インフレ見通しは23年でも1.5%と目標に届かない、不確実性も多く、刺激策の軽減がなぜ正当化されるのか
- ワクチン接種の進展などを背景に経済が回復していると確信している
- そのため、PEPPペースの再調整も妥当だと考えている
- ECBはどの程度の期間にわたって良好な資金調達環境を維持しようとしているのか、コロナ以降も続けるのか、PEPPの終了とともに終わるのか
- PEPPが終了するということは良好な資金調達環境となり、コロナ禍によるインフレ率の悪影響から回復したということだが、それで終わりではない
- PEPP終了後も2%の物価安定目標の達成に向けて取り組む
- PEPPの実施期間で言及されている、新型コロナ危機が去る、とは何をもって判断されるのか
- 今回のPEPP購入ペースの調整についての決定は全会一致でなされたが、次の段階に関する議論はしていない
- 12月の理事会で議論されるべき内容と言える
- 何人かのメンバーがインフレ率の上方リスクや長期化リスクに言及している、これについて理事会で議論したか
- インフレ率の一時的なものと持続するものを区分した結果、今回の見通しになっている
- インフレ圧力には、ベース効果によるもの、供給制約によるもの、対面サービス業の経済再開によるものなどがあるが大部分は一時的と見られる
- 注視するべきは、物価上昇が賃上げ交渉につながるという波及効果(second round effect)でこれは持続的なものになり得る
- 現在のところ賃金上昇は見られず、賃上げ交渉も大幅になるとは考えておらす、緩やかなものとなると見ている
- PEPPの終了について、どの程度前もって市場に伝えるか
- PEPPについては12月の理事会で包括的に議論されると考えている
- 22年の成長率についてそこまで楽観視しないアナリストもいるが、楽観的である理由は何か
- 我々の予測の前提は、封じ込め政策の緩和による好影響は22年も継続し、供給制約も22年前半には解消に向かうと見ている
- コロナ禍前の経済活動水準に戻る時期は当初の見通しより2四半期前倒ししており、現在残っている生産や雇用の弛み(slack)はより早く解消に向かうと見ている
- リスクは中立的で上方リスクも下方リスクも考えられる
- インフレ圧力がより持続的になりスタグフレーションとなるリスクについてどう考えるか
- 物価安定は主要な目的だが、経済や雇用の回復も重要な要素で、スタグフレーションに向かっているとは考えていない
- チーフエコノミストのレーン氏はPEPP終了後の資産購入策は、国債発行額を勘案すると述べているが、賛成するか
- 購入対象は債券全体であり、特定の国債発行状況を勘案はしない
- APPと政策金利の引き上げについて、APPの終了後にすぐ利上げをすることになっているが、時間的余裕や柔軟性を持たせる必要はないか
- 政策金利のフォワードガイダンス以外の部分については以前と同様であるが、現在はPEPPがコロナ禍前での中心の政策であり、他の手段の議論は時期尚早で、12月に議論したいと思う
- PEPPの再調整で決定したペースは全会一致だったか
- 全会一致だった
- 全会一致だった
- 12月のTLTROⅢの終了の後、さらなる長期の資金調達オペは予定していないか
- 今後のデータに基づいて、12月に議論されると思う
- PEPPの終了で国債購入の柔軟性はなくなるか。柔軟性に対する不確実性を先に排除することで、なくなるとの観測でギリシャ国債の投機的な売りを回避することを考えているか。
- ギリシャについては議論されるだろうが、今は時期尚早と言える
- インフレのリスクが上方に傾いているという議論はなされたか
- インフレやリスク評価の文章については全会一致で決められており、その評価は「供給制約が長期化し、賃金上昇率にも影響すれば、価格上昇圧力はより持続的なものになる可能性がある」ということである
- バーゼルⅢの円滑かつ完全実施を求める呼びかけについて支援するか
- 銀行監督はアンドレア・エンリア氏の管轄だが、バーゼルⅢについては工程表に沿って適切に受け入れることが重要だと考えている
- (デギンドス副総裁)早期の完全実施が銀行・経済にとって便益になると考えている
- PEPPの議論を12月にする際には新型コロナ危機が去ったと言えると思うか、その前の10月の理事会は何を予定しているか
- 10月にも議論し確認することはたくさんある
- 12月の方がコロナ禍から2年が経過しコロナ禍前の状況に戻っており、24年までの新しいスタッフ見通しも作成されるためPEPPの議論をするのに重要と言える
- 米国の債券市場からの影響について。米国のテーパリングがECBの決定に影響することがあるか
- (言及なし)
- (言及なし)
- 財政政策について、過去より財政規律に焦点をあてるべきか、不確実性のなかで経済支援を目指すべきか
- 財政政策は非常に重要で、金融政策を支えてきた
- 財政支援は将来的には縮小し、安定・成長協定のような規則を再交渉後に適用するとみられるが、今は時期尚早といえる
- ドイツの政権が変わることによる潜在的な影響について議論したか
- 議論していない
- 5年先5年物のブレークイーブンインフレ率が上昇しているが、今後の政策に影響があるか
- 5年先5年物だけでなく様々なインフレ関係の指標を見て動向を判断する
- PEPPが終了してAPPが増額されれば33%の国債保有上限ルールに達するのではないか、保有上限のルールを引き上げる必要があるのではないか
- 12月に議論する事項と考えている
- コロナ禍の影響を大きく受け、ECBの支援に頼っているイタリアやスペインの状況についてどう見ているか
- 南欧はコロナ禍の影響を大きく受けたが、復興基金からの資金も多く対応余地も多い
- 観光関連産業や対面サービス産業も当初の想定よりも回復している
(2021年09月10日「経済・金融フラッシュ」)
このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1818
経歴
- 【職歴】
2006年 日本生命保険相互会社入社(資金証券部)
2009年 日本経済研究センターへ派遣
2010年 米国カンファレンスボードへ派遣
2011年 ニッセイ基礎研究所(アジア・新興国経済担当)
2014年 同、米国経済担当
2014年 日本生命保険相互会社(証券管理部)
2020年 ニッセイ基礎研究所
2023年より現職
・SBIR(Small Business Innovation Research)制度に係る内閣府スタートアップ
アドバイザー(2024年4月~)
【加入団体等】
・日本証券アナリスト協会 検定会員
高山 武士のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | ユーロ圏GDP(2025年7-9月期)-前期比プラス成長を維持し、成長率は加速 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 2025/10/31 | ユーロ圏失業率(2025年9月)-失業率は6.3%で横ばい推移 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 2025/10/15 | IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 2025/10/15 | 英国雇用関連統計(25年9月)-週平均賃金は前年比5.0%まで再び上昇 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
新着記事
-
2025年10月31日
ユーロ圏GDP(2025年7-9月期)-前期比プラス成長を維持し、成長率は加速 -
2025年10月31日
ユーロ圏失業率(2025年9月)-失業率は6.3%で横ばい推移 -
2025年10月30日
潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 -
2025年10月30日
米FOMC(25年10月)-市場予想通り、政策金利を▲0.25%引き下げ。バランスシート縮小を12月1日で終了することも決定 -
2025年10月30日
試練の5年に踏み出す中国(後編)-「第15次五カ年計画」建議にみる、中国のこれからの針路
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【ECB政策理事会-PEPP購入ペースの減速を決定】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ECB政策理事会-PEPP購入ペースの減速を決定のレポート Topへ

















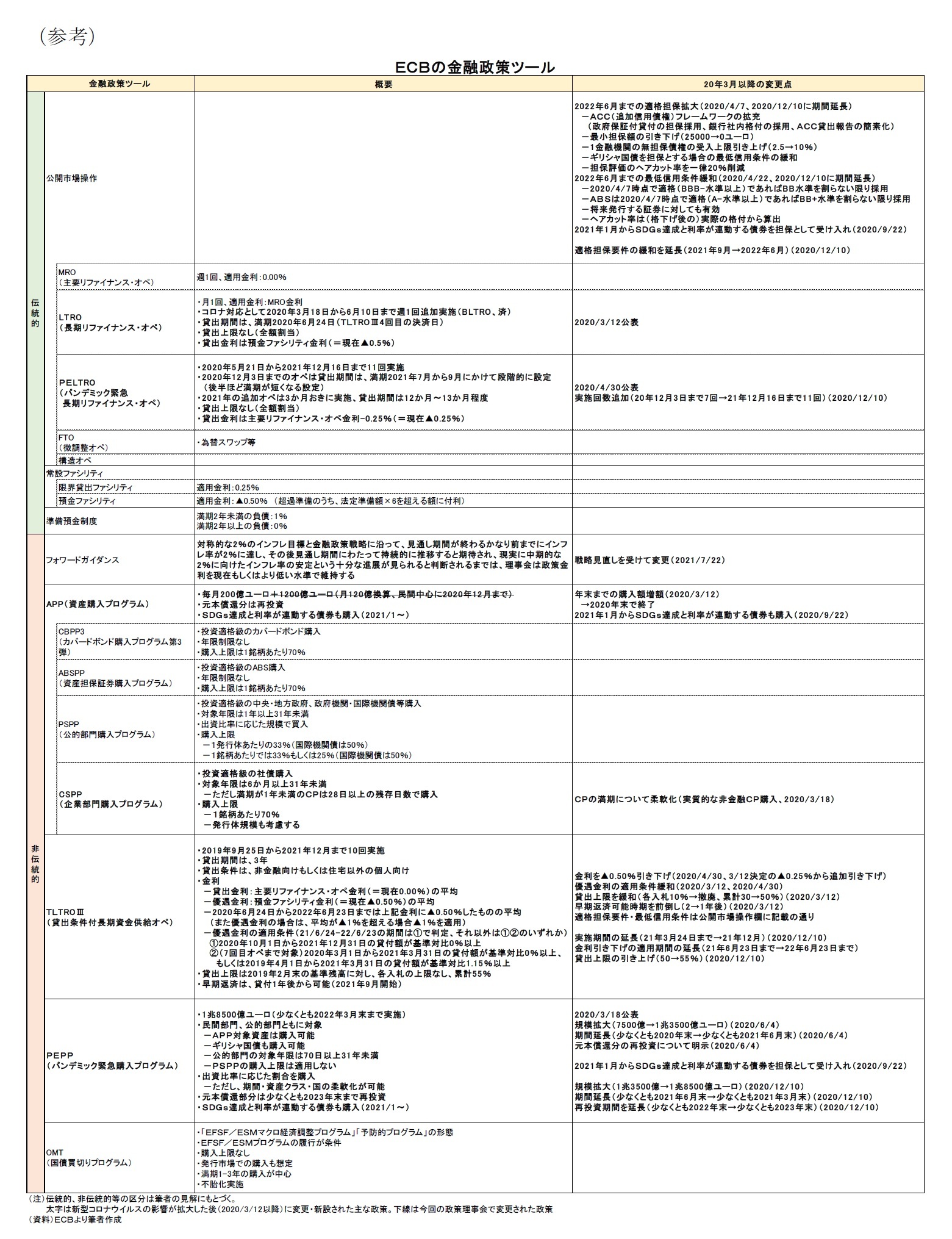

 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




