- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 経済 >
- 欧州経済 >
- ECB政策理事会-中期的な課題に焦点
2020年07月17日
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
(質疑応答(趣旨))
2 財政規律を重視するオランダ、オーストリア、スウェーデン、デンマークの4か国。
- PEPPは全額利用する必要ないかもしれないとする人に対する意見を知りたい
- PEPPは断片化による金融伝達の棄損、コロナ禍に対する金融政策姿勢の緩和という2つの機能がある。PEPPの規模・期間は2つの機能を維持するために修正されている。
- 金融市場が安定し断片化によるリスクが低下したため、購入ペースは低下している
- しかし、大きく事態が改善しない限り、ベースラインとしては総枠を利用する
- 第2の機能である緩和姿勢は依然として求められており、インフレ率をコロナ禍前の軌道に戻すため、引き続きPEPPの総枠を利用して、課題に取り組む必要がある
- ユーロ圏回復の二極化、例えばドイツは他のコロナ禍の影響を大きく受けている国よりもうまくやっていることが言われている。これについて懸念や防止策があるか。
- コロナ禍以前からユーロ圏加盟国での相違があり、コロナ禍後にも続く可能性がある
- これは当然ながら避けるべきであり、理事会がRRF(回復と強靭さのファシリティ)を歓迎するのはコロナ禍で深刻な打撃を受けた国を意図しているからだ
- 汎欧州での変革、発展がコロナ禍前の相違を縮小させる望みもある
- 金融政策の変更について議論したか。金融政策で過剰流動性が増えていることから階層化乗数(tiering multiplier)に興味がある。なぜ乗数を増やさなかったのか。
- 二層化システムはプラスで、金融緩和効果を維持しつつ、銀行に対する直接的な副作用を軽減する意味で、意図したとおりに機能している
- 乗数や免除部分への報酬率(remuneration rate)は変更することができる
- しかし、変更する理由は見当たらない
- 注視している中では再考の必要性は見られず、議論していない
- 米国での感染者数拡大が経済に与える影響は。世界最大の経済大国である米国のコロナ禍長期化は間違いなく、他国に影響を及ぼす。ベースラインは適切か、下方リスクが高まっているか。
- 6月のシナリオやベースラインは、第2波の潜在的リスクや封じ込め政策といった要素も考慮している
- 6月のシナリオやベースラインは、第2波の潜在的リスクや封じ込め政策といった要素も考慮している
- PEPPに関して。金融市場は安定していると言ったが、どの程度安定しているのか。現在の分断化(fragmentation)やスプレッド、金融安定へのリスクについてどう評価しているか。
- 金融市場のセンチメントは改善しているが、コロナ禍前の水準には戻っていない
- 政策公表後に国債・社債スプレッドは縮小し、社債発行も増加し、かなり改善している
- しかし、ほとんどの国で国債利回りはコロナ禍前より高く、企業・家計への金融商品や融資は国債利回りを基礎としているため、金融政策姿勢とも関連する
- こうした数値にも注意を払っている
- 高い需要があったTLTROIIIと銀行システムについて。資本規制緩和や担保基準の緩和などにもかかわらず、貸出姿勢は厳しくなりつつある。ECBは資金調達環境が厳しくなるのを防ぐために何をしようとしているか。
- まず、TLTROは非常に成功した。魅力的な条件だったこと、需要があったこと、利用に汚名(stigma)が伴わなかったことが理由といえる
- 21年9月に貸出実績と基準と比較することが重要で、銀行が少なくとも経済への貸出を維持したかによって優遇金利(預金ファシリティ金利-0.50%)の適用が判断される
- 金融引き締めリスクがあるようには見えず、こうした環境を考慮しなければいけない
- 保証政策の崖については、欧州委員会が保証制度のための最良慣行とガイドラインを公表している
- 財政当局に対して、これを検討し、崖の回避と十分に段階的な廃止管理を実施し、潜在的な引き締めの影響が生じないように奨励したい
- 倹約4か国2の抵抗が復興計画を弱体化させた場合の欧州経済とECBへの影響は。復興計画や条件に対する懸念はあるか。
- 我々のRRFの想定では、融資よりも補助金の割合が多い形でこれが実現すると見ている
- 欧州の重要なプロジェクトのいずれでも、各メンバーの懸念が考慮され交渉のうえ対処しようとしていることは驚くに値しない
- RRFが欧州のグリーン・デジタル化の将来を見据えた回復支援となることを期待する
2 財政規律を重視するオランダ、オーストリア、スウェーデン、デンマークの4か国。
- PEPPの出資比率(capital key)に対する重要性は各委員によって言っていることが異なる。委員会でこの件について議論したか。どの程度、出資比率の逸脱が許容できて、どの程度の速さで収れんさせるべきか
- PEPPが他の資産購入策と異なるのは柔軟性であり、非常に役立っている
- 出資比率はベンチマークであるが、柔軟性の下で効果的・効率的・比例的(proportional)であるため、逸脱ができる
- 出資比率への収れんは、前述した2つの機能の点に鑑みて、金融政策の効率性を損なうことが決してないように実施する
- 戦略見直しについての見解を聞きたい。コロナ禍でなんらか戦略見直しが変わったか。インフレ計測や、責務の解釈が変わるか。来年半ばのとりまとめについて実現可能性はあるか。
- 戦略見直しはまもなく再開しなければならない。9月には検討と議論を開始する
- 21年半ばで完了するかは分からない。やるべきことが多くあり、21年後半かもしれない
- パンデミックとそれが経済、インフレ動態、その他多くの問題に与える影響を考慮しなければならない。パンデミックからの学びを戦略見直しで考慮する決定をしている。
- 気候変動と金融安定でそれぞれ特化したセッションの決定もしている。もともと束ねられていたのだが、それぞれ独立した項目と出版物を作り、それぞれが金融政策との影響を測定できることを私も副総裁も喜んでいる。
- 銀行貸出に関する崖(政策支援の終了)の影響に言及したが、ドイツの所得保障制度(クルツアルバイト)のような政府の支援策に対する同様の懸念はあるか。
- 信用保証制度への懸念と同様の懸念といえる
- 財政当局に、回復がしっかり根付くのと合わせて段階的に縮小するよう心掛けて欲しい
- 経済を維持、支援することと景気を促進するというタイミングのジレンマにある
- 一時休業制度、失業制度、時短勤務制度の措置がすでに回復を止めないことを望む
- 今週のEU首脳会議で復興計画が合意に至らなかった場合、どのような影響があるか。
- 副総裁と私は欧州の終わりのない会議に関してのベテランである
- ブリュッセルでは物事に、時間を要し、交渉には大きな時間と労力を消費することがある
- リーダーの多くは時間を無駄にしないことの重要性、欧州への発信、投資家への発信、世界への発信といったことを認識している
- これらは、比較的すぐに実現される野心的な合意によって証明されると思う
- コロナ禍後の政策の有効性に対する一次評価を知りたい。銀行に供与した流動性が目的地の企業や家計に届いている証拠はあるか。
- 理事会は定期的に、政策の有効性と効率性を測定している
- 金融政策が経済に影響するには時間がかかる。我慢しなければならない。
- すでに効果の兆しは見えており、コロナ禍直後の厳しい金融調達状況から改善している
- 企業向け貸し出しは増加しており、3月から6月までで2500億ユーロが利用された
- 家計向けは数か月間低かったが、5月の変化率はコロナ禍前の水準まで戻っている
- モデルに基づくデータによれば、3-6月の間に政策効果でユーロ圏の実質成長率は1.3%ポイント、インフレ率は0.8%ポイント押し上げられている
- EUレベルでの財政政策がより手厚ければ、金融政策もより効果的だったのか
- 一層の汎ユーロ圏での財政措置があれば、より効果的だったかもしれないことは明らか
- しかし、国としてもユーロ圏としても財政措置は迅速に実施されている
- 財政措置はGDP比で約4%実施されており、加えて保証措置が約20%ある
- 5400億ユーロの政策もまた優れた措置であり、一部はすでに利用され、また我々金融部門の機能強化にも資することは明らか
- 一部エコノミストは倒産の増加と銀行危機を警告している。これについての懸念はあるか
- 政策の崖のリスクや、弱い企業と銀行の関係ついては注視する必要がある
- 一方、銀行の資本は強化されている
- 自己資本比率は2010年の10.4%から19年に14.8%に達し、超過資本が3%ポイントある
- 第二の柱を含む自己資本規制を考慮すると、悪い状況に対処する能力は総合的に強い
- SSM(単一銀行監督制度)の銀行監督委員会はこうしたバッファーを利用し危機に対応することを奨励してきた
- 回復が根付くように十分に長期間支援を行いつつ、段階的に廃止していくという問題
- コミュニケーションについて。ECBの主要な責務は物価安定と強調されているが、多くの人は何兆ユーロも使って、小数点以下のインフレ率数値を引き上げようとすることへの理解はし難い。ECBの2つ目の責務、雇用の最大化などについて、なぜ話し合わないのか
- 主要責務がひとつで、物価の安定という点でECBはFRBとは異なる
- 2003年の戦略見直しでは2%に近いがそれ以下、が最良の測定値とされた
- 今後の戦略見直しの検討・議論の課題である
- しかし、価格の安定がなければ経済が持続的な形で機能しないのは明らかである
- 企業、家計、政府にとって物価の安定は投資、雇用、財政政策を決めるための重要な要素といえる
- 気候変動が懸念すべき問題であり、中央銀行に関係があると言及したとき、気候変動がインフレ動態、生産性、貨幣の流通に影響を与えるため、物価安定を念頭に置いていた
- インフレ率で測定された物価安定の責務には、他の様々な要素が埋め込まれている
- コロナ禍が長期的に貿易に及ぼす影響と、グローバル化へ恒久的に与える影響について教えて欲しい。貿易・輸出に大きく依存する経済は事業モデルを変える必要があるかもしれないか。
- 貿易への影響としては機械的なものが第一にある
- ある国が他の国より急速に回復することで、機能していない海外よりも需要がある国内取引を多くしなければならないということが生じる
- 貿易に大きく依存していた国々でも、国内市場への依存を考慮しなければならない
- 文化的、社会学的、哲学的な変化も起きるかもしれない
- 消費者が原産地や製造場所を気にするという意味で近さが重要になる
- 離れた供給網や複雑で細分化された供給網に依存する企業も近接性の利点を再発見する
- これら機械的な影響と社会学的な影響によって貿易への影響が生じると思う
- 戦略見直しについて。見直しを推進する過程での発見などは都度公表するのか、結果がまとまるまで待つつもりか。
- 理事会は情報伝達手段についてはまだ結論を出していない
- 最終結果発表の〆切のようなものを持っているが、逐次公表することもあるかもしれない
- 公表についてまだ決定したものはなく、議論中である。結果はお伝えする
(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。
(2020年07月17日「経済・金融フラッシュ」)
このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1818
経歴
- 【職歴】
2006年 日本生命保険相互会社入社(資金証券部)
2009年 日本経済研究センターへ派遣
2010年 米国カンファレンスボードへ派遣
2011年 ニッセイ基礎研究所(アジア・新興国経済担当)
2014年 同、米国経済担当
2014年 日本生命保険相互会社(証券管理部)
2020年 ニッセイ基礎研究所
2023年より現職
・SBIR(Small Business Innovation Research)制度に係る内閣府スタートアップ
アドバイザー(2024年4月~)
【加入団体等】
・日本証券アナリスト協会 検定会員
高山 武士のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 2025/10/31 | ユーロ圏GDP(2025年7-9月期)-前期比プラス成長を維持し、成長率は加速 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 2025/10/31 | ユーロ圏失業率(2025年9月)-失業率は6.3%で横ばい推移 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 2025/10/15 | IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
新着記事
-
2025年11月04日
今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -
2025年10月31日
交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -
2025年10月31日
ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -
2025年10月31日
2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -
2025年10月31日
保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【ECB政策理事会-中期的な課題に焦点】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ECB政策理事会-中期的な課題に焦点のレポート Topへ

















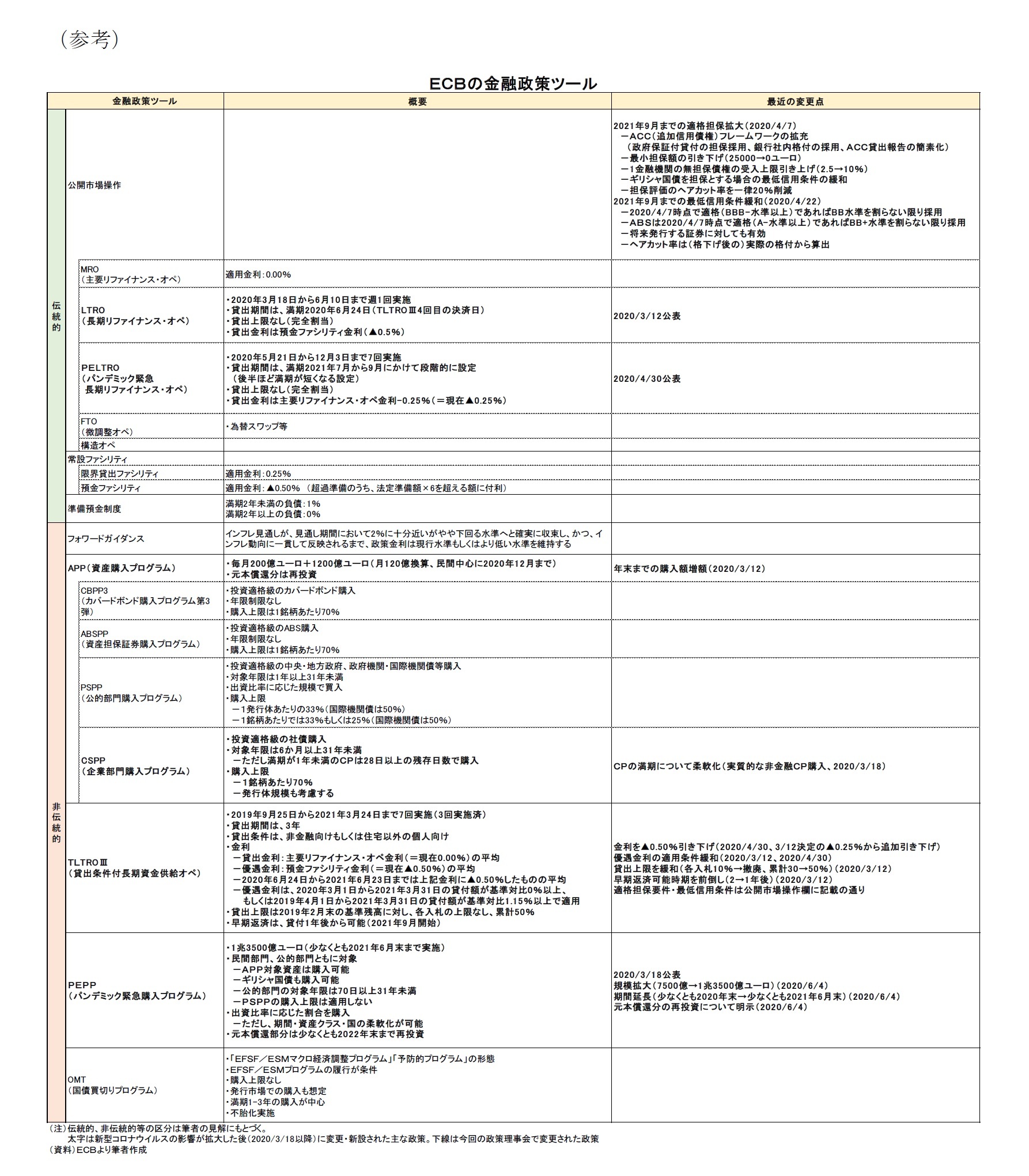

 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




