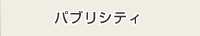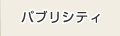- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- パブリシティ >
- イベント(シンポジウム) >
- イベント詳細 >
- 超高齢社会における企業と個人の在り方「討論」
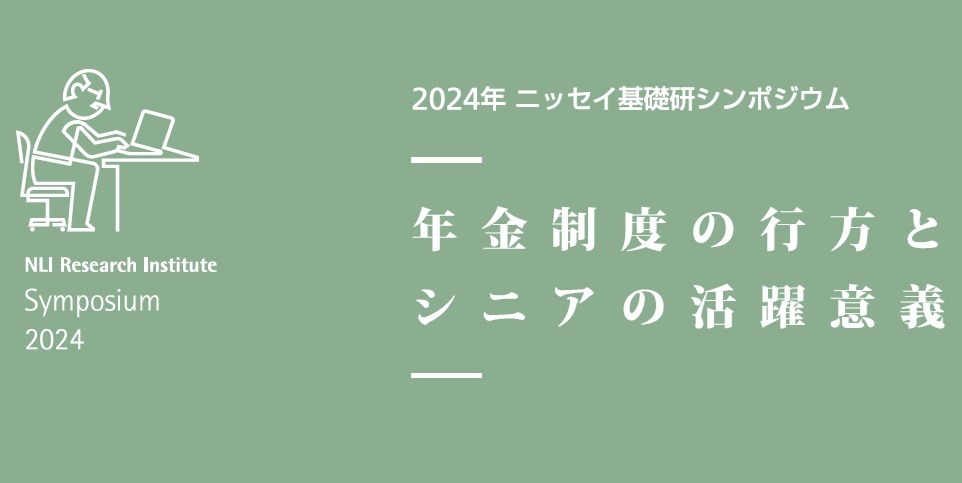
2024年10月22日開催
パネルディスカッション
超高齢社会における企業と個人の在り方「討論」
| パネリスト |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデレータ |
|
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
5――多様な働き方
■徳島 ありがとうございます。今年は、フリーランス法だとか、いろいろ制度も変わっていく中で、働き方も、日本はずっと正規雇用が全てみたいなところから、非正規雇用が入ってきた。そもそも非正規雇用という言葉自身、既に適切ではない言葉だと思っていますが。そういった多様な働き方を認めていく中で、いろいろ企業も変わっていかないといけないということかと思います。
続きまして、中嶋さん、この辺りのテーマでご意見がありましたら教えてください。
■中嶋 今お話があった、非正規というのが古くなっているということですが、非正規という働き方を作ってしまったのは社会保障制度だと思います。そのあたりは社会保障制度が適切に対応して、皆さんが同じように働く環境を整えていくことが大事ではないか、と思います。
もう一つ、中田様から、高齢期に働くことはいいループだというお話がありました。そのループに入るためには、きっかけというのが必要かと思います。私が個人の方に年金のお話をさせていただくときは、私も50代なのですけれども、50代ぐらいの方には年金の目減りは避けようがありません、保険料を上げていないので仕方ないです、と申し上げています。
途中でもお話ししましたけれども、年金の受け取りを遅らせて、その2~3年、長く働いてみたらどうですか。そこに向けて、健康を維持したり、あるいは50の手習いではないですけれども、社会の変化に合わせて新しいスキルを身に付けていくことが大事ですよ、というお話をさせていただいています。企業が変わっていくことも大事ですが、個人の意識の変化も大事ではないかと思っております。
続きまして、中嶋さん、この辺りのテーマでご意見がありましたら教えてください。
■中嶋 今お話があった、非正規というのが古くなっているということですが、非正規という働き方を作ってしまったのは社会保障制度だと思います。そのあたりは社会保障制度が適切に対応して、皆さんが同じように働く環境を整えていくことが大事ではないか、と思います。
もう一つ、中田様から、高齢期に働くことはいいループだというお話がありました。そのループに入るためには、きっかけというのが必要かと思います。私が個人の方に年金のお話をさせていただくときは、私も50代なのですけれども、50代ぐらいの方には年金の目減りは避けようがありません、保険料を上げていないので仕方ないです、と申し上げています。
途中でもお話ししましたけれども、年金の受け取りを遅らせて、その2~3年、長く働いてみたらどうですか。そこに向けて、健康を維持したり、あるいは50の手習いではないですけれども、社会の変化に合わせて新しいスキルを身に付けていくことが大事ですよ、というお話をさせていただいています。企業が変わっていくことも大事ですが、個人の意識の変化も大事ではないかと思っております。
6――議論全般に対するコメント
■徳島 ありがとうございます。それでは、ここまでの議論全般に対して、秋山様からご感想と、秋山様なりのご見解を頂けたらと思います。よろしくお願いします。
■秋山 10年前に、フランスとかイタリアでこういうセカンドライフの就労の話をすると、「定年後に誰が働きたいんだ」と一笑に付されました。年金制度がないのかとか、しっかりしていないからだろうとかいうことでした。むしろ定年前にアーリー・リタイアメントを皆が目指していたのです。どれだけ早くリタイアできるか、リタイアした後、楽しく過ごすことが夢だったのですが、今や、セカンドライフの就労の問題は、先進国共通の課題なのです。国際学会でも、研究報告だとかシンポジウムが最も多いテーマになっております。
昔は、定年を延ばすということを提言した政党は、次の選挙で必ず負けるとヨーロッパで言われたそうですが、今はそんなことは言っていられないというような状況なのです。長く働く、Working longerと言われていますが、長く働くということは、持続可能な社会の実現にとっても、長寿時代に生きる個人のウェルビーイングにとっても、極めて重要な課題であると思っております。
今日の議論は非常に興味深く、全く私とは違う分野から話を伺って、本当に勉強になりました。本日の議論を振り返ると、優先的に取り組む必要があることが幾つかあると思います。一つは何といっても、シニアの就労にブレーキをかけている年金制度を見直すことは必要であるということは、全員一致している。もう一つは、先ほど申しましたように、セカンドライフはマラソンの後半戦と同じで、体力とかいろいろなことで、ばらつきが非常に多いということなので、高齢期にふさわしい柔軟な雇用制度と働き方を編み出すということが必要かなと思います。
これは、シニアの働く人たちの生産性とか安全性を担保すると同時に、一生ずっと働くというと、何か馬車馬みたいに死ぬまで働くのかというように若い人が思って非常に警戒するわけです。そのように働き続けるのではなくて、個人の望む多様なライフデザインを可能にする。働いてもいるし、勉強もするし、遊びもあるしというような形の、個人のライフデザインの中にうまく入っていくような働き方が可能になるような、そういう柔軟な雇用制度、これはできればシニアだけではなくて若い人たちにとってもそうであってほしいなと思います。
もう一つは、そのためには中田さんがおっしゃるようにロールモデルですね。今の段階では、いろいろな形の多様なロールモデルが必要なのだろうと思っております。メディアでも取り上げていただいておりますが、そういうことがそこからどんどん広がっていくといいなと思います。
もう一つは、生涯いつでも学べるというか、リスキリングの環境を整えるということと、シニア自身も常に学び続ける。年取った犬はもう新しいことは覚えない、そういうことではなくて、常に学ぶという機会があると同時に、それを活用するということが必要だと思います。
あと一つ、今日は話題には出ませんでしたが、国際的にも非常に大きな課題は、エイジズム、年齢差別です。これは世界共通の非常に克服が困難な課題だというように考えられております。エイジズムというのは、事業者とか若年世代が年寄りに対する偏見を持っているというだけではなくて、シニア自身にエイジズムというのが結構根強くあるのです。自分はもう年取っているのだからこんなのは無理とか、できないよとか。
先ほど言いましたように、30年前のシニアと今のシニアは随分違うのです。だからできないことはない、できる。エイジズムの克服ということが、結構これから大きな課題になるかなと思っております。そんなことがこれからまず取り組まなくてはいけない重要課題かなと思います。
■秋山 10年前に、フランスとかイタリアでこういうセカンドライフの就労の話をすると、「定年後に誰が働きたいんだ」と一笑に付されました。年金制度がないのかとか、しっかりしていないからだろうとかいうことでした。むしろ定年前にアーリー・リタイアメントを皆が目指していたのです。どれだけ早くリタイアできるか、リタイアした後、楽しく過ごすことが夢だったのですが、今や、セカンドライフの就労の問題は、先進国共通の課題なのです。国際学会でも、研究報告だとかシンポジウムが最も多いテーマになっております。
昔は、定年を延ばすということを提言した政党は、次の選挙で必ず負けるとヨーロッパで言われたそうですが、今はそんなことは言っていられないというような状況なのです。長く働く、Working longerと言われていますが、長く働くということは、持続可能な社会の実現にとっても、長寿時代に生きる個人のウェルビーイングにとっても、極めて重要な課題であると思っております。
今日の議論は非常に興味深く、全く私とは違う分野から話を伺って、本当に勉強になりました。本日の議論を振り返ると、優先的に取り組む必要があることが幾つかあると思います。一つは何といっても、シニアの就労にブレーキをかけている年金制度を見直すことは必要であるということは、全員一致している。もう一つは、先ほど申しましたように、セカンドライフはマラソンの後半戦と同じで、体力とかいろいろなことで、ばらつきが非常に多いということなので、高齢期にふさわしい柔軟な雇用制度と働き方を編み出すということが必要かなと思います。
これは、シニアの働く人たちの生産性とか安全性を担保すると同時に、一生ずっと働くというと、何か馬車馬みたいに死ぬまで働くのかというように若い人が思って非常に警戒するわけです。そのように働き続けるのではなくて、個人の望む多様なライフデザインを可能にする。働いてもいるし、勉強もするし、遊びもあるしというような形の、個人のライフデザインの中にうまく入っていくような働き方が可能になるような、そういう柔軟な雇用制度、これはできればシニアだけではなくて若い人たちにとってもそうであってほしいなと思います。
もう一つは、そのためには中田さんがおっしゃるようにロールモデルですね。今の段階では、いろいろな形の多様なロールモデルが必要なのだろうと思っております。メディアでも取り上げていただいておりますが、そういうことがそこからどんどん広がっていくといいなと思います。
もう一つは、生涯いつでも学べるというか、リスキリングの環境を整えるということと、シニア自身も常に学び続ける。年取った犬はもう新しいことは覚えない、そういうことではなくて、常に学ぶという機会があると同時に、それを活用するということが必要だと思います。
あと一つ、今日は話題には出ませんでしたが、国際的にも非常に大きな課題は、エイジズム、年齢差別です。これは世界共通の非常に克服が困難な課題だというように考えられております。エイジズムというのは、事業者とか若年世代が年寄りに対する偏見を持っているというだけではなくて、シニア自身にエイジズムというのが結構根強くあるのです。自分はもう年取っているのだからこんなのは無理とか、できないよとか。
先ほど言いましたように、30年前のシニアと今のシニアは随分違うのです。だからできないことはない、できる。エイジズムの克服ということが、結構これから大きな課題になるかなと思っております。そんなことがこれからまず取り組まなくてはいけない重要課題かなと思います。
7――まとめのメッセージ
■徳島 ありがとうございます。ここまでいろいろ皆さまにお話を伺ってまいりましたが、もう少しパネルディスカッションの時間がありますので、最後に皆さまに、今後の高齢者のさらなる活躍に向けて、高齢者本人、企業、社会、政府など、さまざまな相手に向けて、要望とか期待など、前向きなメッセージを頂いてディスカッションのまとめにしたいと思います。
7―1. 就業者側の意識
まず私から申し上げますと、就業者個々人が、自分たちの老後についてしっかり考えて、準備をするといったことがまず必要であるというのが、今日の私の学びだったかと思います。それでは中嶋さん、いかがでしょうか。
■中嶋 ありがとうございます。先ほど申し上げたように、個人の意識付けというのが大事ではないかな、と思います。私も50代になりまして、会社人生を振り返ってみると二十数年たちました。60歳あるいは65歳定年と考えると、半ばをだいぶ過ぎたかなと思っていたのですが、70歳ということを考えると、まだ折り返してちょっとしかたっていない、まだまだ先は長いな、先ほど秋山先生からお話があったマラソンの後半戦かな、と思います。
ですので、個人が、寿命が長くなっている、あるいは健康になっているということを意識するのが大事だと思います。例えば年金の受け取りを遅らせなければいけないとしても、寿命が長くなっているので、老後の期間が短くなっているわけではありません。そういったことをしっかり意識して、先ほどお話ししたようにリスキリングとか、そういった形で備えていくことが大事かなと思います。
■徳島 それでは続きまして秋山様、お願いします。
■秋山 一方で、これも先進国共通で、社会的な孤立とか孤独の問題というのが非常に大きくなっています。イギリスなどは孤独大臣、孤独省、そういうのができているというぐらい、非常に深刻な問題なのです。日本でもそういうことが広がっています。単身世帯も非常に増えています。まず一歩、家から出てみようということですよね。外に一歩出れば、あなたの出番はたくさんありますよということを言いたいです。
おそらく、遠からず、80歳ぐらいまで働くのは普通だという社会が来ると思いますので、65歳で閉じこもろうなんてとんでもない話なのです。まず外に出てみよう、出番はありますということです。
■徳島 それでは中田様、お願いします。
■中田 ありがとうございます。さっきの秋山先生の孤独の話で、外に一歩出てみようって、とても素敵だなと思います。実は、すごく深い関係の人とばかりつながっている人が幸せになっているわけではなくて、近所で、スーパーで必ず会って挨拶をする人とか、散歩の時にすれ違う人、犬の名前は知っているけれど名前は知らないとか、そういう人に出会えるだけで、その人とちょっと会話を交わすだけで、実はその人の幸福度はどんどん上がります。外に一歩出ると、社会にはたくさん、いわゆるいろいろな社会に関われる人がいます。そこにもう少し何か好きなことがあれば、共にできるような人がいるというのが、実は幸せになるのかなと思います。
私は企業の支援をしておりますので、どうしても企業にお願いしたい部分もありながらも、企業の人事制度が変わるより、皆さんがおっしゃるように個人が変わる方が、本当はスピードは早いかなと思います。
ただ一方で、ウェルビーイングという領域において、ウェルビーイングを研究されている先生がこの前おっしゃっていたのですが、人が幸せになるポイントでとても簡単なものがあり、それは実は多くの選択肢の中にあり、その多くの選択肢の中から自己決定をする、その作業をやったとき、人間はとても幸せになると言われていました。この働き方しかない、このやり方しかないと思って、ずっと仕事をしてくると、人はつらいのですけれども、その中にたくさん選択肢があって、自分が選んだ、自分でこの選択肢から選んだ瞬間に、急に幸せになると言われていました。
そういう意味で、今日いらっしゃった企業の方は、数多くの選択肢をまず社員の方に提示いただきたいですし、当該の中高年の皆さんは、それをちゃんと自分で選択する。そのためには自身が何をやりたいかというデザインをして、自分でキャリアを作っていくというところで、選んで、ウェルビーイングな気持ちになっていただくと、みんなが当たり前にいろいろなことを選択して、幸せな社会になるのではないかなと思います。私もその社会に貢献できるよう引き続き尽力したいと思います。今日はありがとうございました。
■徳島 ありがとうございました。それでは続きまして、小塩様、お願いいたします。
まず私から申し上げますと、就業者個々人が、自分たちの老後についてしっかり考えて、準備をするといったことがまず必要であるというのが、今日の私の学びだったかと思います。それでは中嶋さん、いかがでしょうか。
■中嶋 ありがとうございます。先ほど申し上げたように、個人の意識付けというのが大事ではないかな、と思います。私も50代になりまして、会社人生を振り返ってみると二十数年たちました。60歳あるいは65歳定年と考えると、半ばをだいぶ過ぎたかなと思っていたのですが、70歳ということを考えると、まだ折り返してちょっとしかたっていない、まだまだ先は長いな、先ほど秋山先生からお話があったマラソンの後半戦かな、と思います。
ですので、個人が、寿命が長くなっている、あるいは健康になっているということを意識するのが大事だと思います。例えば年金の受け取りを遅らせなければいけないとしても、寿命が長くなっているので、老後の期間が短くなっているわけではありません。そういったことをしっかり意識して、先ほどお話ししたようにリスキリングとか、そういった形で備えていくことが大事かなと思います。
■徳島 それでは続きまして秋山様、お願いします。
■秋山 一方で、これも先進国共通で、社会的な孤立とか孤独の問題というのが非常に大きくなっています。イギリスなどは孤独大臣、孤独省、そういうのができているというぐらい、非常に深刻な問題なのです。日本でもそういうことが広がっています。単身世帯も非常に増えています。まず一歩、家から出てみようということですよね。外に一歩出れば、あなたの出番はたくさんありますよということを言いたいです。
おそらく、遠からず、80歳ぐらいまで働くのは普通だという社会が来ると思いますので、65歳で閉じこもろうなんてとんでもない話なのです。まず外に出てみよう、出番はありますということです。
■徳島 それでは中田様、お願いします。
■中田 ありがとうございます。さっきの秋山先生の孤独の話で、外に一歩出てみようって、とても素敵だなと思います。実は、すごく深い関係の人とばかりつながっている人が幸せになっているわけではなくて、近所で、スーパーで必ず会って挨拶をする人とか、散歩の時にすれ違う人、犬の名前は知っているけれど名前は知らないとか、そういう人に出会えるだけで、その人とちょっと会話を交わすだけで、実はその人の幸福度はどんどん上がります。外に一歩出ると、社会にはたくさん、いわゆるいろいろな社会に関われる人がいます。そこにもう少し何か好きなことがあれば、共にできるような人がいるというのが、実は幸せになるのかなと思います。
私は企業の支援をしておりますので、どうしても企業にお願いしたい部分もありながらも、企業の人事制度が変わるより、皆さんがおっしゃるように個人が変わる方が、本当はスピードは早いかなと思います。
ただ一方で、ウェルビーイングという領域において、ウェルビーイングを研究されている先生がこの前おっしゃっていたのですが、人が幸せになるポイントでとても簡単なものがあり、それは実は多くの選択肢の中にあり、その多くの選択肢の中から自己決定をする、その作業をやったとき、人間はとても幸せになると言われていました。この働き方しかない、このやり方しかないと思って、ずっと仕事をしてくると、人はつらいのですけれども、その中にたくさん選択肢があって、自分が選んだ、自分でこの選択肢から選んだ瞬間に、急に幸せになると言われていました。
そういう意味で、今日いらっしゃった企業の方は、数多くの選択肢をまず社員の方に提示いただきたいですし、当該の中高年の皆さんは、それをちゃんと自分で選択する。そのためには自身が何をやりたいかというデザインをして、自分でキャリアを作っていくというところで、選んで、ウェルビーイングな気持ちになっていただくと、みんなが当たり前にいろいろなことを選択して、幸せな社会になるのではないかなと思います。私もその社会に貢献できるよう引き続き尽力したいと思います。今日はありがとうございました。
■徳島 ありがとうございました。それでは続きまして、小塩様、お願いいたします。
7―2. 余力を用意する
■小塩 ありがとうございます。今日はできるだけ明るい話をしましょう、暗い話はできるだけ抑えましょうということでしたが、一つだけ、ちょっと気になることがあります。それは、就職氷河期世代の人たちのことです。この世代の人たちは今、50代に差しかかったぐらいで、まだ健康面で大きな問題はないでしょうし、はっきり言えば、年金をもらっている親御さんの世話になっている方も多いと思うのですけれども、将来、この人たちが年金受給世代になったときの高齢社会の姿は、ワイルドカードになりかねません。この点は、われわれが頭に入れておかないといけないなと思います。
そういう人たちも社会全体で支えないといけないのですね。そうすると、今日は、あまり働くということばかり言わないようにというお話だったのですが、ある程度、働ける人は働いておいて、そういう人たちも支えるというふうな余力を社会に用意しておく必要があるのではないかと思います。
この問題は、現時点で顕在化していないし、政策の俎上にも上がっていませんが、気にしておく必要があるのではないかと思います。いってみれば、おつりが出るような社会も、これから私たちは狙っていく必要があると思いました。
■小塩 ありがとうございます。今日はできるだけ明るい話をしましょう、暗い話はできるだけ抑えましょうということでしたが、一つだけ、ちょっと気になることがあります。それは、就職氷河期世代の人たちのことです。この世代の人たちは今、50代に差しかかったぐらいで、まだ健康面で大きな問題はないでしょうし、はっきり言えば、年金をもらっている親御さんの世話になっている方も多いと思うのですけれども、将来、この人たちが年金受給世代になったときの高齢社会の姿は、ワイルドカードになりかねません。この点は、われわれが頭に入れておかないといけないなと思います。
そういう人たちも社会全体で支えないといけないのですね。そうすると、今日は、あまり働くということばかり言わないようにというお話だったのですが、ある程度、働ける人は働いておいて、そういう人たちも支えるというふうな余力を社会に用意しておく必要があるのではないかと思います。
この問題は、現時点で顕在化していないし、政策の俎上にも上がっていませんが、気にしておく必要があるのではないかと思います。いってみれば、おつりが出るような社会も、これから私たちは狙っていく必要があると思いました。
おわりに
■徳島 ありがとうございます。今日、いろいろ議論させていただいた中で、幾つか考えないといけないのは、なるべく健康を維持すること、そしてもう一つ大きいなことが、社会とのつながりです。企業で就労するというのが今日の一つのテーマであったわけですけれども、それ以外にも社会活動とか、そういったところとつながっていくことが、メンタルヘルス的な観点からも大きな意味があります。
私たちがこれから、皆さんも含めて高齢者になっていく、既に高齢者の方もいらっしゃるのですが、そういった中で、社会とのつながりを持ちつつ、孤立せずに活動していくことが、一つの大きな要素なのかなと拝聴いたしました。
今日はこうやって幅広い観点からいろいろな議論をさせていただきました。必ずしも就労に限らずお話しいただきましたが、私たち働いている人間から見ると、高齢者の就労というのは極めて大きなテーマと思います。そういった中で、個人の努力も必要だし、企業の側にも新たな取り組みが求められる。もちろんご指摘にあったような年金の、一部の仕組みは改めていただけたらといった部分もありました。そういったことで、お聞きになられました皆さまに少しでもご参考になれば幸いでございます。
それでは、これをもちまして、第2部のパネルディスカッションを終了させていただければと思います。どうもご清聴ありがとうございました。
私たちがこれから、皆さんも含めて高齢者になっていく、既に高齢者の方もいらっしゃるのですが、そういった中で、社会とのつながりを持ちつつ、孤立せずに活動していくことが、一つの大きな要素なのかなと拝聴いたしました。
今日はこうやって幅広い観点からいろいろな議論をさせていただきました。必ずしも就労に限らずお話しいただきましたが、私たち働いている人間から見ると、高齢者の就労というのは極めて大きなテーマと思います。そういった中で、個人の努力も必要だし、企業の側にも新たな取り組みが求められる。もちろんご指摘にあったような年金の、一部の仕組みは改めていただけたらといった部分もありました。そういったことで、お聞きになられました皆さまに少しでもご参考になれば幸いでございます。
それでは、これをもちまして、第2部のパネルディスカッションを終了させていただければと思います。どうもご清聴ありがとうございました。
⇒ 基調講演 高齢者の年金・就労・健康を考える
⇒ パネルディスカッション 前編 超高齢社会における企業と個人の在り方「プレゼンテーション」
コンテンツ紹介
-
レポート
-
受託実績・コンサルティング
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る