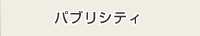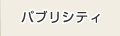- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- パブリシティ >
- イベント(シンポジウム) >
- イベント詳細 >
- 高齢者の年金・就労・健康を考える
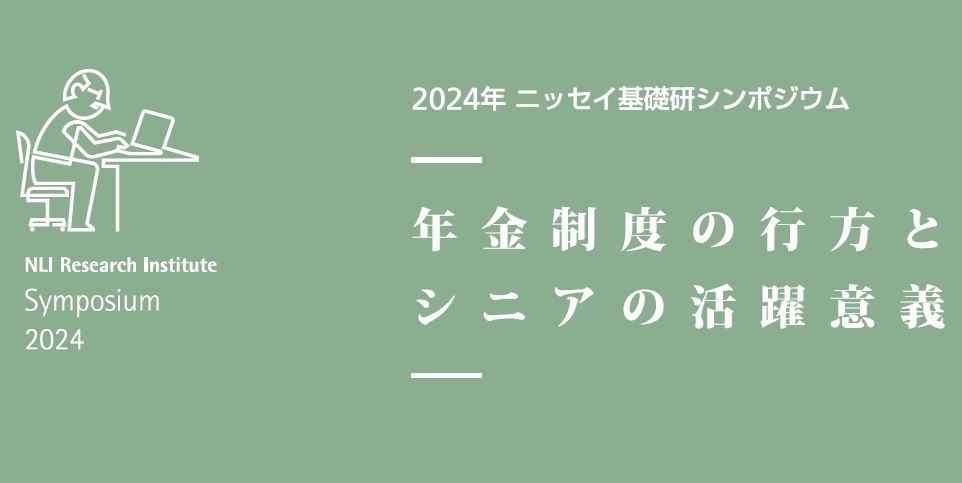
2024年10月22日開催
基調講演
高齢者の年金・就労・健康を考える
| 講師 | 一橋大学経済研究所 特任教授 小塩 隆士氏 |
|---|
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
2024年10月「年金制度の行方とシニアの活躍意義」をテーマにニッセイ基礎研シンポジウムを開催いたしました。
一橋大学経済研究所 特任教授 小塩 隆士氏をお招きして「高齢者の年金・就労・健康を考える」をテーマに講演いただきました。
※ 当日資料はこちら
一橋大学経済研究所 特任教授 小塩 隆士氏をお招きして「高齢者の年金・就労・健康を考える」をテーマに講演いただきました。
※ 当日資料はこちら
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
一橋大学経済研究所の小塩と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
(以下スライド併用)
今日お話しする内容をご紹介します。全部で四つの項目に分かれているのですが、最初にイントロダクションといいますか、私の話のバックグラウンドとして、よく皆さんも耳にされるであろう「全世代型社会保障」の考え方を念頭に置いて、現在日本の高齢化がどのような状況にあるのかというお話をします。それから就労と健康の関係について、統計的にどのようなことが分かるのかをお話しします。次に、高齢になるとライフスタイルが多様化するのですが、それと私たちの心の問題、メンタルヘルスがどういう関係にあるのかという話をします。最後に、まとめと政策的なインプリケーションを申し上げます。
私は1960年生まれです。今年64歳になりますが、現行の年金制度では、今年から年金をもらえることになりました。9月が誕生日ですので、年金の請求に行ってまいりました。そこで初めて、現在の年金の仕組みはどうなっているかということをちゃんと勉強したというわけです。それ以上に、これからの人生をどのように歩むのかということが、自分自身の問題として非常に重要になっています。
私自身に今までの人生は、何らかの形でレールが敷かれていて、その上を走っていたら何とかなったのですが、これからはレールがないという状況です。私は、あと何年生きるかわかりませんが、その残された人生をどのように歩むかは、非常に重要な問題だと思っています。そういう個人的な問題意識も念頭に置きながら、お話を進めさせていただければと思います。
一橋大学経済研究所の小塩と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
(以下スライド併用)
今日お話しする内容をご紹介します。全部で四つの項目に分かれているのですが、最初にイントロダクションといいますか、私の話のバックグラウンドとして、よく皆さんも耳にされるであろう「全世代型社会保障」の考え方を念頭に置いて、現在日本の高齢化がどのような状況にあるのかというお話をします。それから就労と健康の関係について、統計的にどのようなことが分かるのかをお話しします。次に、高齢になるとライフスタイルが多様化するのですが、それと私たちの心の問題、メンタルヘルスがどういう関係にあるのかという話をします。最後に、まとめと政策的なインプリケーションを申し上げます。
私は1960年生まれです。今年64歳になりますが、現行の年金制度では、今年から年金をもらえることになりました。9月が誕生日ですので、年金の請求に行ってまいりました。そこで初めて、現在の年金の仕組みはどうなっているかということをちゃんと勉強したというわけです。それ以上に、これからの人生をどのように歩むのかということが、自分自身の問題として非常に重要になっています。
私自身に今までの人生は、何らかの形でレールが敷かれていて、その上を走っていたら何とかなったのですが、これからはレールがないという状況です。私は、あと何年生きるかわかりませんが、その残された人生をどのように歩むかは、非常に重要な問題だと思っています。そういう個人的な問題意識も念頭に置きながら、お話を進めさせていただければと思います。
1――背景:「全世代型社会保障」の発想
最初にイントロダクションなのですが、今日ここにいらっしゃる方々は、全世代型社会保障という言葉をどこかでお聞きになったことがあるのではないでしょうか。
簡単に言えば、世の中を支える人が減って、支えられる人が増えるという、そういう人口のバランスが変わってしまうという状況の下で、どうしたら社会を維持していけるかという問題意識から、いろいろな制度改革が検討されているわけです。現時点で政府から出ているメッセージは、非常に単純明快でして、支えられている人が支える側にできるだけ回れば、何とかうまく行くのではないかということです。そして、支払う能力がある人には今まで以上に負担してもらって、そうでない人は給付をしっかり受ける。そういうことを念頭に置いて、いろいろな制度改革が行われているところです。
高齢化と言われて、私たちの頭の中にはどのような姿が浮かぶでしょうか。昨年、国立社会保障・人口問題研究所がアップデートした、人口の将来推計をベースにして、人口構成がどのように変化するかをまとめたものがこのグラフです。こういうテーマでお話をすると、必ずこのグラフが出てくるかと思います。
黄緑色の部分が15~64歳で、一般的に生産年齢人口と言われている層です。この人たちのウエートは低下していくでしょう。その一方で、上の方にある青色の部分で示された、65歳以上の人たちは、人数はこれからそれほど増えませんが、比率は高まっていきます。このようにバランスが崩れていくため、どのようにしたらいいかという話をするわけです。世の中全体の支え手が、だんだんと相対的に少なくなっていきます。どうしたらいいでしょうかという問題提起です。
そこで、このグラフを見てください。実は、状況は私たちが想定しているものとは違っており、高齢化と言っても世の中の支え手が比率を落としているわけでは必ずしもないということを認識していただきたいと思います。
1990年、つまり、日本経済がバブルの頂点にあったころをスタートラインにして、下の方に下りている曲線が生産年齢人口です。先ほどのグラフで言うと黄緑色の部分ですが、この比率がどれだけ低下しているかを見ると、この30年ほどで大体10%ポイントほど低下しています。これは支え手が減っているということを示しており、高齢化に対する私たちのイメージに近いと思います。
しかし、よく考えてみると、15歳といっても中学を卒業して、高校に行く人がかなりいます。それから、65歳を過ぎても働いている人がいます。生産年齢人口に属していても働いている人もいれば、いない人もいるということですから、世の中を支えている人はどれだけいるのかを見る場合は、生産年齢人口を見るよりも、むしろ実際に働いている人の比率を見るべきではないでしょうか。それがこの緑色の曲線で示した、就業者の比率です。
これを見ますと、景気の変動の影響は受けているものの、最近では回復基調にあります。1990年をスタートラインにすると、3%ポイントほど上昇しています。ですから、世の中の支え手はむしろ増えているわけで、そのことは認識しておいた方がいいと思います。こういう実態の変化に対して制度が追いついていないのではないかということを考えておく必要があります。
その支え手の増加をけん引している一番重要なのはどの層かを見たのがこの黒い曲線で、65歳以上の人たちになります。高齢者の人たちが世の中の支え手の増加をむしろ引っ張っているという、意外な構図になっているわけです。もちろん、65歳以降になりますと、フルタイムで働く人はそこまで多くはなく、パートタイムで働く人、あるいは被用者ではなくフリーランスとか、あるいは業務委託等々で働く人たちも増えています。後ほどのパネルディスカッションで、こういう働き方の変化をどのように評価するかというのが大きなテーマになるかと思いますが、実態はこのようになっています。
繰り返しますと、世の中の支え手は、むしろ増えています。その支え手の増え方をけん引しているのは高齢者です。その中身も多様化しているということは、ぜひ皆さんの頭の中に置いていただければと思います。
簡単に言えば、世の中を支える人が減って、支えられる人が増えるという、そういう人口のバランスが変わってしまうという状況の下で、どうしたら社会を維持していけるかという問題意識から、いろいろな制度改革が検討されているわけです。現時点で政府から出ているメッセージは、非常に単純明快でして、支えられている人が支える側にできるだけ回れば、何とかうまく行くのではないかということです。そして、支払う能力がある人には今まで以上に負担してもらって、そうでない人は給付をしっかり受ける。そういうことを念頭に置いて、いろいろな制度改革が行われているところです。
高齢化と言われて、私たちの頭の中にはどのような姿が浮かぶでしょうか。昨年、国立社会保障・人口問題研究所がアップデートした、人口の将来推計をベースにして、人口構成がどのように変化するかをまとめたものがこのグラフです。こういうテーマでお話をすると、必ずこのグラフが出てくるかと思います。
黄緑色の部分が15~64歳で、一般的に生産年齢人口と言われている層です。この人たちのウエートは低下していくでしょう。その一方で、上の方にある青色の部分で示された、65歳以上の人たちは、人数はこれからそれほど増えませんが、比率は高まっていきます。このようにバランスが崩れていくため、どのようにしたらいいかという話をするわけです。世の中全体の支え手が、だんだんと相対的に少なくなっていきます。どうしたらいいでしょうかという問題提起です。
そこで、このグラフを見てください。実は、状況は私たちが想定しているものとは違っており、高齢化と言っても世の中の支え手が比率を落としているわけでは必ずしもないということを認識していただきたいと思います。
1990年、つまり、日本経済がバブルの頂点にあったころをスタートラインにして、下の方に下りている曲線が生産年齢人口です。先ほどのグラフで言うと黄緑色の部分ですが、この比率がどれだけ低下しているかを見ると、この30年ほどで大体10%ポイントほど低下しています。これは支え手が減っているということを示しており、高齢化に対する私たちのイメージに近いと思います。
しかし、よく考えてみると、15歳といっても中学を卒業して、高校に行く人がかなりいます。それから、65歳を過ぎても働いている人がいます。生産年齢人口に属していても働いている人もいれば、いない人もいるということですから、世の中を支えている人はどれだけいるのかを見る場合は、生産年齢人口を見るよりも、むしろ実際に働いている人の比率を見るべきではないでしょうか。それがこの緑色の曲線で示した、就業者の比率です。
これを見ますと、景気の変動の影響は受けているものの、最近では回復基調にあります。1990年をスタートラインにすると、3%ポイントほど上昇しています。ですから、世の中の支え手はむしろ増えているわけで、そのことは認識しておいた方がいいと思います。こういう実態の変化に対して制度が追いついていないのではないかということを考えておく必要があります。
その支え手の増加をけん引している一番重要なのはどの層かを見たのがこの黒い曲線で、65歳以上の人たちになります。高齢者の人たちが世の中の支え手の増加をむしろ引っ張っているという、意外な構図になっているわけです。もちろん、65歳以降になりますと、フルタイムで働く人はそこまで多くはなく、パートタイムで働く人、あるいは被用者ではなくフリーランスとか、あるいは業務委託等々で働く人たちも増えています。後ほどのパネルディスカッションで、こういう働き方の変化をどのように評価するかというのが大きなテーマになるかと思いますが、実態はこのようになっています。
繰り返しますと、世の中の支え手は、むしろ増えています。その支え手の増え方をけん引しているのは高齢者です。その中身も多様化しているということは、ぜひ皆さんの頭の中に置いていただければと思います。
2――高齢者の就労と健康
ということで、バックグラウンドのお話は終わりましたので、次に、メインの話に移りたいと思います。今日は、年金を軸にして、高齢者がどのような働き方、あるいは過ごし方をするのかというテーマになるのですが、ここで私たちにとって非常に重要なのは、働くということと健康ということの関係です。
私の経験もそうですが、若いときは結構無理をしても、それほどお医者さんに行かなくてよかったのですが、だんだんと年を取るとお医者さんのお世話になることが多くなりました。今、私は二本の足でちゃんと立っていますが、何年か前に腰部脊柱管狭窄症という病気にかかりました。ご経験のある方もいらっしゃると思いますが、立てなくなりました。そのため、杖をついて歩いていました。整形外科の先生のお世話になり、ようやく歩けるようになったのですが、年を取ると健康面でもいろいろな問題を抱えるようになります。それと就労との関係を見ておきましょう。
私の経験もそうですが、若いときは結構無理をしても、それほどお医者さんに行かなくてよかったのですが、だんだんと年を取るとお医者さんのお世話になることが多くなりました。今、私は二本の足でちゃんと立っていますが、何年か前に腰部脊柱管狭窄症という病気にかかりました。ご経験のある方もいらっしゃると思いますが、立てなくなりました。そのため、杖をついて歩いていました。整形外科の先生のお世話になり、ようやく歩けるようになったのですが、年を取ると健康面でもいろいろな問題を抱えるようになります。それと就労との関係を見ておきましょう。
2―1. 健康が就労に及ぼす影響
まず就労と健康の関係といっても、一方向の因果関係でつながっているのではなく、両方向のベクトルがあります。そこで、まず、健康が就労をどのように作用するのかという因果関係に注目したいと思います。
就労の決定要因として何が問題になるかということですが、ここでは健康だけに注目します。年金とか他の社会保障の制度は無視します。健康であれば、高齢者の就業率をどれだけ高めることができるのか、潜在的にどれぐらい引き上げられるのかという計算を、非常に荒っぽいですがやってみた話をします。
アメリカの有力なシンクタンクで、全米経済研究所、NBERという機関があります。その研究所で、各国のデータを持ち寄って、その計算結果を比べましょうというプロジェクトがありまして、私たちは日本のメンバーとして、そのプロジェクトに参加しました。
そこでは、次のような作業を行いました。一つ目のアプローチとしては、今の高齢者と昔の高齢者を比較しました。昔に比べて今の高齢者は元気だということをよくお聞きになると思いますが、それを実際に見てみたのが、このグラフです。左側が男性、右側が女性です。縦軸は、どれだけの人が働いているかという就業率を示しています。横軸は死亡率です。これは、例えば60歳まで生きた人が61歳までに亡くなる確率は何%かというものを示したものです。だから、死亡率が高くなればなるほど健康状態が悪くなることを示す代理変数だと考えてください。
就業率と死亡率をつなぐと、右下がりのグラフになります。死亡率が高いということは、それだけ健康状態が悪く、年齢の上昇にも対応するわけですが、年齢が上昇すると就業率も低くなるので、右下がりのグラフになります。国勢調査を使って、1980年、2000年、2020年で、そのグラフの位置を調べたのがこちらです。
これを見ると、最近になればなるほどグラフが右下の方にシフトしています。これは何を意味するのか、男性の場合を例にして考えてみます。同じ死亡率4%でも、昔に比べると就業率は落ちています。これは何を意味するかというと、昔の高齢者と今の高齢者を比べたら、健康状態が同じであっても、今の人たちは働かなくなってきているということです。それはなぜかというと、年金制度が充実してきたことや、医療制度が充実して皆さん健康になったからです。これは素晴らしいことです。素晴らしいことですが、冒頭でもお話ししたように、世の中の支え手と支えられ手のバランスが崩れているということを念頭に置くと、もったいないという気もします。そうした状況を示したのがこのグラフです。
もう少し詳しく見ますと、この曲線と下の2本の曲線ではちょっと違いがあります。つまり、1980年から2000年にかけては大きく下にシフトしていますが、2000年以降は大きな変化はありません。これはなぜかというと、1980年代以降、特に1980年代の半ばに大きな年金制度改革が起こりました。昔に比べると年金を厳しくしたのです。それと同じように、2000年に入ってから企業の定年を60歳から65歳に引き上げるという機運が高まって、高齢者でも働くようにしましょうという動きがここで出てきました。
最近に限ると大きな変化はありませんが、30~40年前から比べると高齢者は働かなくなったということです。逆に言えば、もう少し働いてもらっても結構ではないでしょうかとNBERは言いたいわけです。NBERはどちらかというと共和党系のシンクタンクですが、そういう政策提言がここにつながっているということです。
女性についても、そのような傾向が見られますが、男性に比べると少し弱いようです。日本の場合は、女性はこの年齢になるとフルタイムで働く人が少なくなって、パートタイムで働く人が多いため、このような形になっています。しかし、将来はおそらく男性も同じような形になっていくでしょう。
このように、この黒い曲線と青い曲線、赤い曲線の垂直距離を縮める、つまり、もう少し頑張って就業率を引き上げられる、その度合いを示すというのが一つ目のアプローチです。
もう一つのアプローチは、今の高齢者と今の現役世代を比べてみるというものです。今の現役世代のような働き方をすれば、今の高齢者はどれだけ働けるのかということを調べてみるということです。
ちょっと面倒な作業ですが、聞いていただきたいと思います。どのようなことをやったかといいますと、まず、年金をもらう前の50歳代の人たちのデータを見て、健康と就業の関係を調べます。これぐらいの健康状態だったら、これぐらい働けるという関係式を推計します。その関係式が60歳になっても成立すると想定するわけです。これは結構大胆な想定なのですが、健康面に限って言えば、60歳代の人はどれぐらい働いてもおかしくないかという試算をするわけです。健康面だけが問題であったとしたら、60歳代の人たちはどれぐらい働けるか。その一方で、60歳代の人が実際にどれだけ働いているかという就業率があります。その差を取ることにより、どれだけの伸び代があるか、どれだけ就業率を引き上げることができるかが大まかに試算できます。
NBERは、それを各国でやってみろという指令を下しましたので、日本でもやってみたのがこのグラフです。青い部分が、実際にどれぐらいの人が働いたのかを示しています。左が男性、右が女性で、50歳代、60歳代前半、60歳代後半、それから70歳になってからです。健康だけが問題だった場合、どれくらいの比率で働けるのかを聞いているのが、その上に書いてある数字です。例えば60歳代前半ですと、健康面だけが問題であれば88%まで就業率を上げられます。ところが実際には76%ほどしか働いていません。そうすると、健康面だけが問題であったとしたら、そのギャップの分だけ働けるのではないか、そういうことを言いたいというグラフです。もちろん非常に大雑把な想定を置いていますので、特に70歳代を超えると、過大推計ではないかと思いますが、60歳代後半を見てみますと、男性の場合3割ほど、女性の場合2割ほど就業率を引き上げられるという数字が出ており、結構現実的ではないかというような感じがします。もちろん、これは大まかな想定に過ぎなくて、全ての人に働けよということを言いたいがために、このグラフを示しているわけではないのですが、健康面だけを考えたとしたら、もう少し働いていただけるのではないかということを言いたいわけです。
以上が、健康面だけが問題だったとしたら、どれだけ働けるかという話でした。
しかし、高齢者は、実際にはそれほど働いていません。では、何が人々の働く気持ちを萎えさせているのか、何がブレーキになっているのをグラフで示したのが、こちらです。これも各国共通で要因分析をしたものですが、賃金に対してブレーキが何%かかっているかを調べています。これを見ていただくと、一番目立つのが赤い棒です。このグラフは、前回の年金制度改革の前の制度を前提にして描いたものす。後で議論になりますが、60歳代前半でも在職老齢年金という制度がかかっていたのですが、その在職老齢年金がどれだけのブレーキをかけていたのかも分かります。グラフを見ると、赤いところが大きくなっています。ここから、働いたら年金が削られるという仕組みは、人々の働くことに対してやはりブレーキをかけていると言ってよいと思います。今問題になっているのは、60歳代後半の在職老齢年金ですが、これはやはりブレーキになって、人々に働くのに二の足を踏ませていると言えるのではないかと思います。これが一つ目です。
まず就労と健康の関係といっても、一方向の因果関係でつながっているのではなく、両方向のベクトルがあります。そこで、まず、健康が就労をどのように作用するのかという因果関係に注目したいと思います。
就労の決定要因として何が問題になるかということですが、ここでは健康だけに注目します。年金とか他の社会保障の制度は無視します。健康であれば、高齢者の就業率をどれだけ高めることができるのか、潜在的にどれぐらい引き上げられるのかという計算を、非常に荒っぽいですがやってみた話をします。
アメリカの有力なシンクタンクで、全米経済研究所、NBERという機関があります。その研究所で、各国のデータを持ち寄って、その計算結果を比べましょうというプロジェクトがありまして、私たちは日本のメンバーとして、そのプロジェクトに参加しました。
そこでは、次のような作業を行いました。一つ目のアプローチとしては、今の高齢者と昔の高齢者を比較しました。昔に比べて今の高齢者は元気だということをよくお聞きになると思いますが、それを実際に見てみたのが、このグラフです。左側が男性、右側が女性です。縦軸は、どれだけの人が働いているかという就業率を示しています。横軸は死亡率です。これは、例えば60歳まで生きた人が61歳までに亡くなる確率は何%かというものを示したものです。だから、死亡率が高くなればなるほど健康状態が悪くなることを示す代理変数だと考えてください。
就業率と死亡率をつなぐと、右下がりのグラフになります。死亡率が高いということは、それだけ健康状態が悪く、年齢の上昇にも対応するわけですが、年齢が上昇すると就業率も低くなるので、右下がりのグラフになります。国勢調査を使って、1980年、2000年、2020年で、そのグラフの位置を調べたのがこちらです。
これを見ると、最近になればなるほどグラフが右下の方にシフトしています。これは何を意味するのか、男性の場合を例にして考えてみます。同じ死亡率4%でも、昔に比べると就業率は落ちています。これは何を意味するかというと、昔の高齢者と今の高齢者を比べたら、健康状態が同じであっても、今の人たちは働かなくなってきているということです。それはなぜかというと、年金制度が充実してきたことや、医療制度が充実して皆さん健康になったからです。これは素晴らしいことです。素晴らしいことですが、冒頭でもお話ししたように、世の中の支え手と支えられ手のバランスが崩れているということを念頭に置くと、もったいないという気もします。そうした状況を示したのがこのグラフです。
もう少し詳しく見ますと、この曲線と下の2本の曲線ではちょっと違いがあります。つまり、1980年から2000年にかけては大きく下にシフトしていますが、2000年以降は大きな変化はありません。これはなぜかというと、1980年代以降、特に1980年代の半ばに大きな年金制度改革が起こりました。昔に比べると年金を厳しくしたのです。それと同じように、2000年に入ってから企業の定年を60歳から65歳に引き上げるという機運が高まって、高齢者でも働くようにしましょうという動きがここで出てきました。
最近に限ると大きな変化はありませんが、30~40年前から比べると高齢者は働かなくなったということです。逆に言えば、もう少し働いてもらっても結構ではないでしょうかとNBERは言いたいわけです。NBERはどちらかというと共和党系のシンクタンクですが、そういう政策提言がここにつながっているということです。
女性についても、そのような傾向が見られますが、男性に比べると少し弱いようです。日本の場合は、女性はこの年齢になるとフルタイムで働く人が少なくなって、パートタイムで働く人が多いため、このような形になっています。しかし、将来はおそらく男性も同じような形になっていくでしょう。
このように、この黒い曲線と青い曲線、赤い曲線の垂直距離を縮める、つまり、もう少し頑張って就業率を引き上げられる、その度合いを示すというのが一つ目のアプローチです。
もう一つのアプローチは、今の高齢者と今の現役世代を比べてみるというものです。今の現役世代のような働き方をすれば、今の高齢者はどれだけ働けるのかということを調べてみるということです。
ちょっと面倒な作業ですが、聞いていただきたいと思います。どのようなことをやったかといいますと、まず、年金をもらう前の50歳代の人たちのデータを見て、健康と就業の関係を調べます。これぐらいの健康状態だったら、これぐらい働けるという関係式を推計します。その関係式が60歳になっても成立すると想定するわけです。これは結構大胆な想定なのですが、健康面に限って言えば、60歳代の人はどれぐらい働いてもおかしくないかという試算をするわけです。健康面だけが問題であったとしたら、60歳代の人たちはどれぐらい働けるか。その一方で、60歳代の人が実際にどれだけ働いているかという就業率があります。その差を取ることにより、どれだけの伸び代があるか、どれだけ就業率を引き上げることができるかが大まかに試算できます。
NBERは、それを各国でやってみろという指令を下しましたので、日本でもやってみたのがこのグラフです。青い部分が、実際にどれぐらいの人が働いたのかを示しています。左が男性、右が女性で、50歳代、60歳代前半、60歳代後半、それから70歳になってからです。健康だけが問題だった場合、どれくらいの比率で働けるのかを聞いているのが、その上に書いてある数字です。例えば60歳代前半ですと、健康面だけが問題であれば88%まで就業率を上げられます。ところが実際には76%ほどしか働いていません。そうすると、健康面だけが問題であったとしたら、そのギャップの分だけ働けるのではないか、そういうことを言いたいというグラフです。もちろん非常に大雑把な想定を置いていますので、特に70歳代を超えると、過大推計ではないかと思いますが、60歳代後半を見てみますと、男性の場合3割ほど、女性の場合2割ほど就業率を引き上げられるという数字が出ており、結構現実的ではないかというような感じがします。もちろん、これは大まかな想定に過ぎなくて、全ての人に働けよということを言いたいがために、このグラフを示しているわけではないのですが、健康面だけを考えたとしたら、もう少し働いていただけるのではないかということを言いたいわけです。
以上が、健康面だけが問題だったとしたら、どれだけ働けるかという話でした。
しかし、高齢者は、実際にはそれほど働いていません。では、何が人々の働く気持ちを萎えさせているのか、何がブレーキになっているのをグラフで示したのが、こちらです。これも各国共通で要因分析をしたものですが、賃金に対してブレーキが何%かかっているかを調べています。これを見ていただくと、一番目立つのが赤い棒です。このグラフは、前回の年金制度改革の前の制度を前提にして描いたものす。後で議論になりますが、60歳代前半でも在職老齢年金という制度がかかっていたのですが、その在職老齢年金がどれだけのブレーキをかけていたのかも分かります。グラフを見ると、赤いところが大きくなっています。ここから、働いたら年金が削られるという仕組みは、人々の働くことに対してやはりブレーキをかけていると言ってよいと思います。今問題になっているのは、60歳代後半の在職老齢年金ですが、これはやはりブレーキになって、人々に働くのに二の足を踏ませていると言えるのではないかと思います。これが一つ目です。
コンテンツ紹介
-
レポート
-
受託実績・コンサルティング
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る