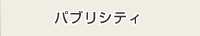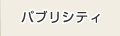- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- パブリシティ >
- イベント(シンポジウム) >
- イベント詳細 >
- 超高齢社会における企業と個人の在り方「プレゼンテーション」
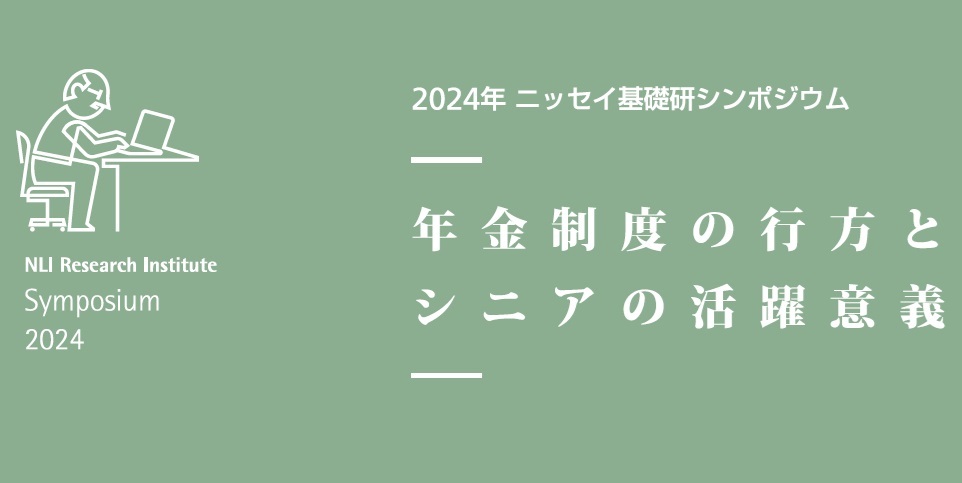
2024年10月22日開催
パネルディスカッション
超高齢社会における企業と個人の在り方「プレゼンテーション」
| パネリスト |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデレータ |
|
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
2024年10月「年金制度の行方とシニアの活躍意義」をテーマにニッセイ基礎研シンポジウムを開催いたしました。
一橋大学経済研究所 特任教授 小塩 隆士氏をお招きして「高齢者の年金・就労・健康を考える」をテーマに講演いただきました。
パネルディスカッションでは「超高齢社会における企業と個人の在り方」をテーマに活発な議論を行っていただきました。
※ 当日資料はこちら
一橋大学経済研究所 特任教授 小塩 隆士氏をお招きして「高齢者の年金・就労・健康を考える」をテーマに講演いただきました。
パネルディスカッションでは「超高齢社会における企業と個人の在り方」をテーマに活発な議論を行っていただきました。
※ 当日資料はこちら
⇒ 基調講演 高齢者の年金・就労・健康を考える
はじめに
■大畑 それではパネルディスカッションに移りたいと思います。当パネルディスカッションのモデレーターを務めますのは、当社取締役研究理事、徳島勝幸でございます。ここからの進行は徳島理事にバトンタッチしたいと思います。それではどうぞよろしくお願いいたします。
■徳島 ニッセイ基礎研究所の徳島でございます。これから1時間少々お付き合いいただけたらと思います。それでは第2部のパネルディスカッションでは、パネリストとして、第1部に続きまして一橋大学経済研究所、特任教授でいらっしゃいます小塩隆士先生、それから東京大学名誉教授の秋山弘子先生、パソナマスターズ代表取締役社長の中田光佐子様、弊社の公的年金調査室長の中嶋邦夫、以上4名の方に参加していただいております。
第1部の小塩様の基調講演、「高齢者の年金・就労・健康を考える」を踏まえて、第2部のパネルディスカッションでは、「超高齢社会における企業と個人の在り方」と題しまして、高齢者の活躍の場、生きがいなどについて、昨今、注目を集めております人的資本経営や、従業員のワーク・ライフ・バランスとか、ウェルビーイングなどのさまざまな論点から、議論をしたいと思います。
最初に、第1部で、小塩様の基調講演の内容に関して、特に最後のウェルビーイング・パラドックス、高齢化と幸福度のところで、日本においても、中国においても、60歳から65歳を過ぎていくと、また幸福度が少し上昇しているというお話を頂きました。これにつきまして、第1部でも、秋山先生のご意見を伺ってみたいというコメントを頂きましたので、秋山先生からコメントを頂戴できたらと思います。よろしくお願いします。
■秋山 秋山でございます。小塩先生から心理学者顔負けの非常に心理学的なお話を頂きまして、非常に興味深く拝聴いたしました。最後のところですが、高齢になると、人生満足度であるとか、ハピネスであるとか、そういうものが高くなるというのは、少なくとも先進国では共通で、おそらく私がまだ学生の頃の40年ぐらい前からそういうことは言われていました。
なぜかということに関しては、小塩先生のお話にありましたように、ネガティブなライフイベントが関係します。今は、退職はハッピーなのかもしれませんが、退職するとか、きょうだいや家族が亡くなるとか、体の具合が悪くなるとかいろいろなことがあるわけです。ですが、高齢になると、なぜか心の穏やかさというか、そういうハピネスみたいな満足度みたいなものは上がるというデータが、どの国でも大体出ているのです。
それについての解釈としては、70年、80年も生きていれば、人生というのが分かって、まあ大体こんなものだろうとか、いろいろあったけど自分もよく頑張ったなというように、そういう満足度みたいなものがあるのではないかとは言われています。超越するということも言われていますが、ただ、それを裏付けるデータはないので、先生がおっしゃったように、いろいろな解釈はあるけれども、まだ臆測の域を出ないということであろうかと思います。
■徳島 ありがとうございます。パネリストで他に、第1部の小塩先生の基調講演に関して何かコメントとかある方がいらっしゃいましたら、挙手をお願いいたします。よろしいですか。では私の方から1つだけお伺いしたいと思います。
小塩先生の基調講演は、かなり多面的なところからメンタルヘルスのところまで、いろいろご講演いただきました。そういった中で、高齢者の就労などに関して、企業に対してどういった役割を期待されているのかについて、この後の議論につながるところで一言コメントを頂けたらと思います。よろしくお願いします。
■小塩 ありがとうございます。私の試算では、就労が続くとメンタルヘルスが悪くなるのではないかという傾向が出てきました。これは原因がないことはなくて、定年前と同じような形で、フルタイムでバリバリ働くということを想定した上で、それで70歳まで働いたらどうなりますかというシミュレーションなのです。ですから、そうするとちょっとつらいなというふうに思われる方も多くなるのではないかなと思います。そのあたりが数字に出てきたのではないかと思います。
これを裏返すと、そうでない働き方が重要になるのではないかと思います。具体的には後で中田さんが説明されるかと思いますが、多様な働き方を許容することが重要ではないかと思います。フルタイムでバリバリ、若い人に負けないで働くという人も、もちろんあってもいいですが、そうではなくて、週に3回ぐらい顔を出そうかな、それ以外は町内の、自治会の仕事をしようかなというふうな人もいるかもしれません。
あるいは働き方も、われわれが働き方改革で想定している場合は、被用者、雇用されるという形態を想定していますが、そうではなく、業務委託とかフリーランスとか、そういう形で、ドライな形で企業と接するということもあっていいと思います。
実は、日本だけではなく、欧米、特にヨーロッパでも高齢者の就業率が回復しているのです。その背景には、もちろん年金が厳しくなって働かないと駄目だというような理由もありますが、働き方が非常に多様化していて、実際にふたを開けてみると、一番コアになるのはもちろん被用者なのですが、それ以外に、フリーランスとか業務委託というような形で働いている人が増えてきているようです。
これは企業にとってもメリットなのです。社会保険料の面倒を見なくてもいい。人件費ではなくて物件費で扱うということで、ドライな関係になれる。しかもそれによって、むしろ働いている人からメリットが受けられるという面もあるかもしれません。ということも含めて、いろいろな働き方を許容するというのが企業に求められることではないかなと思います。
■徳島 ありがとうございます。今、小塩先生から伺った中でも、多様な働き方、そしてそれを認める制度といった形が必要だというご指摘ですが、企業において、どうしても人事制度とか一律的になりがちなところを、いろいろな仕組みを入れていくことが、一つのソリューションになるのかなというお話かと思います。
■徳島 ニッセイ基礎研究所の徳島でございます。これから1時間少々お付き合いいただけたらと思います。それでは第2部のパネルディスカッションでは、パネリストとして、第1部に続きまして一橋大学経済研究所、特任教授でいらっしゃいます小塩隆士先生、それから東京大学名誉教授の秋山弘子先生、パソナマスターズ代表取締役社長の中田光佐子様、弊社の公的年金調査室長の中嶋邦夫、以上4名の方に参加していただいております。
第1部の小塩様の基調講演、「高齢者の年金・就労・健康を考える」を踏まえて、第2部のパネルディスカッションでは、「超高齢社会における企業と個人の在り方」と題しまして、高齢者の活躍の場、生きがいなどについて、昨今、注目を集めております人的資本経営や、従業員のワーク・ライフ・バランスとか、ウェルビーイングなどのさまざまな論点から、議論をしたいと思います。
最初に、第1部で、小塩様の基調講演の内容に関して、特に最後のウェルビーイング・パラドックス、高齢化と幸福度のところで、日本においても、中国においても、60歳から65歳を過ぎていくと、また幸福度が少し上昇しているというお話を頂きました。これにつきまして、第1部でも、秋山先生のご意見を伺ってみたいというコメントを頂きましたので、秋山先生からコメントを頂戴できたらと思います。よろしくお願いします。
■秋山 秋山でございます。小塩先生から心理学者顔負けの非常に心理学的なお話を頂きまして、非常に興味深く拝聴いたしました。最後のところですが、高齢になると、人生満足度であるとか、ハピネスであるとか、そういうものが高くなるというのは、少なくとも先進国では共通で、おそらく私がまだ学生の頃の40年ぐらい前からそういうことは言われていました。
なぜかということに関しては、小塩先生のお話にありましたように、ネガティブなライフイベントが関係します。今は、退職はハッピーなのかもしれませんが、退職するとか、きょうだいや家族が亡くなるとか、体の具合が悪くなるとかいろいろなことがあるわけです。ですが、高齢になると、なぜか心の穏やかさというか、そういうハピネスみたいな満足度みたいなものは上がるというデータが、どの国でも大体出ているのです。
それについての解釈としては、70年、80年も生きていれば、人生というのが分かって、まあ大体こんなものだろうとか、いろいろあったけど自分もよく頑張ったなというように、そういう満足度みたいなものがあるのではないかとは言われています。超越するということも言われていますが、ただ、それを裏付けるデータはないので、先生がおっしゃったように、いろいろな解釈はあるけれども、まだ臆測の域を出ないということであろうかと思います。
■徳島 ありがとうございます。パネリストで他に、第1部の小塩先生の基調講演に関して何かコメントとかある方がいらっしゃいましたら、挙手をお願いいたします。よろしいですか。では私の方から1つだけお伺いしたいと思います。
小塩先生の基調講演は、かなり多面的なところからメンタルヘルスのところまで、いろいろご講演いただきました。そういった中で、高齢者の就労などに関して、企業に対してどういった役割を期待されているのかについて、この後の議論につながるところで一言コメントを頂けたらと思います。よろしくお願いします。
■小塩 ありがとうございます。私の試算では、就労が続くとメンタルヘルスが悪くなるのではないかという傾向が出てきました。これは原因がないことはなくて、定年前と同じような形で、フルタイムでバリバリ働くということを想定した上で、それで70歳まで働いたらどうなりますかというシミュレーションなのです。ですから、そうするとちょっとつらいなというふうに思われる方も多くなるのではないかなと思います。そのあたりが数字に出てきたのではないかと思います。
これを裏返すと、そうでない働き方が重要になるのではないかと思います。具体的には後で中田さんが説明されるかと思いますが、多様な働き方を許容することが重要ではないかと思います。フルタイムでバリバリ、若い人に負けないで働くという人も、もちろんあってもいいですが、そうではなくて、週に3回ぐらい顔を出そうかな、それ以外は町内の、自治会の仕事をしようかなというふうな人もいるかもしれません。
あるいは働き方も、われわれが働き方改革で想定している場合は、被用者、雇用されるという形態を想定していますが、そうではなく、業務委託とかフリーランスとか、そういう形で、ドライな形で企業と接するということもあっていいと思います。
実は、日本だけではなく、欧米、特にヨーロッパでも高齢者の就業率が回復しているのです。その背景には、もちろん年金が厳しくなって働かないと駄目だというような理由もありますが、働き方が非常に多様化していて、実際にふたを開けてみると、一番コアになるのはもちろん被用者なのですが、それ以外に、フリーランスとか業務委託というような形で働いている人が増えてきているようです。
これは企業にとってもメリットなのです。社会保険料の面倒を見なくてもいい。人件費ではなくて物件費で扱うということで、ドライな関係になれる。しかもそれによって、むしろ働いている人からメリットが受けられるという面もあるかもしれません。ということも含めて、いろいろな働き方を許容するというのが企業に求められることではないかなと思います。
■徳島 ありがとうございます。今、小塩先生から伺った中でも、多様な働き方、そしてそれを認める制度といった形が必要だというご指摘ですが、企業において、どうしても人事制度とか一律的になりがちなところを、いろいろな仕組みを入れていくことが、一つのソリューションになるのかなというお話かと思います。
プレゼンテーション
それでは以上の基調講演の振り返りを踏まえまして、今回のテーマである「超高齢社会における企業と個人の在り方というテーマで、ディスカッションに入っていきたいと思います。まず、それぞれのパネリストの皆さんから、ご専門の視点で10分程度ずつプレゼンテーションをお願いしたいと思います。最初に中嶋さんから、次期年金制度改革の方向性についてお願いいたします。
コンテンツ紹介
-
レポート
-
受託実績・コンサルティング
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る