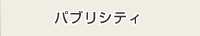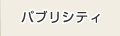- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- パブリシティ >
- イベント(シンポジウム) >
- イベント詳細 >
- 超高齢社会における企業と個人の在り方「プレゼンテーション」
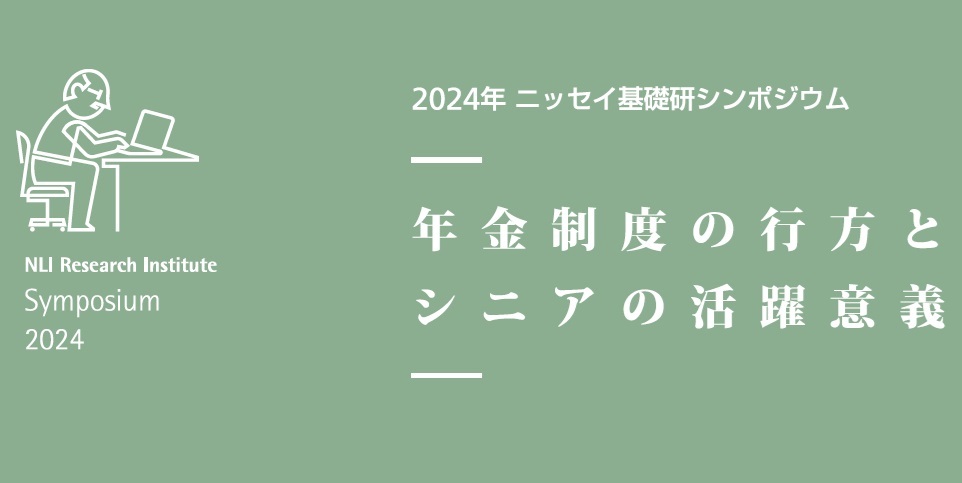
2024年10月22日開催
パネルディスカッション
超高齢社会における企業と個人の在り方「プレゼンテーション」
| パネリスト |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデレータ |
|
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
3――人生100年時代~「長生きを喜べる長寿社会」の実現に必要なこと
■秋山 秋山でございます。私はもともと社会心理学が専門でして、高齢社会というか、私は長寿社会という言葉を好みますが、長寿社会の課題を生活者の立場から常にアプローチしてまいりました。本日もそういう観点からお話をさせていただきたいと思います。スライドが多いので、ちょっと駆け足でまいります。
タイトルは、「人生100年時代」と言われておりますが、「長生きを喜べる長寿社会」の実現にどんなことが必要なのだろうということで、お話をさせていただきます。
タイトルは、「人生100年時代」と言われておりますが、「長生きを喜べる長寿社会」の実現にどんなことが必要なのだろうということで、お話をさせていただきます。
3―1. 長寿社会の課題と可能性
二つありまして、まず初めは、長寿社会の課題と可能性ということで、特に高齢期の就労について焦点を当ててお話をいたします。
これはよくご存じのように、人口の高齢化は、もう地球丸ごと高齢化しております。先月、バリ島で環太平洋の高齢社会の会議がありましたが、もちろん中国やインドとかインドネシアのような、非常に膨大な人口を抱える国が高齢化しているのと同時に、南太平洋の私も名前も知らなかった島の方たちも、高齢化しているというようなことをおっしゃっておりました。
これは、2050年、これから25年先ですが、高齢者が人口の4割を占めると予測されているということです。日本は、人生50年と言われている時代が随分長く、何百年も続いたのですね。そこから比べると、人生が倍近くなっているということで、特に生まれる前は長くなっていないですから、後ろの方に長くなっていまして、大人の生活は80年、特に65歳以上の期間が35年という時代になってきた。そこをどう生きるかということが課題です。
私は長寿社会の課題には、個人と社会と産業界の課題があるというように考えておりますが、今日は個人の課題だけをお話ししたいと思います。私も後期高齢者、働く後期高齢者ですけれども、私たちが若い頃は、男性と女性の生き方も、人生コースが大体決まっていました。エスカレーターみたいにそこにうまく乗っていれば一生が終わったわけですが、今そしてこれからは100年の人生を自ら設計して、かじ取りをしながら生きていく時代になっていくわけです。
従って、ニュー・マップ・オブ・ライフが必要だと。新しい人生航路が必要であるというようなことが言われております。
これがそうですね。普通、銅像というと誰かが彫るものですが、自分で石を刻んで自分自身の体を形づくっていくという、今、これが非常に象徴的なのです。自分の人生を設計して、そしてうまくいかなかったらかじ取りをしながら修正をしていくという生き方です。それはキャリアに関しても同じだということです
二つありまして、まず初めは、長寿社会の課題と可能性ということで、特に高齢期の就労について焦点を当ててお話をいたします。
これはよくご存じのように、人口の高齢化は、もう地球丸ごと高齢化しております。先月、バリ島で環太平洋の高齢社会の会議がありましたが、もちろん中国やインドとかインドネシアのような、非常に膨大な人口を抱える国が高齢化しているのと同時に、南太平洋の私も名前も知らなかった島の方たちも、高齢化しているというようなことをおっしゃっておりました。
これは、2050年、これから25年先ですが、高齢者が人口の4割を占めると予測されているということです。日本は、人生50年と言われている時代が随分長く、何百年も続いたのですね。そこから比べると、人生が倍近くなっているということで、特に生まれる前は長くなっていないですから、後ろの方に長くなっていまして、大人の生活は80年、特に65歳以上の期間が35年という時代になってきた。そこをどう生きるかということが課題です。
私は長寿社会の課題には、個人と社会と産業界の課題があるというように考えておりますが、今日は個人の課題だけをお話ししたいと思います。私も後期高齢者、働く後期高齢者ですけれども、私たちが若い頃は、男性と女性の生き方も、人生コースが大体決まっていました。エスカレーターみたいにそこにうまく乗っていれば一生が終わったわけですが、今そしてこれからは100年の人生を自ら設計して、かじ取りをしながら生きていく時代になっていくわけです。
従って、ニュー・マップ・オブ・ライフが必要だと。新しい人生航路が必要であるというようなことが言われております。
これがそうですね。普通、銅像というと誰かが彫るものですが、自分で石を刻んで自分自身の体を形づくっていくという、今、これが非常に象徴的なのです。自分の人生を設計して、そしてうまくいかなかったらかじ取りをしながら修正をしていくという生き方です。それはキャリアに関しても同じだということです
3―1―1. 人生の発達曲線
私が学生だった50年ぐらい前の話ですが、左側は、これは人生の発達曲線と言われておりまして、私たちはいろいろな能力を持っておりますが、能力というのは大体こうだと。つまり、生まれたときはないけれども、ザーッと伸びて、急速に発達して、20歳ぐらいでピークに達して、しばらくそれを保って、それからだんだん落ちていくのだという、これが発達曲線だというように教科書に載っていたのです。
その後、いろいろな部門の能力の発達を見ると必ずしもそうではない。右側の図は、認知能力は重要な能力ですが、それを一つ取ってみても、認知能力の中で、短期の記憶能力、言語能力、日常問題の解決能力などがあり、発達曲線が違うのです。意味のない数字とか、そういうものを覚えるというような、短期の記憶能力は、先ほどのように20歳ぐらいにピークに達して、その後落ちますが、言語能力は決して30歳になったからといって落ち始めない。日常生活の問題解決能力も非常に重要な能力ですが、年を取っても伸びるというようなデータが出ております。
私が学生だった50年ぐらい前の話ですが、左側は、これは人生の発達曲線と言われておりまして、私たちはいろいろな能力を持っておりますが、能力というのは大体こうだと。つまり、生まれたときはないけれども、ザーッと伸びて、急速に発達して、20歳ぐらいでピークに達して、しばらくそれを保って、それからだんだん落ちていくのだという、これが発達曲線だというように教科書に載っていたのです。
その後、いろいろな部門の能力の発達を見ると必ずしもそうではない。右側の図は、認知能力は重要な能力ですが、それを一つ取ってみても、認知能力の中で、短期の記憶能力、言語能力、日常問題の解決能力などがあり、発達曲線が違うのです。意味のない数字とか、そういうものを覚えるというような、短期の記憶能力は、先ほどのように20歳ぐらいにピークに達して、その後落ちますが、言語能力は決して30歳になったからといって落ち始めない。日常生活の問題解決能力も非常に重要な能力ですが、年を取っても伸びるというようなデータが出ております。
3―1―2. 高齢期の可能性
つまり、人間の能力の変化は多次元で多方向であるということです。多次元というのは、いろいろな能力によって発達の仕方が違う。例えば40歳でもう落ちている能力もあるし、一定の水準を保っているものもあるし、まだ伸びているものもあるということです。従って、人生の各段階で、私たちは能力を最大限に活用して生きるということが重要だということです。
私たちは長く生きるようになっています。こちらの歩行スピードは、非常に簡便な老化の指標として国際的に使われています。普通に歩くスピードです。それを1992年から2017年まで4回にわたって、各年齢別に見ますと、男性も女性も一定して歩行スピードが伸びているのです。ということは、私たちは長生きするだけではなくて、元気で長生きをするようになっているということです。
そして、これは教育の程度になります。私が若いときは、中卒の人が3月になると制服を着て東京の工場に働きに来た、金の卵と呼ばれていたと思います。そういう方は結構多かったですが、今は中卒というのは非常に少なくなり、逆に大学を卒業する人が増えているということで、ひと昔前の高齢者に比べて、今の高齢者は元気でしかも教育を受けて年を取っているという違いがございます。
つまり、人間の能力の変化は多次元で多方向であるということです。多次元というのは、いろいろな能力によって発達の仕方が違う。例えば40歳でもう落ちている能力もあるし、一定の水準を保っているものもあるし、まだ伸びているものもあるということです。従って、人生の各段階で、私たちは能力を最大限に活用して生きるということが重要だということです。
私たちは長く生きるようになっています。こちらの歩行スピードは、非常に簡便な老化の指標として国際的に使われています。普通に歩くスピードです。それを1992年から2017年まで4回にわたって、各年齢別に見ますと、男性も女性も一定して歩行スピードが伸びているのです。ということは、私たちは長生きするだけではなくて、元気で長生きをするようになっているということです。
そして、これは教育の程度になります。私が若いときは、中卒の人が3月になると制服を着て東京の工場に働きに来た、金の卵と呼ばれていたと思います。そういう方は結構多かったですが、今は中卒というのは非常に少なくなり、逆に大学を卒業する人が増えているということで、ひと昔前の高齢者に比べて、今の高齢者は元気でしかも教育を受けて年を取っているという違いがございます。
3―1―3. セカンドライフの空洞化
本題に入ります。定年後をセカンドライフと呼ぶとして、そこの空洞化の問題です。定年までは一生懸命働いてきたけれど、その後の計画を何もしていなかったという人が非常に多い。定年になって花束をもらって帰った次の日から、することがないとか、どこにも行くことがないとか、会いたい人もいない、家族以外に周りの人を知らないという人たちが非常に多いということです。
特に、そこで問題になるのが、I層、II層、III層という分け方をすると、I層というのは専門的なスキルを持っている、上に書いてあるような人たちです。この人たちはあまり心配しなくても、定年がないとか、いろいろな仕事がある。一番下のIII層は、要するに働かないと食べていけないという人たちです。そういう人たちも一定数いるということです。
一番多い、7割、8割の人はII層のところです。いわゆるジェネラリストといいますか、今、サラリーマンという言葉は使いませんけれども、そういう人が多いわけです。その方たちが一番の大きな問題で、セカンドライフの空洞化の対象になります。右に書いてあるのが典型的なII層の方の特性です。
本題に入ります。定年後をセカンドライフと呼ぶとして、そこの空洞化の問題です。定年までは一生懸命働いてきたけれど、その後の計画を何もしていなかったという人が非常に多い。定年になって花束をもらって帰った次の日から、することがないとか、どこにも行くことがないとか、会いたい人もいない、家族以外に周りの人を知らないという人たちが非常に多いということです。
特に、そこで問題になるのが、I層、II層、III層という分け方をすると、I層というのは専門的なスキルを持っている、上に書いてあるような人たちです。この人たちはあまり心配しなくても、定年がないとか、いろいろな仕事がある。一番下のIII層は、要するに働かないと食べていけないという人たちです。そういう人たちも一定数いるということです。
一番多い、7割、8割の人はII層のところです。いわゆるジェネラリストといいますか、今、サラリーマンという言葉は使いませんけれども、そういう人が多いわけです。その方たちが一番の大きな問題で、セカンドライフの空洞化の対象になります。右に書いてあるのが典型的なII層の方の特性です。
3―1―4. 「生きがい就労」創成プロジェクト
東京大学の高齢社会総合研究機構は非常に学際的で、医学部も経済学部も工学部も、皆いろいろ入って、高齢社会の課題を全学の知を結集して解決しようということで立ち上げた組織です。そこで、千葉県の柏市と福井県、ですから首都圏と地方で、長寿社会に対応するまちづくりをしようということで、いろいろなプロジェクトを同時に立ち上げております。その中の一つが、セカンドライフの就労、活躍の場で、それを私たちは担当してきました。
柏市というのは典型的なベッドタウンです。8割以上の方が朝早く家を出て、都心で働いて、夜遅く帰ってくるという生活を四十何年もされて、定年とともに住んでいる柏市に戻って、さあと思ったときに、何をしていいか分からないという方が非常に多い。
何かしたいと思っていても、何をしていいか分からないのです。そういう方に随分聞き取りをしました。そうしますと、まず非常にばらつきがあるということに気が付きました。結局、人生のセカンドライフというのは、マラソンの後半戦と同じで、体力においても、それから自由になる時間、例えば先ほど介護の話が出ましたけれども、介護やお孫さんの世話をするとか、何かやらなくてはいけないことがあって、自由になる時間があまりない人とか、経済力においてもそうだし、いろいろなライフスタイルとか価値観においても非常にばらつきが多い。だから、新卒の学生を雇うこととは全く違うのです。
そういう非常に多様なシニアの人たちが、何をするかということなのですが、話を聞くと、多くの方たちがそのうち何かしようと思いながらやらなくて、家でテレビを見て、時々犬の散歩に行くとかというようなことなのですね。それで、先ほどの小塩先生の話にもありましたが、夫源病というのですか、夫が原因の病気があって、奥さんも非常に困っているし、川柳では「定年後、犬も閉口、5度目の散歩」というのがあるのですが、犬も5回も散歩に連れていかれるともう疲れてしまうわけですよね。
何かそういう現象があるということで、どうしたらいいかと、話をよく聞くと、働くところがあったら一番家から出やすいと言われるのです。それは今までの生活の、ある意味では延長なのです。ただ、今までのように都心に満員電車に揺られて行って、そして夜遅く帰ってくる生活はもう卒業したいし、体力的にも難しいと言われるので、私たちが始めたのは、近場です、住んでいらっしゃる地域になるべくたくさん仕事場を作るというようなことをやりました。
それは、そこの地域にどういう資源があるかによるのですが、柏の場合はもともと農村だったところで、休耕地がたくさんあったりしますので農業とか、他は子育てなどです。今は若い人たちは二人で都心に通勤していますので、保育園とか学童保育とかというニーズがあるということで、そういうところで仕事を作る。そして、なるべくたくさん仕事を作ると同時に、セカンドライフにふさわしい柔軟な働き方ができることも必要でそうしたことにも取り組みました。自分で時間を決めて働ける、また仕事の場は組み合わせてもいいです。農業をやると同時に保育園の朝のお迎えをするというような、自分でうまく組み合わせて働けるような、そういう場と仕組みを作ってきました。
これは仕事なので最低賃金は必ず払うということを、地元の雇用主に約束していただいて、そして、上はいろいろ賃金が違うわけですけれども、そういう形でやったという試みがあります。
そうしますと、ここにありますように、地元で働くと、個人にもいろいろないいことがあるし、社会にとってもいろいろな利点があり、社会の支え合いのバランスを取るということで、こういうことも生涯現役社会の実現の一つの方策ではないかと思います。
昔は介護予防と言われていましたが、今はフレイル、虚弱予防というようなことが言われています。柏の一つの大きなプロジェクトは、フレイル予防のプロジェクトですけれども、そこの研究の結果では、フレイルになる、もちろん運動とか口腔状態とかいろいろあるのですが、一番初めのきっかけは社会性なのです。社会参加、世の中とのつながりがなくなるというところからフレイルが始まるということがありますので、無理のない範囲で働くということが非常に大切であると思います。
東京大学の高齢社会総合研究機構は非常に学際的で、医学部も経済学部も工学部も、皆いろいろ入って、高齢社会の課題を全学の知を結集して解決しようということで立ち上げた組織です。そこで、千葉県の柏市と福井県、ですから首都圏と地方で、長寿社会に対応するまちづくりをしようということで、いろいろなプロジェクトを同時に立ち上げております。その中の一つが、セカンドライフの就労、活躍の場で、それを私たちは担当してきました。
柏市というのは典型的なベッドタウンです。8割以上の方が朝早く家を出て、都心で働いて、夜遅く帰ってくるという生活を四十何年もされて、定年とともに住んでいる柏市に戻って、さあと思ったときに、何をしていいか分からないという方が非常に多い。
何かしたいと思っていても、何をしていいか分からないのです。そういう方に随分聞き取りをしました。そうしますと、まず非常にばらつきがあるということに気が付きました。結局、人生のセカンドライフというのは、マラソンの後半戦と同じで、体力においても、それから自由になる時間、例えば先ほど介護の話が出ましたけれども、介護やお孫さんの世話をするとか、何かやらなくてはいけないことがあって、自由になる時間があまりない人とか、経済力においてもそうだし、いろいろなライフスタイルとか価値観においても非常にばらつきが多い。だから、新卒の学生を雇うこととは全く違うのです。
そういう非常に多様なシニアの人たちが、何をするかということなのですが、話を聞くと、多くの方たちがそのうち何かしようと思いながらやらなくて、家でテレビを見て、時々犬の散歩に行くとかというようなことなのですね。それで、先ほどの小塩先生の話にもありましたが、夫源病というのですか、夫が原因の病気があって、奥さんも非常に困っているし、川柳では「定年後、犬も閉口、5度目の散歩」というのがあるのですが、犬も5回も散歩に連れていかれるともう疲れてしまうわけですよね。
何かそういう現象があるということで、どうしたらいいかと、話をよく聞くと、働くところがあったら一番家から出やすいと言われるのです。それは今までの生活の、ある意味では延長なのです。ただ、今までのように都心に満員電車に揺られて行って、そして夜遅く帰ってくる生活はもう卒業したいし、体力的にも難しいと言われるので、私たちが始めたのは、近場です、住んでいらっしゃる地域になるべくたくさん仕事場を作るというようなことをやりました。
それは、そこの地域にどういう資源があるかによるのですが、柏の場合はもともと農村だったところで、休耕地がたくさんあったりしますので農業とか、他は子育てなどです。今は若い人たちは二人で都心に通勤していますので、保育園とか学童保育とかというニーズがあるということで、そういうところで仕事を作る。そして、なるべくたくさん仕事を作ると同時に、セカンドライフにふさわしい柔軟な働き方ができることも必要でそうしたことにも取り組みました。自分で時間を決めて働ける、また仕事の場は組み合わせてもいいです。農業をやると同時に保育園の朝のお迎えをするというような、自分でうまく組み合わせて働けるような、そういう場と仕組みを作ってきました。
これは仕事なので最低賃金は必ず払うということを、地元の雇用主に約束していただいて、そして、上はいろいろ賃金が違うわけですけれども、そういう形でやったという試みがあります。
そうしますと、ここにありますように、地元で働くと、個人にもいろいろないいことがあるし、社会にとってもいろいろな利点があり、社会の支え合いのバランスを取るということで、こういうことも生涯現役社会の実現の一つの方策ではないかと思います。
昔は介護予防と言われていましたが、今はフレイル、虚弱予防というようなことが言われています。柏の一つの大きなプロジェクトは、フレイル予防のプロジェクトですけれども、そこの研究の結果では、フレイルになる、もちろん運動とか口腔状態とかいろいろあるのですが、一番初めのきっかけは社会性なのです。社会参加、世の中とのつながりがなくなるというところからフレイルが始まるということがありますので、無理のない範囲で働くということが非常に大切であると思います。
3―2. 新たな長寿価値「貢献寿命」という着想
非常に駆け足ですが、もう一つのプロジェクトについてお話ししたいと思います。今、私たちは貢献寿命の延伸ということを提唱しております。
非常に駆け足ですが、もう一つのプロジェクトについてお話ししたいと思います。今、私たちは貢献寿命の延伸ということを提唱しております。
3―2―1. 貢献寿命延伸&GBERプロジェクト
このプロジェクトは、一橋大学、東京大学、ニッセイ基礎研究所、リクルートマネジメントソリューションズによる共同研究です。
秦の始皇帝の頃から、長生きすること、平均寿命を延長することは、人類の長い間の夢でした。それが1970年代に平均寿命が80歳に近くなったときに、結構寿命は長くなったけれども、寝たきりで長く生きている人も目に付くようになったということで、健康寿命ということが言われました。
健康で生きるということは、今も課題ですが、では元気で生きていればそれでいいかということがあります。元気で生きていくということだけではなくて、私たちが今、提唱しているのは、こちらの貢献寿命です。
貢献寿命というのは、社会とつながって、そして役割を持って、必ずしも収入のある仕事だけではなく、何か役割を持って、人から「ありがとう」と言われるような、そういう関わりを持つ人生をなるべく長く保とうということで、貢献寿命という概念を提唱しております。
そのために何ができるかということですが、この辺りは省略します。
一つは、尺度を作って、例えば地域の貢献寿命を測れるとか、そういうこともできるような、個人の尺度と地域の尺度というのを今、作っているところです。
これはスマホアプリで、GBERという名前ですが、地域のいろいろな社会参加の活動、仕事もそうですし、ボランティアもそう、それから生涯学習とかイベントとかを含めて、それが登録した人たちに全部入ってくる。場所がどこで、日にちはこうですよという情報が、全部入ってくる。こうした社会参加の機会の情報が入ってきて、自分の好みとか自分のやりたいこととかをマッチングするというアプリを開発して、それを広めようということもやっております。
また私たちが一つ目指しているのは、モザイク型の就労ということです。モザイク型というのは、みんながフルタイムで働くのではなくて、無理のない範囲で働くために、時間のモザイク、いわゆるワークシェアリングですが、1人分のフルタイムの仕事を3人でうまく調整してやるというのが時間のモザイクです。それから、今はリモートワークもあるので、例えば東京と仙台と鳥取の人たちが一緒に働く、一つの仕事をやるというような空間のモザイクもあります。今、私たちが力を入れてやろうとしているのは、スキルのモザイクです。異なるスキルを持っている人たちをうまく組み合わせて、超能力を持った1人の労働者を作るということを、このツールでやりたいということを考えております。
このプロジェクトは、一橋大学、東京大学、ニッセイ基礎研究所、リクルートマネジメントソリューションズによる共同研究です。
秦の始皇帝の頃から、長生きすること、平均寿命を延長することは、人類の長い間の夢でした。それが1970年代に平均寿命が80歳に近くなったときに、結構寿命は長くなったけれども、寝たきりで長く生きている人も目に付くようになったということで、健康寿命ということが言われました。
健康で生きるということは、今も課題ですが、では元気で生きていればそれでいいかということがあります。元気で生きていくということだけではなくて、私たちが今、提唱しているのは、こちらの貢献寿命です。
貢献寿命というのは、社会とつながって、そして役割を持って、必ずしも収入のある仕事だけではなく、何か役割を持って、人から「ありがとう」と言われるような、そういう関わりを持つ人生をなるべく長く保とうということで、貢献寿命という概念を提唱しております。
そのために何ができるかということですが、この辺りは省略します。
一つは、尺度を作って、例えば地域の貢献寿命を測れるとか、そういうこともできるような、個人の尺度と地域の尺度というのを今、作っているところです。
これはスマホアプリで、GBERという名前ですが、地域のいろいろな社会参加の活動、仕事もそうですし、ボランティアもそう、それから生涯学習とかイベントとかを含めて、それが登録した人たちに全部入ってくる。場所がどこで、日にちはこうですよという情報が、全部入ってくる。こうした社会参加の機会の情報が入ってきて、自分の好みとか自分のやりたいこととかをマッチングするというアプリを開発して、それを広めようということもやっております。
また私たちが一つ目指しているのは、モザイク型の就労ということです。モザイク型というのは、みんながフルタイムで働くのではなくて、無理のない範囲で働くために、時間のモザイク、いわゆるワークシェアリングですが、1人分のフルタイムの仕事を3人でうまく調整してやるというのが時間のモザイクです。それから、今はリモートワークもあるので、例えば東京と仙台と鳥取の人たちが一緒に働く、一つの仕事をやるというような空間のモザイクもあります。今、私たちが力を入れてやろうとしているのは、スキルのモザイクです。異なるスキルを持っている人たちをうまく組み合わせて、超能力を持った1人の労働者を作るということを、このツールでやりたいということを考えております。
3―2―2. まとめ
人生100年時代の理想的な生き方としては、ここにあるように、まず、65歳ぐらいまでは生計のための就労をする。あとは、生きがい就労という言葉がいいかどうかは別としても、無理のない範囲でできるだけ働いて、生涯現役でいて、貢献寿命をできるだけ延ばすというようなことを、社会と企業と個人の努力によって、ぜひ達成したいと思っております。
以上でございます。ご清聴ありがとうございました。
人生100年時代の理想的な生き方としては、ここにあるように、まず、65歳ぐらいまでは生計のための就労をする。あとは、生きがい就労という言葉がいいかどうかは別としても、無理のない範囲でできるだけ働いて、生涯現役でいて、貢献寿命をできるだけ延ばすというようなことを、社会と企業と個人の努力によって、ぜひ達成したいと思っております。
以上でございます。ご清聴ありがとうございました。
⇒ パネルディスカッション 後編 超高齢社会における企業と個人の在り方「討論」
コンテンツ紹介
-
レポート
-
受託実績・コンサルティング
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る