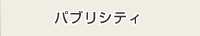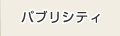- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- パブリシティ >
- イベント(シンポジウム) >
- イベント詳細 >
- 超高齢社会における企業と個人の在り方「プレゼンテーション」
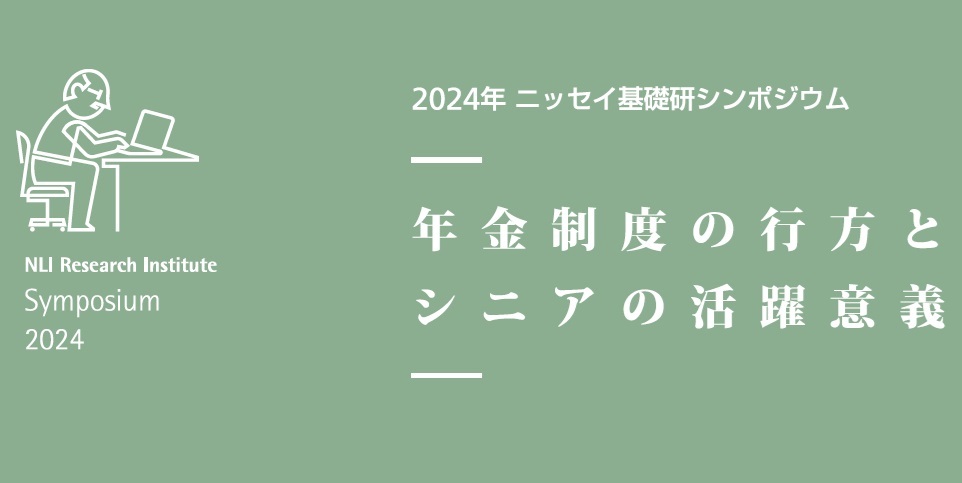
2024年10月22日開催
パネルディスカッション
超高齢社会における企業と個人の在り方「プレゼンテーション」
| パネリスト |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデレータ |
|
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
2――企業におけるシニア活躍の現状とその意義
■中田 改めまして、パソナマスターズの中田でございます。よろしくお願いいたします。
本日は簡単に4点のお話をさせていただきます。
本日は簡単に4点のお話をさせていただきます。
2―1. はじめに
まず初めに、われわれ、パソナマスターズという会社は、パソナグループと申します人材の総合会社で、ミドルとシニア、中高年支援を創業から約22年に亘ってやっております。ここにあります、「人生に定年なし、生涯現役社会の実現を目指して!」ということで、まさに小塩先生と秋山先生とともに、一緒に事業を進めたいなと思いながら、今日のお話を聞かせていただいておりました。
ミドル・シニア層の活躍ということで、二つ大きく掲げております。一つは多様な活躍機会の創出。もう一つは、そういう方々、中高年の現役世代の方を含めて、組織の中でどう活性化しようかということでお悩みの企業様のご支援を行っております。
弊社では、70代を超えたたくさんの方々と一緒にお仕事をしております。コア層は65歳以降ということになりますので、平均年齢が56.4歳の会社になります。
外部のお客さまのご支援や、外部からご相談いただく中高年の支援はしておりますが、弊社の社内においてもシニアを生かすということを毎日奮闘しながら実践しております。今日はそういうところもお話しできたらと思います。
今日は年金に関わるセミナーということで、こちらにありますが、9月30日に経団連が発表しました次期年金制度改正に向けた基本的な見解です。ページを少し抜粋しておりますが、大きくなった文字がこちらのページです。
「今後65歳以降の高齢者の活躍促進にあたって、現在の在職老齢年金が就労意欲にマイナスの影響を与え得るとの指摘などもある」ということで、経団連からこういうものを大きく出していただけるというのは、まさに中高年の支援をしているわれわれとしても非常に追い風になるというところと、どれだけ深刻な人材不足が企業の中で起こって、国を挙げて、経団連を挙げて、高齢者が働きやすい環境づくりをしなくてはいけないというような、強いメッセージが出ているなと思います。
10ページでは、在職老齢年金は将来的に廃止すべきであるという見解をはっきり言い切っております。
13ページには、「企業における高齢社員の活躍は、深刻化する労働力問題への対応の鍵となるだけではなく、高齢社員のエンゲージメント向上を通じてパフォーマンスを高めることで」、実は「企業の生産性向上等にもつながる」ということも書かれています。これもわれわれが日々、いろいろなところでご支援する中で強く感じる内容を、経団連が発表してくれているなというところですので、少し皆さまにご紹介させていただきました。
次のページも、経団連が発表した中から少し抜粋をしています。この次のページと少し重複する部分もありますが、こちらは60代後半以降も働ける制度のある企業の割合は増加しているというデータです。66歳以降、そして70歳以降まで働ける制度がある企業ということです。
ただ、このデータは、大企業ばかりではなく、中小の企業も含めた高齢者の雇用状況の調査結果ということですので、一概に、このデータが全ての会社さんの中で納得できる内容ではないかもしれませんが、定年年齢の引き上げや定年の廃止も視野に入れながら、高齢者のさらなる活躍に向けて、賃金や人事の制度の見直しを図っている会社もこれだけ増えてきているというのが、データで見えていると思います。
まず初めに、われわれ、パソナマスターズという会社は、パソナグループと申します人材の総合会社で、ミドルとシニア、中高年支援を創業から約22年に亘ってやっております。ここにあります、「人生に定年なし、生涯現役社会の実現を目指して!」ということで、まさに小塩先生と秋山先生とともに、一緒に事業を進めたいなと思いながら、今日のお話を聞かせていただいておりました。
ミドル・シニア層の活躍ということで、二つ大きく掲げております。一つは多様な活躍機会の創出。もう一つは、そういう方々、中高年の現役世代の方を含めて、組織の中でどう活性化しようかということでお悩みの企業様のご支援を行っております。
弊社では、70代を超えたたくさんの方々と一緒にお仕事をしております。コア層は65歳以降ということになりますので、平均年齢が56.4歳の会社になります。
外部のお客さまのご支援や、外部からご相談いただく中高年の支援はしておりますが、弊社の社内においてもシニアを生かすということを毎日奮闘しながら実践しております。今日はそういうところもお話しできたらと思います。
今日は年金に関わるセミナーということで、こちらにありますが、9月30日に経団連が発表しました次期年金制度改正に向けた基本的な見解です。ページを少し抜粋しておりますが、大きくなった文字がこちらのページです。
「今後65歳以降の高齢者の活躍促進にあたって、現在の在職老齢年金が就労意欲にマイナスの影響を与え得るとの指摘などもある」ということで、経団連からこういうものを大きく出していただけるというのは、まさに中高年の支援をしているわれわれとしても非常に追い風になるというところと、どれだけ深刻な人材不足が企業の中で起こって、国を挙げて、経団連を挙げて、高齢者が働きやすい環境づくりをしなくてはいけないというような、強いメッセージが出ているなと思います。
10ページでは、在職老齢年金は将来的に廃止すべきであるという見解をはっきり言い切っております。
13ページには、「企業における高齢社員の活躍は、深刻化する労働力問題への対応の鍵となるだけではなく、高齢社員のエンゲージメント向上を通じてパフォーマンスを高めることで」、実は「企業の生産性向上等にもつながる」ということも書かれています。これもわれわれが日々、いろいろなところでご支援する中で強く感じる内容を、経団連が発表してくれているなというところですので、少し皆さまにご紹介させていただきました。
次のページも、経団連が発表した中から少し抜粋をしています。この次のページと少し重複する部分もありますが、こちらは60代後半以降も働ける制度のある企業の割合は増加しているというデータです。66歳以降、そして70歳以降まで働ける制度がある企業ということです。
ただ、このデータは、大企業ばかりではなく、中小の企業も含めた高齢者の雇用状況の調査結果ということですので、一概に、このデータが全ての会社さんの中で納得できる内容ではないかもしれませんが、定年年齢の引き上げや定年の廃止も視野に入れながら、高齢者のさらなる活躍に向けて、賃金や人事の制度の見直しを図っている会社もこれだけ増えてきているというのが、データで見えていると思います。
2―2. 企業における中高年齢者の現状
では、企業の中における中高年齢者の現状です。これは皆さんもご承知かと思いますが、2021年、まさにコロナまっただ中の時に高齢者雇用安定法が改正されまして、70歳までの就業機会の確保措置がスタートしています。これはあくまで努力義務というところなので、義務化まではまだまだ先があるかなというところですが、先ほど小塩先生が被用者というお話をされていたと思いますが、私はこの改正がなされた時に、本当に厚労省が出した内容に身震いがしました。
条文の中に、雇用という言葉ではなくて就業機会という言葉が使われていたのです。決して、必ずしも会社が高齢者を雇い続けるという話ではなく、あくまで就業機会ということで、活躍できる場、就業できる場をたくさん準備し、それを人事制度にして自社の社員に提供しましょうというような内容も含まれています。ただ単に雇用ではなく、業務委託などいろいろな活躍の場、社内外での活躍の場を準備しましょうというところが、まさに高齢者の方々の就業が進んでいる現状の引き金になっているとも感じています。
一方で、ここにあるとおり、70歳までの高齢者のこの制度は、できて3年が経ちますが、まだまだ実施済みと回答されているところは過半数にも行かず、約3割弱です。その中でも、右のグラフにあるとおり、定年制の廃止や定年の引き上げというようなものを実施されているのは7%未満で、まだまだ先は長いかなというところです。
ただ、進めていらっしゃる会社があるということは、必ず、できる仕組みや真似ができる制度があるということですので、そのあたりをわれわれもキャッチアップしながら、いろいろな企業様にお伝えしていければと思っております。
こちらは、先ほどお伝えしたデータと一緒になりますので割愛いたします。
では、実際、深刻な人材不足が進む企業様の中でどういうことが起こっているかです。このグレーの枠を企業の中と見立てたときに、これまで、企業はいろいろな人材採用チャネルでたくさんの人材を雇ってきました。高卒や、地方であれば高専の方々を入れたり、大卒、大学院生だったり、第二新卒、キャリア中途採用というような方々を採用してきましたが、採用難でそういう方々の採用がなかなか難しいのが現状というところです。
それに加えて、国が推し進めている流動化です。今日の日経新聞には少し及び腰というようなことも出ておりましたが、流動化ということで、いろいろな優秀な人材が生産性を上げるために、どんどん世の中に出ていこうというような政策もある中で、若手の働き方改革による離職、中堅層の離職、そして依然として終身雇用性のままで定年退職になる、年齢という区切られた中でご卒業されて、この四角の企業のボックスの中はどんどん人が少なくなっている、人材不足になっているというところです。
併せて、50代、60代になると気力と体力の衰えの中で、どうしても緩やかに仕事をされるようなミドル・シニア層が増えることによって、なかなか活性化せず、そういう方々をどうしたらいいかというところで、今、企業が打っている人材戦略としての一つ目は、ミドル・シニア層の再戦力化と言われるものです。
二つ目は先ほどからお話ししているとおり、シニア層の働く期間を延ばすことで外に出る人を少なくして社内でたくさんの人に活躍していただくことです。
そして三つ目は、今まで採用チャネルとしていなかったシニア層を、新たな採用のリソースとして、外から専門人材、ベテラン人材としてシニアを雇っている、このような会社も増えてきているということです。まさに人材リソース戦略の変化の兆しを非常に強く感じます。
私もパソナマスターズの社長になって6年が経ちまして、今、7年目ですが、社長になった1年目は、どちらかというと、この企業の中にいらっしゃる方が、どのように外で活躍していただく場を探すか、そこに関する施策のご相談が非常に多かったのですが、最近は、中にいる人材をどう活性化するか、そこに関する施策の相談に毎日いろいろとご支援をさせていただいているというところです。
まさにミドル・シニアの再戦力化により企業の中の生産性を上げていこうというところです。
そのために、いろいろな取り組みがなされています。大きく4点あります。
まずはリスキリング機会の提供や、役割の明確化です。同一労働・同一賃金の導入前は、そのままやっていたお仕事を踏襲してできるでしょうというような形で、逆に言うと、何を再雇用中にやったらいいのか明確な指示がないまま、再雇用に入るというような方も多かった中、シニアの皆さまにも、改めてもう一度、どういう役割で活躍してほしいかというような、いわゆるジョブ型のようなマネジメントをスタートされている会社もあります。
そして、多様な活躍の選択肢ということで、ただ単にフル勤務のみならず、再雇用期間に入った場合は、週の出勤日数が選べるような柔軟な人事制度を持ったり、週3日は社内で、週2日は外で越境学習的な社会での活躍ができるような仕組みを持つというような多様な選択肢をご準備されている会社もございます。
そして四つ目は自律的なキャリア形成ということで、そういう日を見越して、40代後半、50代から、いろいろなキャリア形成の場を社員に渡すということで、キャリアコンサルティングやキャリア形成研修など、会社によってはキャリア支援室ということで、独自で人事がそのご支援をされているような会社さんもございます。
その中の企業の事例です。こちらは皆さんもご存じの大手のメーカーさんですが、50代の社員の方の、第2のキャリアの後押しと定義されて、リスキリングの機会を設けています。
会社が通り一遍の研修をするというよりは、希望された方に対してだけ、最大10万円の補助をするということで、これによって資格勉強から起業準備まで、約700人の方が利用されています。これによって、社内での越境体験を得るということで、就業時間の最大2割まで、本来やっていた業務ではないものの経験を積むことができたり、他部署での副業体験ができたり、そして社外でのインターシップの経験をするということで、社内のみならず地方創生のプログラムに入っているような方もいらっしゃいます。
二つ目は役割の明確化です。これもIT大手の会社さんですが、ジョブ型人材マネジメントへのフルモデルチェンジです。ITの会社さんということで、業務の割り振りや業務文書と言われるものが作りやすいというところはありながら、これも随分と時間をかけて作られたモデルになります。
これによって、技術的な、いわゆるスキルギャップが見えて、どういう学びを支援した方がいいのかがわかります。これが逆に、シニア層のみならず若手にまでいい影響を及ぼしているというようなお話も聞いております。
三つ目は自律的なキャリア形成です。われわれが大手の製薬メーカー様にご支援をしている内容となります。定年までの間は、自律的なキャリア形成ということで、いろいろな研修機会やキャリアコンサルティングというようなものを施した後、60歳から65歳の5年間を、リカレント・プログラムと定義付けられています。
まさに今までのキャリアをどう自身の専門にしていくかというジョブ型ですが、約5年間でキャリアの棚卸しをされて、自身の一番の専門職を見つけられた後、そこに、今度は社外に出られたときに、どういうスキルが必要かというようなリスキリングを施された後、65歳以降も、ご卒業後も、まだ元気で働きたいという方は、業界のOB・OGとして活躍される、アフターシニア・プログラムまでご準備されているような会社さんもございます。
ずっと企業の中で学んでこられて、実践され、積んでこられた経験が、ずっと地続きで、卒業後も業界のOBとして活躍できるような、そんな仕組みを作られている会社さんもございます。
では、企業の中における中高年齢者の現状です。これは皆さんもご承知かと思いますが、2021年、まさにコロナまっただ中の時に高齢者雇用安定法が改正されまして、70歳までの就業機会の確保措置がスタートしています。これはあくまで努力義務というところなので、義務化まではまだまだ先があるかなというところですが、先ほど小塩先生が被用者というお話をされていたと思いますが、私はこの改正がなされた時に、本当に厚労省が出した内容に身震いがしました。
条文の中に、雇用という言葉ではなくて就業機会という言葉が使われていたのです。決して、必ずしも会社が高齢者を雇い続けるという話ではなく、あくまで就業機会ということで、活躍できる場、就業できる場をたくさん準備し、それを人事制度にして自社の社員に提供しましょうというような内容も含まれています。ただ単に雇用ではなく、業務委託などいろいろな活躍の場、社内外での活躍の場を準備しましょうというところが、まさに高齢者の方々の就業が進んでいる現状の引き金になっているとも感じています。
一方で、ここにあるとおり、70歳までの高齢者のこの制度は、できて3年が経ちますが、まだまだ実施済みと回答されているところは過半数にも行かず、約3割弱です。その中でも、右のグラフにあるとおり、定年制の廃止や定年の引き上げというようなものを実施されているのは7%未満で、まだまだ先は長いかなというところです。
ただ、進めていらっしゃる会社があるということは、必ず、できる仕組みや真似ができる制度があるということですので、そのあたりをわれわれもキャッチアップしながら、いろいろな企業様にお伝えしていければと思っております。
こちらは、先ほどお伝えしたデータと一緒になりますので割愛いたします。
では、実際、深刻な人材不足が進む企業様の中でどういうことが起こっているかです。このグレーの枠を企業の中と見立てたときに、これまで、企業はいろいろな人材採用チャネルでたくさんの人材を雇ってきました。高卒や、地方であれば高専の方々を入れたり、大卒、大学院生だったり、第二新卒、キャリア中途採用というような方々を採用してきましたが、採用難でそういう方々の採用がなかなか難しいのが現状というところです。
それに加えて、国が推し進めている流動化です。今日の日経新聞には少し及び腰というようなことも出ておりましたが、流動化ということで、いろいろな優秀な人材が生産性を上げるために、どんどん世の中に出ていこうというような政策もある中で、若手の働き方改革による離職、中堅層の離職、そして依然として終身雇用性のままで定年退職になる、年齢という区切られた中でご卒業されて、この四角の企業のボックスの中はどんどん人が少なくなっている、人材不足になっているというところです。
併せて、50代、60代になると気力と体力の衰えの中で、どうしても緩やかに仕事をされるようなミドル・シニア層が増えることによって、なかなか活性化せず、そういう方々をどうしたらいいかというところで、今、企業が打っている人材戦略としての一つ目は、ミドル・シニア層の再戦力化と言われるものです。
二つ目は先ほどからお話ししているとおり、シニア層の働く期間を延ばすことで外に出る人を少なくして社内でたくさんの人に活躍していただくことです。
そして三つ目は、今まで採用チャネルとしていなかったシニア層を、新たな採用のリソースとして、外から専門人材、ベテラン人材としてシニアを雇っている、このような会社も増えてきているということです。まさに人材リソース戦略の変化の兆しを非常に強く感じます。
私もパソナマスターズの社長になって6年が経ちまして、今、7年目ですが、社長になった1年目は、どちらかというと、この企業の中にいらっしゃる方が、どのように外で活躍していただく場を探すか、そこに関する施策のご相談が非常に多かったのですが、最近は、中にいる人材をどう活性化するか、そこに関する施策の相談に毎日いろいろとご支援をさせていただいているというところです。
まさにミドル・シニアの再戦力化により企業の中の生産性を上げていこうというところです。
そのために、いろいろな取り組みがなされています。大きく4点あります。
まずはリスキリング機会の提供や、役割の明確化です。同一労働・同一賃金の導入前は、そのままやっていたお仕事を踏襲してできるでしょうというような形で、逆に言うと、何を再雇用中にやったらいいのか明確な指示がないまま、再雇用に入るというような方も多かった中、シニアの皆さまにも、改めてもう一度、どういう役割で活躍してほしいかというような、いわゆるジョブ型のようなマネジメントをスタートされている会社もあります。
そして、多様な活躍の選択肢ということで、ただ単にフル勤務のみならず、再雇用期間に入った場合は、週の出勤日数が選べるような柔軟な人事制度を持ったり、週3日は社内で、週2日は外で越境学習的な社会での活躍ができるような仕組みを持つというような多様な選択肢をご準備されている会社もございます。
そして四つ目は自律的なキャリア形成ということで、そういう日を見越して、40代後半、50代から、いろいろなキャリア形成の場を社員に渡すということで、キャリアコンサルティングやキャリア形成研修など、会社によってはキャリア支援室ということで、独自で人事がそのご支援をされているような会社さんもございます。
その中の企業の事例です。こちらは皆さんもご存じの大手のメーカーさんですが、50代の社員の方の、第2のキャリアの後押しと定義されて、リスキリングの機会を設けています。
会社が通り一遍の研修をするというよりは、希望された方に対してだけ、最大10万円の補助をするということで、これによって資格勉強から起業準備まで、約700人の方が利用されています。これによって、社内での越境体験を得るということで、就業時間の最大2割まで、本来やっていた業務ではないものの経験を積むことができたり、他部署での副業体験ができたり、そして社外でのインターシップの経験をするということで、社内のみならず地方創生のプログラムに入っているような方もいらっしゃいます。
二つ目は役割の明確化です。これもIT大手の会社さんですが、ジョブ型人材マネジメントへのフルモデルチェンジです。ITの会社さんということで、業務の割り振りや業務文書と言われるものが作りやすいというところはありながら、これも随分と時間をかけて作られたモデルになります。
これによって、技術的な、いわゆるスキルギャップが見えて、どういう学びを支援した方がいいのかがわかります。これが逆に、シニア層のみならず若手にまでいい影響を及ぼしているというようなお話も聞いております。
三つ目は自律的なキャリア形成です。われわれが大手の製薬メーカー様にご支援をしている内容となります。定年までの間は、自律的なキャリア形成ということで、いろいろな研修機会やキャリアコンサルティングというようなものを施した後、60歳から65歳の5年間を、リカレント・プログラムと定義付けられています。
まさに今までのキャリアをどう自身の専門にしていくかというジョブ型ですが、約5年間でキャリアの棚卸しをされて、自身の一番の専門職を見つけられた後、そこに、今度は社外に出られたときに、どういうスキルが必要かというようなリスキリングを施された後、65歳以降も、ご卒業後も、まだ元気で働きたいという方は、業界のOB・OGとして活躍される、アフターシニア・プログラムまでご準備されているような会社さんもございます。
ずっと企業の中で学んでこられて、実践され、積んでこられた経験が、ずっと地続きで、卒業後も業界のOBとして活躍できるような、そんな仕組みを作られている会社さんもございます。
2―3. シニアを生かすことのメリットとその意義
シニアを生かすことのメリットは大きくは三つです。それ以外もたくさんあるかと思いますが、まずは先ほどお伝えしたとおり、人材不足という部分での新しい人材リソース。そして、安心感のあるロールモデルというのは、後輩を含めて、その会社でずっと進んできた先輩が、最後は自身を専門職としてジョブ型にしたり、自分の経験を専門家にしてくれることが、若手の人材にとって、目の前の仕事を愚直に進めると、最後は自身にもああいうキャリアが待っているということが見えることは、非常に素晴らしいロールモデルになると思います。
そして、そうやって元気に働くシニアの姿は、今度は後進のメンバーに、ここにいて、このまま頑張っても大丈夫なんだという、新たな組織の活性化になったり、後進に対していろいろ教えるシニアの方々の生きがいにもつながっていると感じます。
シニアを生かすことというのは、まずはシニアの特性を正しく知って理解することです。私も今、こんなに偉そうに皆さんの前でお話をしていますが、6年前に着任したときに、実は東大のIOG、秋山先生のところのジェロントロジーですとかにいろいろお世話になりながら、シニアというのがどういうものかを非常に勉強させていただきました。
それによって、実は、加齢によって全てを喪失したり衰えるばかりではなく、加齢によっても衰えない能力があったり、加齢ということで、年を重ねることがどんなに素晴らしいことかというのを知ることになりました。
これは結果として、シニアのことを知り、生かすということは、これからわれわれが必ず歩むべき道を知ることになり、実は自分たちがそれを作ることができる、周りのシニアを生かすというのは、必ず自分もそうなる時にもつながるという、最終は自分ごととして返ってくるということを非常に感じさせられます。
そして、年を重ねることが非常に素晴らしいことであり、いろいろなことがまた新たにできるというような新しいイメージを持つことと、先ほど小塩先生のお話にもありました、私はまさにどん底の50代前半なのですが、漠然とした不安ばかりを持つのではなくて、正しく知ることで、実はそういう不安を軽減することが、日々過ごすことの中で非常に重要なことだと思います。
実は私、この前、自分のメンバーにインタビューをしました。70代の、弊社の中で一番のトッププレーヤーというコンサルタントがいるのですが、彼にインタビューをしたら、彼が急に、「実は社長、数字の目標を渡されていることに非常に違和感を感じています」と。実は一番、プレーヤーとして高い数字を出してくれている彼ですが、いろいろな会社の社長もやっていましたが、いつからか、誰かと競い、誰かに評価され、誰かに数字で自分を評価されることに全く興味がなくなったと。なので、数字ではない目標を持たされた方が僕は頑張りますと言われまして、何か間違ったマネジメントをしていたということに気付かされました。
その彼から出た言葉が、「今までとても自己中心的で利己的だったのが、いつからか、誰かの役に立ちたいと、利他的になった」と。彼に言わせると、もしかしたら上手もあるかもしれませんが、彼より少し若い社長が頑張っていることで、社長の役に立ちたいと思うことで、今、頑張っている。メンバーの役に立ちたいということで頑張っているということでした。
それを知ったとき、調べましたら、成人発達理論というものがあることが分かりました。人間というのは、成長期から必ず成熟期になり、これがもしかすると、さっき秋山先生がおっしゃっていたような領域かと思うのですが、そこには利他的なことに魅力を感じて、利他に向かって動きたいと思う、これは人間が本来持っているものというところでした。
こういうものをマネジメントしながらシニアを生かすということがとても大切かなと。それは実は最終的に、シニアを生かすことは企業のブランド向上になります。人材採用等でお悩みの方も、ここにたくさんいらっしゃると思うのですが、必ず1人が1社で勤め上げるだけで終わる人生というのは、これから少なくなると思うのです。社会貢献であっても、転職であっても、必ず自社の看板のブランドを持った社員がどこかでその看板によって仕事をする。そうなったときに、最後、会社に対して良いイメージを持ち、生かされて卒業した方は、その会社のブランドを上げるということをまず理解いただきたいと思います。
そして、先ほどお伝えしたような、シニアの特性を知って、しっかりその人を生かしていくというのは、究極のダイバーシティマネジメントかなと思いますし、今、世の中で言われている真の人的資本経営につながると思っております。
これは、われわれパソナマスターズのちょうど2018年、シニア派遣という事業がスタートしてから丸6年たった分布になるのですが、先ほどのお話にもあったとおり、まさにわれわれのような会社の小さなデータであったとしても、この6年間で約2倍以上、65歳以上の方に就業いただいております。今、稼働者の方々の平均年齢は66.7歳です。
そういう方々がなぜ働き続けるのかという理由に関しては、まさに先ほどお話しした社会とのつながりであったり、自分の存在意義であったり、社会への恩返しであったり、自分が人の役に立てる喜びであったりが理由だと、必ずしも生計だけではないというところをお話しされていました。
これは逆を返すと、これからお仕事の案内をしたり、お客さまから頂く求人票の中に、こういう利他の心をくすぐるようなご依頼内容を頂戴することが、シニアがもっと働きたい、役に立ちたいと、パフォーマンスが高くなるのではないかという、逆のヒントをもらえたような気がします。
シニアを生かすことのメリットは大きくは三つです。それ以外もたくさんあるかと思いますが、まずは先ほどお伝えしたとおり、人材不足という部分での新しい人材リソース。そして、安心感のあるロールモデルというのは、後輩を含めて、その会社でずっと進んできた先輩が、最後は自身を専門職としてジョブ型にしたり、自分の経験を専門家にしてくれることが、若手の人材にとって、目の前の仕事を愚直に進めると、最後は自身にもああいうキャリアが待っているということが見えることは、非常に素晴らしいロールモデルになると思います。
そして、そうやって元気に働くシニアの姿は、今度は後進のメンバーに、ここにいて、このまま頑張っても大丈夫なんだという、新たな組織の活性化になったり、後進に対していろいろ教えるシニアの方々の生きがいにもつながっていると感じます。
シニアを生かすことというのは、まずはシニアの特性を正しく知って理解することです。私も今、こんなに偉そうに皆さんの前でお話をしていますが、6年前に着任したときに、実は東大のIOG、秋山先生のところのジェロントロジーですとかにいろいろお世話になりながら、シニアというのがどういうものかを非常に勉強させていただきました。
それによって、実は、加齢によって全てを喪失したり衰えるばかりではなく、加齢によっても衰えない能力があったり、加齢ということで、年を重ねることがどんなに素晴らしいことかというのを知ることになりました。
これは結果として、シニアのことを知り、生かすということは、これからわれわれが必ず歩むべき道を知ることになり、実は自分たちがそれを作ることができる、周りのシニアを生かすというのは、必ず自分もそうなる時にもつながるという、最終は自分ごととして返ってくるということを非常に感じさせられます。
そして、年を重ねることが非常に素晴らしいことであり、いろいろなことがまた新たにできるというような新しいイメージを持つことと、先ほど小塩先生のお話にもありました、私はまさにどん底の50代前半なのですが、漠然とした不安ばかりを持つのではなくて、正しく知ることで、実はそういう不安を軽減することが、日々過ごすことの中で非常に重要なことだと思います。
実は私、この前、自分のメンバーにインタビューをしました。70代の、弊社の中で一番のトッププレーヤーというコンサルタントがいるのですが、彼にインタビューをしたら、彼が急に、「実は社長、数字の目標を渡されていることに非常に違和感を感じています」と。実は一番、プレーヤーとして高い数字を出してくれている彼ですが、いろいろな会社の社長もやっていましたが、いつからか、誰かと競い、誰かに評価され、誰かに数字で自分を評価されることに全く興味がなくなったと。なので、数字ではない目標を持たされた方が僕は頑張りますと言われまして、何か間違ったマネジメントをしていたということに気付かされました。
その彼から出た言葉が、「今までとても自己中心的で利己的だったのが、いつからか、誰かの役に立ちたいと、利他的になった」と。彼に言わせると、もしかしたら上手もあるかもしれませんが、彼より少し若い社長が頑張っていることで、社長の役に立ちたいと思うことで、今、頑張っている。メンバーの役に立ちたいということで頑張っているということでした。
それを知ったとき、調べましたら、成人発達理論というものがあることが分かりました。人間というのは、成長期から必ず成熟期になり、これがもしかすると、さっき秋山先生がおっしゃっていたような領域かと思うのですが、そこには利他的なことに魅力を感じて、利他に向かって動きたいと思う、これは人間が本来持っているものというところでした。
こういうものをマネジメントしながらシニアを生かすということがとても大切かなと。それは実は最終的に、シニアを生かすことは企業のブランド向上になります。人材採用等でお悩みの方も、ここにたくさんいらっしゃると思うのですが、必ず1人が1社で勤め上げるだけで終わる人生というのは、これから少なくなると思うのです。社会貢献であっても、転職であっても、必ず自社の看板のブランドを持った社員がどこかでその看板によって仕事をする。そうなったときに、最後、会社に対して良いイメージを持ち、生かされて卒業した方は、その会社のブランドを上げるということをまず理解いただきたいと思います。
そして、先ほどお伝えしたような、シニアの特性を知って、しっかりその人を生かしていくというのは、究極のダイバーシティマネジメントかなと思いますし、今、世の中で言われている真の人的資本経営につながると思っております。
これは、われわれパソナマスターズのちょうど2018年、シニア派遣という事業がスタートしてから丸6年たった分布になるのですが、先ほどのお話にもあったとおり、まさにわれわれのような会社の小さなデータであったとしても、この6年間で約2倍以上、65歳以上の方に就業いただいております。今、稼働者の方々の平均年齢は66.7歳です。
そういう方々がなぜ働き続けるのかという理由に関しては、まさに先ほどお話しした社会とのつながりであったり、自分の存在意義であったり、社会への恩返しであったり、自分が人の役に立てる喜びであったりが理由だと、必ずしも生計だけではないというところをお話しされていました。
これは逆を返すと、これからお仕事の案内をしたり、お客さまから頂く求人票の中に、こういう利他の心をくすぐるようなご依頼内容を頂戴することが、シニアがもっと働きたい、役に立ちたいと、パフォーマンスが高くなるのではないかという、逆のヒントをもらえたような気がします。
2―4. まとめ
最後にまとめです。シニアを生かすことは新たな人材リソースになり、組織で歩む道を教えてくれる、安心感のあるロールモデルをたくさん作ることになり、最終は組織の活性化につながります。
その方々を生かすことは究極のダイバーシティマネジメントであり、それが実は企業のブランディング向上、そして真の人的資本経営になると思っております。
人には個々に可能性があり、その可能性をお互いに信じきって、お互いが生かし合うというのは本当に素晴らしいことだなと思いますし、それは、決してシニアを生かすことではなく、最後は自分自身に返ってくる、自分ごとにつながることがシニアを生かすことかなと思っております。
ご清聴ありがとうございました。
■徳島 ありがとうございました。それでは最後になりますけれども、秋山様より、「~人生100年時代~『長生きを喜べる長寿社会』の実現に必要なこと」というプレゼンテーションをお願いいたします。
最後にまとめです。シニアを生かすことは新たな人材リソースになり、組織で歩む道を教えてくれる、安心感のあるロールモデルをたくさん作ることになり、最終は組織の活性化につながります。
その方々を生かすことは究極のダイバーシティマネジメントであり、それが実は企業のブランディング向上、そして真の人的資本経営になると思っております。
人には個々に可能性があり、その可能性をお互いに信じきって、お互いが生かし合うというのは本当に素晴らしいことだなと思いますし、それは、決してシニアを生かすことではなく、最後は自分自身に返ってくる、自分ごとにつながることがシニアを生かすことかなと思っております。
ご清聴ありがとうございました。
■徳島 ありがとうございました。それでは最後になりますけれども、秋山様より、「~人生100年時代~『長生きを喜べる長寿社会』の実現に必要なこと」というプレゼンテーションをお願いいたします。
コンテンツ紹介
-
レポート
-
受託実績・コンサルティング
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る