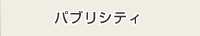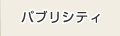- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- パブリシティ >
- イベント(シンポジウム) >
- イベント詳細 >
- 超高齢社会における企業と個人の在り方「プレゼンテーション」
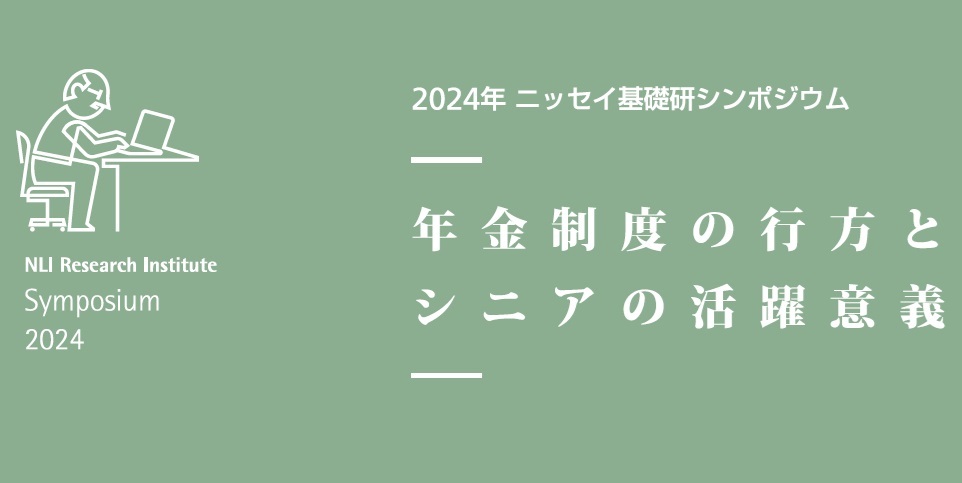
2024年10月22日開催
パネルディスカッション
超高齢社会における企業と個人の在り方「プレゼンテーション」
| パネリスト |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデレータ |
|
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
1――次期年金改革の方向性~高齢期就労との関連を中心に~
■中嶋 中嶋でございます。私からは、次期年金改革の方向性について、高齢期就労との関連を中心にお話しさせていただきます。
1―1. 年金制度改正の年
今年は、年金制度改正の年に当たっております。上の段にありますように、5年に1度行われる国勢調査を起点にして将来の人口の見通しを作成し、年金の将来見通しを少なくとも5年に1度は国民に示すことが、法律によって政府に義務付けられております。それが今年の7月に公表された将来見通しとなります。
これと並行して、一昨年から、社会保障審議会の年金部会が招集されて、次の制度改正にどういったことを行うのかを議論しています。その一部は、この将来見通しの中に、こういう制度改正を行うとこういう結果になる、ああいう制度改正を行うとああいう結果になるという形で入っております。それを踏まえて年末に向けて審議会の意見をまとめて、さらに来年度の通常国会に法案を提出していく、というのが年金改革の流れになっています。
今年は、年金制度改正の年に当たっております。上の段にありますように、5年に1度行われる国勢調査を起点にして将来の人口の見通しを作成し、年金の将来見通しを少なくとも5年に1度は国民に示すことが、法律によって政府に義務付けられております。それが今年の7月に公表された将来見通しとなります。
これと並行して、一昨年から、社会保障審議会の年金部会が招集されて、次の制度改正にどういったことを行うのかを議論しています。その一部は、この将来見通しの中に、こういう制度改正を行うとこういう結果になる、ああいう制度改正を行うとああいう結果になるという形で入っております。それを踏まえて年末に向けて審議会の意見をまとめて、さらに来年度の通常国会に法案を提出していく、というのが年金改革の流れになっています。
1―2. 次期制度改正の方向性
次の年金制度改正の方向性ですが、政府は大きく三つの柱を打ち出しています。一つが左上にある働き方に中立的な制度。もう一つが隣にある高齢期の経済基盤安定や所得保障・再分配の強化。そして三つ目が左下にあるライフスタイル等の多様化への対応です。一昨年から議論を始めまして、既に見送りになっているものも幾つかあります。例えば、今年の春先にテレビなどで話題になりました基礎年金の拠出期間の延長、あるいは障害年金の見直しというところが、今回は見送るという方向性になっています。
上の方では、働き方に中立的な制度と高齢期の経済基盤安定の二つに分かれておりますが、働き方に中立的な制度の中身を見てみますと、例えば、厚生年金の適用拡大というのは将来受け取れる厚生年金の金額を増やそうという制度改正ですし、あるいは在職老齢年金というのは減額の制度を廃止して受け取る年金額を増やそうという制度改正になっています。
このように制度改正全体としてみれば、やはり高齢期の経済基盤の安定というところが大きなテーマになっています。これには、現在の年金制度の仕組みが大きく影響しています。
現在の年金制度は、2004年に改正されたものがベースになっています。2004年にどういう制度改正が行われたかといいますと、保険料が自然体よりも低めで打ち止めされることになりました。この図の赤い点線で書いておりますが、2004年の改革当時の年金の給付水準を将来にわたって維持しようと思うと、厚生年金の場合、会社と本人の合計で、給料の23%の保険料を払わないとやっていけない、という見通しが出ました。ところが、当時の保険料の水準は13%くらいでしたので、倍近く上がるのはかなわないということで、企業側も従業員側も反対しました。そのため、最終的には間を取ったような、18.3%で打ち止めにすることになりました。
年金の保険料が思ったほど上がらないということはメリットに感じられるかもしれませんが、その当時の給付水準を将来にわたって維持できないということになりましたので、年金の水準をだんだんと下げていく仕組みが入りました。
それがマクロ経済スライドと呼ばれている仕組みでして、現役世代の減少や長寿化に連動する形で、だんだんと年金の水準を目減りさせていきます。健全化したらその目減りを停止するわけですが、いつ年金財政が健全化するかは、将来の人口や経済の状況によって変わってきます。
たくさんパターンが出ていますが、例えば経済が比較的成長した場合ですと、大体、現在と比べると1割弱ぐらいの目減りになる。経済が過去30年を投影したような予想に基づくと、大体、2割弱ぐらいの目減りになる。残念ながら1人当たりの成長率がゼロのような状況が今後100年ずっと続くとすると、年金の水準は5割ぐらいになってしまう。このような見通しになっています。
次の年金制度改正の方向性ですが、政府は大きく三つの柱を打ち出しています。一つが左上にある働き方に中立的な制度。もう一つが隣にある高齢期の経済基盤安定や所得保障・再分配の強化。そして三つ目が左下にあるライフスタイル等の多様化への対応です。一昨年から議論を始めまして、既に見送りになっているものも幾つかあります。例えば、今年の春先にテレビなどで話題になりました基礎年金の拠出期間の延長、あるいは障害年金の見直しというところが、今回は見送るという方向性になっています。
上の方では、働き方に中立的な制度と高齢期の経済基盤安定の二つに分かれておりますが、働き方に中立的な制度の中身を見てみますと、例えば、厚生年金の適用拡大というのは将来受け取れる厚生年金の金額を増やそうという制度改正ですし、あるいは在職老齢年金というのは減額の制度を廃止して受け取る年金額を増やそうという制度改正になっています。
このように制度改正全体としてみれば、やはり高齢期の経済基盤の安定というところが大きなテーマになっています。これには、現在の年金制度の仕組みが大きく影響しています。
現在の年金制度は、2004年に改正されたものがベースになっています。2004年にどういう制度改正が行われたかといいますと、保険料が自然体よりも低めで打ち止めされることになりました。この図の赤い点線で書いておりますが、2004年の改革当時の年金の給付水準を将来にわたって維持しようと思うと、厚生年金の場合、会社と本人の合計で、給料の23%の保険料を払わないとやっていけない、という見通しが出ました。ところが、当時の保険料の水準は13%くらいでしたので、倍近く上がるのはかなわないということで、企業側も従業員側も反対しました。そのため、最終的には間を取ったような、18.3%で打ち止めにすることになりました。
年金の保険料が思ったほど上がらないということはメリットに感じられるかもしれませんが、その当時の給付水準を将来にわたって維持できないということになりましたので、年金の水準をだんだんと下げていく仕組みが入りました。
それがマクロ経済スライドと呼ばれている仕組みでして、現役世代の減少や長寿化に連動する形で、だんだんと年金の水準を目減りさせていきます。健全化したらその目減りを停止するわけですが、いつ年金財政が健全化するかは、将来の人口や経済の状況によって変わってきます。
たくさんパターンが出ていますが、例えば経済が比較的成長した場合ですと、大体、現在と比べると1割弱ぐらいの目減りになる。経済が過去30年を投影したような予想に基づくと、大体、2割弱ぐらいの目減りになる。残念ながら1人当たりの成長率がゼロのような状況が今後100年ずっと続くとすると、年金の水準は5割ぐらいになってしまう。このような見通しになっています。
1―3. 就労の延長と繰り下げ受給
このように年金の水準が目減りしていくわけですが、それを補う手立てとして、政府は一つの例を出しております。それが、就労の延長と、年金の受給開始の延期、いわゆる繰り下げ受給というものの組み合わせになります。
下の表は少し込み入っていますが、一番左にあるのが現在の高齢者の年金の水準です。これを100としますと、先ほどご覧いただいたいろいろなパターンの中で、一番真ん中のケースで、大体18%ぐらい目減りしますので、100という水準が82という水準になります。
ただこれは、いわゆるモデル世帯、60歳まで40年間働くというパターンで、仮に65歳まで働くようになると、5%上乗せされることになります。さらに、もう少し働いて年金の受け取りを大体2~3年延期すると、元の100という水準を回復できるような、こういう見通しになっています。
今、年金の受け取り始めを遅らせるということをお話ししましたが、実は現状ではあまり行われていません。これは、先ほど小塩先生からも冒頭でお話がありましたが、現在は60代前半の年金というのが経過措置のような形で出ておりまして、この60代前半の年金は受け取りを延期することができません。そのため、いったん年金を受け取って、その後に65歳以降の年金を延期する必要があるということで、煩雑な手続きになります。
ただ、上の方に書きましたように、男性は2025年、女性は2030年に、年金の支給開始年齢が65歳に上がります。そうしますと、右下にありますように、年金の受給を経験せずに65歳からの年金を繰り下げできるということで、単純で実行しやすくなると言われております。
このように年金の水準が目減りしていくわけですが、それを補う手立てとして、政府は一つの例を出しております。それが、就労の延長と、年金の受給開始の延期、いわゆる繰り下げ受給というものの組み合わせになります。
下の表は少し込み入っていますが、一番左にあるのが現在の高齢者の年金の水準です。これを100としますと、先ほどご覧いただいたいろいろなパターンの中で、一番真ん中のケースで、大体18%ぐらい目減りしますので、100という水準が82という水準になります。
ただこれは、いわゆるモデル世帯、60歳まで40年間働くというパターンで、仮に65歳まで働くようになると、5%上乗せされることになります。さらに、もう少し働いて年金の受け取りを大体2~3年延期すると、元の100という水準を回復できるような、こういう見通しになっています。
今、年金の受け取り始めを遅らせるということをお話ししましたが、実は現状ではあまり行われていません。これは、先ほど小塩先生からも冒頭でお話がありましたが、現在は60代前半の年金というのが経過措置のような形で出ておりまして、この60代前半の年金は受け取りを延期することができません。そのため、いったん年金を受け取って、その後に65歳以降の年金を延期する必要があるということで、煩雑な手続きになります。
ただ、上の方に書きましたように、男性は2025年、女性は2030年に、年金の支給開始年齢が65歳に上がります。そうしますと、右下にありますように、年金の受給を経験せずに65歳からの年金を繰り下げできるということで、単純で実行しやすくなると言われております。
1―4. 在職老齢年金
この年金の受け取りを延期している間は収入がないので、働こうという方も多いわけですが、高いお給料で働くと年金の減額の対象になってしまいます。
年金の受け取りを遅らせる繰り下げ受給をしますと、その期間は実際には年金を受け取ってはいないわけですが、もし受け取っていたらこのぐらいだという年金額と、その時に受け取っている給料で、減額になるかどうかが判定されます。もし減額の対象になるようでしたら、その減額分を差し引いた残りが割増の対象になるということです。このあたりが、せっかく年金の受け取りを遅らせると割増になるのに、その意欲が削がれてしまうのではないかということで、厚生労働省も問題視しております。
ただ、働いている方の全員が年金を減額されるわけではありません。在職時の減額の仕組みをごく簡単に申し上げますと、月当たりの給料と厚生年金の合計が基準額を超えると、減額の対象になります。この基準額というのは、現役の男性の平均的な給料が基準になっておりまして、今年度の場合は50万円ということになります。65歳以上で50万円以上の収入がある方ということになりますと、ある程度限られてまいります。
少し前の統計にはなりますけれども、この2021年度当時の減額の対象になる方は、65歳以上で働いて厚生年金に入っておられる方の17%ぐらいということで、上位2割の方ということになります。この在職老齢年金の減額の廃止を行うと、こういう高所得の方が有利になるということで、金持ち優遇という批判が出たりします。
あるいは、この減額を気にして働くのを控えているのではないか、ということがよく言われます。しかし、実際のデータを見てみますと、赤丸で囲ったところのように、この引っかかるところの手前で少し山になっているところが、控えている方だと思われます。この方々は、1.2%、3万人ぐらいしかいないということで、あまり影響はないのではないかと言われたりします。
ただ、意識調査などを見てみますと、60代前半の方の半分ぐらいは、やはり減額を気にして働き方を減らそうとしている。あるいは60代後半でも、4割ぐらいの方が減額を気にされているということです。制度としては、先ほどお話ししたようにある程度高い基準額にはなっているのですが、その基準額の高さを知らずに就労を控えている方も少なからずおられるのではないかと思います。
ですので、今回の制度改正で、もしこの減額廃止が大きく打ち出されますと、そういうふうに知らずに控えていた方々にも、働こうかなという刺激になるのではないかなと思っております。
この年金の受け取りを延期している間は収入がないので、働こうという方も多いわけですが、高いお給料で働くと年金の減額の対象になってしまいます。
年金の受け取りを遅らせる繰り下げ受給をしますと、その期間は実際には年金を受け取ってはいないわけですが、もし受け取っていたらこのぐらいだという年金額と、その時に受け取っている給料で、減額になるかどうかが判定されます。もし減額の対象になるようでしたら、その減額分を差し引いた残りが割増の対象になるということです。このあたりが、せっかく年金の受け取りを遅らせると割増になるのに、その意欲が削がれてしまうのではないかということで、厚生労働省も問題視しております。
ただ、働いている方の全員が年金を減額されるわけではありません。在職時の減額の仕組みをごく簡単に申し上げますと、月当たりの給料と厚生年金の合計が基準額を超えると、減額の対象になります。この基準額というのは、現役の男性の平均的な給料が基準になっておりまして、今年度の場合は50万円ということになります。65歳以上で50万円以上の収入がある方ということになりますと、ある程度限られてまいります。
少し前の統計にはなりますけれども、この2021年度当時の減額の対象になる方は、65歳以上で働いて厚生年金に入っておられる方の17%ぐらいということで、上位2割の方ということになります。この在職老齢年金の減額の廃止を行うと、こういう高所得の方が有利になるということで、金持ち優遇という批判が出たりします。
あるいは、この減額を気にして働くのを控えているのではないか、ということがよく言われます。しかし、実際のデータを見てみますと、赤丸で囲ったところのように、この引っかかるところの手前で少し山になっているところが、控えている方だと思われます。この方々は、1.2%、3万人ぐらいしかいないということで、あまり影響はないのではないかと言われたりします。
ただ、意識調査などを見てみますと、60代前半の方の半分ぐらいは、やはり減額を気にして働き方を減らそうとしている。あるいは60代後半でも、4割ぐらいの方が減額を気にされているということです。制度としては、先ほどお話ししたようにある程度高い基準額にはなっているのですが、その基準額の高さを知らずに就労を控えている方も少なからずおられるのではないかと思います。
ですので、今回の制度改正で、もしこの減額廃止が大きく打ち出されますと、そういうふうに知らずに控えていた方々にも、働こうかなという刺激になるのではないかなと思っております。
1―5. パートへの厚生年金適用拡大
また、先ほどお示ししました今回の制度改正の項目の中で、企業や働き方に影響する項目としては、厚生年金の適用拡大、あるいは「年収の壁」というものもございます。
厚生年金の適用拡大といいますと、パート労働者の方が話題の中心になっています。パート労働者の方が厚生年金の対象になるかどうかということに関しては、幾つかの要件がありますが、次の制度改正に向けては、規模要件、いわゆる法人の正社員の人数の要件を撤廃するというところで、現時点では大筋合意ということになっております。
この企業規模の要件は経過措置になっておりまして、段階的に拡大されており、今年の10月、まさに現在ですが、50人を超えるところが新しく対象になってきたということになります。さらに次の制度改正では、それを広げて、この条件をなくすというところで大筋合意になっております。
もう一方、パートタイムの方と年金といいますと、いわゆる「年収の壁」ということで、昨年ぐらいに大きく話題になりました。これに関しては、パートタイムの方が厚生年金に該当するかを判定する賃金ですとか、あるいは時間の要件というのがあって、例えば経団連はこの引き下げを要望していました。しかし、国民年金保険料とのバランスや、あるいはその方を被用者として認めていいのかというところの決着がつかず、今回は見送りということになりました。
パートタイムの方への厚生年金の適用拡大というと、専業主婦の方をイメージされる方も多いかと思うのですが、高齢期の働き方にもだいぶ影響してまいります。先ほどの小塩先生のお話にも少しありましたが、60代前半の、特に男性だけ見てみますと、正規として働く方が増えてきてはいますが、女性あるいは60代後半ということになりますと、非正規で働いている方が増えてきているという状況になります。
社会保障制度をなるべく年収の壁なく広げるということになると、こういった方々も厚生年金の対象になってくる、適用拡大というのが影響してくるわけです。
そのため、年金の充実ということと同時に、この就労抑制の回避が大事になるのではないかと思っております。私からは以上になります。
■徳島 ありがとうございます。1点、余談で申し上げておきますと、今回の年金改革の前提となる経済前提を見ているときに、前回の5年前と今回で違ったのが、労働参加率がかなり上昇しているといった現象がはっきり確認できました。中でも、高齢層の労働参加が増えているというのが、5年前に予想したものよりも顕著に出ていたことが、今後の年金財政にも大きな影響があると考えております。ありがとうございました。
それでは続きまして、中田様より、「企業におけるシニア活躍の現状とその意義」について、ご発表をお願いいたします。
また、先ほどお示ししました今回の制度改正の項目の中で、企業や働き方に影響する項目としては、厚生年金の適用拡大、あるいは「年収の壁」というものもございます。
厚生年金の適用拡大といいますと、パート労働者の方が話題の中心になっています。パート労働者の方が厚生年金の対象になるかどうかということに関しては、幾つかの要件がありますが、次の制度改正に向けては、規模要件、いわゆる法人の正社員の人数の要件を撤廃するというところで、現時点では大筋合意ということになっております。
この企業規模の要件は経過措置になっておりまして、段階的に拡大されており、今年の10月、まさに現在ですが、50人を超えるところが新しく対象になってきたということになります。さらに次の制度改正では、それを広げて、この条件をなくすというところで大筋合意になっております。
もう一方、パートタイムの方と年金といいますと、いわゆる「年収の壁」ということで、昨年ぐらいに大きく話題になりました。これに関しては、パートタイムの方が厚生年金に該当するかを判定する賃金ですとか、あるいは時間の要件というのがあって、例えば経団連はこの引き下げを要望していました。しかし、国民年金保険料とのバランスや、あるいはその方を被用者として認めていいのかというところの決着がつかず、今回は見送りということになりました。
パートタイムの方への厚生年金の適用拡大というと、専業主婦の方をイメージされる方も多いかと思うのですが、高齢期の働き方にもだいぶ影響してまいります。先ほどの小塩先生のお話にも少しありましたが、60代前半の、特に男性だけ見てみますと、正規として働く方が増えてきてはいますが、女性あるいは60代後半ということになりますと、非正規で働いている方が増えてきているという状況になります。
社会保障制度をなるべく年収の壁なく広げるということになると、こういった方々も厚生年金の対象になってくる、適用拡大というのが影響してくるわけです。
そのため、年金の充実ということと同時に、この就労抑制の回避が大事になるのではないかと思っております。私からは以上になります。
■徳島 ありがとうございます。1点、余談で申し上げておきますと、今回の年金改革の前提となる経済前提を見ているときに、前回の5年前と今回で違ったのが、労働参加率がかなり上昇しているといった現象がはっきり確認できました。中でも、高齢層の労働参加が増えているというのが、5年前に予想したものよりも顕著に出ていたことが、今後の年金財政にも大きな影響があると考えております。ありがとうございました。
それでは続きまして、中田様より、「企業におけるシニア活躍の現状とその意義」について、ご発表をお願いいたします。
コンテンツ紹介
-
レポート
-
受託実績・コンサルティング
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る