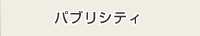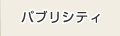- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- パブリシティ >
- イベント(シンポジウム) >
- イベント詳細 >
- 激変する経済安全保障環境「経済安全保障を成長機会に変えるには」
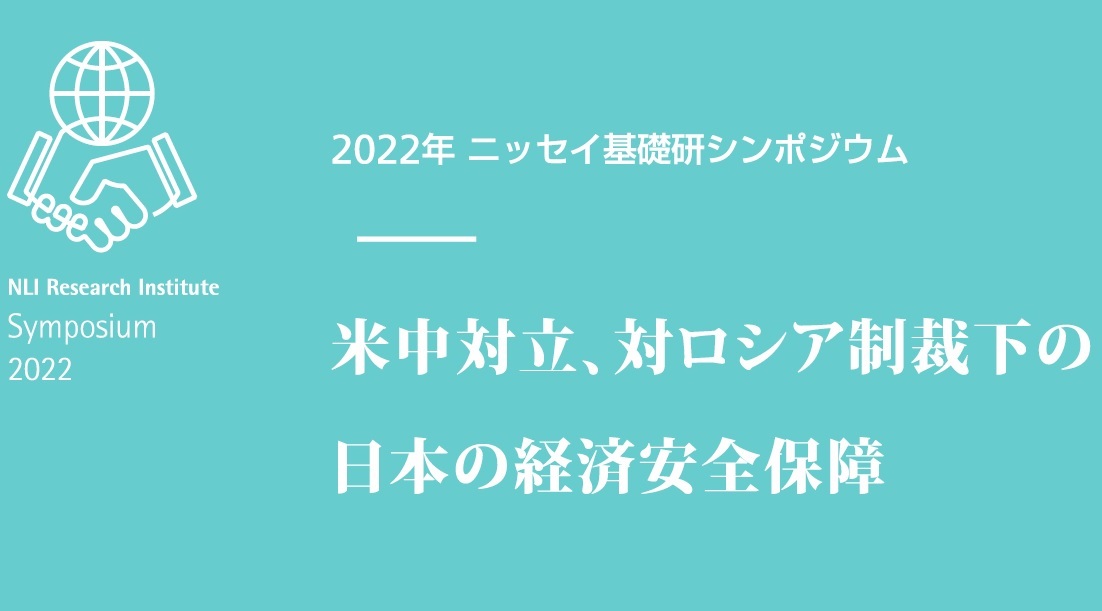
2022年10月13日開催
パネルディスカッション
激変する経済安全保障環境「経済安全保障を成長機会に変えるには」
| パネリスト |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コーディネーター |
|
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
■伊藤 ありがとうございます。日本の経済安全保障の議論で常に意識されている相手方というのが中国市場、中国経済ということになるわけですが、これは皆さまにお尋ねしたいと思っております。
兼原様からは、中国は戦争のリスクありということを念頭に置いて対応策を備える必要があるというお話を頂きました。私は兼原様とある研究会でご一緒させていただいていて、そのときに習近平主席とお会いになられたときの印象論のような話をされたのが非常に心に残っております。習近平主席は共産党大会を経て恐らく3期目に入っていくということになると思うのですが、そもそもの非常に大きな話にはなってしまうのですが、中国経済のリスクはやはり高まっていく方向にあるのか。
それから、戦争リスクという側面もそうなのですが、経済安全保障として威圧の手段を行使する度合いを高めていくとそもそも考えておくべきなのか。それとも、一方で中国自身も非常に経済安全保障的なものに対する意識を高めて、内向き化するリスクもあるのではないかというふうに私は懸念を持っております。習近平3期目の中国はどういうふうに動いていくのかといったところについて皆さま方からお話を伺えればと思うのですが、兼原様、矢嶋様、山本様、鈴木様という順番でお願いできればと思います。
■兼原 ありがとうございます。私たちは中国とは全然違う国なので、中国がどういう原理で動いているかというのを考える必要があります。毛沢東という人があの国を作ってから、「大躍進」で数千万が餓死して、その後、毛沢東を排斥しようとする動きが出るのですけれども、これを毛沢東がひっくり返して「文化大革命」というのをやります。子どもを動員して「造反有理」等と唆して、社会全体を破壊し、自らに抵抗しそうな共産党のエリート層を完全につぶしたわけです。彼はそうやって生き残ったのです。その結果、彼が死んだ1976年には、中国はぼろぼろでした。10年間全く教育を受けていない世代が育った。それが習近平たちの世代です。
毛沢東の死後鄧小平時代から中国の発展が始まって、うまく軌道に乗ったかなと思う頃に、残念ながら天安門事件が起きるのです。これは東欧とソ連が崩壊したからです。中国共産党も消えてなくなると彼らは恐怖したわけです。だから、やらなくてもいい子どもの虐殺をやってしまったわけです。
鄧小平が偉かったのは、子飼いの改革派の胡耀邦と趙紫陽は切りましたけれども、それでもやはり国を開けて外資を入れた。ただ、そのとき彼がやった譲歩は、絶対に共産党独裁は負けません、民主化はしません、共産党は永遠ですということを彼は誓った上で経済的にだけ国を開けたのです。これは体は開いても心は閉ざした攘夷開国だったので。本当の開国ではなかったのです。中国共産党のの最終的な目的は常に共産党の存続です。これが一番根っこにあるのです。
彼らが急激に伸びてきてやっているのは、軍民融合や富国強兵です。中国は元の国力を取り返す、中国共産党の下で中国は世界最強の国になるのだということをやってきたわけです。中国は、ロシアのようにいきなり暴力的なことはやりませんので、いろいろな国際機関の中で味方を増やして、自分たちの地位を上げていこうと真面目にやってきたのですけれども、中国はやはり私たちとは違います。
例えば彼らの電子情報産業がすごく伸びたのは、これは14億人を監視するためです。よく上海の交通がコンピューターで管理されていて素晴らしいとか、中国はキャッシュレスが進んでいるとか、いろいろなことをおっしゃる方がいらっしゃいますが、あれは14億人をスパコンで監視するためです。現金を使わせないのは、全ての個人の消費行動の統計を取るためです。だから、彼らの電子情報技術は驚くほど急激に発展したのです。
今、習近平の下で何が起きているかというと、実は逆向きのことが起きていて、先進コンピューター技術を使った金融機関のアリババとか、共産党を超える力を持った金融組織の存在を許さないという方針が見えてきました。市場経済に共産党が権力維持のために手を突っ込み始めた。経済音痴が経済政策に過剰介入すると、中国経済にガタが来ます。不動産会社も締め付けられています。中国のGDPは日本の3倍ありますけれども、その3分の1は不動産関連なのです。紅衛兵時代に青春を過ごした習近平はイデオロギー性が強いので、不動産会社がぼろもうけをしていると国民が怒っているとなると、つぶしてみようかと考えます。あのエバーグランデをつぶしてしまったわけです。共産党の支配を揺るがせるような経済発展は許さないということで、習近平は若干逆向きのことを始めているということです。
アメリカは対中技術輸出を厳しく締めてくるというのは中国も分かっています。彼らはアメリカとの関係では最終的には長期的な競争に勝つと思いこんでいますから、何をやるかといいますと、例えば半導体内製化です。これは私たちもやっているわけですけれども、戦争が始まったら、半導体市場は逼迫するとお互いに思っているので、習近平も内製化に入っています。それはアメリカも日本もそうです。
中国指導部は、最後は台湾を巡って米国と戦争かもしれないといつも思っている人たちですから、エネルギー安保にも配慮しています。私たち日本人は、石油を半年分、戦略備蓄してあります。しかし青空タンクなので、ミサイルで簡単に吹っ飛びます。その後は毎日20万tタンカーが15隻入ってこないと、この国は倒れます。それもあってサハリンから油を少し入れていたのです。最近プーチンがウクライナ侵略をやってしまったので、あれも止めるか止めないかという話になっていますけれども。実は、日本の経済安全保障で最も遅れているのは、エネルギー分野と安全保障分野の政策的統合です。
これに対し、中国は恐ろしい勢いでパイプラインをトルクメニスタンに引き、カザフスタンに引き、マラッカ海峡を通らなくてもいいようにミャンマーのチャウピューやパキスタンのグワーダル港を開けているのです。エネルギー安全保障、輸入減の多角化、エネルギー輸送路の多様化と確保など、抜かりがありません。彼らは初めから自分たちの体制が生き残るための戦略を組んでいるわけであって、経済はその道具に過ぎません。何があっても自分たち中国共産党は生き残る、そのための態勢を組んでいく。それは対外的にも国内的にも同じだということだと思います。
兼原様からは、中国は戦争のリスクありということを念頭に置いて対応策を備える必要があるというお話を頂きました。私は兼原様とある研究会でご一緒させていただいていて、そのときに習近平主席とお会いになられたときの印象論のような話をされたのが非常に心に残っております。習近平主席は共産党大会を経て恐らく3期目に入っていくということになると思うのですが、そもそもの非常に大きな話にはなってしまうのですが、中国経済のリスクはやはり高まっていく方向にあるのか。
それから、戦争リスクという側面もそうなのですが、経済安全保障として威圧の手段を行使する度合いを高めていくとそもそも考えておくべきなのか。それとも、一方で中国自身も非常に経済安全保障的なものに対する意識を高めて、内向き化するリスクもあるのではないかというふうに私は懸念を持っております。習近平3期目の中国はどういうふうに動いていくのかといったところについて皆さま方からお話を伺えればと思うのですが、兼原様、矢嶋様、山本様、鈴木様という順番でお願いできればと思います。
■兼原 ありがとうございます。私たちは中国とは全然違う国なので、中国がどういう原理で動いているかというのを考える必要があります。毛沢東という人があの国を作ってから、「大躍進」で数千万が餓死して、その後、毛沢東を排斥しようとする動きが出るのですけれども、これを毛沢東がひっくり返して「文化大革命」というのをやります。子どもを動員して「造反有理」等と唆して、社会全体を破壊し、自らに抵抗しそうな共産党のエリート層を完全につぶしたわけです。彼はそうやって生き残ったのです。その結果、彼が死んだ1976年には、中国はぼろぼろでした。10年間全く教育を受けていない世代が育った。それが習近平たちの世代です。
毛沢東の死後鄧小平時代から中国の発展が始まって、うまく軌道に乗ったかなと思う頃に、残念ながら天安門事件が起きるのです。これは東欧とソ連が崩壊したからです。中国共産党も消えてなくなると彼らは恐怖したわけです。だから、やらなくてもいい子どもの虐殺をやってしまったわけです。
鄧小平が偉かったのは、子飼いの改革派の胡耀邦と趙紫陽は切りましたけれども、それでもやはり国を開けて外資を入れた。ただ、そのとき彼がやった譲歩は、絶対に共産党独裁は負けません、民主化はしません、共産党は永遠ですということを彼は誓った上で経済的にだけ国を開けたのです。これは体は開いても心は閉ざした攘夷開国だったので。本当の開国ではなかったのです。中国共産党のの最終的な目的は常に共産党の存続です。これが一番根っこにあるのです。
彼らが急激に伸びてきてやっているのは、軍民融合や富国強兵です。中国は元の国力を取り返す、中国共産党の下で中国は世界最強の国になるのだということをやってきたわけです。中国は、ロシアのようにいきなり暴力的なことはやりませんので、いろいろな国際機関の中で味方を増やして、自分たちの地位を上げていこうと真面目にやってきたのですけれども、中国はやはり私たちとは違います。
例えば彼らの電子情報産業がすごく伸びたのは、これは14億人を監視するためです。よく上海の交通がコンピューターで管理されていて素晴らしいとか、中国はキャッシュレスが進んでいるとか、いろいろなことをおっしゃる方がいらっしゃいますが、あれは14億人をスパコンで監視するためです。現金を使わせないのは、全ての個人の消費行動の統計を取るためです。だから、彼らの電子情報技術は驚くほど急激に発展したのです。
今、習近平の下で何が起きているかというと、実は逆向きのことが起きていて、先進コンピューター技術を使った金融機関のアリババとか、共産党を超える力を持った金融組織の存在を許さないという方針が見えてきました。市場経済に共産党が権力維持のために手を突っ込み始めた。経済音痴が経済政策に過剰介入すると、中国経済にガタが来ます。不動産会社も締め付けられています。中国のGDPは日本の3倍ありますけれども、その3分の1は不動産関連なのです。紅衛兵時代に青春を過ごした習近平はイデオロギー性が強いので、不動産会社がぼろもうけをしていると国民が怒っているとなると、つぶしてみようかと考えます。あのエバーグランデをつぶしてしまったわけです。共産党の支配を揺るがせるような経済発展は許さないということで、習近平は若干逆向きのことを始めているということです。
アメリカは対中技術輸出を厳しく締めてくるというのは中国も分かっています。彼らはアメリカとの関係では最終的には長期的な競争に勝つと思いこんでいますから、何をやるかといいますと、例えば半導体内製化です。これは私たちもやっているわけですけれども、戦争が始まったら、半導体市場は逼迫するとお互いに思っているので、習近平も内製化に入っています。それはアメリカも日本もそうです。
中国指導部は、最後は台湾を巡って米国と戦争かもしれないといつも思っている人たちですから、エネルギー安保にも配慮しています。私たち日本人は、石油を半年分、戦略備蓄してあります。しかし青空タンクなので、ミサイルで簡単に吹っ飛びます。その後は毎日20万tタンカーが15隻入ってこないと、この国は倒れます。それもあってサハリンから油を少し入れていたのです。最近プーチンがウクライナ侵略をやってしまったので、あれも止めるか止めないかという話になっていますけれども。実は、日本の経済安全保障で最も遅れているのは、エネルギー分野と安全保障分野の政策的統合です。
これに対し、中国は恐ろしい勢いでパイプラインをトルクメニスタンに引き、カザフスタンに引き、マラッカ海峡を通らなくてもいいようにミャンマーのチャウピューやパキスタンのグワーダル港を開けているのです。エネルギー安全保障、輸入減の多角化、エネルギー輸送路の多様化と確保など、抜かりがありません。彼らは初めから自分たちの体制が生き残るための戦略を組んでいるわけであって、経済はその道具に過ぎません。何があっても自分たち中国共産党は生き残る、そのための態勢を組んでいく。それは対外的にも国内的にも同じだということだと思います。
■伊藤 ありがとうございました。矢嶋さん、いかがでしょうか。
■矢嶋 体制などいろいろなものが10年、20年かけてどうなっているかということを考えるときに、中国に成長で屈折が起きないかということが一つ大きなテーマなのかなといつも思っています。どういうことかというと、2000年ぐらいから中国が実際に10%成長を始めた環境を考えると、いろいろなものをある意味技術なども盗んで、コストもかけずに作り、成長を達成して来たのだと思うのですが、今後を考えると、経済安保の話が広がるということは、恐らく安くいろいろなものを入手することができなくなるし、人口構成で見たときに、これからびっくりするほど高齢化が進む国になるというのが中国の姿なのだと思うのです。
そういう意味では、少しここで成長屈折が起きる可能性があるとすると、その帰結がまだちょっと分からないのですが、対アメリカとの関係を考えたときに、軍事力や経済力などいろいろな部分で肩を並べる状況になったら、本当に対抗していくのか、それとも先の成長屈折が見えている状況になると、前倒しでいろいろなことを始めていくのかという、様々なシナリオが見えるかと思うのです。私自身は経済の専門家というところから考えると、中国のこの先の体制を考える上で、成長屈折がここ10年ぐらいで起こるのかどうかというのが、中国を見る上で非常に重要なポイントなのではないかと思っています。以上です。
■矢嶋 体制などいろいろなものが10年、20年かけてどうなっているかということを考えるときに、中国に成長で屈折が起きないかということが一つ大きなテーマなのかなといつも思っています。どういうことかというと、2000年ぐらいから中国が実際に10%成長を始めた環境を考えると、いろいろなものをある意味技術なども盗んで、コストもかけずに作り、成長を達成して来たのだと思うのですが、今後を考えると、経済安保の話が広がるということは、恐らく安くいろいろなものを入手することができなくなるし、人口構成で見たときに、これからびっくりするほど高齢化が進む国になるというのが中国の姿なのだと思うのです。
そういう意味では、少しここで成長屈折が起きる可能性があるとすると、その帰結がまだちょっと分からないのですが、対アメリカとの関係を考えたときに、軍事力や経済力などいろいろな部分で肩を並べる状況になったら、本当に対抗していくのか、それとも先の成長屈折が見えている状況になると、前倒しでいろいろなことを始めていくのかという、様々なシナリオが見えるかと思うのです。私自身は経済の専門家というところから考えると、中国のこの先の体制を考える上で、成長屈折がここ10年ぐらいで起こるのかどうかというのが、中国を見る上で非常に重要なポイントなのではないかと思っています。以上です。
■伊藤 ありがとうございました。山本様、お願いします。
■山本 ありがとうございます。私は対中リスクをどう今後変化していくかという観点で見ていると、リスクは減らないと思います。ただ、どういうリスクが高まっているのかというのは、データから見ていくことが重要だと感じます。
特に経年の変化を捉えていくこと、例えば中国がどういう業種や企業を支配しようとしているのかを数カ月、1年単位で見ているだけでも、強く投資したいところの領域が分かります。また少し前に言われていた千人計画に代表されるような、最先端の研究者たちがどういったところと手を組んでいるのか、あるいはどういう地域に散らばっているのかという情報があふれておりましたが、半年、1年でそういったウェブサイトが意図的に消されてしまっています。こういったところでも中国側の何らかの意志を捉えることができると思います。
別の観点で行った研究があります。「人民日報」の記事に対するウェイボーの反応を解析したことがあり、ネガティブやポジティブといったどういった記事が人々の関心があるかということをしばらく解析していたのです。クローリングは怪しまれて止められたという経緯もあるのですが。その中で、ある記事については人々がすごく支持していて、ただ意外なところにネガティブな反応が出ているということもデータで捉えることができます。
こういったことを年次や四半期、月次、日次で追っていくと、明らかに高まっているリスク、それに加えてチャンスのようなところも捉えられると思いますので、こういったところから情報提供できる可能性があるのではないかと思っております。
■山本 ありがとうございます。私は対中リスクをどう今後変化していくかという観点で見ていると、リスクは減らないと思います。ただ、どういうリスクが高まっているのかというのは、データから見ていくことが重要だと感じます。
特に経年の変化を捉えていくこと、例えば中国がどういう業種や企業を支配しようとしているのかを数カ月、1年単位で見ているだけでも、強く投資したいところの領域が分かります。また少し前に言われていた千人計画に代表されるような、最先端の研究者たちがどういったところと手を組んでいるのか、あるいはどういう地域に散らばっているのかという情報があふれておりましたが、半年、1年でそういったウェブサイトが意図的に消されてしまっています。こういったところでも中国側の何らかの意志を捉えることができると思います。
別の観点で行った研究があります。「人民日報」の記事に対するウェイボーの反応を解析したことがあり、ネガティブやポジティブといったどういった記事が人々の関心があるかということをしばらく解析していたのです。クローリングは怪しまれて止められたという経緯もあるのですが。その中で、ある記事については人々がすごく支持していて、ただ意外なところにネガティブな反応が出ているということもデータで捉えることができます。
こういったことを年次や四半期、月次、日次で追っていくと、明らかに高まっているリスク、それに加えてチャンスのようなところも捉えられると思いますので、こういったところから情報提供できる可能性があるのではないかと思っております。
■伊藤 ありがとうございました。鈴木様、お願いします。
■鈴木 経済安全保障の問題を考える上で重要になってくるのは、経済安全保障というのはあくまで手段の問題であって、ある種の政治的な意図、ないしは目指すところ、ないしは外交関係の中でそれが果たして手段として使えるかどうかということがポイントになってくると思っています。
その点で、これから習近平第3期目が始まって、2027年、32年と延びていく中で、果たして習近平自身ないしは中国自身がどのような政治を行っていこうとしているのか、どのような世界をつくろうとしているのか、果たしてアメリカとの関係をどういうふうに制御しようとしているのかということを考えますと、恐らくこれから、先ほど矢嶋さんからも話がありましたけれども、かなり中国自身が抱えている問題があって、いつまでも経済成長が続くということではないと。
そうなっていくと、やはり大国としてどうやって自分たちは生き残っていくのか、ないしは自分たちがアメリカや他の国から負けないようにするにはどうしたらいいのかという選択をしていくことになっていくだろうと思います。その際に、武力を使って攻撃することは中国にとっても必ずしもメリットではないということを考えますと、今後経済的なエコノミック・ステイトクラフト、つまり経済的な攻撃手段というのはかなり多用してくる可能性があるのではないかと。
つまり、それによって他国に威圧をかけ、そして途上国に対しては例えば一帯一路における投資や「債務の罠」のようなことが言われますけれども、さまざまな形で国際金融を通じて影響力を行使しようとしていく。そうすることによって中国もいわゆるフレンドショアリングというか、自分の仲間を増やしていこうとする。そういうことをやって自分たちのシマに手を出すなということで、逆に西側諸国の影響力の排除を目指していくような方向性が見えてくるのではないかと思います。
もちろんシナリオは一つではないので、さまざまなことが可能性としてあるのですが、今後の傾向としてそうした威圧の手段として経済を使っていくという可能性はどんどん高まっていきますし、中国は独自の技術開発、先ほど千人計画の話が山本さんから出ましたけれども、千人計画のような、自分たちが弱みになっている、つまり自分たちが持っていない技術は人を招くというか、引き抜いてくる形でそこを強化し、また自分たちが優位になっている技術については圧倒的な投資をかけてその優位性を伸ばしていって、日本やアメリカが中国に依存するような状況をつくり出そうとしている。そういう観点からしますと、やはり中国はこれからも経済的な手段を使って、他国に対する攻撃ができるような準備、つまり依存度を高めるような状況をつくっていくと同時に、自国にはフレンドショアリングのような形で資源やエネルギーを確保するルートをつくっていこうとするという傾向が恐らく見えてくるのではないかと考えています。
■鈴木 経済安全保障の問題を考える上で重要になってくるのは、経済安全保障というのはあくまで手段の問題であって、ある種の政治的な意図、ないしは目指すところ、ないしは外交関係の中でそれが果たして手段として使えるかどうかということがポイントになってくると思っています。
その点で、これから習近平第3期目が始まって、2027年、32年と延びていく中で、果たして習近平自身ないしは中国自身がどのような政治を行っていこうとしているのか、どのような世界をつくろうとしているのか、果たしてアメリカとの関係をどういうふうに制御しようとしているのかということを考えますと、恐らくこれから、先ほど矢嶋さんからも話がありましたけれども、かなり中国自身が抱えている問題があって、いつまでも経済成長が続くということではないと。
そうなっていくと、やはり大国としてどうやって自分たちは生き残っていくのか、ないしは自分たちがアメリカや他の国から負けないようにするにはどうしたらいいのかという選択をしていくことになっていくだろうと思います。その際に、武力を使って攻撃することは中国にとっても必ずしもメリットではないということを考えますと、今後経済的なエコノミック・ステイトクラフト、つまり経済的な攻撃手段というのはかなり多用してくる可能性があるのではないかと。
つまり、それによって他国に威圧をかけ、そして途上国に対しては例えば一帯一路における投資や「債務の罠」のようなことが言われますけれども、さまざまな形で国際金融を通じて影響力を行使しようとしていく。そうすることによって中国もいわゆるフレンドショアリングというか、自分の仲間を増やしていこうとする。そういうことをやって自分たちのシマに手を出すなということで、逆に西側諸国の影響力の排除を目指していくような方向性が見えてくるのではないかと思います。
もちろんシナリオは一つではないので、さまざまなことが可能性としてあるのですが、今後の傾向としてそうした威圧の手段として経済を使っていくという可能性はどんどん高まっていきますし、中国は独自の技術開発、先ほど千人計画の話が山本さんから出ましたけれども、千人計画のような、自分たちが弱みになっている、つまり自分たちが持っていない技術は人を招くというか、引き抜いてくる形でそこを強化し、また自分たちが優位になっている技術については圧倒的な投資をかけてその優位性を伸ばしていって、日本やアメリカが中国に依存するような状況をつくり出そうとしている。そういう観点からしますと、やはり中国はこれからも経済的な手段を使って、他国に対する攻撃ができるような準備、つまり依存度を高めるような状況をつくっていくと同時に、自国にはフレンドショアリングのような形で資源やエネルギーを確保するルートをつくっていこうとするという傾向が恐らく見えてくるのではないかと考えています。
■伊藤 ありがとうございました。矢嶋さんの問題提起の中で、中国との緊密な結び付きというご指摘がありました。それから、日本がこれだけグローバル化しているのかというお話もありました。実際、日本企業のグローバル展開というのは80年代以降、着実に進んできて、海外で事業を持っている国、事業を展開している企業数も非常に増えています。その中にあって、中国市場が特別だと思うのは、中小規模の企業も含めて非常に裾野の広い日本企業が現地でビジネスを展開しているということです。
先ほど、リスクを管理しながら中国ビジネスは展開すべきなのだというお話を兼原様から頂いたわけなのですが、ただ一方で中小企業のことが心配であるというご指摘も頂きました。実は私も、いろいろなAIの解析によるソリューションの提供、それからサプライチェーンを管理していくという意味でも、大企業はそういうものに対する対応力を持っているけれども、中小企業がそういうトレンドに乗り切れずにビジネスチャンスを逃すことになってしまうのではないか、結果として日本の産業基盤が弱くなってしまうのではないかという危惧を抱いております。その点について、山本様、それから矢嶋さんのお二人にお願いできますでしょうか。
■山本 ありがとうございます。おっしゃるとおりで、今、われわれのところに具体的にご相談来てくださる企業は100%大企業、しかもグローバルで展開していらっしゃる超大手といわれる企業です。そういった企業では経済安全保障室も立ち上がっていて、担当の役員もいらっしゃって、もちろん調達や購買、資材部などいろいろな方たちがプロジェクトとして関わっていらっしゃるという状況です。一方で中堅・中小で非常に技術力があるところに対しては、まだわれわれとして何かご支援できる機会はないということです。
また、業界団体や官公庁とお話をさせていただく中で、そういった仕組み化、政府と例えばわれわれが一緒に組んで支援するということはできるのではないかと思っておりますし、業界団体と一緒にご支援することもできると思います。そういった新しい取り組みについては、われわれとしてもいろいろな工夫や検討をしていきたいと思っております。
先ほど、リスクを管理しながら中国ビジネスは展開すべきなのだというお話を兼原様から頂いたわけなのですが、ただ一方で中小企業のことが心配であるというご指摘も頂きました。実は私も、いろいろなAIの解析によるソリューションの提供、それからサプライチェーンを管理していくという意味でも、大企業はそういうものに対する対応力を持っているけれども、中小企業がそういうトレンドに乗り切れずにビジネスチャンスを逃すことになってしまうのではないか、結果として日本の産業基盤が弱くなってしまうのではないかという危惧を抱いております。その点について、山本様、それから矢嶋さんのお二人にお願いできますでしょうか。
■山本 ありがとうございます。おっしゃるとおりで、今、われわれのところに具体的にご相談来てくださる企業は100%大企業、しかもグローバルで展開していらっしゃる超大手といわれる企業です。そういった企業では経済安全保障室も立ち上がっていて、担当の役員もいらっしゃって、もちろん調達や購買、資材部などいろいろな方たちがプロジェクトとして関わっていらっしゃるという状況です。一方で中堅・中小で非常に技術力があるところに対しては、まだわれわれとして何かご支援できる機会はないということです。
また、業界団体や官公庁とお話をさせていただく中で、そういった仕組み化、政府と例えばわれわれが一緒に組んで支援するということはできるのではないかと思っておりますし、業界団体と一緒にご支援することもできると思います。そういった新しい取り組みについては、われわれとしてもいろいろな工夫や検討をしていきたいと思っております。
■伊藤 ありがとうございました。矢嶋さん、お願いします。
■矢嶋 二つ重要なのかなと思うのですが、一つは、中小企業は大企業に比べて圧倒的に情報やデータのようなものが少ないので、それをどうやって確保するのかというのを、いろいろなルートで考えていくのが一つポイントになると思います。それからもう一つは、やはり自分では限界があるというのも真実だと思うので、日本企業を考えたときに、海外からものすごく批判されながらもずっと構築してきている、系列とか取引のある日本企業との関係の中で、信頼できる取引先と一緒に海外展開していくというのが、中小・中堅企業の方々にとって、現実的な解になるのではないかと思います。
■矢嶋 二つ重要なのかなと思うのですが、一つは、中小企業は大企業に比べて圧倒的に情報やデータのようなものが少ないので、それをどうやって確保するのかというのを、いろいろなルートで考えていくのが一つポイントになると思います。それからもう一つは、やはり自分では限界があるというのも真実だと思うので、日本企業を考えたときに、海外からものすごく批判されながらもずっと構築してきている、系列とか取引のある日本企業との関係の中で、信頼できる取引先と一緒に海外展開していくというのが、中小・中堅企業の方々にとって、現実的な解になるのではないかと思います。
■伊藤 ありがとうございました。大変興味深いお話ばかりで、もっともっと深めていきたい論点がたくさんあるのですが、残ったお時間が4分ほどということになりまして、お一人1分ほどでおまとめいただければと思います。
特に今、経済安全保障環境が激変する中にあって、非常にグローバル経済がデカップリングしていくのではないかといった懸念があります。ただ、今日のお話を伺う限りは、そういう形の真っ二つというよりは、もっとコントロールされた形での変容なのではないかという印象を受けているわけですが、グローバル化の行方について、それから経済安全保障という課題を成長機会に変えるために政府あるいは企業が心掛けるべきこと、あるいは求めること、そういった点についてお一人1分という形でおまとめいただければと思います。それでは、鈴木様から。
■鈴木 ありがとうございます。グローバル化がどういうふうに変わっていくかというか、恐らくグローバリズムとグローバル化、グローバリゼーションというのが恐らく分かれていくのだろうと。グローバルにつながっていくサプライチェーンというのは恐らく切れないし、先ほど山本さんの図の中でも出てきたと思うのですが、デカップリングというのは恐らくできないし、コントロールされていくだろう。しかし、これまでのようにどこでも自由に投資して、どの国であっても、中国であっても、ロシアであっても、取引をしても大丈夫だと考えるような、要するにグローバルにフラットな世界はもう想像できなくなってくるのかなと。
つまり、かつてトム・フリードマンという人は「World is flat」と言いましたけれども、グローバル化が進んで世界はフラットになっていく、どこでも自由に投資ができ、ビジネス活動ができると言ったわけですけれども、もう世界はフラットではない。やはり地球は丸いのだということです。どこに自分たちの強みがあり、どこに危険があるのか、そういったことを察知しながら、自らの強みを生かせる場所、そしてそれが自分たちの利益につながるようなビジネス活動はどうあるべきなのかということをもう一度精査することで、成長につながることになっていくのではないかと思います。
特に今、経済安全保障環境が激変する中にあって、非常にグローバル経済がデカップリングしていくのではないかといった懸念があります。ただ、今日のお話を伺う限りは、そういう形の真っ二つというよりは、もっとコントロールされた形での変容なのではないかという印象を受けているわけですが、グローバル化の行方について、それから経済安全保障という課題を成長機会に変えるために政府あるいは企業が心掛けるべきこと、あるいは求めること、そういった点についてお一人1分という形でおまとめいただければと思います。それでは、鈴木様から。
■鈴木 ありがとうございます。グローバル化がどういうふうに変わっていくかというか、恐らくグローバリズムとグローバル化、グローバリゼーションというのが恐らく分かれていくのだろうと。グローバルにつながっていくサプライチェーンというのは恐らく切れないし、先ほど山本さんの図の中でも出てきたと思うのですが、デカップリングというのは恐らくできないし、コントロールされていくだろう。しかし、これまでのようにどこでも自由に投資して、どの国であっても、中国であっても、ロシアであっても、取引をしても大丈夫だと考えるような、要するにグローバルにフラットな世界はもう想像できなくなってくるのかなと。
つまり、かつてトム・フリードマンという人は「World is flat」と言いましたけれども、グローバル化が進んで世界はフラットになっていく、どこでも自由に投資ができ、ビジネス活動ができると言ったわけですけれども、もう世界はフラットではない。やはり地球は丸いのだということです。どこに自分たちの強みがあり、どこに危険があるのか、そういったことを察知しながら、自らの強みを生かせる場所、そしてそれが自分たちの利益につながるようなビジネス活動はどうあるべきなのかということをもう一度精査することで、成長につながることになっていくのではないかと思います。
■伊藤 ありがとうございました。山本様、お願いします。
■山本 ありがとうございます。私は、経済安全保障は企業の経営戦略そのものだと思っております。例えば今日の議論でもあったように、米中の対立や各国の法規制を捉えていくということも当然重要です。
またグローバルの中で日本が既におさえているチョークポイントや、逆に今後チョークポイントとなり得る領域を把握しおさえていくことも検討する必要があります。ファクトを知ることによって、日本企業はまだまだ自立性、不可欠性を高められると思っておりますので、こういった観点で議論が進むとようご支援し、新たな情報提供をしていきたいと考えております。
■山本 ありがとうございます。私は、経済安全保障は企業の経営戦略そのものだと思っております。例えば今日の議論でもあったように、米中の対立や各国の法規制を捉えていくということも当然重要です。
またグローバルの中で日本が既におさえているチョークポイントや、逆に今後チョークポイントとなり得る領域を把握しおさえていくことも検討する必要があります。ファクトを知ることによって、日本企業はまだまだ自立性、不可欠性を高められると思っておりますので、こういった観点で議論が進むとようご支援し、新たな情報提供をしていきたいと考えております。
■伊藤 ありがとうございました。
■矢嶋 2点お話しさせていただきたいと思います。一つは、日本はエネルギーもないので、グローバル化は絶対に捨てられない。そういう意味では、いろいろなビジネスにリスクはあるけれども、リスクを最小化するということをこれからもやらないといけないというのが1点目だと思います。
それからもう一つは、日本が信頼される国ということが、成長戦略につながるために非常に重要なポイントになると思うのです。そういう意味でアジアの中で生きていくことを考えると、直近アメリカがものすごく利上げを始めていますので、小さな国は恐らく、通貨安、それから国債の暴落、株の安値、今起こっているエネルギー高等々、いろいろな意味で困ることが起きて来ると思うのです。こういうときだからこそ、日本も内向きにならないで、ぜひ海外に幅広にスピード感を持った支援をしていく。それが非常に必要な時期になっているのだと思います。以上です。
■矢嶋 2点お話しさせていただきたいと思います。一つは、日本はエネルギーもないので、グローバル化は絶対に捨てられない。そういう意味では、いろいろなビジネスにリスクはあるけれども、リスクを最小化するということをこれからもやらないといけないというのが1点目だと思います。
それからもう一つは、日本が信頼される国ということが、成長戦略につながるために非常に重要なポイントになると思うのです。そういう意味でアジアの中で生きていくことを考えると、直近アメリカがものすごく利上げを始めていますので、小さな国は恐らく、通貨安、それから国債の暴落、株の安値、今起こっているエネルギー高等々、いろいろな意味で困ることが起きて来ると思うのです。こういうときだからこそ、日本も内向きにならないで、ぜひ海外に幅広にスピード感を持った支援をしていく。それが非常に必要な時期になっているのだと思います。以上です。
■伊藤 ありがとうございました。兼原様、お願いします。
■兼原 ありがとうございました。手短に3点申し上げたいと思います。マーケットの力は偉大ですので、グローバリゼーションは続くと思うのです。ただ、今問題になっているのは中国という国があまりに大きいのと、あまりに異質であるということです。中国共産党はマーケット論理に従って動いているわけでは全くありません。中国共産党自体は全ての法から規制を受けない勝手な動きをする権力組織であって、それが中国政府あるいは中国市場の上にあるということです。彼らがありとあらゆる手段を用いて、技術を盗んだりしているということが最大の問題です。しかも、その中国が、アメリカにチャレンジし得る力を持ってきたということです。これが現実です。これがまず1点目です。
2点目が、日本は戦後ずっと、安全保障はアメリカにお任せだ、それでいいではないかという感覚で来ていて、実は政府の中でも警察、外務省、防衛省以外は、冷戦という意識や、日本は西側の一員だという意識はあまりなかったですね。むしろ経済官庁にはミリタリーリテラシーがなく、日米経済摩擦だけを見ていて「もう一遍アメリカと勝負だ」という狭量な雰囲気がありました。実はアメリカに守ってもらっている安全保障の部分が揺れるとどうなるかということは、日本人は幸いにしてあまり経験していないのです。朝鮮戦争とベトナム戦争はあまり日本にとっては痛くなかったというのが実態でした。しかし、台湾戦争は日本にとっても本当に痛い戦争になりますので、よく予め考えておく必要があるということです。
最後に3点目が、平時の時に何を一体注意すればいいですかという問題と、台湾戦争が始まったらどうするかという問題は全然違う問題です。有事の問題は、国民の生命財産が大規模に危険にさらされている緊急事態だという前提で考えていただく必要があると思います。以上です。
■伊藤 ありがとうございました。本日、このテーマで本当にベストともいえるような方々におそろいいただきました。とても興味深い議論が展開できたのではないかと思います。皆さま方の日々のビジネス等に役立つような情報が提供できるのであれば大変うれしく思うところです。このパネルディスカッションはここで締めくくりとさせていただきたいと思います。
■兼原 ありがとうございました。手短に3点申し上げたいと思います。マーケットの力は偉大ですので、グローバリゼーションは続くと思うのです。ただ、今問題になっているのは中国という国があまりに大きいのと、あまりに異質であるということです。中国共産党はマーケット論理に従って動いているわけでは全くありません。中国共産党自体は全ての法から規制を受けない勝手な動きをする権力組織であって、それが中国政府あるいは中国市場の上にあるということです。彼らがありとあらゆる手段を用いて、技術を盗んだりしているということが最大の問題です。しかも、その中国が、アメリカにチャレンジし得る力を持ってきたということです。これが現実です。これがまず1点目です。
2点目が、日本は戦後ずっと、安全保障はアメリカにお任せだ、それでいいではないかという感覚で来ていて、実は政府の中でも警察、外務省、防衛省以外は、冷戦という意識や、日本は西側の一員だという意識はあまりなかったですね。むしろ経済官庁にはミリタリーリテラシーがなく、日米経済摩擦だけを見ていて「もう一遍アメリカと勝負だ」という狭量な雰囲気がありました。実はアメリカに守ってもらっている安全保障の部分が揺れるとどうなるかということは、日本人は幸いにしてあまり経験していないのです。朝鮮戦争とベトナム戦争はあまり日本にとっては痛くなかったというのが実態でした。しかし、台湾戦争は日本にとっても本当に痛い戦争になりますので、よく予め考えておく必要があるということです。
最後に3点目が、平時の時に何を一体注意すればいいですかという問題と、台湾戦争が始まったらどうするかという問題は全然違う問題です。有事の問題は、国民の生命財産が大規模に危険にさらされている緊急事態だという前提で考えていただく必要があると思います。以上です。
■伊藤 ありがとうございました。本日、このテーマで本当にベストともいえるような方々におそろいいただきました。とても興味深い議論が展開できたのではないかと思います。皆さま方の日々のビジネス等に役立つような情報が提供できるのであれば大変うれしく思うところです。このパネルディスカッションはここで締めくくりとさせていただきたいと思います。
コンテンツ紹介
-
レポート
-
受託実績・コンサルティング
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る