- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 金融・為替 >
- 金融政策 >
- 日銀と市場との対話再構築
コラム
2007年01月23日
| ●消費と物価の判断―フォワードルッキング型運営にいつ戻れるか 1月18日の決定会合では、久々に反対票が入った(三票反対票が入るのは、03年10月以来)が、賛成多数で利上げ見送りが決定された。今後の利上げの可能性は、1月会合で利上げ見送りを主張した6人がいつ景気の現状、先行きに自信が持てるか、鍵となるのは12月の決定会合後の会見で福井総裁が利上げを見送った理由として挙げた弱い消費と物価について、判断がいつ変わるかにかかっている。 消費については、家計調査などの月次統計を見る限り7-9月期の大きな減少が10-12月期では戻ってきている事は確認される。日銀も7-9月期の落ち込みは天候などの一時的な要因であったとの見方に自信を強めている。2月決定会合(2月20、21日)の前(15日)に公表される10-12月期GDP統計は、7-9月期でマイナスだった消費が大きくプラスとなりそうで追加利上げには追い風となるだろう。 ただし、物価統計は利上げ判断の足かせとなりそうだ。図表1が示すように原油価格(WTI)は2006年7月頃の1バレル80ドル近い水準から、2007年に入って1バレル50ドル近くにまで大幅に下落している。原油価格低下が石油製品の上昇率を低下させ、物価全体を押し下げる可能性が高まっている。全国コアCPIは11月,前年比0.2%だったが、これから春先から夏にかけ、ゼロないしマイナスに転じる可能性が出ている。早くも1月の決定会合後の総裁会見では、「CPI上昇率が低くなったから利上げが遠のくという単純なものではない」と予防線が張られているが、この先しばらく、発表される物価統計は低飛行が続きそうだ。 ただ、足元の統計が弱くとも、利上げ見送りとも直結しないはず。ここ数ヶ月崩れているフォワードルッキング型の政策運営に日銀自体が自信を持てるかどうか、先行きの景気・物価情勢に自信が持てれば、多少足元の統計が奮わなくとも利上げを模索する展開はありうる。追加利上げの時期を探るには、発表される統計とともに、日銀メンバーの発言などがどのように変わってくるのか引き続き注目だ。 ● ギクシャクした日銀と市場との対話 12月以降の日銀と市場との対話を見ていると、筆者は、市場サイドにはかなり日銀に裏切られたとの感覚が残ってしまった、との印象を持っている。早期利上げを模索する日銀にとって、この点障害が残ったことは間違いないだろう。 つまり、12月、1月の決定会合とも事前に市場は利上げを織り込みにいき、会合直前に利上げ見送り報道がなされ、市場は右往左往することとなった。こういうことが繰り返されたことで今後、日銀の情報発信に対して市場が「素直」に利上げを織り込まなくなる、「信認低下」のリスクは高まったと言えよう。 できるだけ利上げ前に市場に織り込ますことで市場の混乱を回避するという、望ましい日銀の政策運営に障害が生じたことになる。 また政治との関係も大きな影を落とした。実際、政治的な圧力があったかどうかは別にしても、市場は1月の利上げ見送りに際して政治圧力が大きく関与したとの印象を強く持った。夏の参院選挙に向けて政府からの日銀牽制は強まるとの見方が強いだけに、今後市場が政府サイドからの発言に大きく振られるリスクも高まった。 さらにもう一点、日銀とマスコミとの関係も市場からすれば疑心暗鬼を生む形で状況を悪化させることになった。政治圧力の思惑と絡んでリークが市場を動かしたとの印象が強く持たれたのではないか。 日銀の情報発信は展望リポートや金融経済月報などの日銀の発信物、総裁会見、各審議委員の公演などで行われるはずで、非公式情報のマスコミ報道により市場が過度に揺れることはないに越したことはない。日銀がマスコミとどういう関係を築くのか、日銀が行う情報発信の中でマスコミの位置づけをどうするのかといった課題も浮き彫りとなった。 こうして、追加利上げの実現には、経済・物価情勢の難しい判断とともに、市場との対話再構築という新たな課題も大きく残ったこととなったのである。
|
(2007年01月23日「エコノミストの眼」)
このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1837
経歴
- ・ 1992年 :日本生命保険相互会社
・ 1995年 :ニッセイ基礎研究所へ
・ 2025年から現職
・ 早稲田大学・政治経済学部(2004年度~2006年度・2008年度)、上智大学・経済学部(2006年度~2014年度)非常勤講師を兼務
・ 2015年 参議院予算委員会調査室 客員調査員
矢嶋 康次のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/21 | トランプ1.0のトラウマ-不確実性の高まりが世界の活動を止める | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |
| 2025/02/12 | 供給制約をどう乗り切るか-設備投資の増勢を維持するために | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |
| 2025/02/07 | 日米貿易交渉の課題-第一次トランプ政権時代の教訓 | 矢嶋 康次 | 基礎研マンスリー |
| 2024/12/03 | 日米貿易交渉の課題-第一次トランプ政権時代の教訓 | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |
新着記事
-
2025年11月04日
今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -
2025年10月31日
交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -
2025年10月31日
ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -
2025年10月31日
2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -
2025年10月31日
保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【日銀と市場との対話再構築】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
日銀と市場との対話再構築のレポート Topへ

















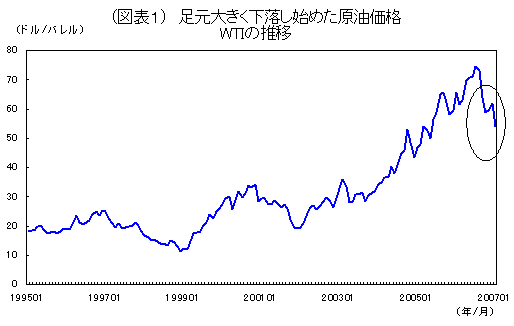

 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




