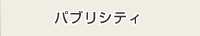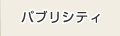- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- パブリシティ >
- イベント(シンポジウム) >
- イベント詳細 >
- 中国リスクの軽減(デリスキング)と今後の国際戦略「コメント・討論」
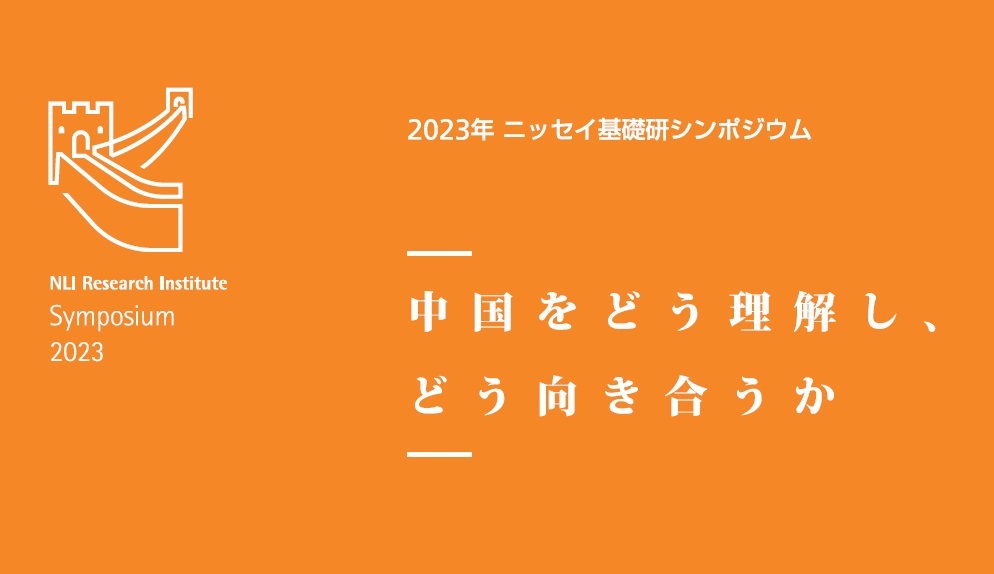
2023年10月31日開催
パネルディスカッション
中国リスクの軽減(デリスキング)と今後の国際戦略「コメント・討論」
| パネリスト |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデレータ |
|
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
5――討論
■伊藤さゆり ありがとうございました。今、川島様からご提示いただきました、幾つかの論点とともに、私からも若干質問を加えさせていただいて、先ほどのご登壇順にコメントを頂ければと思います。
私自身、大庭様のご報告の中で、中国のリスク以上にアメリカのかなり厳格なルール、規制に対する懸念が大きいという話をいただいたかと思います。それと先ほどの川島様からのご提案、コメントとリンクした問題意識なのですが、例えば日本企業の悩みとして、厳格なルールで、ここからここまできっちり適用ということであれば対応可能なのだけれど、ぼんやりとしたルールであるからこそ、どうなるのかが分からなくて不安であるという声を耳にすることがあります。その結果、日本企業は少し過剰にリスクヘッジしてしまう傾向があるとも言われます。大庭様、伊藤様には、こういった論点も盛り込んでコメントを頂ければと思います。
特に伊藤様には、先ほども地産地消のリスクというようなことを言われておりました。ヨーロッパの企業なども、かなり今地産地消を進めているということが各種の研究などからも分かっているのですが、サプライヤーとして、あるいはカスタマーとして欧米企業などとのお付き合いもあろうかと思います。日本企業と欧米企業とのスタンスの違いについてもコメントをただければと思います。
それから三尾さんには、経済をご専門とされる立場から、今の川島様のコメントに加えまして、先ほど伊藤さんの七つのリスクの一つに中国経済の先が読めないという点についてお尋ねしたいことがあります。先が読めない理由として、特に習近平政権3期目の経済閣僚があまり経済に精通していないことがあるのではないかということです。過去のいろいろな問題が蓄積している中で、適時適切に対処を、米国と対峙しながら進めなければいけないという難しい状況にありながら、経済の適切なマネジメント力を欠いているのではないかという懸念を日本企業の方々が抱いておられるのではないかと思います。この点についてもコメントを頂ければと思います。
それでは、大庭様からお願いできますでしょうか。
私自身、大庭様のご報告の中で、中国のリスク以上にアメリカのかなり厳格なルール、規制に対する懸念が大きいという話をいただいたかと思います。それと先ほどの川島様からのご提案、コメントとリンクした問題意識なのですが、例えば日本企業の悩みとして、厳格なルールで、ここからここまできっちり適用ということであれば対応可能なのだけれど、ぼんやりとしたルールであるからこそ、どうなるのかが分からなくて不安であるという声を耳にすることがあります。その結果、日本企業は少し過剰にリスクヘッジしてしまう傾向があるとも言われます。大庭様、伊藤様には、こういった論点も盛り込んでコメントを頂ければと思います。
特に伊藤様には、先ほども地産地消のリスクというようなことを言われておりました。ヨーロッパの企業なども、かなり今地産地消を進めているということが各種の研究などからも分かっているのですが、サプライヤーとして、あるいはカスタマーとして欧米企業などとのお付き合いもあろうかと思います。日本企業と欧米企業とのスタンスの違いについてもコメントをただければと思います。
それから三尾さんには、経済をご専門とされる立場から、今の川島様のコメントに加えまして、先ほど伊藤さんの七つのリスクの一つに中国経済の先が読めないという点についてお尋ねしたいことがあります。先が読めない理由として、特に習近平政権3期目の経済閣僚があまり経済に精通していないことがあるのではないかということです。過去のいろいろな問題が蓄積している中で、適時適切に対処を、米国と対峙しながら進めなければいけないという難しい状況にありながら、経済の適切なマネジメント力を欠いているのではないかという懸念を日本企業の方々が抱いておられるのではないかと思います。この点についてもコメントを頂ければと思います。
それでは、大庭様からお願いできますでしょうか。
5―1. ASEAN諸国の視点
■大庭 ご質問ありがとうございます。また川島さんから貴重なコメント、そして特にAutonomyについてのコメントおよび質問をいただいたと理解しています。指摘点としては、非常に重要な点なので、少し私の方から補足したいと思います。
まず、伊藤さんから、アメリカの輸出規制が厳格で、それに対する懸念などの話がありました。ASEAN諸国は、先ほども少しお話ししましたが、現実問題として、機微で先端の技術にそれほど関わっていないので、今何がどうするというリスクをアメリカから感じているわけではないと思います。
しかし、中国企業との付き合い方でいろいろ考えなければいけないのは、規制が厳しければそのとおりだし、あとやはり中国への輸出ということでも考えなければいけないことが出てくる。非常に間接的ですが、アメリカが割と執拗にターゲティングして、いろいろな規制をかけてくることについて、非常にリスクであると考えているということだと思います。
あともう一つは、東南アジア諸国でもいいのですが、ASEAN諸国にとって中国との経済的な関係というのは、もう「常態」なので、やはりそこに何らかの制限がかかるとか、あるいは先ほどお話しした東アジアにおけるFactory Asiaに支障を来すような話というのは警戒するわけですよね。もちろんアメリカの関税や輸出規制に関して、中国もやり返していますが、そうするとアメリカの方のやり方にそんなに同調もできないし、かといって中国のいいなりというのも、彼らにとって望ましくもなく、どちらにもつきたくないということだと思います。
あと、やはり彼らなりのデリスキングは、IPEFに参加したということに現れています。IPEFはASEAN諸国で直接いろいろな人に聞くと、「あんなもの、バイデン政権の次になったらどうなるか分からない」という、かなりネガティブな言い方をする人も多いわけです。しかし、そうはいっても、その場に入っていないと、逆にアメリカの次の出方が分からない。アメリカが共通の、それこそサプライチェーンの強靱化も含めた、さまざまな分野において、どのようなルールを設定しようとしているか分からない。やはりそこは、内部に入っておかないといけないというのが、彼らのデリスキング的行動の一つなのだろうと思います。だから彼らのIPEFへの参加は、アメリカの方についているとかではなくて、彼ら自身のデリスキングなのだろうなと考えます。
さっきの川島先生の講演でもありましたが、中国にとってASEAN諸国は全然脅威ではない。中国よりも、シンガポールのようにある種の経済的な水準が高いところもありますが、技術水準などが低い国はそれほどリスクではないわけだから、それを追い落とそうとか攻撃しようとかは中国は思ってないわけです。そうすると、ますますASEAN諸国のさまざまな企業や事業体、あるいは国家にとって、中国からの投資や支援をリスクなく選びやすい。数ある中から中国を選べる国、それから中国に依存せざるを得ない国、国によって違いますが、どちらのカテゴリーに属する国にとっても、中国は大変大事なパートナーです。
そうすると、そこからリスクという発想がなかなか出てこない。一つあるとすると、中国に対して過剰に依存する危険性ですが、それも彼らはよく分かっている。これはラオスでもカンボジアでも理解しています。だから第3のパートナーが欲しいということになるのです。そうすると、期待が集まるのはEUであり、日本だったりするということだろうと思います。
Autonomyに関しては、自立性ということで、かなり微妙なのですが、実はASEAN諸国側から日本に対して「もっと自立しろ、Autonomyを持て」と言われたりもするのです。「アメリカばかりにくっ付いているな」という、かなり厳しいことをよく東南アジアの人々から言われます。それはさておき、東南アジア諸国のAutonomyに話を戻すと、自らの経済発展をすることで力をつけるということと、複数のパートナーを持っておくということ、これらが、彼らにとってのデリスキングであり、さらにはそれがAutonomyにつながるということだと考えます。
先ほども少し言及しましたが、近年、東南アジアにおける政界と財界と、それから市民社会のリーダーたちにアンケートを採っている「The States of Southeast Asia」が毎年発行されています。そのアンケート結果によると、現在米中対立が非常に高まっている中で、ASEANがとるべき戦略は何かといったときに、これは複数回答ですが31%ぐらいは「今までのように米中選ばない、テイクサイドしない」と言っているのですが、他方で「ASEANの団結を高めて、そこを乗り越える」と言っている人が、どこまで本気か分からないですが45%ぐらいいるのですね。
だからやはり彼らにとってのASEANというのは、もちろんASEANの団結はなかなか難しいのだけれど、ASEANが一種のアセットになっていて、そこにそれなりの期待を寄せなければいけないのではないか、と考えているのではないか、という印象を持っています。以上です。
■伊藤さゆり ありがとうございました。伊藤様、お願いいたします。
■大庭 ご質問ありがとうございます。また川島さんから貴重なコメント、そして特にAutonomyについてのコメントおよび質問をいただいたと理解しています。指摘点としては、非常に重要な点なので、少し私の方から補足したいと思います。
まず、伊藤さんから、アメリカの輸出規制が厳格で、それに対する懸念などの話がありました。ASEAN諸国は、先ほども少しお話ししましたが、現実問題として、機微で先端の技術にそれほど関わっていないので、今何がどうするというリスクをアメリカから感じているわけではないと思います。
しかし、中国企業との付き合い方でいろいろ考えなければいけないのは、規制が厳しければそのとおりだし、あとやはり中国への輸出ということでも考えなければいけないことが出てくる。非常に間接的ですが、アメリカが割と執拗にターゲティングして、いろいろな規制をかけてくることについて、非常にリスクであると考えているということだと思います。
あともう一つは、東南アジア諸国でもいいのですが、ASEAN諸国にとって中国との経済的な関係というのは、もう「常態」なので、やはりそこに何らかの制限がかかるとか、あるいは先ほどお話しした東アジアにおけるFactory Asiaに支障を来すような話というのは警戒するわけですよね。もちろんアメリカの関税や輸出規制に関して、中国もやり返していますが、そうするとアメリカの方のやり方にそんなに同調もできないし、かといって中国のいいなりというのも、彼らにとって望ましくもなく、どちらにもつきたくないということだと思います。
あと、やはり彼らなりのデリスキングは、IPEFに参加したということに現れています。IPEFはASEAN諸国で直接いろいろな人に聞くと、「あんなもの、バイデン政権の次になったらどうなるか分からない」という、かなりネガティブな言い方をする人も多いわけです。しかし、そうはいっても、その場に入っていないと、逆にアメリカの次の出方が分からない。アメリカが共通の、それこそサプライチェーンの強靱化も含めた、さまざまな分野において、どのようなルールを設定しようとしているか分からない。やはりそこは、内部に入っておかないといけないというのが、彼らのデリスキング的行動の一つなのだろうと思います。だから彼らのIPEFへの参加は、アメリカの方についているとかではなくて、彼ら自身のデリスキングなのだろうなと考えます。
さっきの川島先生の講演でもありましたが、中国にとってASEAN諸国は全然脅威ではない。中国よりも、シンガポールのようにある種の経済的な水準が高いところもありますが、技術水準などが低い国はそれほどリスクではないわけだから、それを追い落とそうとか攻撃しようとかは中国は思ってないわけです。そうすると、ますますASEAN諸国のさまざまな企業や事業体、あるいは国家にとって、中国からの投資や支援をリスクなく選びやすい。数ある中から中国を選べる国、それから中国に依存せざるを得ない国、国によって違いますが、どちらのカテゴリーに属する国にとっても、中国は大変大事なパートナーです。
そうすると、そこからリスクという発想がなかなか出てこない。一つあるとすると、中国に対して過剰に依存する危険性ですが、それも彼らはよく分かっている。これはラオスでもカンボジアでも理解しています。だから第3のパートナーが欲しいということになるのです。そうすると、期待が集まるのはEUであり、日本だったりするということだろうと思います。
Autonomyに関しては、自立性ということで、かなり微妙なのですが、実はASEAN諸国側から日本に対して「もっと自立しろ、Autonomyを持て」と言われたりもするのです。「アメリカばかりにくっ付いているな」という、かなり厳しいことをよく東南アジアの人々から言われます。それはさておき、東南アジア諸国のAutonomyに話を戻すと、自らの経済発展をすることで力をつけるということと、複数のパートナーを持っておくということ、これらが、彼らにとってのデリスキングであり、さらにはそれがAutonomyにつながるということだと考えます。
先ほども少し言及しましたが、近年、東南アジアにおける政界と財界と、それから市民社会のリーダーたちにアンケートを採っている「The States of Southeast Asia」が毎年発行されています。そのアンケート結果によると、現在米中対立が非常に高まっている中で、ASEANがとるべき戦略は何かといったときに、これは複数回答ですが31%ぐらいは「今までのように米中選ばない、テイクサイドしない」と言っているのですが、他方で「ASEANの団結を高めて、そこを乗り越える」と言っている人が、どこまで本気か分からないですが45%ぐらいいるのですね。
だからやはり彼らにとってのASEANというのは、もちろんASEANの団結はなかなか難しいのだけれど、ASEANが一種のアセットになっていて、そこにそれなりの期待を寄せなければいけないのではないか、と考えているのではないか、という印象を持っています。以上です。
■伊藤さゆり ありがとうございました。伊藤様、お願いいたします。
5―2. サプライチェーンに対する各国の傾向
■伊藤隆 ありがとうございます。川島さんもご指摘ありがとうございます。ご指摘のありました、日本企業の中国におけるアセットですとか、あるいは日本人の出向者、出張者のリスク認識というのは、まさにそのとおりだと思っております。どうもありがとうございます。
それから米国に対する意識ですが、2020年11月に、当時梶山経産大臣が記者会見で、「基本的に米国の法律に対してオーバーコンプライし過ぎるな」と言われておりました。アメリカの法律を守るというのは域外適用が書いてあるからなのですが、オーバーコンプライして、例えばファーウェイ向けのビジネスは全てやめてしまうとか、中国との取引を全てやめてしまうということをすると、これは逆に別の問題を起こしてしまう。やはり規制は規制で、冷静に見定めて対処した方がいいということを記者会見で言われていたと思っています。これは私たち三菱電機が経済安全保障活動をを進める上で心の支えになっている言葉です。やはり一つ一つ、各国の規制であったり、あるいは外為法であったりというのは規制の外延をしっかり見定めていくことは大事です。米国から出てくる規制に対して、日本政府がそれにどう反応して、どういう形で規制を作り込んでいくのかというところも、やはり見定めていかなければならないだろうと思っております。
では、欧米の企業がどうしているのか。別に全ての会社にインタビューをして聞いているわけではありませんが、例えばドイツの会社でサプライチェーンについてしっかりと見ていますかという話をすると、むしろドイツの企業の方から「三菱電機、どうやっているの」という質問を返してきます。昨年もシュタインマイヤー大統領やショルツ首相が相次いで来日されましたが、シュタインマイヤー大統領から、私どももサプライチェーンについて質問を受けました。当時、まだAIを導入は完了していませんでしたが、「AIの導入まで考えています」とお答えしました。
だからというわけではありませんが、今年になって、人権問題を中心に、ドイツでは「サプライチェーン・デューデリジェンス法」が出来上がっています。ドイツにおいては、コンプライアンスとしてサプライチェーンを見定めていこうという動きが出てきたのだろうなと感じてます。EU指令も昨年2月の時点の案で止まっていますが、やはりサプライチェーンに対してコンプライアンスとして管理していこうという動きが出てきています。
ではアメリカは?。2週間前アメリカに行って参りました。私どもがやっている活動を話すと、「へー、すごいね」と言うぐらいの反応しかありません。彼らが欲しがる情報は、オルタナティブなサプライチェーンはどうなっているのかという話ばかりです。一足飛びに、次のサプライチェーンを早く考えようよという、割と結論を急いでいるタイプの議論が多かったと感じています。私たちは「必要なのはまずビジュアライズ」、次が妥当な打ち手だと考えています。見える化を飛ばしていきなりオルタナティブなサプライチェーンを考えるというやり方は、特に中国依存の高い日本の経済社会では別のリスクを招くのではないか考えています。アメリカ企業とはその辺の価値観が噛み合わず議論が進まなかったというのが正直なところです。
そういう意味で、コンプライアンスで迫る欧州、自らのリスクヘッジを個社の特性に合わせて追及する日本企業、そして結論を急ぎがちな米国企業という特徴があると、私は印象を有しています。
■伊藤さゆり 大変、実体験に即した貴重なコメントを頂きまして大変参考になりました。ありがとうございます。では三尾さん、お願いいたします。
■伊藤隆 ありがとうございます。川島さんもご指摘ありがとうございます。ご指摘のありました、日本企業の中国におけるアセットですとか、あるいは日本人の出向者、出張者のリスク認識というのは、まさにそのとおりだと思っております。どうもありがとうございます。
それから米国に対する意識ですが、2020年11月に、当時梶山経産大臣が記者会見で、「基本的に米国の法律に対してオーバーコンプライし過ぎるな」と言われておりました。アメリカの法律を守るというのは域外適用が書いてあるからなのですが、オーバーコンプライして、例えばファーウェイ向けのビジネスは全てやめてしまうとか、中国との取引を全てやめてしまうということをすると、これは逆に別の問題を起こしてしまう。やはり規制は規制で、冷静に見定めて対処した方がいいということを記者会見で言われていたと思っています。これは私たち三菱電機が経済安全保障活動をを進める上で心の支えになっている言葉です。やはり一つ一つ、各国の規制であったり、あるいは外為法であったりというのは規制の外延をしっかり見定めていくことは大事です。米国から出てくる規制に対して、日本政府がそれにどう反応して、どういう形で規制を作り込んでいくのかというところも、やはり見定めていかなければならないだろうと思っております。
では、欧米の企業がどうしているのか。別に全ての会社にインタビューをして聞いているわけではありませんが、例えばドイツの会社でサプライチェーンについてしっかりと見ていますかという話をすると、むしろドイツの企業の方から「三菱電機、どうやっているの」という質問を返してきます。昨年もシュタインマイヤー大統領やショルツ首相が相次いで来日されましたが、シュタインマイヤー大統領から、私どももサプライチェーンについて質問を受けました。当時、まだAIを導入は完了していませんでしたが、「AIの導入まで考えています」とお答えしました。
だからというわけではありませんが、今年になって、人権問題を中心に、ドイツでは「サプライチェーン・デューデリジェンス法」が出来上がっています。ドイツにおいては、コンプライアンスとしてサプライチェーンを見定めていこうという動きが出てきたのだろうなと感じてます。EU指令も昨年2月の時点の案で止まっていますが、やはりサプライチェーンに対してコンプライアンスとして管理していこうという動きが出てきています。
ではアメリカは?。2週間前アメリカに行って参りました。私どもがやっている活動を話すと、「へー、すごいね」と言うぐらいの反応しかありません。彼らが欲しがる情報は、オルタナティブなサプライチェーンはどうなっているのかという話ばかりです。一足飛びに、次のサプライチェーンを早く考えようよという、割と結論を急いでいるタイプの議論が多かったと感じています。私たちは「必要なのはまずビジュアライズ」、次が妥当な打ち手だと考えています。見える化を飛ばしていきなりオルタナティブなサプライチェーンを考えるというやり方は、特に中国依存の高い日本の経済社会では別のリスクを招くのではないか考えています。アメリカ企業とはその辺の価値観が噛み合わず議論が進まなかったというのが正直なところです。
そういう意味で、コンプライアンスで迫る欧州、自らのリスクヘッジを個社の特性に合わせて追及する日本企業、そして結論を急ぎがちな米国企業という特徴があると、私は印象を有しています。
■伊藤さゆり 大変、実体験に即した貴重なコメントを頂きまして大変参考になりました。ありがとうございます。では三尾さん、お願いいたします。
5―3. 不安視する中国社会
■三尾 川島先生、ありがとうございました。いろいろご指摘を頂いたのですけれども、まず財政については、ひょっとしたら国の債務ということで誤解を与えたかもしれません。地方の財政が重要だというご指摘で、ちょっと説明不足だったかと反省しております。
特に地方の財政については、不動産税が少し絡んでいます。どこも固定資産税みたいなものは地方政府の収入なのですが、今不動産市場がこういう状態なので、なかなかそれが進まないと。そういう意味では、地方の財政の問題というのはなおさら大きな問題だなと痛感しております。
それから成長率が2.2%台まで下がっていくと、1人当たりGDPは2万ドルぐらいということで、まさにそうなのですけれども、想定では上海や北京は恐らく4~5万ドル。つまり台湾や日本、韓国とそれほど違いはないレベルにいて、地方が取り残されてしまう。まさにもう一つのご指摘でありましたデジタル化で格差が拡大するという話と、厳密には違うかも分からないですけれども、似通ったところがあって、そういう意味ではそうなっても大丈夫かどうかというのは私もちょっと不安なところがあります。そうなってくると、社会不安が加速する恐れはあるのかなとは思っています。そのプロセスの中で、どういう形で進んでいくかというのは、これから見定めていきたいと思っています。
それからもう一つ、社会主義市場経済についてのご指摘も頂きました。社会主義は政治で、市場経済は経済というわけではないですけれども、ただ社会主義と計画経済というのは比較的親和性が高いということもあって、共産党が独裁というか指導(領導)する形でやっていくと、どうも見渡せるものを思ったとおりにやりたいという思考になりがちで、市場がどう動くかを見定めながら、あるいは市場の反応を見ながら軌道修正するということにつながりにくいところがあると、私は思っています。
そういう意味では、今回3期目の政権の中に、市場経済に精通した人はいるのですけれども、幹部が残らなかったというのも、習近平氏の社会主義的な思想がどちらかというと計画経済的な考え方に近く、統制してコントロールできると。特に昔は、手で計算していたものが、今や一瞬のうちに分かるようになり、監視カメラなども出て、要は監視できるのでソ連が崩壊したときとはちょっと違って、ひょっとしたらできると思っているのかも分かりません。そういう意味では、どうしても計画経済的な方向に傾きやすいし、採用する人、つまり幹部もそういう人を選びがちです。そこに不安を感じているというところで、ちょっと話したのだとご理解いただければと思います。
■三尾 川島先生、ありがとうございました。いろいろご指摘を頂いたのですけれども、まず財政については、ひょっとしたら国の債務ということで誤解を与えたかもしれません。地方の財政が重要だというご指摘で、ちょっと説明不足だったかと反省しております。
特に地方の財政については、不動産税が少し絡んでいます。どこも固定資産税みたいなものは地方政府の収入なのですが、今不動産市場がこういう状態なので、なかなかそれが進まないと。そういう意味では、地方の財政の問題というのはなおさら大きな問題だなと痛感しております。
それから成長率が2.2%台まで下がっていくと、1人当たりGDPは2万ドルぐらいということで、まさにそうなのですけれども、想定では上海や北京は恐らく4~5万ドル。つまり台湾や日本、韓国とそれほど違いはないレベルにいて、地方が取り残されてしまう。まさにもう一つのご指摘でありましたデジタル化で格差が拡大するという話と、厳密には違うかも分からないですけれども、似通ったところがあって、そういう意味ではそうなっても大丈夫かどうかというのは私もちょっと不安なところがあります。そうなってくると、社会不安が加速する恐れはあるのかなとは思っています。そのプロセスの中で、どういう形で進んでいくかというのは、これから見定めていきたいと思っています。
それからもう一つ、社会主義市場経済についてのご指摘も頂きました。社会主義は政治で、市場経済は経済というわけではないですけれども、ただ社会主義と計画経済というのは比較的親和性が高いということもあって、共産党が独裁というか指導(領導)する形でやっていくと、どうも見渡せるものを思ったとおりにやりたいという思考になりがちで、市場がどう動くかを見定めながら、あるいは市場の反応を見ながら軌道修正するということにつながりにくいところがあると、私は思っています。
そういう意味では、今回3期目の政権の中に、市場経済に精通した人はいるのですけれども、幹部が残らなかったというのも、習近平氏の社会主義的な思想がどちらかというと計画経済的な考え方に近く、統制してコントロールできると。特に昔は、手で計算していたものが、今や一瞬のうちに分かるようになり、監視カメラなども出て、要は監視できるのでソ連が崩壊したときとはちょっと違って、ひょっとしたらできると思っているのかも分かりません。そういう意味では、どうしても計画経済的な方向に傾きやすいし、採用する人、つまり幹部もそういう人を選びがちです。そこに不安を感じているというところで、ちょっと話したのだとご理解いただければと思います。
コンテンツ紹介
-
レポート
-
受託実績・コンサルティング
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る