- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 社会保障制度 >
- アジアの社会保障制度 >
- 中国版iDeCo、誕生へ
2022年07月06日
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
2022年4月、中国政府は老後の生活資金に備える新たな制度のガイドラインを発表した1。この「個人養老金制度(中国語)」は中国版iDeCoの様相を呈しており、中国内で早くも注目を集めている。現在、関係省庁が詳細な運営規定や法整備を進めており、今後のタイムスケジュールとしては、パイロット都市を選定し、試行を1年ほどしてから本格導入となる。
中国版iDeCoは、個人型確定拠出年金の私的年金制度の1つで、加入は任意である。公的年金制度と併せて給付を受けることが可能となっている。掛け金の拠出やその運用を自身で行うことで、より豊かな老後の生活を送るために備える制度である。
対象者は、中国の公的年金制度に加入している被保険者である(図表1)。つまり、都市職工年金に加入している会社員、自営業者、公務員、都市・農村住民年金に加入している農業従事者などが対象となる。ただし、中国の場合、日本の国民年金第3号被保険者のような仕組みはないため、主婦は対象外となる。中国の就労開始年齢が16歳で、現行の法定退職年齢(年金受給開始年齢)が60歳(男性)であることを考えると、男性の場合最長44年間加入が可能ということとなる。
加入する際は、主務官庁(人力資源社会保障部)が運営する専用のプラットフォーム(個人養老金情報管理サービスプラットフォーム)に口座を開設し、加入手続きをする。併せて許可を得た金融機関に口座を開設し(または口座を指定し)、掛け金の納付、収益の積み立て、個人所得税の支払いを行う。
運用は、運営管理機関が指定した運用商品から加入者が選択をすることになる。現時点では運営管理機関がまだ発表されていないが、運用商品としては、預貯金や銀行の理財商品、保険商品などが検討されている。
掛け金は加入者個人が拠出し、運用額の上限は年間12,000元(約24万円)である。運用額は対象者別で異なる日本とは違い、一律となっている。運用額については経済状況や年金の給付状況などに応じて調整される。
給付は、原則として年金支給開始年齢以降となっており、それまで引き出すことはできない。中国の場合、現時点で法定退職年齢が年金支給開始年齢となっており、男性60歳、女性の場合は50歳(一般職)または55歳(管理職)となっている。また、傷病などによって労働能力が喪失された場合(障がい給付金)、海外へ定住する場合なども受給が可能となっている。受給は、月ごと、定期、一括を選択できるが、1回決定すると変更はできない。なお、加入者が死亡した場合には、その遺族が死亡一時金を受け取ることができる。また、日本の場合は60歳時点での加入期間が10年に満たない場合、支給開始年齢の引き延ばし措置があるが、中国の場合は現時点でその措置への言及はない。
税優遇については、詳細な規定はまだ発表されておらず、現在、検討がされている。日本の場合は掛け金について全額所得控除となり、運用益は運用中が非課税、給付時は年金として受給する場合は公的年金等控除、一時金として受給する場合は退職所得控除となっており、中国においても相応の検討がなされると考えられる。
中国では、現在、関係省庁によって詳細な運営規定の制定やパイロット都市の検討がされている。老後保障の問題に苦悩する中国において、10億人が加入対象となる中国版iDeCoには大きな期待が寄せられている。
中国版iDeCoは、個人型確定拠出年金の私的年金制度の1つで、加入は任意である。公的年金制度と併せて給付を受けることが可能となっている。掛け金の拠出やその運用を自身で行うことで、より豊かな老後の生活を送るために備える制度である。
対象者は、中国の公的年金制度に加入している被保険者である(図表1)。つまり、都市職工年金に加入している会社員、自営業者、公務員、都市・農村住民年金に加入している農業従事者などが対象となる。ただし、中国の場合、日本の国民年金第3号被保険者のような仕組みはないため、主婦は対象外となる。中国の就労開始年齢が16歳で、現行の法定退職年齢(年金受給開始年齢)が60歳(男性)であることを考えると、男性の場合最長44年間加入が可能ということとなる。
加入する際は、主務官庁(人力資源社会保障部)が運営する専用のプラットフォーム(個人養老金情報管理サービスプラットフォーム)に口座を開設し、加入手続きをする。併せて許可を得た金融機関に口座を開設し(または口座を指定し)、掛け金の納付、収益の積み立て、個人所得税の支払いを行う。
運用は、運営管理機関が指定した運用商品から加入者が選択をすることになる。現時点では運営管理機関がまだ発表されていないが、運用商品としては、預貯金や銀行の理財商品、保険商品などが検討されている。
掛け金は加入者個人が拠出し、運用額の上限は年間12,000元(約24万円)である。運用額は対象者別で異なる日本とは違い、一律となっている。運用額については経済状況や年金の給付状況などに応じて調整される。
給付は、原則として年金支給開始年齢以降となっており、それまで引き出すことはできない。中国の場合、現時点で法定退職年齢が年金支給開始年齢となっており、男性60歳、女性の場合は50歳(一般職)または55歳(管理職)となっている。また、傷病などによって労働能力が喪失された場合(障がい給付金)、海外へ定住する場合なども受給が可能となっている。受給は、月ごと、定期、一括を選択できるが、1回決定すると変更はできない。なお、加入者が死亡した場合には、その遺族が死亡一時金を受け取ることができる。また、日本の場合は60歳時点での加入期間が10年に満たない場合、支給開始年齢の引き延ばし措置があるが、中国の場合は現時点でその措置への言及はない。
税優遇については、詳細な規定はまだ発表されておらず、現在、検討がされている。日本の場合は掛け金について全額所得控除となり、運用益は運用中が非課税、給付時は年金として受給する場合は公的年金等控除、一時金として受給する場合は退職所得控除となっており、中国においても相応の検討がなされると考えられる。
中国では、現在、関係省庁によって詳細な運営規定の制定やパイロット都市の検討がされている。老後保障の問題に苦悩する中国において、10億人が加入対象となる中国版iDeCoには大きな期待が寄せられている。
1 国務院「国務院弁公庁関于推動個人養老金発展的意見」、2022年4月21日公布
http://www.gov.cn/zhengce/content/2022-04/21/content_5686402.htm 2022年6月30日アクセス
(2022年07月06日「基礎研レター」)
このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1784
経歴
- 【職歴】
2005年 ニッセイ基礎研究所(2022年7月より現職)
(2023年 東京外国語大学大学院総合国際学研究科博士後期課程修了、博士(学術)) 【社外委員等】
・日本経済団体連合会21世紀政策研究所研究委員
(2019~2020年度・2023年度~)
・金融庁 中国金融研究会委員(2024年度~)
・生命保険経営学会 編集委員・海外ニュース委員
・千葉大学客員教授(2024年度~)
・千葉大学客員准教授(2023年度) 【加入団体等】
日本保険学会、社会政策学会、他
【書籍】
第15回日本保険学会賞 受賞 『十四億人の安寧-デジタル国家中国の社会保障戦略』
片山 ゆきのレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/21 | 中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) | 片山 ゆき | 保険・年金フォーカス |
| 2025/09/02 | 中国、社会保険料の納付強化 | 片山 ゆき | 基礎研レター |
| 2025/08/08 | 中国、3歳まで育児手当支給へ | 片山 ゆき | 基礎研レター |
| 2025/08/05 | 消費喚起と社会保障(中国)【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(70) | 片山 ゆき | 保険・年金フォーカス |
新着記事
-
2025年11月04日
今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -
2025年10月31日
交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -
2025年10月31日
ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -
2025年10月31日
2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -
2025年10月31日
保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【中国版iDeCo、誕生へ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
中国版iDeCo、誕生へのレポート Topへ

















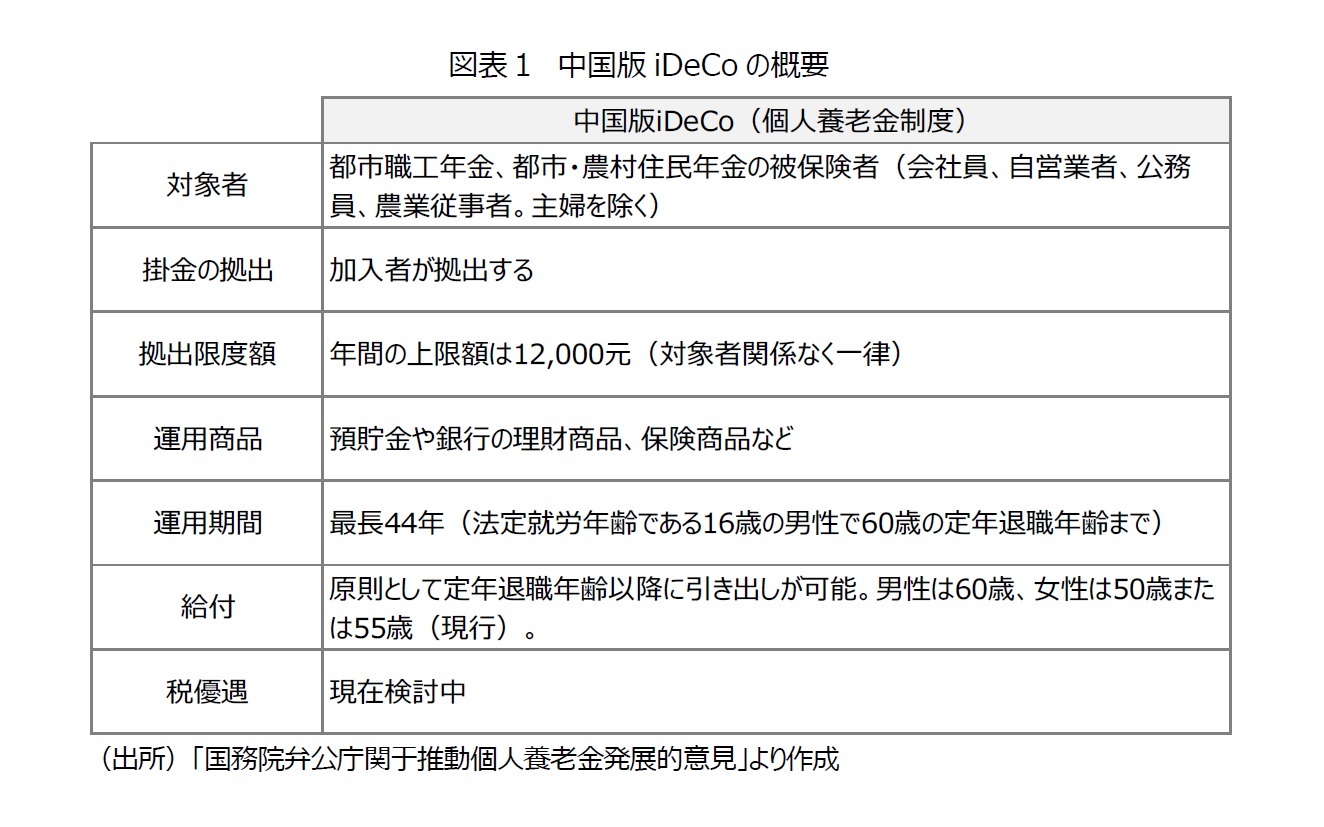

 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




