- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 不動産 >
- 都市計画 >
- ポスト2020の課題と対応策~魅力ある世界都市へのプロセスと課題 4/4
2017年01月17日
ポスト2020の課題と対応策~魅力ある世界都市へのプロセスと課題 4/4
【ポスト2020、魅力ある世界都市へ 訪日客数4000万人時代への挑戦】
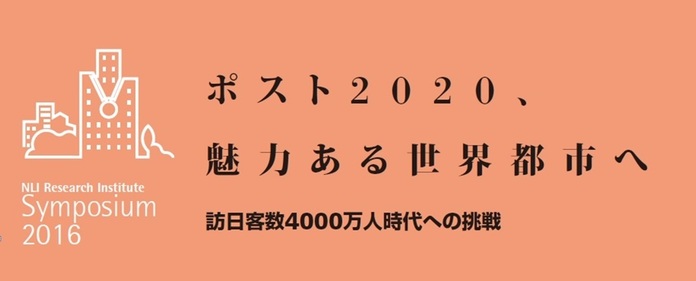
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
2016年10月18日「ポスト2020、魅力ある世界都市へ - 訪日客数4000万人時代への挑戦 -」をテーマにニッセイ基礎研シンポジウムを開催しました。
基調講演では明治大学公共政策大学院 ガバナンス研究科 教授の青山 佾氏をお招きして「オリンピック・パラリンピックと都市」をテーマに講演頂きました。
基調講演
「オリンピック・パラリンピックと都市」
パネルディスカッションでは「魅力ある世界都市へのプロセスと課題」をテーマに活発な議論を行っていただきました。
いま4/4記事目を読んでいます
基調講演では明治大学公共政策大学院 ガバナンス研究科 教授の青山 佾氏をお招きして「オリンピック・パラリンピックと都市」をテーマに講演頂きました。
基調講演
「オリンピック・パラリンピックと都市」
パネルディスカッションでは「魅力ある世界都市へのプロセスと課題」をテーマに活発な議論を行っていただきました。
いま4/4記事目を読んでいます
--------------------
パネルディスカッション
「魅力ある世界都市へのプロセスと課題」
パネリスト
明治大学公共政策大学院 教授
青山 佾 氏
ウィズダムツリージャパン株式会社
最高経営責任者
イェスパー・コール 氏
オラガ総研株式会社 代表取締役社長
牧野 知弘 氏
ニッセイ基礎研究所 研究理事
吉本 光宏
コーディネーター
ニッセイ基礎研究所 不動産運用調査室長
加藤 えり子
パネルディスカッション
「魅力ある世界都市へのプロセスと課題」
パネリスト
明治大学公共政策大学院 教授
青山 佾 氏
ウィズダムツリージャパン株式会社
最高経営責任者
イェスパー・コール 氏
オラガ総研株式会社 代表取締役社長
牧野 知弘 氏
ニッセイ基礎研究所 研究理事
吉本 光宏
コーディネーター
ニッセイ基礎研究所 不動産運用調査室長
加藤 えり子
6.訪日客4000万人の受け入れに向けて
■加藤
ありがとうございます。これは今後の動きに期待というところかもしれません。
それでは二つ目のトピックの4000万人訪日客を受け入れるために、どう取り組んでいったらいいのかということに移りたいと思います。
牧野さん、地方で直接受け入れるお話があったのですが、東京と地方の相対的な関係はどうなってくるのでしょうか。
■牧野
先ほどもちらっとお話ししましたが、私が地方都市でいろいろお話を伺っていると、何だか東京になろうと考えている地方都市が多いような気がします。
そうではなくて、この地方の魅力と東京との違いをもっと明確に打ち出した方がいいような気がしています。
東京は素晴らしい都市である反面、これだけの人口が集まってくると、やや人がだぶついてしまっています。従って、地方は逆に人口減少の問題に直面してしまっていますが、人口が減っていく中でどうすれば人が集まってくるのかが課題です。
一つは観光客なのですが、コールさんがおっしゃったとおり、観光客は来て帰ってしまうのです。
ところが、私がお手伝いをしている大分県別府市では、先ほどの私のプレゼンでも出てきた立命館アジア太平洋大学という大変立派な学校を誘致されて、ここにアジアの優秀な学生が大量に来ています。
この学生たちが卒業して、大分県あるいは別府市で起業したり、ここで働いたりすると、仲間が集まって、この都市ならではの発展が本当はできるはずなのです。
私が「本当は」と申し上げたのは、別府市の長野市長とお話ししたときに、市長の最大の悩みが立命館アジア太平洋大を卒業した学生のうち、1人も別府市で働いてくれない、全員出ていってしまうというのです。
せっかくこういう整備をしたのに、別府市内で彼らが活躍できるシステムがまだ整っていないのです。
世界中から「ここは魅力的だ」と思われるようなソフトウエアを含めたものがまだ開発できていません。考え方までは良かったのだけれども、ここから先、大分ならでは、別府ならではといったことを町づくりの中でやっていかないといけないというのは、私は大変感銘を受けました。
そういった意味では、東京ではない地方でどうやって情報を発信していくのかに懸かっています。それによって人を引き付け、場合によっては東京や大阪から地方都市に面白そうではないかといって移り住むような仕掛けができる都市が、これからも発展していくと思っています。
■加藤
ありがとうございます。相互にネットワークというか、行き来というか、働きかけるというような、少し深いつながりが必要なのかなと思いました。
それでは青山先生、東京の受け入れ体制という意味で、いろいろなインフラが整ってきているのかどうかという点と、東京の観光資源は何なのかということについてお願いいたします。
■青山
受け入れ体制について言うと、まず一番問題になるのはホテルだと思います。
最近、ホテルを建てる場合の容積率緩和の政策を出していて、具体的な対応はまだこれからですが、オリンピックまでまだ4年近くありますので、効果は相当期待できると思います。
それから意外と盲点なのですが、最近は鉄道駅周辺、神田や湯島など都心近くの地域の今まではマンションを建てていた敷地に、ビジネスホテル風の、それもいろいろ工夫がされているビジネスホテルが結構たくさんできていることに気が付いた方も多いと思います。
私は大体、ニューヨーク市役所やロンドン市役所から人が来ると、割とビジネスホテルに泊めるのですが、初めて泊まってみると案外喜ばれるのです。都心まで歩いて行ける所に1万円台で泊まれて、清潔で安全だということで喜ばれるのですが、これは一つの売りだと思います。
それから、民泊が随分話題になりましたが、民泊からさらにホームステイができるところが日本は非常に少ないです。
これからは、今まで大家族が住んでいた広い家に1人住まいというケースもどんどん増えていき、そういう意味ではヨーロッパやアメリカのようにホームステイ先が非常に多くなる状況に日本もこれからなっていくので、これは一つあるのかなと思います。
いずれにしろ、特にビジネスホテルなどは、2020年前後に一気に需要が膨らむのですが、その後の長期的なことを考えると、ある程度リノベーションができるようなことも考えていった方がいいのではないかとも思います。
それからもう一つは、観光のための資源についてだったと思うのですが、これは先ほど来いろいろ話も出ましたけれど、私は牧野さんが言った田植えの話が非常に印象的でした。
東京でも実は、稼いでいる農家は結構稼いでいまして、一番稼いでいるのはやはり果実のもぎ取りです。ナシや大粒のブドウなどのもぎ取り観光は非常にお金になります。
農家がもうかっていると言っているのではなくて、それなりに現金収入になるということなのですが、実は都市でも農業がかなりうまくいっている農家はうまくいっているという側面があります。
都市計画法では、10年以内に市街化区域内の農地を全て廃止すると宣言したのですが、生産緑地法のおかげもあって、40年たってもまだかなり残っているというのが東京独特なので、これも利用できる面があると思います。
それから東京の場合で言うと、食文化だと思います。ニューヨークなどでは、かつてのすしから今は丼物とよくいわれるのですが、ニューヨークのタイムズスクエアなどで丼の旗がはためいているお店に入ると、日本人は一人もいなくて、皆さん箸で丼を食べている光景を最近はよく見掛けるようになりました。
先ほど来、話も出ているのですが、日本独特の食文化がかなりあるので、これは観光資源としては特に東京はあるのだと思います。
ただ、その場合に少し理屈を言っておくと、日本人は清潔好きで、食品安全に対して良いイメージをコールさんなどは持っていただいて大変ありがたいのですが、同時にこれからはヨーロッパやアメリカで流行していることで言うと、国際認証制度でGAPや何かをどんどん取っていくとか、ハラル認証を取っていくとか、ハラル認証についても議論があって、それをやらなくてもいいという人もいるのですが、やはりそういう多様な対応ができるような形も、オリンピックがあるちょうどいい機会なのでやっていくといいと思います。
■加藤
多様な人々が来日するのに対応していってインフラを作っていくということでしょうか。そうしましたら、コールさんとしては、さらに外国の方が来るためには何が必要だとお考えですか。
■コール
先ほどイノベーションセンターと言いましたが、これは実はAppleとかGoogleとかではなくて、中小企業なのです。職人の企業なのです。
これはレストランのビジネスとか、そういう職人で、やはり日本型のマイスター制を頂ければすごく役に立つ、すごくレガシーをつくることになるわけです。
そしてもう一つは、外国人あるいは移民のために何かを作るべきという考え方ではなくて、まず日本人のために何をやるべきかということです。
これはどういうことかというと、当たり前のことなのですが、人口減少があると、もっと子どもをつくらないといけないわけです。でも、夫婦関係、家族関係に優しい環境をまずつくらないといけません。
だから、ホームヘルパーなどは今、東京で特区の議論が始まったわけですが、これはどうもフィリピンやインドネシアから入ってくる女性がほとんどになると思いますが、そのために優しい制度を作るべきだということは、実は日本も思っているわけです。
私はドイツ人なのですが、留学はアメリカ、仕事はパリでしまして、日本に来ました。外国人に一番優しいところは、日本なのです。フランスはドイツ人に対して大変厳しいのです。
役所に行ったら大変です。冗談ではなくて、考えていただきたいのですが、ニューヨークに行っても、パリに行っても、ソウルに行っても、上海に行っても、英語が書いてある看板などはありますか。やはりないわけです。
だから、まず選択としては外国の移民、外国の労働者に対して何をやるべきかということより、まず日本の社会のために何をやるべきかだと思います。移民はファイターだから入ってくると何とかなります。
■加藤
まず日本の社会が輝かないといけないということですか。
■コール
そうだと思います。そして、もう一つ具体的なこととして、先生のチャートでちょうど留学が今は大変増えているわけなのですが、これはすごく大事なポイントなのです。
東京に来て、大阪に来て、大学に行って日本語をきちんと勉強して、その後はどうするかということなのですが、本当に日本の会社の社内文化は外から入ってくる人を受け入れているかというのは大きな疑問です。
実は、アメリカから来日して日本語を勉強して、大体60~70%は戻ってしまいます。そして日本に無関心ということになってしまいます。なぜかというのは、日本の会社にはほとんど入れないからなのです。
■加藤
入ったとしても扱いが別枠だったりしますものね。
■コール
そうです。Bチームです。
■加藤
そのあたりは一体化するような政策がないと入ってきてくれないということですね。吉本さん、4000万人という目標について、どう捉えているかということなのです。
■吉本
4000万人というのは、今日のシンポジウムのサブタイトルになっているのですけれども、4000万人というのは東京の目標ではないと私は考えています。
正直なところ、東京はこれ以上混雑してほしくないと私は個人的に思っていまして、この4000万人は日本全体の目標だと思うのです。
それで先ほど地方空港に直接入ってくるという話もありましたけれど、ではどうやって4000万人の観光客に地方都市へ行っていただくかというときに、やはり文化というのが私はすごく重要なキーワードになるのではないかと思っています。
ご覧いただいているのは、これもイギリスで恐縮なのですが、ラフガイドという旅行ガイドブック大手のホームページの日本の「THINGS NOT TO MISS」、つまり日本で見逃してはいけないものので、その1番は京都なのですが、2番がスキー、3番が築地、4番がさっぽろ雪まつり、5番が奈良、そして6番目に直島というのが出ています。
直島をご存じの方はいらっしゃるでしょうか。瀬戸内の小さな島なのですけれども、今はアートの島として世界的に有名になっているのです。
これは草間彌生さんという日本人のアーティストの直島を代表するシンボルの作品なのですが、今年は瀬戸内国際芸術祭というものが開かれています。今回で3回目なのですが、先日、高松市長に伺ったら、来場者の10%以上が外国人だそうです。3年前の前回はわずか3%だったそうです。
台湾、香港の方が多いと伺いましたが、次に多いのはフランスの方らしいのです。フランスの人は東京には文化を見に来ないけれど、直島には行っているというわけです。
それぐらい文化の力は地方都市のインバウンドに重要で、それを世界中にアピールするのは、2020年が絶好のチャンスだと思っていて、私は文化プログラムの一つとして提案しているのがこれなのです。
日本の文化の特徴、文化的に強いものを全国で例えば2000カ所ぐらい選んで、専用のホームページを作って、英語、ドイツ語、フランス語、韓国語、中国語は当たり前ですが、世界中のマイナーな言語にも対応した専用サイトを作ってしまいます。
一旦作れば2020年以降の更新は簡単ですから、将来的に観光のインフラ、レガシーとなって残り、2020年以降に地方へのインバウンドの実現に寄与するのではないかと思います。
ですので、東京に関して言うと、もちろん観光客に来ていただいて、いろいろお金も使っていただいて、経済的に潤うことは重要だと思うのですが、東京が今考えなければいけないのは、10万人の観光客を誘致するよりも、10人の世界のトップレベルのクリエーターをどうやって引き付けるかということの方が、私は重要ではないかと思っています。
ありがとうございます。これは今後の動きに期待というところかもしれません。
それでは二つ目のトピックの4000万人訪日客を受け入れるために、どう取り組んでいったらいいのかということに移りたいと思います。
牧野さん、地方で直接受け入れるお話があったのですが、東京と地方の相対的な関係はどうなってくるのでしょうか。
■牧野
先ほどもちらっとお話ししましたが、私が地方都市でいろいろお話を伺っていると、何だか東京になろうと考えている地方都市が多いような気がします。
そうではなくて、この地方の魅力と東京との違いをもっと明確に打ち出した方がいいような気がしています。
東京は素晴らしい都市である反面、これだけの人口が集まってくると、やや人がだぶついてしまっています。従って、地方は逆に人口減少の問題に直面してしまっていますが、人口が減っていく中でどうすれば人が集まってくるのかが課題です。
一つは観光客なのですが、コールさんがおっしゃったとおり、観光客は来て帰ってしまうのです。
ところが、私がお手伝いをしている大分県別府市では、先ほどの私のプレゼンでも出てきた立命館アジア太平洋大学という大変立派な学校を誘致されて、ここにアジアの優秀な学生が大量に来ています。
この学生たちが卒業して、大分県あるいは別府市で起業したり、ここで働いたりすると、仲間が集まって、この都市ならではの発展が本当はできるはずなのです。
私が「本当は」と申し上げたのは、別府市の長野市長とお話ししたときに、市長の最大の悩みが立命館アジア太平洋大を卒業した学生のうち、1人も別府市で働いてくれない、全員出ていってしまうというのです。
せっかくこういう整備をしたのに、別府市内で彼らが活躍できるシステムがまだ整っていないのです。
世界中から「ここは魅力的だ」と思われるようなソフトウエアを含めたものがまだ開発できていません。考え方までは良かったのだけれども、ここから先、大分ならでは、別府ならではといったことを町づくりの中でやっていかないといけないというのは、私は大変感銘を受けました。
そういった意味では、東京ではない地方でどうやって情報を発信していくのかに懸かっています。それによって人を引き付け、場合によっては東京や大阪から地方都市に面白そうではないかといって移り住むような仕掛けができる都市が、これからも発展していくと思っています。
■加藤
ありがとうございます。相互にネットワークというか、行き来というか、働きかけるというような、少し深いつながりが必要なのかなと思いました。
それでは青山先生、東京の受け入れ体制という意味で、いろいろなインフラが整ってきているのかどうかという点と、東京の観光資源は何なのかということについてお願いいたします。
■青山
受け入れ体制について言うと、まず一番問題になるのはホテルだと思います。
最近、ホテルを建てる場合の容積率緩和の政策を出していて、具体的な対応はまだこれからですが、オリンピックまでまだ4年近くありますので、効果は相当期待できると思います。
それから意外と盲点なのですが、最近は鉄道駅周辺、神田や湯島など都心近くの地域の今まではマンションを建てていた敷地に、ビジネスホテル風の、それもいろいろ工夫がされているビジネスホテルが結構たくさんできていることに気が付いた方も多いと思います。
私は大体、ニューヨーク市役所やロンドン市役所から人が来ると、割とビジネスホテルに泊めるのですが、初めて泊まってみると案外喜ばれるのです。都心まで歩いて行ける所に1万円台で泊まれて、清潔で安全だということで喜ばれるのですが、これは一つの売りだと思います。
それから、民泊が随分話題になりましたが、民泊からさらにホームステイができるところが日本は非常に少ないです。
これからは、今まで大家族が住んでいた広い家に1人住まいというケースもどんどん増えていき、そういう意味ではヨーロッパやアメリカのようにホームステイ先が非常に多くなる状況に日本もこれからなっていくので、これは一つあるのかなと思います。
いずれにしろ、特にビジネスホテルなどは、2020年前後に一気に需要が膨らむのですが、その後の長期的なことを考えると、ある程度リノベーションができるようなことも考えていった方がいいのではないかとも思います。
それからもう一つは、観光のための資源についてだったと思うのですが、これは先ほど来いろいろ話も出ましたけれど、私は牧野さんが言った田植えの話が非常に印象的でした。
東京でも実は、稼いでいる農家は結構稼いでいまして、一番稼いでいるのはやはり果実のもぎ取りです。ナシや大粒のブドウなどのもぎ取り観光は非常にお金になります。
農家がもうかっていると言っているのではなくて、それなりに現金収入になるということなのですが、実は都市でも農業がかなりうまくいっている農家はうまくいっているという側面があります。
都市計画法では、10年以内に市街化区域内の農地を全て廃止すると宣言したのですが、生産緑地法のおかげもあって、40年たってもまだかなり残っているというのが東京独特なので、これも利用できる面があると思います。
それから東京の場合で言うと、食文化だと思います。ニューヨークなどでは、かつてのすしから今は丼物とよくいわれるのですが、ニューヨークのタイムズスクエアなどで丼の旗がはためいているお店に入ると、日本人は一人もいなくて、皆さん箸で丼を食べている光景を最近はよく見掛けるようになりました。
先ほど来、話も出ているのですが、日本独特の食文化がかなりあるので、これは観光資源としては特に東京はあるのだと思います。
ただ、その場合に少し理屈を言っておくと、日本人は清潔好きで、食品安全に対して良いイメージをコールさんなどは持っていただいて大変ありがたいのですが、同時にこれからはヨーロッパやアメリカで流行していることで言うと、国際認証制度でGAPや何かをどんどん取っていくとか、ハラル認証を取っていくとか、ハラル認証についても議論があって、それをやらなくてもいいという人もいるのですが、やはりそういう多様な対応ができるような形も、オリンピックがあるちょうどいい機会なのでやっていくといいと思います。
■加藤
多様な人々が来日するのに対応していってインフラを作っていくということでしょうか。そうしましたら、コールさんとしては、さらに外国の方が来るためには何が必要だとお考えですか。
■コール
先ほどイノベーションセンターと言いましたが、これは実はAppleとかGoogleとかではなくて、中小企業なのです。職人の企業なのです。
これはレストランのビジネスとか、そういう職人で、やはり日本型のマイスター制を頂ければすごく役に立つ、すごくレガシーをつくることになるわけです。
そしてもう一つは、外国人あるいは移民のために何かを作るべきという考え方ではなくて、まず日本人のために何をやるべきかということです。
これはどういうことかというと、当たり前のことなのですが、人口減少があると、もっと子どもをつくらないといけないわけです。でも、夫婦関係、家族関係に優しい環境をまずつくらないといけません。
だから、ホームヘルパーなどは今、東京で特区の議論が始まったわけですが、これはどうもフィリピンやインドネシアから入ってくる女性がほとんどになると思いますが、そのために優しい制度を作るべきだということは、実は日本も思っているわけです。
私はドイツ人なのですが、留学はアメリカ、仕事はパリでしまして、日本に来ました。外国人に一番優しいところは、日本なのです。フランスはドイツ人に対して大変厳しいのです。
役所に行ったら大変です。冗談ではなくて、考えていただきたいのですが、ニューヨークに行っても、パリに行っても、ソウルに行っても、上海に行っても、英語が書いてある看板などはありますか。やはりないわけです。
だから、まず選択としては外国の移民、外国の労働者に対して何をやるべきかということより、まず日本の社会のために何をやるべきかだと思います。移民はファイターだから入ってくると何とかなります。
■加藤
まず日本の社会が輝かないといけないということですか。
■コール
そうだと思います。そして、もう一つ具体的なこととして、先生のチャートでちょうど留学が今は大変増えているわけなのですが、これはすごく大事なポイントなのです。
東京に来て、大阪に来て、大学に行って日本語をきちんと勉強して、その後はどうするかということなのですが、本当に日本の会社の社内文化は外から入ってくる人を受け入れているかというのは大きな疑問です。
実は、アメリカから来日して日本語を勉強して、大体60~70%は戻ってしまいます。そして日本に無関心ということになってしまいます。なぜかというのは、日本の会社にはほとんど入れないからなのです。
■加藤
入ったとしても扱いが別枠だったりしますものね。
■コール
そうです。Bチームです。
■加藤
そのあたりは一体化するような政策がないと入ってきてくれないということですね。吉本さん、4000万人という目標について、どう捉えているかということなのです。
■吉本
4000万人というのは、今日のシンポジウムのサブタイトルになっているのですけれども、4000万人というのは東京の目標ではないと私は考えています。
正直なところ、東京はこれ以上混雑してほしくないと私は個人的に思っていまして、この4000万人は日本全体の目標だと思うのです。
それで先ほど地方空港に直接入ってくるという話もありましたけれど、ではどうやって4000万人の観光客に地方都市へ行っていただくかというときに、やはり文化というのが私はすごく重要なキーワードになるのではないかと思っています。
ご覧いただいているのは、これもイギリスで恐縮なのですが、ラフガイドという旅行ガイドブック大手のホームページの日本の「THINGS NOT TO MISS」、つまり日本で見逃してはいけないものので、その1番は京都なのですが、2番がスキー、3番が築地、4番がさっぽろ雪まつり、5番が奈良、そして6番目に直島というのが出ています。
直島をご存じの方はいらっしゃるでしょうか。瀬戸内の小さな島なのですけれども、今はアートの島として世界的に有名になっているのです。
これは草間彌生さんという日本人のアーティストの直島を代表するシンボルの作品なのですが、今年は瀬戸内国際芸術祭というものが開かれています。今回で3回目なのですが、先日、高松市長に伺ったら、来場者の10%以上が外国人だそうです。3年前の前回はわずか3%だったそうです。
台湾、香港の方が多いと伺いましたが、次に多いのはフランスの方らしいのです。フランスの人は東京には文化を見に来ないけれど、直島には行っているというわけです。
それぐらい文化の力は地方都市のインバウンドに重要で、それを世界中にアピールするのは、2020年が絶好のチャンスだと思っていて、私は文化プログラムの一つとして提案しているのがこれなのです。
日本の文化の特徴、文化的に強いものを全国で例えば2000カ所ぐらい選んで、専用のホームページを作って、英語、ドイツ語、フランス語、韓国語、中国語は当たり前ですが、世界中のマイナーな言語にも対応した専用サイトを作ってしまいます。
一旦作れば2020年以降の更新は簡単ですから、将来的に観光のインフラ、レガシーとなって残り、2020年以降に地方へのインバウンドの実現に寄与するのではないかと思います。
ですので、東京に関して言うと、もちろん観光客に来ていただいて、いろいろお金も使っていただいて、経済的に潤うことは重要だと思うのですが、東京が今考えなければいけないのは、10万人の観光客を誘致するよりも、10人の世界のトップレベルのクリエーターをどうやって引き付けるかということの方が、私は重要ではないかと思っています。
(2017年01月17日「その他レポート」)
新着記事
-
2025年11月04日
数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが- -
2025年11月04日
ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続 -
2025年11月04日
米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- -
2025年11月04日
パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える -
2025年11月04日
「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【ポスト2020の課題と対応策~魅力ある世界都市へのプロセスと課題 4/4】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ポスト2020の課題と対応策~魅力ある世界都市へのプロセスと課題 4/4のレポート Topへ


















 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




