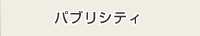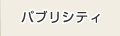- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- パブリシティ >
- イベント(シンポジウム) >
- イベント詳細 >
- 高齢者の年金・就労・健康を考える
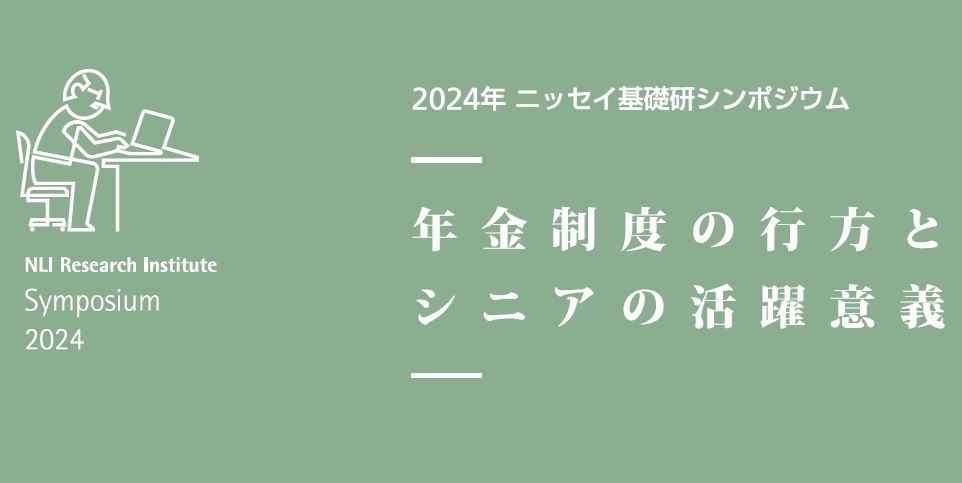
2024年10月22日開催
基調講演
高齢者の年金・就労・健康を考える
| 講師 | 一橋大学経済研究所 特任教授 小塩 隆士氏 |
|---|
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
4――まとめと政策課題
今日のお話はこれで大体終わります。これまで、特に定年後、親の介護が始まったりすると、いろいろなメンタルヘルス面で大きな問題が出てくるわけですが、それを克服する、あるいは軽減するにはどうしたらいいかという話をしてきました。
話をまとめますと、高齢者はもう少し働くことはできる、それは言えると思います。せっかく健康なのだから、もう少し働く余地はあると言えます。ただ、ブレーキをかけているものは、きちんと取り除かないといけません。その代表的な例は、今日の後半のお話でも出てくると思いますが、在職老齢年金の仕組みだろうと思います。
それから、働いたら基本的には健康面にプラスの影響が出てくるとのですが、フルタイムでがんがん働くということになると、問題があるのではないか。多様な働き方を認めれば、働くということを軸にしてメンタルヘルスは良くなる余地はあるのではないかと思います。
ただ、高齢時にはいろいろなリスクイベントが発生します。その一番大きいものが、家族介護が始まるということです。既に直面されている方もここにいらっしゃるかと思いますが、これは政策を立案する場合も重要だろうということです。「高齢社会対策大綱」が9月に発表されましたが、基本的には要介護状態になった人、あるいは病気になった人たちが議論の前面に出てきます。それは当然なのですが、それと同じような重要性を持っているのは、そういう人たちを家族として抱えている人たちです。要介護状態になっている親御さんをケアしないといけない人たち、そういう人たちのことも考えないといけません。そういう丁寧な議論が必要になると思います。
それから、政策的にはあまり前面に出てきませんが、いろいろな社会参加の仕組みが、人々の健康リスクの悪化を軽減する、あるいは、むしろポジティブに作用するという効果は、いろいろな実証分析でも確認できます。これは政策的にコストパフォーマンスが非常にいいのです。お金はあまりかからず、行政サイドから何か仕掛け、きっかけをつくると、それが非常に大きな効果を及ぼすこともよく知られています。ちょっとした工夫で、高齢社会がとても豊かな社会になるのではないかと思います。
最後に、おまけを付けておきましょう。
これは、私が分析していて、そこで得られた分析をどのように解釈していいか困っており、特に秋山先生にご示唆を頂ければ非常にありがたいと思っているものです。この図は、横軸に年齢を取りました。縦軸は、何らかの形で幸福度を数値化したものです。国によって比較できるように標準化しています。もちろん、それぞれの年齢で差が大きいので、あまり平均の議論をしてもよくないかもしれませんが、平均的な幸福度の状況をドットで示しました。そして、そのドットをうまく説明できるように、外から曲線を当てはめてみました。そうした作業を日本と中国でやってみたのです。
そうすると、日本の場合は、ボトム、つまり人生の中で一番つらいなと思うのは、ここにもいらっしゃるかもしれませんが、50歳代前半です。住宅ローンがあるとか、子どもの受験とかいろいろあると思いますが、それを越えると、幸福度はむしろ改善していくのです。健康状態は悪くなるはずです。それから親の介護とかいろいろなリスクイベントが発生するにもかかわらず、幸福度は高くなります。中国は、もっとはっきりしていまして、ボトムは、もう少し若い年齢で発生するのですが、お年寄りになると非常にハッピーな状況が出てきます。状況は、国によって違います。ヨーロッパでは、フランスはこれに近いのですが、イギリスとかドイツで見ると、ぐにゃぐにゃになって、二次曲線ではなくて三次曲線になることがあります。
普通に考えれば、年を取ると健康状態も悪くなるし、幸福度のようなウェルビーイングも悪くなるのではないかと思うのですが、統計的に見るとむしろ良くなる傾向があります。もちろん、いろいろな仮説があると思います。年を取ったら、いろいろなことを諦めてしまうとか、幸せのハードルが落ちるとか、いろいろな解釈ができると思うのですが、私が先行研究で見る限り、決定打はありません。非常に不思議な状況なのです。
これはむしろいい話でもあるかもしれません。年を取ることには、何か暗いイメージがありますが、本当は潜在的にもっと明るいのだということになります。もし、その明るいことを引き下げているような要因があるのであれば、それを払拭したら、もっと明るい人生がわれわれを待っているのではないでしょうか。65歳とか60歳で現役を退いた後、まだ30年、40年とあるわけですから、そのときをどのように楽しく生きるかということは、先ほど言ったようにレールがないので、われわれ試行錯誤しなければいけないと思いますが、潜在的には、あるいは既に統計で見ても明らかなように、年を取るほどハッピーになるということを念頭に置いた上で、よりハッピーにするために政策を変えていくとか、あるいは企業の在り方を変えていくということを議論していったらいいのではないかなと思いました。
以上、おまけも付けたのですが、皆さんにお話しようとご用意してきた資料は以上です。どうもありがとうございました(拍手)。
話をまとめますと、高齢者はもう少し働くことはできる、それは言えると思います。せっかく健康なのだから、もう少し働く余地はあると言えます。ただ、ブレーキをかけているものは、きちんと取り除かないといけません。その代表的な例は、今日の後半のお話でも出てくると思いますが、在職老齢年金の仕組みだろうと思います。
それから、働いたら基本的には健康面にプラスの影響が出てくるとのですが、フルタイムでがんがん働くということになると、問題があるのではないか。多様な働き方を認めれば、働くということを軸にしてメンタルヘルスは良くなる余地はあるのではないかと思います。
ただ、高齢時にはいろいろなリスクイベントが発生します。その一番大きいものが、家族介護が始まるということです。既に直面されている方もここにいらっしゃるかと思いますが、これは政策を立案する場合も重要だろうということです。「高齢社会対策大綱」が9月に発表されましたが、基本的には要介護状態になった人、あるいは病気になった人たちが議論の前面に出てきます。それは当然なのですが、それと同じような重要性を持っているのは、そういう人たちを家族として抱えている人たちです。要介護状態になっている親御さんをケアしないといけない人たち、そういう人たちのことも考えないといけません。そういう丁寧な議論が必要になると思います。
それから、政策的にはあまり前面に出てきませんが、いろいろな社会参加の仕組みが、人々の健康リスクの悪化を軽減する、あるいは、むしろポジティブに作用するという効果は、いろいろな実証分析でも確認できます。これは政策的にコストパフォーマンスが非常にいいのです。お金はあまりかからず、行政サイドから何か仕掛け、きっかけをつくると、それが非常に大きな効果を及ぼすこともよく知られています。ちょっとした工夫で、高齢社会がとても豊かな社会になるのではないかと思います。
最後に、おまけを付けておきましょう。
これは、私が分析していて、そこで得られた分析をどのように解釈していいか困っており、特に秋山先生にご示唆を頂ければ非常にありがたいと思っているものです。この図は、横軸に年齢を取りました。縦軸は、何らかの形で幸福度を数値化したものです。国によって比較できるように標準化しています。もちろん、それぞれの年齢で差が大きいので、あまり平均の議論をしてもよくないかもしれませんが、平均的な幸福度の状況をドットで示しました。そして、そのドットをうまく説明できるように、外から曲線を当てはめてみました。そうした作業を日本と中国でやってみたのです。
そうすると、日本の場合は、ボトム、つまり人生の中で一番つらいなと思うのは、ここにもいらっしゃるかもしれませんが、50歳代前半です。住宅ローンがあるとか、子どもの受験とかいろいろあると思いますが、それを越えると、幸福度はむしろ改善していくのです。健康状態は悪くなるはずです。それから親の介護とかいろいろなリスクイベントが発生するにもかかわらず、幸福度は高くなります。中国は、もっとはっきりしていまして、ボトムは、もう少し若い年齢で発生するのですが、お年寄りになると非常にハッピーな状況が出てきます。状況は、国によって違います。ヨーロッパでは、フランスはこれに近いのですが、イギリスとかドイツで見ると、ぐにゃぐにゃになって、二次曲線ではなくて三次曲線になることがあります。
普通に考えれば、年を取ると健康状態も悪くなるし、幸福度のようなウェルビーイングも悪くなるのではないかと思うのですが、統計的に見るとむしろ良くなる傾向があります。もちろん、いろいろな仮説があると思います。年を取ったら、いろいろなことを諦めてしまうとか、幸せのハードルが落ちるとか、いろいろな解釈ができると思うのですが、私が先行研究で見る限り、決定打はありません。非常に不思議な状況なのです。
これはむしろいい話でもあるかもしれません。年を取ることには、何か暗いイメージがありますが、本当は潜在的にもっと明るいのだということになります。もし、その明るいことを引き下げているような要因があるのであれば、それを払拭したら、もっと明るい人生がわれわれを待っているのではないでしょうか。65歳とか60歳で現役を退いた後、まだ30年、40年とあるわけですから、そのときをどのように楽しく生きるかということは、先ほど言ったようにレールがないので、われわれ試行錯誤しなければいけないと思いますが、潜在的には、あるいは既に統計で見ても明らかなように、年を取るほどハッピーになるということを念頭に置いた上で、よりハッピーにするために政策を変えていくとか、あるいは企業の在り方を変えていくということを議論していったらいいのではないかなと思いました。
以上、おまけも付けたのですが、皆さんにお話しようとご用意してきた資料は以上です。どうもありがとうございました(拍手)。
⇒ パネルディスカッション 前編
超高齢社会における企業と個人の在り方(2/20公開予定)
超高齢社会における企業と個人の在り方(2/20公開予定)
コンテンツ紹介
-
レポート
-
受託実績・コンサルティング
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る